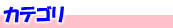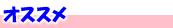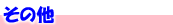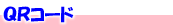なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その2)

藤子・F・不二雄『チンプイ』「殿下に負けないで」より
(承前)では『チンプイ』はどんな結末を迎えるはずだったのか。それについて論じる前に、まず「エリのクローンを作ってマール星へ行ってもらう」説を片づけておく。
といっても、「クローン人間はコピー人間ではない」という事実を指摘しておくだけで十分だろう。一卵性双生児は性格までそっくりと勘違いしている人も多いようだが、そんなことはない。エリのクローン人間を作ったとして、性格も知力体力も音楽の趣味も、全く異なる人間ができあがる。これでは解決にはならない。
それともマール星の科法は、単なるクローン人間ではなく、精神まで完璧にそっくりにコピーする技術を有しているのかもしれない。しかし、人間の心だとか人格だとか、そんなものまで自由自在に操れる技術があるのであれば、もう何だってアリだろう。さっさとエリを洗脳してマール星へ連れて行け。一体ワンダユウは何を苦労しているのだろうか。
人の心は自由にはならないという制約があるからこそ、人の世にドラマは生まれるのである。
しかしこのクローン人間説の最大の問題は、その発想の貧困さにある。読者の願いは、エリが幸せになることである。しかし「エリが幸せになる」ということと、「エリの欲求が通る」ということは別のことのはずだ。なぜ、エリの気が変わる可能性は絶対にないということを前提にする必要があるのか。
エリはルルロフ殿下のお妃になんかなりたくないと言っている。しかしエリのその気持の根拠は相当薄弱なものだ、という描き方は第一話から一貫している。エリはルルロフ殿下やマール星について十分な知識を持っていないし、持とうと思うことすらない。とにかく嫌なものは嫌だと言っているだけである。虫歯になった子供が歯医者に行くのを嫌がって駄々をこねているのと大して違いはない。
チンプイの立場に立って考えたい。ワンダユウがマール星本位の考えをエリに押し付けようとする傾向があるのに対して、チンプイはエリのことが純粋に好きである。そのチンプイが、エリにマール星に来て妃殿下になってほしいと言っている。それがエリにとっても幸せなことだという強い確信があるからである。そしてエリの側は、マール星なんかに行きたくないという自分の気持ちを相手に分からせるには、どういう言い方をすればいいのだろうか、と考えてみようとすら思わない。結末は最初から目に見えている。(続く)
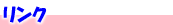
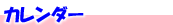
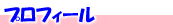
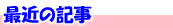
- なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その2) (05/18)
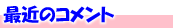
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ percetakan jakarta (04/20)
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
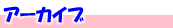
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)