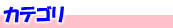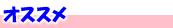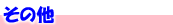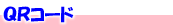逃げ道を確保する雨宮慶太(前編)

『ジェットマン VOL.3』(スーパークエスト文庫、1994年)には鈴木武幸プロデューサーが寄稿。雨宮慶太氏を起用した経緯についても言及がある。
高寺成紀氏に対しては、私は「敵ながら見事」と思っている。自分(一人)が作った『仮面ライダークウガ』という作品の偉大さを喧伝するためならば、昭和ライダー(末期)や宇宙刑事や戦隊シリーズのファンを全部敵に回すのも厭わないという、その潔い態度に感服するからである。
ひるがえって、安全な逃げ道を確保しながら自分の功績を大きく見せかけようとする人に対しては、私は一切の信をおくことはできない。
戦隊シリーズ打ち切りの危機について調べていたら、こんなツイートが出てきた。雨宮慶太氏というのは『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)のパイロット監督。
ジェットマンは戦隊シリーズが今年で終わりで最後だからって事で、当時ペーペーだった俺と井上が鈴木Pに呼ばれて始まったのだ。(2012年8月23日)最後というのは誰が言ったのか?
どういう場所で出た話なのか?
いつの時点での話だったのか。また撤回されたのはいつか?
どの位の人数の間で共有されていた話なのか?
具体的な話が全然ない。
もしこの雨宮氏に対して質問攻めにする奴がいたら? 多分「いやあ、昔のことだから記憶が定かでなくて。でも確かにそんな話が……」で追及をかわしていたことだろう。しかし質問をする奴はいなかったし、だから当時スーパー戦隊シリーズは打ち切りの危機だった(そして自分は救世主?)という噂を流布するのに成功したわけだ。
つまりこれは雨宮氏にとって賭けだったのである。負ければ小損、勝てば大得、という。
誰もがやっていることだ、そんなことで一々卑怯とか言われてはたまったものではない、と言われるかもしれない。しかしそれでも汚いものは汚いと思う。
だいたいこれは鈴木プロデューサーの言っていることと正反対である。もちろん鈴木氏の方が勘違いしているという可能性もあるが、ここまで露骨に恩を仇で返すような発言をしていいのだろうか。しかも、井上敏樹先生まで巻き込むようなまねをして。(続く)
「世代」を特権化したがる人たち
「小谷野敦の本はなぜ売れるのか」(前・中・後)の補論。小谷野敦『ウルトラマンがいた時代』の終章の最後の一文より。
小学生で七〇年代のウルトラマンに出会い、それから二十年ないし四十年を隔てて再び出会うということは、実に私の世代の特権的な体験だったのだ。言いたかったのは結局それかい。
そのために丸々一冊の本を書いたとは、御苦労なことです。
「特権的」、すなわち特別にいい思いをした、という意味で使っているんだろうけど、こういう「自分たちの世代は他の世代とは違って特別なんだ」ということをやたら言いたがる人たちに対しては、別に腹も立たない。かわいそうに思うだけ。
去年同志を募って大川めぐみさんに会いに行った時のことである。どうせおっさんしか来ないだろうと思っていたら、ものすごく若い人が来ていたのには驚いた。というのは、最近の若いモンに彼女の魅力などどうせ分かるはずあるまい、とひそかに思っていたからである。態度には絶対に出さないようにしていたが、心の奥底ではそうだった。1980年代という、未来には希望があると誰もが屈託なく信じることのできた時代だったからこそ、彼女の魅力は光り輝いていたのだと思っていた。ところがその若者に聞いてみたら、最近DVDで見て虜になったという。さらに話を聞き出すと、ひょっとしたらこいつの桃園ミキ(大川めぐみ)に対する思い入れは、自分よりも上ではないかとすら思った。後生畏るべし。
小谷野敦氏一人のことではなくて、ウルトラシリーズのファンには、リアルタイムで見たという事実をやたらと特権化したがる人達がいる。そういう人たちがマスメディア等で、自分たちこそファンの代表という顔をして、でかい声を上げている。そういう声に制作サイドが耳を傾けた時こそが、ウルトラシリーズの終わる時だろう。
いずれにせよ今年もまた大川さんに会いに行くのが楽しみだ。今年はどんな人が来るのだろう。
小谷野敦の本はなぜ売れるのか(後編)
(承前)『ドラえもん』の劇場映画はなぜ年に一度なのだろう?
毎年巨額の利益を出してる映画である。だったら春休み夏休み冬休みの年三回公開にすれば、もっと利益が出るだろう。子どもたちだって喜ぶはずだ。……なんてことを考える人はいないわな。日本の誇る偉大なクリエイター、藤子・F・不二雄先生の遺産を粗略に扱うなど許されるはずもない。
ひるがえって『仮面ライダー』はというと、年三回公開という体制が定着して久しい。
逼迫したスケジュールがたたってクォリティは落ちる一方、それでも黒字が出ている以上、本数を減らすことはありえない。だいたい東映のスタッフも全員、石ノ森章太郎先生の魂を受け継いで『仮面ライダー』という作品を大切に作っていきますと言ってはいるものの、それが口先だけのものだということは、ファンもみんな了解している。
これが特撮のファン気質なのだ。
このブログで何度も何度も書いてきたが、私は商業主義を全否定するわけではない。問題はバランスなのだ。特撮作品の世界では、商業主義が暴走した際にブレーキ役を果たす存在が何もない。権威主義が通用しないということには良い面も悪い面もあると前回書いた。その悪い面がこれである。
『ウルトラセブン』第12話「遊星より愛をこめて」も、それが本当に被爆者に対して差別的な作品かということは、どうでもいいことなのだ。安藤健二『封印作品の謎』にもそんな書き方がしてあった。つまり、差別的なエピソードが含まれていると言われることが『ウルトラセブン』のイメージを悪化させ、そのことがもたらす損害額と、第12話をソフト化して上げられる利益額、その両者を比較して、前者が後者を上回ると円谷プロが判断した。そうである以上、どうしようもないことなのだ。ファンもみんな分かっている。
そんな現状がいいことだとは私も思わない。特撮ファンはもっと教養を高め、社会問題に対して目を向けるよう務めるべきである、という意見もある。そのためには、この特撮村に来てほしいのは、鳥なき里の蝙蝠なんかではなく、本物の鳥類である。芥川賞に落ちたことを売りにしている人なんかではなく、芥川賞なんかどうでもいいから真摯に小説に打ち込んでいるような人……。
7/29に補論
小谷野敦の本はなぜ売れるのか(中編)
(承前)『ウルトラマンのいた時代』、「序章」の最後の文。
スーザン・ソンタグに「反解釈」という評論があるが(ちくま学芸文庫)、「解釈」するのではなく、あの時代の雰囲気を表しつつ、ウルトラマンを論じる方法を考えて、本書を書いた。ほほう。で、そのソンタグという人はどんなことを言ってんの。と思ったら、何の説明もない。
外国の偉い学者の名前を出しさえすれば、読者は恐れ入ってひれ伏すだろうと思ったらしい。
その後も、「西洋古典への親炙」(p.64)だとか、無教養な人間が自分を賢く見せようと無理して難しい単語を使いまくり、しかもそれが誤用ときては大笑いである。この人には、なんと『頭の悪い日本語』などというタイトルの著書があるらしい。自分のことを書いたのだろうか。
こんな見え透いたこけおどしに引っかかる読者もどうかと思うが、ではなぜ特撮ファンにだけは、この権威主義の手法が通用しなかったのだろうか。
それは、特撮ファンこそは、「権威」から最も遠ざけられた人たちだからである。
『ウルトラセブン』の第12話「遊星より愛をこめて」は欠番になっている。そして解除を求めるファンの声も大きくない。それは、被爆者差別は許せないという権威に膝を屈しているからだ、と小谷野氏は考えた。そこに自分が乗り込んでいけばヒーローになれるに違いない。権威に対抗するためには自らも権威で武装することが必要だ。
だがそれが間違いなのである。
『セブン』12話の解除をファンが求めないのは、単につまらない話だからである。
面白いものは面白いと言う。つまらないものはつまらないと言う。それが特撮ファンである。権威の前に頭を垂れ、つまらないものを面白いと言ったりすることは、絶対にないとは言わないが、他のジャンルに比べれば少ない。
そしてそんな土壌を持った世界に、権威主義の鎧で身を固めた部外者がノコノコやってきて、ピエロを演じる羽目になったというわけである。
権威主義が通じないこの世界を私は愛する。そして自分がその一員であることを誇りに思う。ただ、いいことばかりというわけでもない。(続く)
小谷野敦の本はなぜ売れるのか(前編)

小谷野敦『ウルトラマンがいた時代』(KKベストセラーズ、2013年)
二年前に出た時に、ネットで無茶苦茶叩かれた本である。
別に小谷野氏をかばう義理は私にはない。当時、この本に加えられた批判の九割は、今から考えても妥当なものである。事実関係は間違いだらけだし、そしてそれを突きつけられた時の筆者の言い逃れや開き直った態度の見苦しさは記憶に新しい。特撮をダシに正義を語ろうとするような本とは一線を画すのだとかいいながら、やってることは単なる自分史をダラダラと書き並べているだけ。何歳の時にレトルトカレーを初めて食べたとか、そんな話がウルトラマンのいた時代を理解するのに一体何の関係があるのだろうか。ウルトラヒロインで誰が誰より美人だとかいう話が延々と続くのに対しては、そんなもんお前の好みだろとしか言いようがない。
だからといって残りの一割を見過ごしていいわけではない。明らかに過剰な叩きは存在していた。
「この小谷野という奴は、文学とか歴史とか社会問題とかをテーマにした本を出す際には、決してこのような間違いだらけの本を出そうとは思わなかっただろう。こいつは特撮を他のジャンルに対して明らかに低く見ているのだ。所詮子ども向けの娯楽だと思って馬鹿にしているのだ」という批判が当時あった。だが、小谷野氏は決してそのような人ではない。このことは、氏の名誉のためにも断言しておく。なぜそんなことが言えるのか。この人の、文学とか歴史とか社会問題とかをテーマにした他の本も、似たり寄ったりだからである。そしてアマゾンのレビューなんかを見てみると、「歯に衣着せぬ鋭い舌鋒」「歯切れの良さが痛快」などと褒めたたえ、買う人がいっぱいいる。そのように馬鹿をだまして食い物にするテクニックを自家薬籠中のものとしているのが、小谷野敦という人なのである。
そしてそのような手口が唯一通用しなかった相手が、特撮ファンだったのだ。(続く)
戦隊における「司令」と「総司令」の区別
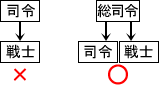
プロ野球といえば、十年くらい前までは、チームが強いのも弱いのも全部監督の責任のように考えられていた。
チーム作りには「選手の獲得」と「選手の指導」という二つの作業が必要である。監督はこのうちの後者の責任者であるに過ぎない。全体を統括する責任者はゼネラル・マネージャー(GM)という。ところがなぜか日本では「GM」という概念自体が長らく知られておらず、監督にGMの仕事までさせるとか、GMに相当する人間は存在しているのだが表に出ず、チーム作りが成功しても失敗しても監督を矢面に立たせるとかしていた。なぜこんな異常な状態がずっと続いていたのかよく分からない。日本のタテ社会の人間関係とからめて論じれば、日本人論が一本できそうな気もするが、まあそれはともかく。
最近ではプロ野球ファンの意識も昔に比べて随分と進歩したようで、なんでもかんでも監督の責任にするような論調は以前に比べて弱まっているように思われる。
さて戦隊の分類である。
戦隊の性格を分析するのに、「戦士がどのようにして集められたのか」に着目するのは常道である。地球防衛軍に所属する優秀な隊員であり、厳しい選抜試験をくぐり抜けて選ばれたのか。それともたまたま道を歩いていたら偶然事故が起こって強化人間になってしまったのか。しかしこんな分析方法では、チームのことは半分しか把握できない。司令官についても同様の検討をしなくては、その戦隊の全貌を把握したとは言えない。優秀な指揮能力を持った人間が選抜されたのか、それとも他に人がいないから仕方なくなったのか。
戦士を選ぶのは司令官の仕事ではない。司令官にも上司がいるはずで、仮にそれを総司令官と呼んでおくと、そいつが戦士を選んだはずだ。もっとも作品を作っている側も、そのへんをキチッと詰めて考えているとも限らなかったりするのだが。
地球を守る組織にとって、戦士がパーツに過ぎないと考えるのであれば、司令官だってパーツに過ぎないのである。戦士と司令官は横に並んでいる存在である。上下関係ではない。しかし人と人との関係を、我々はどうしてもそのような図式にあてはめて考えようとする。日本人の悪い癖である。
スーパー戦隊のファンはプロ野球ファンの意識に追いつけることができるであろうか。
フェミニズムに媚びる杉作J太郎

『大戦隊ゴーグルファイブ』(1982年)第7話「幽霊になったパパ」より
1986年の男女雇用機会均等法の施行を、フェミニズムにとって勝利だと勘違いしている奴は当時からいた。だが、フェミニズムの真の目標は、矛盾に満ちた現行の社会体制を変革することであり、現行の社会体制をそのままにして女が男並みになることを求めたりすることではない。その「男並みになる」という発想そのものが粉砕対象なのである。
だが、そんな1980年代的な勘違いを、この2015年になって未だに持ち続けている男どもがいるという事実には、さすがに驚きを禁じえなかった。
――今までの時代だと、車は男性が運転して女性が助手席っていうのが通例だったと思うんですが、『シャイダー』では2人別々の車に乗ってるじゃないですか。(中略)女性が助手席から飛び出したっていうのは新しいな〜と思ったんですよ。まずはこの発言の内容自体が完全な見当違い。だいたい1984年の時点でヒロインが車を運転する程度のことで驚くか? 『大戦隊ゴーグルファイブ』(1982年)では、黄島を助手席に座らせてミキが転する場面すらある。
(『宇宙刑事ダイナミックガイドブック』澤井信一郎・森永奈緒美インタビューより。この発言主は杉作J太郎)
しかしそれよりも重要なのは、女が男並みになることを進歩だとか発展だとか決めつける勘違いのほうだ。アニーが車を運転する。その結果としてアニーとシャイダーとの間にどのような関係性が構築されていたか。問題はそこであって、それを論じることなく単に女が車を運転をしたからといって、そんなものは進歩でも退歩でもない。女性の人権なんてハナから興味も持っていなさそうな奴が、口先だけはフェミニズムに対して理解のありそうなことを言って女性の歓心を買おうとし、結果として一層糾弾されるハメになるという場面を、私は1980年代にウンザリするほど見聞き……。
うわあ嫌なことを思い出してしまった。とにかく21世紀にもなってこんなアホな本出すな。
伊上勝の孝行息子

竹中清・井上敏樹『伊上勝評伝』
井上敏樹というのは実はいい人なのではと前から思っていたが、やっぱりいい人のようだ。この本に載っていた、父君である伊上勝氏に関する思い出を綴った文章を読んでいたら、そう思った。
伊上勝氏の偉大さについては今さら述べるまでもあるまい。東映特撮のヒーローの原型を、脚本家として全部一人で作った人である。その超売れっ子がわずか十年ほどの間に才能を枯渇させ何も書けなくなり、酒に溺れて惨めな晩年を過ごすことになったのは、まあ本人に責任がある。売れている間に、自分の作風の幅を広げる努力を何もしなかった(あるいはしたけど実を結ばなかった)からである。
私は時々考える。時代が父を追い越したのか、それとも時代には関係なく父は書けなくなったのか。きっとどちらとも言える。いずれにせよ父は書けなくなったに違いない。ずっと同じ井戸を掘っていてはいずれ水は涸れてしまう。こう井上氏は書く。だが「どちらとも言える」は違う。事実は明らかに後者だ。井上氏によれば、かつてヒーローとは孤独なものであり、一般人にとっては遠くから憧れる対象であった。それが時代とともに変化し、身近で親しみやすい存在となることを要求されるようになっていく。しかし私の見たところ、ヒーロー像が完全に交代したのは1990年代前半頃である。伊上氏が書けなくなったのは1980年頃。明らかに井上氏は、父君を可能な限りかばいたい、という意図を持ちながら書いている。
戦隊シリーズで言えば、曽田博久氏なんてのも明らかにヒーローの孤独さを描く人であった。戦隊って仲間が一杯いるのに孤独なのか、と言われるかもしれない。しかし曽田氏が全共闘の活動家であり、そのスローガンが「連帯を求めて孤立を恐れず」であることを思い起こせば平仄はあっている。
そしてその「大衆にとって遠い存在であるヒーロー」という像に完全に引導を渡したのが、井上氏がメインライターを務めた『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)である。伊上氏はそれを毎週楽しみに見ていたらしい。
自分の息子が自分と同じ職業を選び、自分を乗り越える。これほど父親冥利に尽きることはあるまい。こんなによく出来た、こんなに立派な息子を持ちながら、伊上氏は一体何が不満でアル中になんかになったのだろう。
よっぽど弱い人だったのだろうか。
『ニンニンジャー』と「志」の問題(補足)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「サカユメンでいい夢見よう」(画・たかや健二)
7月7日のエントリへの追記
もし仮に脚本家の仕事が、なんの独創性も要らず、ただただスポンサーやテレビ局やプロデューサーの指示に従って台本に文字を埋めるだけの作業であるならば、それはもはやクリエイターとは呼べない。しかしそれでも最低限の内容を備えた無難な台本を、毎週毎週締め切りを守って仕上げるのであれば、その職人技に敬意を払いたいとは思う。だが、『ニンニンジャー』の下山健人氏はそれすら出来ていないように見える。
白倉伸一郎センセイを筆頭に、仮面ライダーのスタッフは、スーパー戦隊に対して妙に見下すようなことを言う、ということはこのブログでもさんざん言ってきた。つまり、戦隊にはフォーマットというものがある。今年は忍者だ、恐竜だ、侍だ、とお題を与えられ、それをフォーマットに当てはめれば、どんな番組が出来上がるかはほぼ決まる。楽な仕事だ。それに比べて仮面ライダーは……とかなんとか。
しかし仮に戦隊シリーズにそんなフォーマットがあったとして、コンスタントに60点の作品を完成させるのも、決して簡単な仕事ではない。なぜなら、個性を殺すことは個性を生かすことと同じように難しいからである。嘘だと思う人は、『ドラえもん』で時々絵が変になっているコマを見れば良い。藤子・F・不二雄先生が忙しくてアシスタントに代筆させたのである。アシスタントたちは必死に自分のタッチを殺し、藤子・F先生に似せようと必死に描く。それでもやっぱり個性は出てしまう。
もし下山氏が、戦隊のメインライターとして自分がやりたいことなんか何もない、と本気で思っているのであれば、『ニンニンジャー』だってもっと無難にやればいいのだ。60点を確実に保証、とは言わないが、55点くらいなら確実にとれる方法はある。とりあえず主人公に「俺は人を守るために戦うぞ」と言わせておく。過去の戦隊でも、主人公の目的がゴチャゴチャとっちらかってイマイチ何がしたいのか分からなかった作品が、途中でそれをやって一気に話が分かりやすくなったというケースは何度かある。作品名は出さないでおくが。『ニンニンジャー』で、やれラストニンジャの称号がどうこう言っている時点で、下山氏がクリエイターとしての志を完全に捨て去っていないことは明らかである。
もっとも、そんなもの持っていたところで何かの役に立つとも思えんが。
『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(後編)

次のページでは↓

『ドラえもん』「ラジコン大海戦」より
(承前)藤子・F・不二雄は国民学校六年生の時に終戦を迎えた。
物心ついた時から神国日本は不滅と教えこまれ、それに何の疑問も持つことなく育った少年。それがある日を境に突然、大人たちが掌を返すがごとくアメリカ軍に尻尾を振って民主主義バンザイを叫び始めたことが、幼き日の藤本弘少年の心にどんな痕跡を残したかは容易に想像できる。
ウルトラ・スーパー・デラックスマンを筆頭に、藤子・F・不二雄ワールドに出てくる「正義感の強い人間」はまず間違いなくどこか心が歪んでいるのは、このことと無関係ではあるまい。
では藤子・F先生は反戦平和主義者なのであろうか。それも違う。氏の主張は『ドラえもん』の「ラジコン大海戦」に明確である。戦いに敗れ、ずぶ濡れになってトボトボと家路につきながら、つぶやくスネ夫とスネ吉。「戦争は金ばかりかかって、空しいものだなあ」。
ここだけ見るとあたかも反戦のようにも見える。だが次のページに行くと戦いに勝ち潜水艦をゲットしたのび太の満面の笑顔。
「反戦思想なんてのは所詮戦いに負けた奴の言うことだ」。藤子・F先生の心の叫びが聞こえてくるかのようである。
「正義のための戦い」などというものは存在しない。そのことを幼き日に胸に深く刻み込んだ藤子・F先生にしてみれば、「反戦」もまた一つの正義でしかない。
そしてそれは、所詮この世は弱肉強食、泣く子と地頭には勝てぬというニヒリズムとは紙一重のところにある。『のび太の宇宙小戦争』にしたって、必ずしも嫌々書いた作品とばかり決めつけることもできまい。できれば、この話には続編があり、悪の独裁者を倒した後でスネ夫がピリカ星人に帰化してこの星に居続けたいと駄々をこね、やがて疎ましく思ったピリカ星人たちが毒殺を企てる、などという結末を見たかったところではある。もっともチビっ子の読者にとってはそんなもん見せられても困るだけだろうが(何の話か分かりますね)。
勧善懲悪の考えを否定することがかえって勧善懲悪を推し進めることがある。逆もまたしかり。だいたい「勧善懲悪はダメな作品、勧善懲悪でないのは良い作品」という発想の形式そのものが勧善懲悪的ではないか。そしてその逆説を理解できたときに初めて、「『ノンマルトの使者』は勧善懲悪でないからすばらしい」などという決めつけの安易さもまた見えてくる。
『ニンニンジャー』と「志」の問題

僕の本当にやりたいことは、朝のフォーマットでできるわけがない。(『キャラクターランド』Vol.1 『手裏剣戦隊ニンニンジャー』メインライター下山健人インタビュー)「朝」というのはニチアサ(日曜朝に放映されるスーパー戦隊・仮面ライダー)を指しているように思われる。
スーパー戦隊シリーズのメインライターに初めて起用された人が、こういう志の低いことを考えていたとしても、最近の時勢を鑑みれば無理のない話ではある。しかしこういうことを公言したり、それが活字になったりすることを、体面が悪いと判断する人は誰もいなかったのだろうか。
たとえば『仮面ライダー鎧武』のメインライターを務めた虚淵玄氏は、番組終わってから雑誌でインタビューを受けまくりだが、あれはダメ、これはダメと表現規制でがんじがらめの上に玩具スケジュールはギッチギチ、思い通りに筆をふるうことができず随分と悔しい思いをしたであろうことは文面から容易に推察される。もともとは平成仮面ライダー初期のテイストを取り戻したいという意気込みゆえにメインライターを引き受けた人である。プロデューサーの武部直美氏も板挟みで相当苦労したに違いない。それに比べれば、もう最初から「やりたいことは別にありません」と言ってくれる下山氏は、武部氏にとってどれほど有り難く思えたことか。そして、新しいヒーロー像の創出に何の情熱も持つことなく、ただテレビ局やスポンサーの言うことに従って台本に文字を埋めるだけの脚本家が今後ますます重用されていく。
井上敏樹氏は私の尊敬する脚本家の一人であるが、『語ろう! 555 剣 響鬼』で「新しいことにチャレンジして失敗するのは良い。最近の若いもんはチャレンジすらしない」などという内容のことを言っているのには心底ガッカリした。この人も、若い頃は「新しいことにチャレンジするだけなら簡単だ。新しいことにチャレンジした上で成功させて初めて評価される」ぐらいのことは言っていたのではなかろうか。知らんけど。あるいは、あの不遜な態度を売りにしている井上氏にすらこんな弱気なことを吐かせるくらいに、今のニチアサをとりまく状況は閉塞感に満ちているということなのだろうか。
7月13日に追記
名作すぎる『ウルトラセブン』
最初に断っておくと、森次晃嗣氏を批判したいわけではないです。批判するほど詳しくないし。ただ「ひし美ゆり子に対する疑念(後編)」のコメント欄で「森次氏は本当に『ウルトラセブン』に思い入れがあるのだろうか」という内容のことを書いてしまって、これが言葉足らずのために誤解を広める事になってしまっては申し訳ないので、補足しておいたほうがよかろうと思った次第。
そもそも『語ろう! 555 剣 響鬼』という本に森次氏のインタビューが載っているのは、『剣』に天王路という役で出演したからである。しかし質問のほとんどが『セブン』に関係したものである。それ自体変なことではあるが、その中身が妙に模範生的なのが気になったのである。まるで、こういう質問をされたらこう答える、ああいう質問をされたらああ答える、というアンチョコが既にあってそれに従って機械的に答えているかのような。
しかしそれは森次氏が『セブン』に対して思い入れがないのではなく、『セブン』という作品が余りにも名作として今まで語られすぎたがゆえに生じた事態なのかもしれない。「ノンマルトの使者」ならこういう解釈、「第四惑星の悪夢」ならこういう解釈、というのがもう完全に固定されてしまって、新しい解釈なんかもう出す余地がないみたいな雰囲気を、『セブン』という作品について感じるのである。
いや、別にそんなに難しく考えることはなく、単にインタビュアーの谷田俊太郎氏の技術が下手というだけのことかもしれない。インタビューというのは相手の本音を引き出すのが仕事であり、自分の意見をしゃべって相手に同意を求めたりするなど問題外。ちなみに脚本家の上原正三氏は『帰ってきたウルトラマン』の「怪獣使いと少年」について聞かれて「あれはテーマ性がナマで出すぎて自分としては気に入っていない」なんてことをしゃべったりしている。そのことがかえって上原氏のウルトラシリーズに対する思い入れをファンに強く感じさせるのである。
インタビューというのはする方もされる方も「段位」というものがあるんじゃないだろうか。
『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
(承前)「理に落ちる」という言葉がある。『のび太の宇宙小戦争』で、ラストの銃殺寸前からの大逆転を見た時に脳裏に浮かんだのは、まさにそれである。
理屈が通っていて悪いことはないだろう、と言われるかもしれない。しかし冒険活劇である以上、読者は主人公が理屈を超えた活躍をするのを見たいのである。正義と平和を愛する心でもいいし、仲間との信頼の絆でも自分の力を信じる心でも構わない、それが奇跡を呼び起こし、彼我の圧倒的な戦力差をひっくりかえして勝利する。我々は普段の生活では奇跡など滅多に起こらないことを知っている。だからこそフィクションの世界ではカタルシスを感じさせてほしいのである。もちろんやりすぎると、御都合主義という批判を招かざるをえないが。
フィクションには二種類ある。常識を守る物語と、常識を壊す物語である。藤子・F・不二雄の作家としての資質は明らかに前者を向いている。『ドラえもん』でも、のび太はひみつ道具を使って常に失敗をする。パーマン、魔美、左江内氏と、超常の力を持った主人公も決して常識の枠を超えた活躍をすることはない。奇跡の大逆転が起きないのがFワールドの掟である。
この二種類の物語は、どっちが高級でどっちが低級ということはない。ほんとうに良質の作品を作ろうと志す者にとっては、道の険しさはどちらも等しい。だが、現代は量産の時代である。何かヒット作が生まれれば、たちまちシリーズ化され、じっくりとアイディアを練る暇もなく次から次へと作品を作るよう急かされる。派手な注目を浴びて客を呼びやすいのは常識破壊型、作るのが楽なのは常識防御型である。常識は疑うより守るほうがやりやすい。その結果として、見かけは常識破壊型でありながら中身は常識防御型、という作品が巷に氾濫することになる。その欺瞞性の極北が『水戸黄門』であろう。
そして我々が「勧善懲悪なんかくだらない」と言う際にイメージするのは、まさにそのような物語なのではないか。だからといって勧善懲悪を十把ひとからげに否定するのは間違っているし、そのような不毛な認識の上に立って一足飛びに「故郷は地球」「ノンマルトの使者」「怪獣使いと少年」等を持ち上げたところで、それらの作品に対しても失礼なことである。(続く)
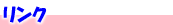
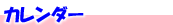
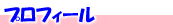
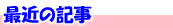
- 逃げ道を確保する雨宮慶太(前編) (07/31)
- 「世代」を特権化したがる人たち (07/29)
- 小谷野敦の本はなぜ売れるのか(後編) (07/27)
- 小谷野敦の本はなぜ売れるのか(中編) (07/25)
- 小谷野敦の本はなぜ売れるのか(前編) (07/23)
- 戦隊における「司令」と「総司令」の区別 (07/21)
- フェミニズムに媚びる杉作J太郎 (07/18)
- 伊上勝の孝行息子 (07/16)
- 『ニンニンジャー』と「志」の問題(補足) (07/13)
- 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(後編) (07/10)
- 『ニンニンジャー』と「志」の問題 (07/07)
- 名作すぎる『ウルトラセブン』 (07/05)
- 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編) (07/02)
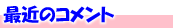
- スーツアクターという難題
⇒ Manju (10/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19)
- スーツアクターという難題
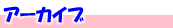
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)