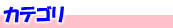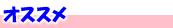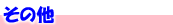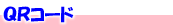特撮ヒーローへの「誇りの強要」(補論)

『東映ヒーロー悪役列伝』(2006年12月30日)
特撮ヒーローへの「誇りの強要」への補論
特撮ヒーロー番組に出演し、誇らしい思い出として持っている人は、当然そのように言う。イベントにも出るしインタビュー記事にもなる。しかし嫌な思い出しか持っていない人も当然いるはずで、そのような人は黙っている。わざわざファンの夢を壊したいと思う人はいない。その結果として、ヒーロー番組に出たらそれを誇らしく思うのが当たり前である、などという勘違いが生まれる。
ところが、「嫌な思い出しかない」ということが、いろいろな偶然が重なって公になることもある。故・曽我町子氏にとっての魔女バンドーラ(『恐竜戦隊ジュウレンジャー』)がそうである。この本に掲載された曽我氏のインタビュー記事は、ヘドリアン女王をはじめとする戦隊悪役への出演について熱く語りながらバンドーラについての言及が一切ない。そして編集部からの追記がある。ちなみにその本の発売時点で曽我氏は故人。
編集部としては、当然この作品についてもうかがい、曽我さんから熱いコメントをいただいたのですが、後日、その内容に関して、ご本人から「話した内容をそのまま載せると一部の関係者の方に迷惑がかかる。かと言って、『ジュウレンジャー』について自分が語るのなら、先日あなた方に話した内容しかない」という旨の連絡を受けました。わざわざこんなこと書くなよとは思うが、書かなければファンから「なぜ触れられていないのか」という問い合わせがうるさいから書いたそうだ。
しかしこんな思わせぶりな書き方をしても、曽我氏が『ジュウレン』出演でどんな不快な思いをしたかなどという話は、ネットで調べれば出てくるわけですよ。ただそのネットの情報だけでは、どの程度の不快さだったのか分からない。両方の情報を組み合わせることによって、もう本気で腹を立てていたということが分かる。
もっともそのネット情報を読む限りにおいては、曽我さんのほうが誤解しているんじゃないかなあ、と思う部分もある。しかし曽我さんも、曽我さんが腹を立てた相手も故人となった今となっては詳しい事情が発掘される可能性は限りなく低い。
もし仮に、『ジュウレンジャー』の良い思い出も悪い思い出もフランクに話せるような風潮があったなら、その過程で曽我さんの誤解が解かれる可能性があったかもしれない(誤解だったとしてだが)。そしてバンドーラを演じて良かったと考えを改める機会を持つことができた可能性もある。もっとも「ファンの夢を壊すな」というのも一つの考えではあるから、どっちがいいと一概に言えない。
藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(前編)

藤子・F・不二雄『21エモン』「あやしい客」より。
最初に断っておくと、藤子・F・不二雄『ドラえもん』の「ぞうとおじさん」や「白ゆりのような女の子」は、児童に戦争体験を伝えるという意味において非常に優れた作品だと私は思っている。そしてそれを読んだ子どもたちが、やがて成長して色々な本を読んで勉強を積み重ね、戦争について更に理解を深めていくのであれば、申し分のないことである。
ところがどうも現実はそうはなっていない。
この国の大人の大多数は、戦争に対する認識が『ドラえもん』のレベルにとどまっているように思われる。
そうなると、藤子F作品における戦争の描かれ方についても、きちんと検討を加えておく必要があるのではないか。もちろん、これはF先生の責任ではない。F先生は『ドラえもん』が大人の鑑賞に堪える作品であるなどと発言したことなど一度もないのだから(多分)。この国が余りにも幼稚なのが悪いのである。
さて、藤子F先生にとって「戦後」とはどのようなものだったのか。
それが最も端的に現れたのは、『21エモン』(1968年)の「あやしい客」(前後編)ではないかと思う。『21エモン』の舞台は2018年のトーキョー。地球連邦政府が樹立され世界から戦争はなくなり、また科学技術の長足の進歩によって人々は極めて便利で快適な生活を営んでいる。まさに夢のような未来世界。だが、裏設定を読んでいると、これはまさしくアメリカの庇護のもとで「平和と繁栄」を謳歌している戦後日本の姿そのものであることが分かる。
裏設定? そんなものがあるの? 『21エモン』の愛読者でも、そう思う人が大多数であろう。一度雑誌に掲載されたっきりで、2010年に『藤子・F・不二雄大全集』で初めて単行本に収録されたとあれば、広く知られていないのも仕方がない。
そしてこの、平和で豊かで、理想そのものに見えるこの世界において、社会体制に不満をもつ人間が登場した唯一の回が「あやしい客」である。つづれ屋に泊まったこの二人連れの客が、新左翼の活動家をモチーフにしていることは一目瞭然。ちなみにこの「あやしい客」も、最初と二度目の単行本化の際には省かれ、三度目でやっと収録された。(続く)
特撮ヒーローへの「誇りの強要」(後編)
(承前) 鈴木美潮のdonna 「赤祭」に戦隊の歴史支えた20人、「ムネアツ」超える感動!(2015年9月4日)についての続き。
今年も「激しい爆発シーンで、1年間の放送期間中に何度も爆風で飛ばされた」「ロープが切れて崖から落ちたのにその事故映像がそのままオンエアで使われた(もちろんDVDにもなっている)」「崖から落ちて肋骨を折ったが撮影はそのまま続行された」などのすさまじいエピソードが飛び出した。この手の、昔はこんなに危険な思いをして撮影をしていたんですよ(それに比べて今は……)、というような自慢話については、素直に感心できないところがある。
もちろん当時の撮影の現場に、いい作品を作りたい、迫力のある画を撮りたいという情熱がみなぎっていたというのは事実であろう。それが彼らを命知らずのアクションへと突き動かしていたとすれば、それ自体は非常に素晴らしいことである。しかし色々調べていていくと、それは単に安全管理に対する意識が低かっただけではないのかという疑念もぬぐえない。
平山亨氏や吉川進氏の回顧録を読んでも、東映という会社自体にジャリ番を差別する雰囲気があり、予算やスタジオの使用順位といった面で不遇を味わっていたという。それで現場だけが高い士気を維持していたという話を額面通りに受け取っていいのかどうか。危険な撮影も、監督に怒鳴られるのが怖くて嫌々やっていたけど、年を取れば若いころの苦労も懐かしく、記憶を美化してしゃべっている人もいるだろう。その一方で辛い思い出は辛い思い出のまま、という人もいるに違いなく、そういう人はイベントに出ることもなければインタビューを受ける機会もない。
実態はどうであったかは、簡単に結論が下せるような問題とは思えない。特撮ヒーロー番組に出たことを、誇りに思う人もいれば、思っていない人もいるはずで、それを一方的に誇りに思うのが正しく思わないのが間違っていると決めつけるような風潮には、はっきりと異議を唱えておきたい。
それはそうと、今の番組が昔ほどの迫力がないのは、命がけでやっていないからだ、という意見がある。しかしその迫力とやらが、スタッフや役者の人命に対する軽視ゆえに生み出されたものであるならば、そんなものはもう見たいとは思わない。CGで我慢する。一生障害が残るような大ケガをした人もいるし、あるいは死人だって出ていたのではないか。表沙汰になっていないだけで(別に事件を隠蔽したというのではなく、単にニュースバリューがなくて)。
補論あり
特撮ヒーローへの「誇りの強要」(前編)
鈴木美潮のdonna 「赤祭」に戦隊の歴史支えた20人、「ムネアツ」超える感動!(2015年9月4日)
まして、ヒーロー番組が「ジャリ番」と呼ばれ、今よりその地位がずっと低かった時代である。きっと、皆さんが胸を張ってヒーローを演じたことを語り出すまでには、長い時間が必要だったと思う。しつこいようだけど、鈴木美潮という人の、特撮ヒーロー番組に出た人は、その出演歴を誇りに思うはずである、思わなければならない、という決めつけは、一体どこに由来するのだろうか。この前出た本でもそうだったが。
私も以前、元特撮ヒーローの俳優がやっている店に行ったことがある。そのことを別に売りにしているわけでもなく、かといって隠しているわけでもない店である。ファンだと言って話しかけたら、普通に喜んでくれた。特撮ヒーローを演じたことを、特に誇らしく思っているわけでもないが、かといって恥と思っているわけでもない。しかし若いころの辛くも楽しい思い出となれば自然に話も弾みがつく。たっぷり話ができて満足だった。
こういうものだろうと思う。
特撮以外の元俳優でも、元スポーツ選手でも元マンガ家でも、事情はみんな同じようなものではないのか。
ネット上では、ヒーロー番組に出た俳優は、ヒーロー番組に出た俳優であることを誇りに思うか恥と思うかのどちらかしかない、と決めつけるような風潮が存在しているようで、イベントに出てこなければ「黒歴史にしている」と速攻でレッテル貼りだ。実際に人とふれあったこともなく、ネット上で人の品定めばかりしている人が、自分の頭で物を考える術をなくしたとしても不思議はないが、しかし鈴木氏は長年イベントを開催し、大勢の特撮番組のスタッフやキャストと交流を持っている人である。それがなんでこういうことになるのだろうか。それとも読売新聞の政治部に入って官邸や自民党の担当に配属されたら、こんなふうになるのだろうか。
コナン・ドイルがシャーロック・ホームズを嫌っていたというのは有名な話ではあるが、しかしそんな事実はホームズファンにとってはどうでもいいことである。同じことはモンゴメリの『赤毛のアン』についても言える。(続く)
仮面ライダーと日本国憲法

白井聡『永続敗戦論』。特に目新しいことが書いてあるわけではないが、こういう本が売れるということは、その程度には日本人の意識も変わりつつある?
ショッカーによって力を与えられた主人公が、その力を使ってショッカーと戦うという『仮面ライダー』の構図は、日本国憲法と似たところがある。
日本国憲法がアメリカによる押しつけ憲法だというのは、いやでも認めざるをえない事実である。井上ひさしや鶴見俊輔といった人たちの本を読むと、学者や知識人は皆そのことを分かっていた。そして分かっていたからこそ、守る価値を見出していたのだった。一言で言えば「敵の武器を奪って使う」。アメリカから与えられた憲法を盾にして、アメリカの言いなりから脱しようという戦略がここにはあった。そのためには、それが元々は敵製の武器だったということ、つまり我々は自力で武器を調達することすらできない情けない国民なのだという屈辱を、国民一人一人が直視する必要があった。しかしその戦略は結局は実を結ばなかった。
現実問題として政治の世界で力を持つためには、選挙で勝たねばならない。難しい話では大衆の理解も得にくいし票にもならず、だからもっと単純明快でわかりやすいスローガンが必要だった。だから護憲政党は、日本国憲法は世界にさきがけて人類の未来を照らす理想をうたったものだとかなんとかキレイ事で主張を塗り固め、その甲斐あって常に国会で三分の一強の議席を占めるほどの勢力は保ち、自民党が対米従属一辺倒に走るのを牽制する程度の役割は務めたものの、結局は政権につくこともなかったし、情勢が変わってアメリカから集団的自衛権を認めるよう本気で迫られれば、ひとたまりもなかったのである。
そしてそれは、敵の力を使って戦うという設定を持った『仮面ライダー』が、早々にテコ入れをされ、明るく単純な勧善懲悪劇へと作風を変化させていく中で大ヒット番組になったという事実とかぶって見える。「同族殺し」「改造人間の悲哀」という重苦しいテーマは、商業作品として人気を得るためには障害にしかならず、かといって石森章太郎先生から授かったテーマを粗略に扱うわけにもいかず。密教顕教の二重構造は解消されぬまま今に至っている。
あるいは平成仮面ライダーというのは、それを解消しようという試みだったのだろうか?
なぜ元ヒーローのブログは恥ずかしいのか
先日、何気なくある戦隊ヒーロー俳優の名前で検索をかけていたら、なんかものすごく恥ずかしい物を見つけてしまった。
佐村河内守・交響曲1番「HIROSHIMA」(2012年11月10日)佐村河内守氏のゴーストライター騒動は2014年2月である。その時、それまで佐村河内氏の音楽の素晴らしさを称えるような記事を載せていたブログは、当該記事を一斉に抹消した。まるで、自分は今まで佐村河内氏の音楽を称えたことなど一度もありませんよ、とでも言うかのように。それはそれで卑怯な態度だとは思うが、しかし記事を上げたことを忘れ、放ったらかしにする人もいることを思えばまだ随分とマシという気がする。
それにしても、かつてヒーローを演じたことのある俳優がやっているブログやツイッターやフェイスブック等々は、なぜああも恥ずかしいのだろうか。
現在俳優を続けている人はいい。今は別の職業についたり、何か社会的な活動をやっていて、その内容を報告するという明確な目的を持っているブログも同様である。それ以外の人のやっているブログは、恥ずかしいエントリを上げたから恥ずかしいとかいうのではなく、もう存在そのものが恥ずかしい。
いや、そもそもブログとはそういうものであって、元ヒーローのブログが特に恥ずかしいわけではない、という反論があろう。昼飯は何を食ったとかいう、どうでもいいような身辺雑記を延々と続けたり、普段から本なんか全然読んでいないくせに政治について語ったりするブログなんてのがよくある。それを無名の人間がやっているのであれば、別に恥ずかしくはない。平凡な人間が、自分は昼飯に何を食ったかという情報すらニュースバリューが生じるほどのVIPだと勘違いする。単によくある話である。
しかし元ヒーローの場合、俳優業を引退して何年経とうが、ファンにとっては雲の上の存在である。もちろんそんな幻想につきあう義務があるわけではない。自分は今は普通に社会人やってます、という態度をとるならとるで構わない。そして、そういう人のブログの中味が身辺雑記や床屋政談だったりする。
カッコいい人間であることを求められている人が、カッコいい人間であろうと努め、結果それが傍目に全然カッコよくない。この三拍子がそろうことは滅多にあるものではない。
パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
(承前)インターネットをやっていると、最近のスーパー戦隊はダメだ、昔はよかった、と言っている人と、いやそんなことはない、今のほうが面白い、と言っている人との間で不毛な罵り合いが行なわれている場に容易に出くわす。「不毛」と書いたのは、両者とも議論の前提が共有されていないということが分かっておらず、自分にとっての常識を相手に押し付けているだけだからである。
それは何かというと、「使命の重さ」の描き方、この一点に集約されるように思われる。
大勢の人々の命のかかった戦いである。主人公たちは重圧を感じてしかるべきであり、それが最近の作品からは感じられない、という点については両者とも異論あるとは思われない。意見が別れるのは、昔に比べて脚本や演出や俳優の技量が落ちたためにそうなっているのか、それとも描く必要性が昔に比べてなくなったから描かれなくなっただけなのか、という点である。
そもそもヒーロー番組の根底にあるのは「暴力」である。ヒーローが暴力をふるうのも、大勢の人々の命を救いたいという思いがあるからこそ正当化されうるのであって、それをないがしろにするということは、単に正義の名のもとに強いものが弱いものをやっつける快感を子どもたちに植えつけるだけの行為にすぎない。これはもっともな批判である。それに対して、だいたい子どもたちは使命の重責に苦しむヒーローを見たいとは思わない、という反論がある。実際、それは視聴率によって裏づけられている。
つまりここには子供番組とはいかにあるべきか、という古くて新しい問題が横たわっている。「大人が子どもに見せたがるもの」か、それとも「子ども自身が見たがるもの」か、という。
どっちが正しいかについて、容易に結論の出せる問題ではない。さしあたって必要なのは、意見の違いがある、ということを認識することである。不毛な議論をするよりは、実りのある議論をしたほうがよい。ただ、議論が起こるということ自体は、特撮ヒーロー番組がいかに人々から愛される存在であるかの証であるから、悪いことではない。いくつになっても、ヒーロー番組は心の故郷なのだ。同じ子ども向けの作品である、『ドラえもん』と比べてみると、そのことがより一層痛感できる(結局言いたかったのはそれかい)。
「戦隊初の女性監督」という記事を批判する(後編)
(承前)もとはといえばこの『福島民友』の記事は、今年の6月にスーパー戦隊シリーズ史上において初めて女性がメガホンをとった作品(『烈車戦隊トッキュウジャー』OV版)が発売になったことを受けて書かれたものである。その荒川史絵監督は福島県出身者であり、長年の夢をかなえたという、それ自体はとても素晴らしいことである。しかしそれと、スーパー戦隊シリーズにおける女戦士の台頭、および戦後日本における女性の社会進出、この三つを無理矢理結びつけて一つの記事にしたものだから、訳の分からない記事が出来上がってしまった。
ところでこの記事が示唆(断定ではない)するように、女性であることを理由に助監督から監督への昇進が遅れたという事実はあったのだろうか。
まあ多分あったと思う。というか、なかったら逆に不自然だろう。というのは最近の戦隊にしろ仮面ライダーにしろ、正真正銘「三十分の玩具CM」になりつつあるからである。
このブログで何度も書いていることだが、昔は特撮ヒーロー番組は作品であると同時に商品であった。今は単なる商品である。いい作品・おもしろい作品を作ることは二の次で、見ている子どもたちに玩具を買いたい気持ちを喚起させることが最も重要な事になっている。これは私の憶測ではない。雑誌のインタビュー記事でも、みんな結構本音をポロポロ漏らす。玩具を買うのは圧倒的に男児であり、そして過去に男児であったことのある人間のほうが、そのような番組作りにおいて圧倒的に有利であるのは言うまでもない。特撮ヒーロー番組の世界では、監督とは違って脚本家は昔から女性もいた。しかしそれも、玩具を売る以外にも大切なことがあると考えられていた時代であったればこそだ。今後はどうなることやら。
あるいは今後、子供たちに玩具を買いたい気にさせる映像を作る手法をマスターし、男に劣らぬ(あるいは上回る)手腕の持ち主と評価される女監督が続々と出てくるかもしれない。そしてテレビ本編のローテに入ってバリバリ活躍するようになったとして、それが果たして戦隊シリーズにとって祝福すべき未来と言えるのかどうか。
パーマンをやることは義務なのか(その4)
(承前)「等身大のヒーロー」と聞けば、ああこれは『パーマン』のテーマだなと藤子・F・不二雄ファンなら思うところであろうが、実はこれ1990年代半ばのスーパー戦隊(『激走戦隊カーレンジャー』や『電磁戦隊メガレンジャー』等)のテーマでもあった。
ただし『パーマン』が正真正銘の等身大であったのに対して、戦隊の場合はじっくり見れば決して視聴者にとって等身大の存在であったとはいえない。
メガレンジャーになる五人は高校生である。そして彼らにとって最も関心があるのは、地球の平和とか人類の未来とかいうことよりも、自分たちの高校生活を充実したものにすることである。つまり勉強とか、仲間との友情とか、文化祭とか、そしてその一環として、メガレンジャーとしての活動が位置づけられている。
しかしそれは決して、それ以前の戦隊ヒーローに比べて彼らが任務に対して真面目さに欠けているということを意味しない。学園生活を充実させるためにこそ、メガレンジャーとしての活動に真剣に打ち込む必要があるのだ。そして、人類は果たして守るに値する存在なのか、などといった困難な問題とも真正面からぶつからざるをえなくなる。それが戦隊史上随一とさえいえる、最終盤の展開の重苦しさである。
一見彼らはフツーの高校生のように見える。しかし何十億人もの人類の運命を背負って戦っているという事実が厳然として存在している以上、高い意識を持った戦士へと成長しないわけにはいかない。厳密な意味で「視聴者と等身大」であることなど不可能である。狭い世界(身近な人間関係)と広い世界(地球の平和)との関係が、いちおう切断されている『パーマン』の世界とは違って、戦隊ではそれは切り離すことはできない。
ところがどうも最近の戦隊を見ていると、スタッフは本当の意味で等身大ヒーローを作ろうとしているのではないか、という気がしてならない。それこそ「鵜の真似をする烏」なのだが、そう考えた時、たとえば今年の『手裏剣戦隊ニンニンジャー』を面白いと言っている人もいれば、つまらないと言っている人もいる、その両方の気持ちが理解できるはずだ。
なんかダラダラ書いてきたが、いよいよ結論が見えてきたような感じがする。(続く)
「戦隊初の女性監督」という記事を批判する(前編)

『福島民友』2015年8月21日の「回想の戦後70年 漫画・特撮編(5) ヒロイン最前線へ 戦隊史上初の女性監督」(ウェブ版は図表省略)という記事がひどい。今までも女性の社会進出と戦隊ヒロインとを安直に結びつけるような論考は何度も読んだことがあるが、これほどひどい記事は読んだことがない。
日本における管理職に占める女性の割合は何%で、女性国会議員の比率は何%で、これは先進国中最下位であって、これを引き上げる目標を政府が掲げたなどというニュースを、我々はテレビや新聞でよく目や耳にする。これはフェミニズムに基づいた政策であると思い込んでいる人も多いであろう。とんでもないことだ。これほど反フェミニズム的な主張もないのである。もっとも、当のフェミニストでそういう勘違いをしている人も多いし、そしてそういう人が大学で偉い職に就いて、マスコミで派手に露出活動をしていたりするから、一般大衆が誤解するのも無理もないのだが。
だいたい先進国中最下位だからダメ、という考えは、西欧文明こそが世界で最も優れたものであり、日本も西欧みたいになってこそ国際社会で認められるのだという植民地根性そのものである。
フェミニズムは救済思想ではない。現在の男中心社会では、女性は不利な立場に置かれている、というそこまではよい。だからそこから解放されるために、女性はどのような生き方をすればいいかを教えてあげます――ってふざけんな! それは単に奴隷主から解放された奴隷が、新たな奴隷主を求めているのと同じだぞ。
揺籃期のスーパー戦隊シリーズのヒロインたちの誰も彼も魅力的なのは、自分はどのような戦い方をしたらいいのか、教えてくれる人など誰もいなかったからだ。自分の進むべき道を指し示すことができるのは自分だけだったからだ。そしてシリーズが安定して続き、戦隊ヒロインの模範像が確立されるや急激に魅力を減らしていく。
この『福島民友』の記事では、戦隊シリーズ38作品における女性の比率は26.8%であって、安倍政権の掲げる女性管理職比率30%という目標値に肉薄していてヨロシイという。自民党がそんな政策を掲げるのは、女性を労働力として組み込むことによって現行の体制を強化するためだ。こんな記事を書いたのはどこのどいつだと思ったら、また鈴木美潮氏が噛んでいるのか。って『福島民友』、読売の子会社なのかい。(続く)
パーマンをやることは義務なのか(その3)

藤子・F・不二雄『モジャ公』「ナイナイ星のかたきうち」。仲間が命を狙われているってのにこの態度。これで人気が出るわけがないだろ……。
(承前)『ドラえもん』にしろ『パーマン』にしろ、藤子・F・不二雄の児童マンガを大人になってから読んで違和感を感じるのは「責任感」というものの描き方である。
大きな力を持つ者は、大きな責任もまた背負う。その大きな力をふるうことによって、大勢の人々の運命を救うこともできるし、あるいは破滅に導くこともできるからである。にもかかわらず、ドラえもんやパーマンたちはなぜ重圧に押しつぶされそうにならないのだろうか。ドラえもんの四次元ポケットの中には、それこそ世界の運命を左右しうる力を持った道具が満載であるにもかかわらず。
藤子・F・不二雄の最も得意とするのは、小学生の日常生活という「狭い世界」を舞台にした日常ギャグマンガであり、『オバケのQ太郎』(1964年〜)が大ヒットして以来、そのジャンルで次々と名作をものにしてきた。ところがマンガ家というもの、「好き」と「上手」は一致するとは限らないようで、本当に描きたかったのは、宇宙や未来を舞台にして活躍する冒険活劇だったらしい。『モジャ公』という、作者の大のお気に入り作品は、不人気ゆえに一年ももたずに打ち切られている。
それでも作者は未練があったのだろうか、『ドラえもん』でも時々妙にスケールの大きい「広い世界」を舞台にした話が描かれることがある。しかしキャラクターは普段通り、「狭い世界」を舞台にした時の感覚そのままに動くから、色々変な所が出てくる。長編だとその傾向はさらに著しい。
ただしそれは結果的に『ドラえもん』の長編映画の人気向上には貢献したのではないか。子どもたちは、大きな力をふるって大活躍するヒーローに憧れはするが、その上で、大きな力を持つ者としての責任を背負わされるのはイヤなのである。そういう虫のいい願望を、『ドラえもん』の映画は充足させてくれる。そしてそれは大人が見たところで何の感動ももたらされることはない。
とはいっても『ドラえもん』は大人の鑑賞に堪える作品であるべきだなど思っている人などいるとは思えないから、別にそれはいい。しかし、スーパー戦隊シリーズがそれでは困るのである。(続く)
パーマンをやることは義務なのか(その2)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「ぞうとおじさん」。このコマだけは大人になってから読んでもじわじわくる。
(承前)いちおうここはスーパー戦隊のブログである。それがなぜ最近藤子・F・不二雄先生のマンガの話ばっかりしているかというと、それが「子ども向け作品とはどうあるべきか」という問題について考える際の、格好の補助線になると思うからであって、最後はスーパー戦隊の話に着地させる予定である。
子ども向け作品を作るにあたっては二つの立場がある。一つは、子どもが喜びさえすればそれでいい、というもの。もう一つは、子どもが喜ぶのは当然として、その子どもが成長し大人になってもなお心に訴えかけるものがあるような作品であるべきだ、というもの。どっちが正しいかを性急に決めるつもりはないのだが、ただ伝統的には特撮ヒーロー物というのは後者でずっとやってきたわけだし、最近になって前者の立場が大きくなってきたことに対する反発の声が上がるのは当然であろう。その二つの異なる考えが存在しているということを、まず理解しておく必要がある。
さて、『ドラえもん』の「ぞうとおじさん」もまた、大人になってから読み返すと非常に違和感を感じる話である。
なぜドラえもんとのび太はゾウ一匹救って大満足なのだろうか。
タイムマシンを使って過去を改変するなどという行為が許されるのであれば、なぜ第二次世界大戦の勃発そのものを防がないのか。大きな改変は許されないが、小さな改変は許されるという話なのだろうか。だったら、同じ動物園のトラやライオンもついでに救おうと思わなかったのか。それで大して手間が増えるとも思えない。戦中に殺処分された動物園の生き物は、他にもたくさんいたということを知らぬはずはあるまい。
タイムパラドックスがどうのこうのという、SF設定のまずさは今はとりあえず棚に上げておく。問題にしたいのはドラえもんとのび太の心である。ゾウはかわいい動物だから救わなければならないが、トラやライオンなんか別に殺されたところでどうでもいいという考えのもとにドラえもんやのび太は行動したというのは紛れもない事実である。そしてそれが心あたたまる感動的な物語として、この国の子どもたちによって読み継がれてきたという事実を、一体どのように考えたらいいのか?(続く)
パーマンをやることは義務なのか(その1)

「反面教師としての『ドラえもん』」からの続き
「正義のために戦う」ということについて、藤子・F・不二雄先生はやっぱりよく分かっていなかったのではないか――ということを感じさせるのが、『パーマン』の「パーマンはつらいよ」という話である。
みつ夫にとってパーマンの活動が過剰負担になっているというのが話の発端である(負担軽減のためにコピーロボットがあるのだが、それでも追いつかない)。だから辞めたいとスーパーマンに直訴する。最後には翻意しパーマンの活動を続けることを決心するラストシーンは、なんか美談っぽくまとめてはあるものの、どうもこれは作者がこの問題について徹底的に突き詰めて考えることを放棄した結果としか思えない。
パーマンは常人の6600倍のパワーを持つ。そのような力を持ちながら、なぜ当時苛烈さを増していたベトナム戦争を終わらせるために力をふるわなかったのだろうか。
外国のことなんか知ったことではないのかもしれない。しかし国内に限っても、事故や犯罪や自然災害が起きて多くの人々が死んだり傷ついたりしない日など一日もない。パーマンが救った人命など、パーマンが救えなかった人命に比べればほんのわずかだ。その中には、学校なんか行かず、パーマンが駆けつけておれば助かった人命もたくさんあっただろう。その事実に思いを馳せ、みつ夫が心を痛めるなどというシーンは、決して作中に出てこない。
『パーマン』とはそういう話なのである。別に人類を救うとか世の中を良くするとか地上に平和をもたらすとかのために戦っているのではない。自分のできる範囲内で頑張ろう。それが一番大事なことなのだ。そういう話なのである。
だったら辞めたくなったら辞めればいいではないか。
パーマンの活動が過剰負担だというのなら、少しくらいサボっても、責められるいわれなんかないはずである。そのせいで何千人の人命が失われたとして、なんで今さらそんなことが問題になるのか。なんでこの回に限って唐突に、「大きな力を持てる者の義務」みたいな話が出てくるのか?
もともと藤子F先生は児童マンガ一筋の人である。だから分相応に、たわいのない話だけ描いていればよかったのだ。それを何を勘違いしたのか「ヒーローの責任」みたいな深刻なテーマを作品に盛り込もうとし、結果として墓穴を掘った――と言っていいのだろうか?(続く)
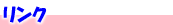
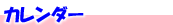
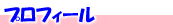
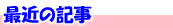
- 特撮ヒーローへの「誇りの強要」(補論) (09/29)
- 藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(前編) (09/26)
- 特撮ヒーローへの「誇りの強要」(後編) (09/24)
- 特撮ヒーローへの「誇りの強要」(前編) (09/21)
- 仮面ライダーと日本国憲法 (09/18)
- なぜ元ヒーローのブログは恥ずかしいのか (09/16)
- パーマンをやることは義務なのか(その5=完結) (09/14)
- 「戦隊初の女性監督」という記事を批判する(後編) (09/12)
- パーマンをやることは義務なのか(その4) (09/10)
- 「戦隊初の女性監督」という記事を批判する(前編) (09/07)
- パーマンをやることは義務なのか(その3) (09/05)
- パーマンをやることは義務なのか(その2) (09/03)
- パーマンをやることは義務なのか(その1) (09/01)
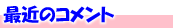
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ percetakan jakarta (04/20)
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
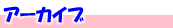
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)