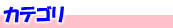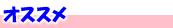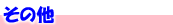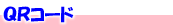『ウルトラマンメビウス』の大迷惑
私自身はウルトラシリーズのファンではないし、ウルトラシリーズが何をやろうが文句をつける筋合いはない。ただ、『ウルトラマンメビウス』(2006年)を感動的ともてはやすような風潮が、戦隊シリーズにまで伝播してきたりしたら大変なことになる。両シリーズの土壌の違いを無視して同じようなことをやったら無残な結果になることは目に見えていると、注意を促しておいたほうがいいのだろうか。あまり気の進まぬことではあるが。
『メビウス』の中で特に話題になったのは、『A』と『80』に関するエピソードのようだ。この二作品に共通しているのは、当時「投げっぱなし」をやったという点である。『A』では南夕子、『80』では教師設定。目先の数字、つまり視聴率とか商品売り上げに目を奪われ、小さなファンたちの心を踏みにじった。その投げっぱなしにした設定を回収し、きちんとした決着をつけ、ファンは感涙にむせんだ――どうもそういうことらしい。過ちは償わないよりも償ったほうがいい。しかしだったら最初から過ちをしなければ、もっとよかったはずだ。
その点戦隊シリーズは、投げっぱなしというのは余りやらない。ファンの思い入れを大切にしないという点では、東映だって決して人後に落ちないはずだが、なぜか最終回の決着だけはきちんとつけることが多い。きれいに終わった話には、後日譚は作れない。無理して作っても蛇足になることは確定的だし、それでもなんとか頑張って、作品に対する愛情と優秀な技量を持ったスタッフをかき集めて全力投球したところで自ずと限界はある。
それにしても、円谷プロだって別に改悛したわけではないだろう。商売の都合で状況によってクルクル方針を変えているだけで、ファンもよくこんな筋の通らない掌返しを許す気になれるな。その「おおらかさ」こそがウルトラファンのいいところなのだ、と言えば聞こえはいいが、それが頑固さとか、筋を通すことを軽蔑する風潮にもつながっているんじゃないの。そしてそれは、篠田三郎氏を大した根拠もなく裏切り者呼ばわりする人たちが、決して多数派ではないにせよ根強く存在していることと、無関係ではないような気もするけどね。
岸祐二『ゴーカイジャー』出演の謎

『海賊戦隊ゴーカイジャー』では戦隊OB・OGがドカドカ出てきたわけだが、本当はああいうことはやりたくなかったらしい、という噂があって、根拠をずっと調べていたのだが、どうやら『東映ヒーローMAX』vol.38(2011.9)に掲載された宇都宮孝明プロデューサーのインタビュー記事が元のようだ。ところがこの記事、どうも変なところが多い。
どうしてこうなったのか、あまり思い出せないんですけどね(笑)。まぁ、最初にマジレッドの橋本(淳)くんが出てくれることになって、じゃあ近年の戦隊についてはゲストで出てもらいましょう、と。デカレンジャー、ゲキレンジャー、ガオレンジャーあたりがその流れですね。ところが、カーレンジャーの岸(祐二)くんも出てくれそうだ、ということで、そのへんから、解釈が広がっていったんです。「思い出せない」って、それはないだろう。
テレビ番組では、作ってる最中に予定が変更になったりすることがある。トラブルが生じて代役を立てざるをえなくなったとか、また単にプロデューサーの気まぐれのこともある。それが大ヒットになるケースも過去にないわけではない。最も有名な例は、もちろん初代『仮面ライダー』における藤岡弘、氏の怪我だ。しかし、そんなのは十に一つもあればいいほうで、急激な予定変更は、ほぼ確実に制作者とって不本意な出来ばえに終わる。数少ない成功例が伝説化し人々の話題にのぼり、失敗例は目立たず忘れ去られる。ノストラダムスの予言的中率が99%とか言われる現象と同じだ。
もし『ゴーカイジャー』も予定の変更があったのなら、それはかなり重々しい雰囲気のなかで決断が下されたはずであって、「思い出せない」わけがなかろう。レジェンド大量出演のしわ寄せを受けて、本当はやりたかったのにやれなくなったこともあったはずだ。この手のインタビューで「思い出せない」というのは明らかに「答えられない」を意味する。しかし本当にファンに対してオープンにできない裏事情があるのであれば、そんなもん編集の段階で質問自体消しておくべきだ。
さらに訳が分からないのは、岸祐二氏。制作スタッフは岸氏に出てほしいわけでは全然ないにもかかわらず、オファー出したということなのか? それとも岸氏が「なんで俺を出さないんだ」とスタッフに凄んで詰め寄って、無理矢理出演を要求でもしたんだろうか。それはそれで考えられない話だが。
意味不明なことが多すぎる。継続して調査する必要があるのだろうか。いずれにせよ、『ゴーカイジャー』はスタッフが心から楽しんで作っているのではないというのは最初から見え見えだったけどさ。
革命作になりそこねた『ダイレンジャー』
白倉伸一郎氏が常々スーパー戦隊シリーズについて見下すような発言を繰り返していることと、氏が戦隊シリーズのプロデューサー(当然サブだが)を『恐竜戦隊ジュウレンジャー』(1992年)と『五星戦隊ダイレンジャー』(1993年)の二作だけしか務めなかったということは、無関係ではないように思われる。
この頃は戦隊シリーズ四十年の歴史の中で、最も守りに入っていた時期といえる。白倉氏は「正義とは何か」「ヒーローは何のために戦うのか」という問題について特に深い関心を持っているプロデューサーである。『ジュウレン』はもともと無難さを目指した作品だからいいとして、『ダイレン』は特撮ヒーロー物の歴史に革命を起こす可能性を秘めながら、結局は無難に終わった作品であり、若き日の白倉氏がその体験を元に「戦隊では俺のやりたいことはできない」と心に刻んだとしても無理もない。
その『ダイレン』が秘めていた可能性とは何か。
結局のところ嘉挧は嘘をついていたわけだ。「人類を守れるのはお前たち五人しかいない」とか言っていたが、実は嘉挧にとってはゴーマに戦いを止めさせるための複数のプランを練っていた。そして他の手段のメドが立てば、ダイレンジャーなんかいつでも解散する予定だった。だから第45話でそれが露見した際、五人は改めて「自分たちはなぜ戦わねばならないのか」という問いがつきつけられたはずだった。自分たちを導いてくれる指導者もなければ、既成品の理念もない。戦いを継続するにせよ解散するにせよ、あくまでも自分たちの主体性を賭けて決断を下さなくてはならなかったはずだ。
その問題に真正面からぶつかっていれば、『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)が切り開いた新境地の、そのさらに先を行くものになっていたに違いない。
ところが五人は、俺たちはどうしたらいいんだあ、とオロオロするだけ。
スーパー戦隊シリーズがその問題について格闘するのは、結局『未来戦隊タイムレンジャー』(2000年)まで先送りになる。といってもそれは、白倉伸一郎センセイが初めて平成仮面ライダーのプロデューサーを務める、一年前のことになりますが。
鈴木美潮という特オタ女の勘違い(補論)
8月14日の記事への補論
鈴木美潮『ヒーローたちの戦いは報われたか』は、論ずるに値する中味など何もない本ではあるが、第七章「ヒロイン、前線に立つ」については少しだけ引っかかることがあった。
しかし、この「紅一点」モデルの定着は罪でもあった。戦隊などで女が一人だけ入っていることについて何か言いたいらしいのだが、そもそもモモレンジャーに対する「男並みに働く女」という認識自体が恐ろしくステロタイプである上に、驚いたことに、この筆者は自分のことをモモレンジャーに重ね合わせているらしい。
男並みに働くとができるうえに女らしさも兼ね備えているスーパーウーマンしか、男性と平等に働くことはできない、という誤った固定観念を、筆者を含め多くの女子の胸に刻んでしまったからだ。
アメリカの大学に入って修士号を取得、読売新聞社に入社して政治部記者としてエリートコースを歩み続け現在はメディア局編集委員。うらやむべき経歴である。男社会の中で「男並みに働く女」であろうと必死に頑張ってきた人なんだろうなというのは容易に想像がつく。そして男社会に馴化適応していく中で、自分というものを失っていったことについても。政治部記者として、なにかユニークな記事を執筆して注目されたとか、スクープをものにしたとか、そういう話はなさそうだし。
それは仕事の上のことだけではない。自分の大好きな(はずの)特撮ヒーローについての本を出したら、それは既に今まで特撮ファンであればどこかで見聞きしたようなことのツギハギしかない本の一丁上がり。著者の独自視点は何一つない。特撮ファンの世界自体が男社会なのだから、確かに平仄はあっている。
「女の特オタなんてのは、イケメン俳優の顔しか見ていない」ということを言う人が時々いる。そういう人たちは、こういう「名誉男性」が書いた本についてはどういう評価を下すのだろう?
ちなみにこの本のこの箇所、竹信三恵子『女性を活用する国、しない国』を参考にしたらしい。しかしこれは日本社会の構造を分析した本だ。それを特撮ヒーロー番組に機械的に当てはめる奴があるか。耳学問ここに極まれりだ。ちなみに竹信氏というのも新聞記者。朝日だけど。
反面教師としての『ドラえもん』(その4=完結)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「正義のみかたセルフ仮面」。正義のヒーロー「あらわし仮面」の活躍をテレビで見て興奮するのび太(六年生)。
(承前)七十年前に日本が大東亜戦争に敗北して終わった時、その反省は国内の世論に二種類の潮流を生んだ。
一つは、もう二度とこのような誤った戦争はするまいという誓い。
もう一つは、もう二度と戦争はするまいという誓い。
もちろん理論的に正しいのは前者である。スーパー戦隊や仮面ライダーも当然こちらの側に立った。ただ、正しい戦争などありえない、今後日本という国は一切の戦争を拒否する、という考えも容易に否定できるわけではない。徹底すればそれも一つの信念である。国民学校六年生で終戦を迎えた藤子・F・不二雄先生もまた後者の立場に立つ者であったことは、その作品の傾向から判断してまず間違いないと思われる。
だが結局それも徹底されることはなかった。1980年に『のび太の恐竜』劇場公開。成功への野心に目がくらみ、作家としての魂を捨てたF先生は、とうとう悪者をやっつける話に手を染めた。一度そこに手を出してしまった以上、もはや後戻りはできない。以後ドラえもんたちが正義の拳を悪者どもの上にふるい続ける話を続けざるをえなくなった。ペンを手に机に突っ伏して死ぬその日まで。
「あらわし仮面」をバカにしていたドラえもんは、自分が同じことをすることになったことを、どう思っていたのだろうか。
そしてそれは日本の戦後の平和運動が常に負け続け、ずるずると後退戦を強いられてきた歴史と重なり合う。
もちろん戦争はしないにこしたことはない。だからといって実際に戦争が起きた時のことを考えずに済ますことはできない。普段から常に平和とはなにか、正義とはなにかという問題について真剣に考えておくことは必要であって、スーパー戦隊も仮面ライダーもその通りにやってきた。「現実に目を向けない理想主義者」は、現実に戦争の可能性が目前に迫ったら何をどうしていいのか分からなくなる。そして目の前にエサをぶら下げられるや、いとも簡単に「理想に目を向けない現実主義者」に豹変する。
『ドラえもん』の話をするつもりが、なんでまたこんな話になったんだろう。別に安保法制の話なんかする気なんか全然なかったんだけど。
「パーマンをやることは義務なのか」に続く
反面教師としての『ドラえもん』(その3)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「ぼく、桃太郎のなんなのさ」 鬼退治に来たはずのドラえもんたちは意外な真実を知る。
(承前)「桃太郎」に題材を得た創作作品は昔から数限りなくあるが、実は鬼のほうが被害者であり、村人のほうが狭量陰険な加害者であったなどという発想を持ち込んだ人は他にいただろうか。『ドラえもん』の「ぼく、桃太郎のなんなのさ」は、まぎれもなく藤子・F・不二雄先生が不世出の大天才であることの証となる作品である。
しかしその天才の輝きが大長編において発揮されたことはただの一度もなかった。
大長編ではだいたい中盤になって「いいもん」と「悪いもん」が出てくる。そして悪いもんをやっつける話になる。しかしその悪いもんは本当に悪い人たちなのか? 彼らは一体どのような出自を持ち、どのような理念に基づいて行動しているのか、何も明らかにならない。たいていの場合、いいもんの方がドラえもんたちに先に接触する。「○○人は悪いやつらなんだ」「○○人さえやっつければ、世の中に平和が取り戻されるんだ」。ドラえもんたちはその言い分を鵜呑みにし、○○人をやっつけ、最後は英雄気取りで元の日常生活へと戻ってゆく。本当にそれで平和が戻ったのかどうか、確認することもなく。
それは子ども向け作品としては正しい態度である。
その点、スーパー戦隊や仮面ライダーのほうが異常なのかもしれない。
もちろん、『ドラえもん』みたいな話がないわけではない。しかしそんな作品を作れば必ず批判される。「どうせ子ども向けなんだから」という擁護は通用しない。むしろ、子ども向けだからこそ疎かにするなと言われるくらいだ。戦隊シリーズでは、悪役というものを登場させる時、なぜ彼らが悪なのか、具体的にどのような悪いことをしているのかについての説明を省くことなど絶対にあってはならないことである。少なくとも建前では。それをやれば、単に正義の名を借りて強い奴が弱い奴をやっつけるだけの話になってしまうからである。
同じ子ども向け作品でありながら、この差は一体どこから出てくるのだろう。
結局は、藤子・F・不二雄という天才をもってしても、戦後日本の絶対平和主義という枠組みから逃れることはできなかったということなのだろうか。なんか話がどんどん大きくなってきた。まとまるんだろうか。(続く)
鈴木美潮という特オタ女の勘違い

鈴木美潮『ヒーローたちの戦いは報われたか』 オビの推薦文には藤岡弘、、佐々木剛、宮内洋、水木一郎の名前が並ぶ
書き手の「熱」というものを、これほど感じさせない特撮本というのも珍しい。
よく調べてあるなあとは思う。作品についてもその時代背景についても。ただしそれだけの本。
一例だけ挙げると、p.56には仮面ライダーがなぜ正義のために戦うヒーローではないのかについての分析が載っている。おい、仮面ライダーが劇中で「正義」という言葉を使いまくり、挿入歌でも歌詞に「正義」が頻繁に出てくることを知らんのか。
仮面ライダーが戦うのは正義のためではない、というのは平山亨プロデューサーが生前常々言っていたことである。インタビュイーは常に本当のことを言うとは限らない。その発言の中から何が真実で何が嘘かを見極める目が必要なのだ。言われたことをそのまま受け取る奴があるか。よくこんなんで政治部の新聞記者が務まるな、と思ったら、読売だった。読売なら仕方ないか。
自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で感じたことを自分の言葉で綴った本ではない。作品に関する分析も、その背景にある社会情勢に対する考察も、すべてどこかからの受け売りばかり。
なんでこんな本が出たのだろう?
逆のパターンはよくある。事実関係については間違いだらけなのだが、筆者の特撮に対する熱い思い入れがほとばしっている本。そういう本は少なくとも読んでて退屈はしない。この本はひたすら退屈なだけだ。
おそらく、この著者が女性であるということと無関係ではないと思われる。
特撮オタクにとって女性は稀少である。だからイベントなんかの場でさんざん「美潮ちゃん、そんなことよく知っているね」「美潮ちゃん、よくそんなことに気がついたね」などとチヤホヤされてきたことは容易に想像がつく。それはもちろん言っている方は「女の子にしては」という前提つきなのだが、言われた方は、自分が本当に一家言の持ち主としてみんなから認められたと勘違い、その結果がこの本なのだろう。
特撮界ではいまだに、女にゃ分からぬ男の世界、という風潮が根強くある。作品の作り手の側からも、女性蔑視的な失言が途絶えないのはそういうことだ。この本が、そのような特撮界の偏見を一層助長することにならないことを願う。
8月21日に補論
反面教師としての『ドラえもん』(その2)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「恐竜ハンター」より。未来の世界で流行っている「おもしろいスポーツ」。狩った恐竜はペットにする。
(承前)大長編第一作「のび太の恐竜」を子供の頃に見て、その懐かしい思い出を大人になってからも持ち続けている、というだけの人については別に何か言いたいとは思わない。だが大人になってからこの作品を読んで感動したなどと言っている人とは、絶対にお近づきになりたくないと思う。
ピー助は生まれた時から人間に育てられ、自力で餌をとったことはない。それをもうこれ以上育てられなくなったといって、白亜紀に置きざりにされたのでは、常識的に考えて生きていけるわけないだろう。
のび太のやったことは、飽きたからペットを捨てる人間の行為と何が違うのか。
元はといえば、のび太がピー助を飼い始めたのも見栄のためである。
この長編の中盤には恐竜ハンターというのが出てくる。悪役として。しかしドラえもんやのび太のやっていることが正しく、恐竜ハンターのやっていることが間違いであるということに何の根拠があるのか。やっていることは同じではないか。人間さまの都合で動物を飼ったり、またそれを自然に戻したりしているという点において。ドラえもんやのび太自身が恐竜狩りの経験者である。しまいには恐竜ハンターをなじるにあたって「航時法」という法律まで持ち出す。おい、セワシくんがドラえもんをのび太の家に送り込んだという行為が航時法違反でなくて何だというのだ?
自己正当化しようとすればするほどボロが次から次へと出てくるドラえもん。
ふだん勧善懲悪を書いたことのない作家が勧善懲悪物を書くとどうなるかの典型である。
もちろん優れた作家である藤子・F先生が、この問題について苦悩しなかったとは思えない。そしてそれを瑣末な問題として無視することに決めたその瞬間、藤子・F先生は作家としての誇りを捨て、堕落への第一歩を踏み出したのである。
スーパー戦隊や仮面ライダーにおいても、悪役というものは必ず登場する。そしてその悪役がなぜ悪なのか、具体的にどのような悪いことをしているのか。それは絶対に揺るがせにしてはならない最重点事項である。それを揺るがせにした瞬間、正義のヒーローは単なる暴力の行使者と何も変わらなくなってしまうからである。(続く)
反面教師としての『ドラえもん』(その1)
「子供をだますのは大人をだますのよりも難しい」
特撮ファンであれば誰もが耳にしたことのあるセリフであろう。スタッフやキャストのインタビューによく出てくる。子ども向け作品を作るのは大人向け作品よりも難しい、という文脈で。しかしこういう言い方、もうそろそろ止めにしたほうがいいのではないだろうか。
実際子供と大人とどっちがだましやすいかと言われれば、「場合による」というのが正解である。大人は子供よりも人生経験や知識が豊富である。しかしそれが先入観となって、面白いものを面白いと感じる感性を鈍らせるということはありうる。大雑把に言って、大人向け作品は理性重視、子ども向け作品は感性重視といえようか。
しかし世の中には「子供だまし」という言葉はあるが「大人だまし」という言葉はない。子供をだますのは大人をだますのよりも易しいというのが世間の多数派の意見である。それに対抗するために、戦略してとあえて逆の主張をしていたのである。
そもそも、クリエイターにはプライドというものがある。子ども向け作品は、子供が喜びさえすればよい。だが、その子供が成長し大人になっても心の片隅に残り続けるような作品を作りたいとクリエイターは常に願うものである。そのためには、理性と感性の両方に強く訴える作品でなければならず、それは最初から大人向けに的を絞った作品を作るよりも当然ハードルは高くなる。
昨今はインターネットの普及により、子供としての幼稚な心を持ったまま大人になったような人が、自分の意見を発表する場を持つようになった。そういう人たちによって、子供だましでしかない作品が、「子ども向けでありながら、大人になっても楽しめる作品」などと持ち上げられ方をされるような妙な傾向が出てきた。
藤子・F・不二雄先生の『大長編ドラえもん』もまたそのような作品の一つに思える。(続く)
炎上商法をナメるな――『進撃の巨人』をめぐって
8月1日に公開された映画『進撃の巨人』は炎上商法をやっているのではないか、という噂が立っている。
というのは公開日を前後して、町山智浩、西村喜廣、樋口真嗣、福田裕彦と、制作スタッフあるいは彼らのお友達が、ファンの神経を逆撫でるような発言を次から次へと行なったからである。こんなに失言が矢継ぎ早に出るのも不自然ではないか、あるいは話題作りのためにワザとやっているのではないか……。
ハッキリ言ってやる。こんなものが炎上商法のワケがない。真面目に炎上商法をやっている人に対して失礼である。
炎上商法の達人として、今の日本映画界において第一に指を屈するのは東映の白倉伸一郎氏である。
白倉氏という人も毀誉褒貶の激しい人である。しかし、自分のプロデュースした作品をヒットさせるためならば、どんな汚い手を使うことも厭わないという、その姿勢に対しては一種の敬服の念を持たざるをえない。氏のすごいところは、どんなクソ映画を作っても、素晴らしい傑作ができましたと、記者会見の場でぬけぬけと自信たっぷりに言い放つことである。だから怒る人も出る代わりに、だまされたと思ってちょっと行ってみるかという気にさせられる人も出るのである(そして見終わってから怒るのである。後の祭りである)。
ひるがえって『進撃の巨人』の連中はどうか。原作厨だとか、冷笑家だとか、ハリウッド厨だとか、この映画を見て楽しめない人がいるとすれば、問題はそいつの方にあると決めつけるようなことばかり言っている。予防線を張るのは作品の出来ばえに自信がないことの現れだというのが透けて見える。それが劇場に足を運ぼうという気を萎えさせる。制作スタッフ自身が客を減らすような真似をしてどうするのだ。
『進撃の巨人』のスタッフは白倉伸一郎氏に土下座して、炎上商法のノウハウを教えてもらえ。もう遅いか。
戦隊マップ(新版)・第一案
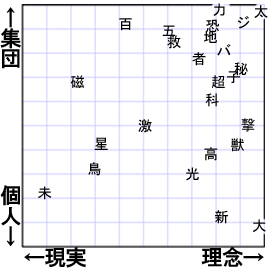
戦隊マップ新版を試作してみて一番意外だったのは、激走戦隊カーレンジャーが一番中央に来てしまったことである。これではまるで、最も特徴のない戦隊みたいだ。
原因はクルマジックパワーが曖昧な設定になっているからである。『電撃戦隊チェンジマン』のアースフォースなんかと比べてみるとハッキリする。地球が危機に陥ったことは過去に何度もある。その度ごとにアースフォースが発動して地球は救われた、このことは記録に残っており、確実なことである。それに基いて地球平和守備隊内に巨大設備を前もって作っておいた。アースフォースは神秘の力と作中で言われているが、別に不思議パワーでもなんでもない。それが地球を救う力であるということは、絶対確実な事実として作品世界の中に存在している。
ひるがえってクルマジックパワーはというと、これが地球を守る力であるという保証があるんだかないんだかよく分からない。よく分からないから、イチかバチかとにかくやるしかない!という姿勢で戦っているかというと、それすらよく分からない。当然それが組織に属する力なのか個人に属する力なのかも分からない。分からないことばかりである。
『激走戦隊カーレンジャー』は人気は高いし私も好きな作品ではあるが、結局異色作としてしか評価されていないというのは、このへんに原因があるような気がする。
脚本家の浦沢義雄先生を責めることはできない。勧善懲悪のヒーロー物は不慣れなのだから、こういうことはプロデューサーがきちんと手綱を取らなければだめだ。で、プロデューサーは誰かというと、高寺成紀氏なのである。やたらと設定に凝るのを作風としている人である。凝らなくてもいい所に凝ってトラブルを起こしたこともある。そんな人が制作した作品が、なんでこんなユルユルの設定になっているのか。さらに、『メガレンジャー』と『ギンガマン』はきちんと地球を守る力の設定がしてあるというのが一層意味不明である。
白倉伸一郎氏の『ヒーローと正義』は大して面白い本ではないが、『カーレンジャー』のラストについての批判はまっとうなものであり、両氏のライバル意識が見られるという点でも貴重なものである。
逃げ道を確保する雨宮慶太(後編)
(承前)その『ジェットマン VOL.3』での鈴木武幸プロデューサーの寄稿文から引用する。『鳥人戦隊ジェットマン』の企画立ち上げの頃の回想で、井上敏樹氏をメインライターとして抜擢する決定を下し、それに引き続き
若いライターには、若い監督が欲しい。それも、ビジュアルに凝り、新鮮で、絵作りにしっかりしたポリシーを持つ監督。「未来忍者」の雨宮慶太監督しか私には浮かんでこなかった。テレビシリーズは、未経験の彼だったが、私には障害はなかった。以下雨宮監督の才能に対する賛辞が延々と続く。
ただこれは鈴木氏にとっての自慢話でもある。若い才能を見抜く眼力が自分にあったからこそ、経験の浅い雨宮氏を起用するなどという大胆な決断ができたのだ、という。それは雨宮氏の言っていることと正反対である。戦隊シリーズが終了するなどという、大変な事態に直面でもしない限り、思い切った決断などできない人だ。鈴木氏に対して雨宮氏はこう言ったも同然である。
どっちが正しいのだろうか。軽々しく判断できる問題ではない。しかし経緯はともかくとして、結果的に雨宮氏にとっては鈴木氏は恩人ではないのか。それでこういう言い方をするのか。いやもちろん鈴木氏のプロデューサーとしてのやり方に批判があるならば、正々堂々きちんと批判すればいいのである。それこそ一種の「恩返し」だとも言える。なんでこんな仄めかしてケチをつけるような言い方をするのか。
また雨宮氏は、井上敏樹氏がメインライターに抜擢された経緯も、自分と同じようなものであったという印象を人に与えるような書き方をしている。これはもう明らかに事実と異なる。
そういえば井上敏樹氏もまた、戦隊シリーズの打ち切りの危機を救った救世主であるかのような噂を立てられることの多い人である。しかし本人はというと、自分をそのようにアピールするような発言はない(管見の範囲だが)。井上氏といえば、平成仮面ライダーやアニメの脚本、また小説の執筆と、幅広い分野で活躍し、また作品も高く評価されている人である。本物の勲章をたくさん持っている人は、ニセの勲章を欲しがる理由なんかないのであろう。
スーパー戦隊シリーズの視聴率(改訂版)
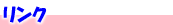
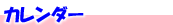
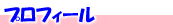
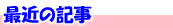
- 『ウルトラマンメビウス』の大迷惑 (08/29)
- 岸祐二『ゴーカイジャー』出演の謎 (08/27)
- 革命作になりそこねた『ダイレンジャー』 (08/24)
- 鈴木美潮という特オタ女の勘違い(補論) (08/21)
- 反面教師としての『ドラえもん』(その4=完結) (08/19)
- 反面教師としての『ドラえもん』(その3) (08/16)
- 鈴木美潮という特オタ女の勘違い (08/14)
- 反面教師としての『ドラえもん』(その2) (08/12)
- 反面教師としての『ドラえもん』(その1) (08/10)
- 炎上商法をナメるな――『進撃の巨人』をめぐって (08/07)
- 戦隊マップ(新版)・第一案 (08/05)
- 逃げ道を確保する雨宮慶太(後編) (08/03)
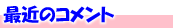
- スーツアクターという難題
⇒ Manju (10/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19)
- スーツアクターという難題
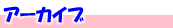
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)