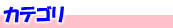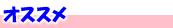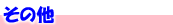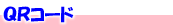平成の次に来るヒーロー?(前編)
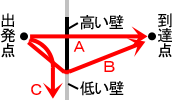
A:昭和 B:平成 C:平成の次?
「平成仮面ライダーの初期作品は素晴らしかった。それに比べて最近のは……」
という声が上がるのに接すると、かつて昭和ライダーのファンを懐古厨と呼んでバカにしていた連中が、今度は呼ばれる側になったのか、と感慨にふけりたくなってくる。しかし話はそれほど単純でもないようだ。
昭和/平成(より正確に言うと改元より少し後の1990年代前半)を境にした、ヒーロー像の変化というのは確かにあった。中断期間がない分だけ、ライダーよりも戦隊の方で傾向の違いは明瞭なのだが、具体的に言うと、かつてヒーローはいかなる高い障壁をも乗り越え、到達点まで一直線に突き進むべきものであった。実際は迂回することもあったが、それは力が足りなくて止むをえずそうしていただけである。それが社会の変化に従って、「巨大な悪」がリアリティを失うとともに、「高い壁は迂回し、低い壁は乗り越える」のも決して仕方なくやっているのではなく、それこそが正義のために戦う者が歩むべき道だというふうに変化していった。
この「到達点」が何を指すかというと、もちろん「戦いのない世界」である。ヒーローにとって戦いはあくまでも手段であって目的ではないのだから、「ヒーローたちが戦うのは、戦いが必要とされない世界を作るためである」というのも別に逆説的ではない。もちろんそんな境地に「達する」ことが簡単にできるわけではない。肝心なのは「近づく」ことである。
だが、最近の戦隊を見ていると、そのような目標とすべき到達点そのものを、持っていないようにも見える。
戦隊マップの現実/理念の対立で言えば、A(昭和)が理念型、B(平成)が現実・理念の混合型ということになる。とすれば、いずれはCの現実型へと移行するのは理の必然ともいえる。それが今だということになるのだろうか。そう考えると、1990年代前半にも比肩するような、大きなヒーロー像の変革が、今まさに進行中のような気もしてくる。しかし、25年前はソ連の崩壊があり冷戦が終結し、日本の社会は1945年の敗戦以来の大激動期を迎えていた。最近それに匹敵するような大事件って何かあっただろうか……?(続く)
特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(後編)
(承前)先日の「ゴレンジャー同窓会」でもそうだったが、戦隊の作品に出演した俳優が集まるイベントが執り行われた際、主演だった五人のうち四人しか集まらないことがある。その場合、あろうことか、残りの一人に対して非難の矛先を向ける声がネットで上がったりする。来たくなかったから来なかったのか、それとも来たかったのに仕事が忙しくて来れなかったのかもお構いなし。彼らの頭中では、とにかくこういうイベントに出てくる人はファンを大切にする人であり、出てこない人はファンを大切にしない人だという決めつけがある。
そういうのが現実に多数派か少数派か分からないが、とにかく声の大きいほうがファンの代表的な意見であるとしてまかり通ったりするのは困ったことである。
ところで、私も特撮出演俳優に会いに行ったことがある。その人はイベントなんかには全然出てこない人であるが、理由を聞いたら、俳優の才能はないと思ってさっさと引退した自分のような人間に、会いたいファンがいるとは思わなかったからだそうである。だからこっちから居場所を突き止めて押しかけていった。それでどうだったかというと、あまり詳しくは書く気がしない。なぜならイベントのような金銭を介在させた出会いとは違って、個人的なことをあまり大っぴらぴらにするものではないと思うからである。行ってよかったと思えるものであったとだけ書いておく。同様のことをした人は他にもいるであろう。多分みんなそんな感じに違いない。
だったらなんでオマエはこんなブログを書いているんだと言われそうだが、黙っていて、イベントに出てこない奴は特撮番組に出演したことを黒歴史にしているなどと見なす空気がさらに支配的になったりしては困るからである。そして出てこない人に対して心理的圧力がかかり、「やっばり出たほうがいいのだろうか」と嫌々出席するような事態が生じたりすることを懸念するからである。私とて、わざわざ人が楽しんでいることに対して、ケチを付けるような真似はしたくないのであって、やむをえず書いたのである。
特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(中編)
(承前)カドの立たないような言い方はないかとずっと考えていたのだが、結局ないようなので、もうはっきり書くことにする。
俳優として大成できなかったにもかかわらず、ファンから金を巻き上げることに精を出す姿は見苦しい。
別に他人が何をやろうと自由である。そしてその行為について、他人が感想を述べるのもまた自由である。別に止めろと言っているわけではない。
だいたい芸能界というのは、毎年膨大な数の人がデビューする。そして同じ数だけの人が消える。テレビ番組で一年間レギュラーの役を務めはしたものの、それ以外はあまりパッとすることもなく引退した俳優など星の数ほどもいるだろう。彼らは引退すれば即座にファンの記憶から消えてゆく。ところが特撮に出てヒーロー・ヒロインを演じた人たちに限ってはそうではない。引退して何年も経ってから、イベントに呼ばれて当時の思い出話をするよう求められたりすることがある。そして特に面白い話が出るわけでもない、冬の撮影は寒かったとか、どうでもいい話が聞けるだけのイベントのチケットに、五千円以上もする値段がつけられたりするのである。
もちろんそのような商売は、特撮ファンの勘違いの上に成立している。ファンは望んで勘違いをしているのだし、だから別に俳優は何か悪どいことをしているわけではない。
勘違いというのは具体的に言うと、「役と役者の混同」のことである。
特撮ファンが憧れの感情を抱く対象は、あくまでもヒーローであって、ヒーローを演じた役者ではない。しかし混同は容易に生じる。劇中でカッコいいヒーローを演じた役者は、役者自身も普段からカッコいい人だとファンは誤解する。ヒーローがカッコいいのは、もちろん役者の演技力もあろうが、プロデューサーや脚本家や監督や、その他大勢のフタッフの努力の結果である。それを、まるで自分一人の実力によってカッコいいヒーロー像を作り上げたかのように勘違いした俳優が、そのイメージを利用してファンから金を巻き上げる行為に加担し、その上ファンに幻滅を味わわせるような行為を働いたりする。これを見苦しいと言わずして、何を見苦しいと言うのか。(続く)
『七人の侍』は本当に名作か
娯楽作品というものは芸術作品よりも低く評価されるのが普通である。
しかるに、『七人の侍』はなぜかくも高く評価を受けているのだろう。不思議だ。日本映画オールタイム・ベストを選ぶという企画があればほぼ確実に一位。今さら言うまでもないことであるが、『七人の侍』は純然たる娯楽作品である。もちろん、娯楽作品としては超一級の作品であることには間違いはないが、娯楽作品としての限界もまた存在している。だから1954年に公開された当初は、批判的な評もあった。それがベネチア映画祭で銀獅子賞をとったら賛美一色になったらしい。いかにもこの国にありそうなことだが。
どんな批判かというと、さんざん語られ尽くして今さら書くまでもないのだが、要するにこの映画には侍・百姓・野伏せりの三種類の人間が出てくるのだが、それが完全に固定化されてしまっているということである。現実は、人間は誰でも気高き侍にもなりうるし、卑小な百姓にも残虐凶暴な野伏せりにもなりうる。秀吉の刀狩り以前という時代設定を考えれば、考証的にもおかしい。
そしてそのように人間の複雑さを切り落として単純な図式に落としこんだからこそ、世界中で大ヒットしたのである。
実際、2015年の現実を生きている我々には、たとえ娯楽映画といえども正義や悪というものをそんな単純な図式で描いていいものであろうか、という意識がちらつく。にもかかわらず『七人の侍』を見ると、理屈抜きにぐんぐんと画面に引き込まれてしまうのである。これはやはり黒澤明を筆頭とする当時のスタッフや俳優がよっぽど偉大だったのか、それとも以後の日本映画のシステムがどんどんダメになっていったということの証左なのか、邦画界のことについてはよく知らないが。
さてスーパー戦隊でも仮面ライダーでも、「大人の鑑賞に堪える」なんてことがよく言われる。単純な勧善懲悪もいいが、人間の複雑さを描いてこそ、見ている子どもたちの心に後々まで残る作品が出来上がる、とか。しかし『七人の侍』のような単純な作品が今なお名作と称えられている現状を鑑みると、問題はそれほど簡単ではないように思える。私自身も1970〜80年代のスーパー戦隊を今見ると、価値観が古いと感じぬわけでもない。それでも今の作品よりは見ていてワクワクする。これを単に懐古厨の戯言と片づけて良いものかどうか。
特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(前編)
最初に、好きなものを好きと言うのならともかく、嫌いなものをわざわざ嫌いと言うことに何の意味があるのか、という批判に対する反論。
好きなものに対しては好きと言う、嫌いなものに対しては嫌いと言わない。それが普通の生き方だとは思う。しかし世の中そんな人間ばっかりになってしまったら、「俺のやっていることは、誰からも好かれているのだ」などと勘違いする人が続出する。星新一の『妖精配給会社』の世界。だから誰かが言う必要があるのだ。
どうもこのブログも最近はネガティブなことばかり書いているような気もするし、コメント欄でもそのことを指摘されたばかりであるが、書いてる当人の心持ちは至ってポジティブである。
特撮に出たことのある俳優は、そのことを一生の宝物として誇りに思うはずである、などという思い込みは、特撮ファンの間に相当広く浸透しているように思われる。そういう人達は、一生の宝物というほどではないが大切にしている人もいる、ということが理解できない。オダギリジョーは『仮面ライダークウガ』に出たことを黒歴史にしているけしからん奴だ、という噂もそこに由来する。オダギリ氏はこの前ラジオに出て、自分は黒歴史にしたことなど一度もないと、きっぱりと否定していたが、それで噂が消えるものかどうか。
しかしなんでそんな誤解が浸透しているのだろうか。俳優がそういうことを言うからである。イベントとか、インタビューとか。本心からか、リップサービスからかは知らないが、そういうことを言ったらファンが喜ぶだろうと思って言う。しかしそんなファンばかりではない。もちろんファンとしては、特撮番組に出たことを大切な思い出として持っていて欲しいとは思う。しかし大切に思えば思うほどよい、というわけでもない。一生の宝物とまで思ったりする人は嫌だ、というファンだっている。そういうファンはわざわざそんなことを口にはしない。イベントにも行かない。無視するだけ。
そして俳優の方はますます勘違いしていくのである。(続く)
ギャバンとアトムと維新の党
維新の党の分裂騒ぎを見ていると、頭の中で『宇宙刑事ギャバン』の「チェイス!ギャバン」が延々と鳴り響いて困る。
敵が多いほど うれしくなるのさいやもちろんそういう意味じゃないってことは分かっているんですが。
強いやつほど 大歓迎
「敵を作る」というのが今の日本の政界において最も手っ取り早く有権者の歓心を買う手段になってから久しい。「守旧派」だの「抵抗勢力」だの「既得権益層」だの、とにかく敵認定してレッテルを貼るテクニックだけが大流行して、壮大な理想を語る人が誰もいなくなってしまった。でもそんなやり方は期限切れも早い。人気を維持しようと思ったら、絶えず敵を作っては叩き作っては叩きを繰り返す必要がある。
また思い出すのが、手塚治虫が『鉄腕アトム』を嫌っていたという話である。初の国産テレビアニメであり、スケジュールの逼迫度は想像を絶するものがあったようだ。一話一話じっくりと時間なんかかけておられず、そうするとどうしても悪いロボットを出してそれをアトムがやっつける、という話ばっかりになってしまう。勧善懲悪というのは作るのが一番手っ取り早いらしい。ソースは当時虫プロで絵コンテを描きまくっていた富野由悠季氏の自伝『だから僕は…』。
1981〜95年の15年間連続でスーパー戦隊シリーズのプロデューサーを務めた鈴木武幸氏が、以前こんなことを誇らしそうに言っていた。昔は子供がヒーロー物なんか見ていたら、親は顔をしかめていたものだが、今はそんなことはない。我々の努力が実を結んだ結果だ、と。素直に喜んでいいのだろうか。昔も、勧善懲悪物それ自体が教育に悪いと考えられていたわけではない。しかし、子供が勧善懲悪物だけを見ていたら、味方でないものは敵、敵でないものは味方という、きわめて単純な善悪二元論的なものの考え方しかできない大人になるのではないかという懸念があった。そしてそんな子どもたちが今や大人になって親となり、彼らは誰もそのような懸念を口にすることはない。多分、かつての懸念が的中したのだろう。
スーパー戦隊における「レシピと食材」
夕食のカレーの中にコンニャクとサトイモが入っていたら何としよう?
多分、ニンジンもジャガイモもなかったのだが忙しくて買い物に行く暇がなく、仕方なく冷蔵庫にあるもので間に合わせようとしてそういう料理ができてしまった、と考えるのが妥当なところだ。いかにも不味そうだし。しかし、本当にそう断定していいのだろうか。そういう創作料理だという可能性もないとは言えないのではないか。
料理の仕方には二種類ある。一つは、最初にレシピがあって、それに合わせて材料を集め、料理を作る。もう一つは、最初に食材があって、それに合わせて料理法を考える。実際はこの二種類の方法が混合して使われる。では目の前に料理があって、これはレシピ→食材が7割、食材→レシピが3割、といった具合に作られたのだ、ということを、どうやったら判断できるのだろうか。
いったい何の話をしているのだ、戦隊と何の関係があるんだ、と言われるかもしれない。
要は、戦隊の分類をしたいのである。つまり、理念型と現実型と。侵略者から地球の平和を守るためには、こういう戦い方をすべき、というのが最初にあって、それにふさわしい人間を集めて訓練を施し戦隊を結成するのか。それとも、俺たち五人で戦うんだというのがまず最初に決まっていて、どういう戦い方をするかは、五人の能力に応じて決めよう、というやり方か。この分類方法によってこそ、戦隊シリーズの歴史を一望のもとに見渡せる戦隊マップができるはずなのだ。しかし実際にやってみようとすると、意外に難しいのである。主観に左右されず、ここを見れば判断できる、というできるだけ簡便な方法を何としても見つけたいんだけど。
たとえば『超電子バイオマン』では、バイオの血を引くものが戦士に選ばれたということになっている。しかしそれは、バイオの血は濃ければ濃いほど戦士としての適性度は上がるというものなのか、それともある一定の濃度さえあれば誰でもいいのか。ピーボがどのような基準によって五人を集めたのかを明らかにしない限り、この作品の本質を理解することはできない、と思うのだが、私以外にそういう考察をやっている人もいない。
最近の本サイトに関しては、全然更新してないといっても、何もしていなかったわけではないのです。ううん、結局弁解になってしまった。
オダギリジョーはいったい何をバカにしたのか?(後編)
(承前)「自分は『クウガ』を黒歴史にしたことなど一度もない。にもかかわらずそのように言われる」
というようなことを「高寺成徳の怪獣ラジオ」2015年10月31日放映分でオダギリジョー氏自らが言っていた。もちろん原因は思い込みの激しいファンの方にあるのだが、オダギリ氏に責任が全くないわけでもない。
オダギリ氏は『クウガ』の主役に決まった時、自殺を考えたという。冷静に考えれば、そんなことがあるわけがない。イヤなら断ればいいのである。しかし純情なファンはこんなことを本気にしたりする。そして、結局はオダギリ氏は五代雄介役を引き受けたということは、まさに命がけの覚悟でこの『クウガ』という作品に臨んだということだ。しかるに、『クウガ』が終わった後も、オダギリ氏は特撮ヒーロー物なんてあんまり好きじゃないなどという発言を続けている。ああ、やっぱりオダギリ氏は『クウガ』なんか演じたことを後悔しているのだ、黒歴史にしているのだ……。まあそういう流れである。
私もそのラジオを聞いたんだが、オダギリ氏の口調から判断するに、やはり『クウガ』は大切な思い出の作品ではあるが、自分にとっての一番大切な作品というわけでもない、今までこなしてきた数多くの仕事の中の一つである、まあ多分そんな感じである。そりゃそうだ。仕事を一つ引き受けるたびに、いちいち命がけの覚悟なんかしていたら体がいくつあっても足りない。だからこの場合、勘違いするファンが悪いのである。しかしファンをそのような勘違いに仕向けたのもオダギリ氏である。
じゃあ、最初から正直に、僕は今回この役を引き受けましたが、単なる仕事と思ってこなします、などと言えばよかったのか。それはそれでマズイだろう。芸能人というのは幻想を売るのが商売なのだから。芸能人とファンの関係というのは恐ろしく複雑微妙な構造の上に成り立っているのであり、特撮ファンというのは、その中でも特に思い込みが激しい人が多い。オダギリ先生は、今回のラジオ出演で誤解が払拭されることを望んでいるようだが、そんなに都合よくいくまい。現に、オダギリ氏の「特撮物は好きじゃない」という発言を、「あれは『クウガ』を除く特撮物は好きじゃないという意味なのだ」などと勝手な解釈をし、掲示板荒らしをしている『クウガ』ファンがさっそく見られる。
オダギリジョーはいったい何をバカにしたのか?(前編)
オダギリジョーといえば、『仮面ライダークウガ』(2000年)の主演俳優であり、戦隊シリーズを侮辱するような発言をしている人である、と聞いていたので、いずれは筆誅をくわえてやらねばと前々から思っていたら、2015年10月31日の「高寺成徳の怪獣ラジオ」を聞いたら、どうもこの人は単に見栄を張って話を盛っているだけのような気がしてきた。そんな人を叩いたってしょうがない。
オダギリ氏は、『クウガ』の前年に『救急戦隊ゴーゴーファイブ』のオーディションを受けた際に特撮ヒーローをバカにするような発言を審査員に向かって行ない、つまみ出されたということで有名な人である。
僕が俳優の勉強をしているのは、リアルな芝居をやりたいためであって、変身とかヒーローとか、そういうものになるつもりはありません。変身ヒーロー物のオーディションをわざわざ受けに行って、こんなことを言ってきたというんだから、痛い人だと思われるのも当然だ。本人によれば、事務所に行けと言われて仕方なく、受かりたくもないオーディションに行ったという。どうも信じられない。そんな奴が最終選考まで残ったりするのだろうか? 審査する方の目だって節穴ではないだろう。
本当は受かりたくて受かりたくてたまらなかったんだけど、場の空気を読み違えて盛大にスベり、審査員を怒らせる結果になった。しかしそんな失敗談はみっともない。だから見栄を張って、最初から落とされるつもりだったんだ、みたいな話に作り変えた。真相はそんなところだろう。イソップにも確かそんな話があったような気がする。
そう考えていくと、翌年に『クウガ』の主役が決まった時だって、本当は天にも昇るような心地だったんだけど、素直に喜んだら自分を安っぽく見せてしまうことになるから、真剣に悩んだことにしておこうとしたとか、そういう可能性もある。「自殺を考えた」なんてのは明らかに誇張だろうけれども。
だいたいオダギリ氏が今回「怪獣ラジオ」という番組に出た目的の一つは、『クウガ』という作品に対する自分の思いが曲解されてファンの間に広まっており、それを払拭することであったという。しかしなあ、俳優にとって自分のありのままの本心をファンの前にさらさない権利があるのなら、ファンも俳優の発言をありのままに受け取らない権利があるのですよ。(続く)
作品を作ることの喜びと悲しみと

藤子・F・不二雄『未来の想い出』
ふええ、藤子・F先生もこんなこと考えてマンガ描いてたのか、晩年の作品のマンネリっぷりは本人も自覚していたんだなあ……などと勘違いしてはいけません。まあ、このコマだけ取り出して見せられたら勘違いして当然だけど(ごめんなさい)。
『未来の想い出』(1991年)はエッセイマンガではなくて、純然たるフィクションである。主人公の納戸理人はマンガ家だが、戦後生まれで出身は山梨。自伝的な要素はない。ただ、主人公の顔は作者の自画像の流用。それでこんなセリフをつぶやいてるんだから、読んでる方は当然ギョッとする。
日本一のマンガ家になるぞと青雲の志を立てて上京し、数多くの苦難を経てようやっと花開いた才能、そして大ヒット作家へ……と思ったその時点で既にマンガを描く喜びは消えていた。それだけでも悲劇だが、その上さらに悲劇的なのは、その悲劇を悲劇と感じる感覚すら麻痺してしまっているということだ。普通のマンガ家は、自分は今マンガを描いていて幸せなのだろうか、などと自問することすらない。
「ものを作る喜び」というのは、それほど簡単に消えるものらしい。それに代わって作家を突き動かす原動力となるのは、金や名声に対する執着心である。そっちの方はずっと強力で長続きする。というようなことを石ノ森章太郎も『マンガ家入門』(1965-66年)で書いていた。超一流の作家だけが気づく悩みというものがあるようだ。『未来の想い出』の安直な結末も、逆に現実の厳しさを浮き立たせているようで、かえって切ない。これが『ドラえもん』を除く最後の連載作品になる。
さて東映特撮の話だが、雑誌のインタビューとかを読んでいると、現代において仮面ライダーを作ることの意義はなにか、ということを熱っぽく語っている人が、別の所では、商品の売上高とか興収とか、まるで金のことにしか興味がないかのようにしゃべったりすることがある。どっちが本心なのだろうか。多分どっちも本心なのだろう。藤子・Fや石ノ森などには及ぶべくもないが、プロとして食っていくことに不自由はしないだけの才能はあるクリエイターにとって、「ものを作るということ」は、そういうことであるに違いない。
マジイエローの『ニンニンジャー』への出演について

藤子・F・不二雄『中年スーパーマン左江内氏』「日暮れて道遠し」
1977年、藤子・F・不二雄氏は『中年スーパーマン左江内氏』で初めて青年誌で連載を持つ。今まで少年誌で数多くのヒット作を飛ばしてきた藤子・F氏の、マンガ家として更に新しい境地を切り開こうという意気が込められた作品である。話の内容は「大人向けにテーマを練り直した『パーマン』」とでも言うべきものであり、しかし最終回では結局『パーマン』と何も違わない結論になってしまって、最後にはパーやん(パーマン4号)まで出てくる。あまり素直に喜べる客演ではない。まあ作品としては面白いんだけど。
2011年、スーパー戦隊シリーズ第35作『海賊戦隊ゴーカイジャー』については、もう放映が始まる前から批判が出始めていた。過去のヒーローの登場のさせ方が問題になったのではない、過去のヒーローを登場させるという、その発想自体が既にして批判の対象だったのである。
戦隊シリーズでは作品間のつながりは持たせない。どんなに人気が出ても一年たったら使い捨てにする。それでずっとやってきた。正義とは何か、ヒーローの使命とはどうあるべきか、そのような基本的な価値観からして作品ごとに違う。だから仮に新旧のヒーローが作品の垣根を超えてバッタリ出会ったとしても、意見が一致する保証もない。VSシリーズはどうなんだと言われそうだが、あれは本編とは関係のないお遊びだという認識が前提になっている。
毎年毎年作品世界の設定をゼロから作り直す、という作業は体力を著しく要求する。しかしそれこそが、スーパー戦隊シリーズを途切れることなく三十年以上にもわたって継続させてきた原動力なのである。
さて今年の『手裏剣戦隊ニンニンジャー』では、春にニンジャレッドとハリケンレッドが出てきたと思ったら、今度は『魔法戦隊マジレンジャー』のマジイエローまで出てくるらしい。それに対してもはや批判の声など影も形も見当たらないのは、かつてのスーパー戦隊シリーズが持っていた体力が、今はもうないということに、みんな気づいてしまったからなのだろう。
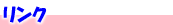
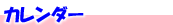
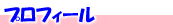
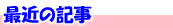
- 平成の次に来るヒーロー?(前編) (11/29)
- 特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(後編) (11/26)
- 特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(中編) (11/24)
- 『七人の侍』は本当に名作か (11/19)
- 特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(前編) (11/17)
- ギャバンとアトムと維新の党 (11/15)
- スーパー戦隊における「レシピと食材」 (11/12)
- オダギリジョーはいったい何をバカにしたのか?(後編) (11/10)
- オダギリジョーはいったい何をバカにしたのか?(前編) (11/08)
- 作品を作ることの喜びと悲しみと (11/04)
- マジイエローの『ニンニンジャー』への出演について (11/02)
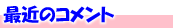
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ percetakan jakarta (04/20)
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
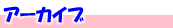
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)