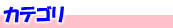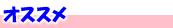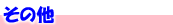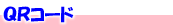フェミニズムに媚びる杉作J太郎

『大戦隊ゴーグルファイブ』(1982年)第7話「幽霊になったパパ」より
1986年の男女雇用機会均等法の施行を、フェミニズムにとって勝利だと勘違いしている奴は当時からいた。だが、フェミニズムの真の目標は、矛盾に満ちた現行の社会体制を変革することであり、現行の社会体制をそのままにして女が男並みになることを求めたりすることではない。その「男並みになる」という発想そのものが粉砕対象なのである。
だが、そんな1980年代的な勘違いを、この2015年になって未だに持ち続けている男どもがいるという事実には、さすがに驚きを禁じえなかった。
――今までの時代だと、車は男性が運転して女性が助手席っていうのが通例だったと思うんですが、『シャイダー』では2人別々の車に乗ってるじゃないですか。(中略)女性が助手席から飛び出したっていうのは新しいな〜と思ったんですよ。まずはこの発言の内容自体が完全な見当違い。だいたい1984年の時点でヒロインが車を運転する程度のことで驚くか? 『大戦隊ゴーグルファイブ』(1982年)では、黄島を助手席に座らせてミキが転する場面すらある。
(『宇宙刑事ダイナミックガイドブック』澤井信一郎・森永奈緒美インタビューより。この発言主は杉作J太郎)
しかしそれよりも重要なのは、女が男並みになることを進歩だとか発展だとか決めつける勘違いのほうだ。アニーが車を運転する。その結果としてアニーとシャイダーとの間にどのような関係性が構築されていたか。問題はそこであって、それを論じることなく単に女が車を運転をしたからといって、そんなものは進歩でも退歩でもない。女性の人権なんてハナから興味も持っていなさそうな奴が、口先だけはフェミニズムに対して理解のありそうなことを言って女性の歓心を買おうとし、結果として一層糾弾されるハメになるという場面を、私は1980年代にウンザリするほど見聞き……。
うわあ嫌なことを思い出してしまった。とにかく21世紀にもなってこんなアホな本出すな。
ひし美ゆり子に対する疑念(後編)
最初、実相寺さんに持っていった話なんです。そうしたら彼が僕にハガキかなにかを寄越した。こうやって滅ぼされる宇宙人は弱いからだ、こういう弱い宇宙人には興味がない、みたいなことを書いてきた。「ああ、この人はマジョリティだ」と思った。彼はウチナーンチュ(内地人=沖縄人)の僕とは違う。そういう視点を持っていない。それですぐ引き取って、野長瀬三摩地監督に持っていったんです上原正三氏の「300年間の復讐」に関する発言。『東映ヒーローMAX Vol.31』(2009年12月)。ちなみにインタビュアーは切通理作氏。これに続けて
ただ、彼はまたそういう民衆臭さのないところに味がある。それが実相寺らしくて支持されるところじゃないですか民衆の視点があるから良い作品である、民衆の視点がないから悪い作品である――というわけではない。もっとも今どきそんな時代錯誤のプロレタリア芸術論なんか採ってる奴がいたら、そっちのほうがよっぽど変である。ちなみに第43話「第四惑星の悪夢」、シナリオ段階では住民の反抗が描かれていたらしい。それが最終的に省かれ、唐突にウルトラセブンが巨大化してビルを壊すという展開になったのは、単に尺の都合だったのかそれともそれ以上の意味があったのかについては判断を差し控える。
「遊星より愛をこめて」に民衆の視点なんかない。別にそれは構わない。しかし糾弾の矢面に立たされ、立場が悪くなった途端に「民衆」という権威にすがりついて批判をかわそうとする。よくあるパターンではある。しかしそういうのを卑劣な行為と言うのである。
樋口尚文氏は本当に『ウルトラセブン』のファンなのであろうか。だとすればファンの風上にも置けない。それとも単にカネのために仕事をしているだけなのだろうか。そっちの可能性のほうが高そうな気がする。
そしてその疑念は、その樋口氏と組んでこんな本を出したひし美ゆり子氏に対しても当然向けられるべきものである。
ひし美ゆり子に対する疑念(中編)
(承前)これはインタビューではなく、樋口尚文氏の文章。
スペル星人に仮託されたものは、自滅の危機に瀕しながらも軍事力を増すために核兵器開発競争に走る愚かしい為政者のイメージであって、その愚昧とエゴが国境を越えようとする純な民衆の祈願を踏みにじるという悲劇が「遊星より愛をこめて」である。為政者? 民衆?
一体何の話だ?
第12話におけるスペル星人は、単なる悪者である。何の同情の余地もない。そして正義の戦士であるウルトラセブンにやっつけられるのである。
スペル星人の最大の問題点は、あのケロイドむき出しのデザインである。被爆者一般に対するイメージが投影されたものだと言われて、反論するのはなかなか難しい。被爆者を邪悪なものとして描いているという批判については、そうそう簡単に論破できるようなものではないのだ。そこで樋口氏は第12話を擁護しようとして、民衆だの為政者だのといった本編とは何の関係もない、コジツケとすら言えない超理論を持ち出さざるをえなかった。これはつまり第12話には問題があるということを、逆に主張してしまっているも同然である。
第12話の封印解除を本当に願っているファンにとっては、樋口氏のやっていることは利敵行為以外の何物でもない。
スペル星人をあんなデザインにしたのは監督の実相寺昭雄氏である。デザイナーの成田亨氏は反対し、それを押し切った。そして実相寺氏に民衆の視点なんかあるわけがないだろう。
「300年間の復讐」という、『セブン』用に書かれた脚本がある。執筆者は上原正三氏。ファンの間でも有名なストーリーで、結局はボツになったものの、惜しく思うファンも多い。そしてその映像化阻止に加担したのが実相寺氏である。(続く)
ひし美ゆり子に対する疑念(前編)

ひし美ゆり子・樋口尚文『万華鏡の女』(2011年)
ひし美ゆり子という人は本当に『ウルトラセブン』という作品に思い入れがあるのだろうか?
それとも、ファンにチヤホヤしてもらえるしイベントにも呼んでもらえるからそんなふうに言っているだけであり、本当は『セブン』に対して関心なんか全然ないのではあるまいか? ――そういう疑念がわきおこらざるをえない本である。
といっても私もこの本全部読んでないんだが、第12話「遊星より愛をこめて」が『セブン』にとって最もデリケートな問題だということに議論の余地はない。それについて無思慮きわまりない発言をしているというだけで十分であろう。
第12話には何の問題もない、という主張をするならするでいい。しかしそれなら相応の論理的な根拠を述べるべきだ。安藤健二『封印作品の謎』は私はあまり高く評価してる本ではないが、せめてこの本に書かれた程度の知識くらいは持っていなくては話にならない。しかし樋口氏もひし美氏も、スペル星人の問題点について全く理解していない。そもそも、インタビュアーであるはずの樋口氏が一方的に自分の主張をぶつけ、それに対してひし美氏が調子を合わせてうなずいているだけ。これはもうインタビュー記事としても体をなしていない。
樋口氏は、「三年間何の抗議もなかった」という事実をもって、第12話自体には何の落ち度もなく「ひばく星人」と記した雑誌記事だけが問題であった、というふうに話をすりかえている。現代史について無知すぎだろう。昔の雑誌なんかを今読むと、左翼とか進歩派とか言われている文化人ですら、マイノリティに対する差別的な言辞を普通に吐いていたりする。当時が普通で今が過敏なのか、当時が過鈍で今が普通なのかは知らんが、とにかく1960年代末ごろに社会思想の大転換が起こったというのは戦後史の常識である。『セブン』の初放映は1967年、初めて抗議が来たのが1970年。放映当初は問題なかったのが、後になって問題アリとなったとしても、別に不自然なことは全然ない。(続く)
幻のアンヌ隊員? 誰よそれ(再再)

21日のエントリで「そもそも特撮ヒロインのファンなどという存在自体が、常軌を逸しているのである」などと書いた。これは1980年代の人間にとっては当たり前の感覚ではあるのだが(多分)、若い人にはもっと詳しく説明しないと意味が分からないかもしれない。
『C調アイドル大語解』(初版1988年、翌年に改訂新版)という本をたまたま読んでいたら、大川めぐみ、萩原佐代子、森永奈緒美、森恵など特撮の人もちゃんと項目があった。ただしその十把一絡げにするような記述からは、当時は依然として普通の芸能アイドルとは別カテゴリーみたいな認識をされていたことが読み取れる。
じゃあどんなカテゴリーだったのか? 多分「女優」だろう。歌手・俳優とアイドルの違いは、前者はあくまでも歌唱力とか演技力とかの芸を売り物にしているのに対して、後者の売り物はファンとの「疑似恋愛」である。音痴や大根であることが却ってファンの「ボクが応援してあげなければ」という気持ちを掻き立てて人気が出る、などという転倒した状況すら生まれる。中島らもが「新アイドル論」で詳しく論じていたので、興味のある人は読んでください(エッセイ集『空からぎろちん』に収録)。
といっても疑似はあくまでも擬似である。本物の恋愛の場合は、相手は僕のことを好きでなかったらどうしようという悩みは深刻である。相手がアイドルの場合はそんな必要はない。この娘を応援しようと思ったら、相手はありがたく思うに決まっている。なぜならこっちは金を払っているからだ。
特撮ヒロインがいまだアイドルという範疇になかった時代にあっては、ファンレターを出すということは、現実の知り合いの女の子にラブレターを出すのに匹敵するくらいの勇気が必要だったのである。ひし美ゆり子の人気が顕在化するまでに十年以上の歳月が必要だった、というのも多分そこに関係しているはずだ。ただし、その時に感じた気持ちの高ぶりもまた、現実の恋愛に匹敵するくらいのものだった。
その壁を初めて突破したのが、大川めぐみということになるんだろうか。大川めぐみのファンに、その熱意が常軌を逸している人が多いというのも、それが理由である。
今の若い人達にとっては、特撮ヒロインも普通にアイドルの一範疇なのだろうか?
幻のアンヌ隊員? 誰よそれ(再)

史上初の特撮ヒロイン本『スーパーギャルズコレクション』(1983年)。その表紙のイラスト、これ、誰?
4月15日のエントリの補足。
アンヌ隊員のファンというのか、ひし美ゆり子のファンというのか、どうも私には理解できない所がある。世代の壁というのか、あの人達は何故ああもマトモなのだろうか。
マトモなのはいいことだろ、と言われるかもしれない。しかし、そもそも特撮ヒロインのファンなどという存在自体が、常軌を逸しているのである。子供が、テレビに出てきたきれいな女の人に小さな胸をときめかせたりする、そこまではよくある話として、しかしそんな思いを成人になってもずっと心に持ち続ける、それが常軌を逸していると言わずしてなんと言うのか。
11日の神戸のイベントについて、ひし美氏がさっそく自分のブログで報告をしている。そこで「豊浦さまがアンヌ隊員をやられてたら、どんなウルトラセブンだったでしょうか」などとコメントをしている奴がいる。そんなもん、大失敗作になったに決まってるだろ。いや知らんけど。しかしファンならそう書くべきだ。そんなこと書いたら荒れるかもしれんが、それがどうしたというのか。むしろ荒れるべきだろう。
実際、1968年に『セブン』をリアルタイムで見てアンヌ隊員を好きになった奴らというのは、別にファンレターを出すわけでもなく、何かファン活動に駆り立てられることもなかった、と聞いている。とてもマトモな人たちだ。そしてそのマトモさゆえに、アンヌ人気が形成されるまで十年以上の歳月を要したという。
常軌といえば、2ちゃんねるの過去スレを漁っていたら、1984年ごろに新聞記事に大川めぐみが載ったことがあったらしくて、その出所を知りたくて当時の朝日・毎日・読売・日経・中日の縮刷版を全部調べた、なんてことを書いてる奴がいた。結局見つからなかったらしいが、それに対して「お前すごいな」などというレスがつくわけでもなく、淡々と続くレスのやりとり。お前らはお前らで常軌を逸しすぎじゃ。
よろしい、産経は俺が調べてやる。
23日に補足
5/3追記 産経でもなかった。
素人小説『アニーの大冒険』(上原正三)を読む

私は懐古主義者ではないから「昔は良かった」なんて言わない。昔もそれほど良かったわけではないことを知っているからである。もっとも、「昔も良くなかった」と言ったところで、今の良くない状況が改善されるわけでもないのだが。
『宇宙船』24号(1985年6月号)から29号(1986年4月号)に掲載された『女宇宙刑事アニーの大冒険』という小説を最近手に入れたら、あまりにもひどい出来にビックリした。だいたい脚本家の書いた小説は読みにくくて当たり前。サッカー選手がプレーする野球、あるいは中華料理のシェフが作ったフランス料理みたいなものだ。脚本を書く際の文章のリズムと小説を書く際の文章のリズムは全くの別物である。もっともテクニックは下手であっても、作品やキャラクターに対する激しい情熱のほとばしりが感じられ、それが読者の心を打つということはある。しかしこれは文章が下手であるのみならず、ストーリーもつまらない。もっとも上原正三氏がアニーというキャラクターに何の思い入れも持っていないことは、『宇宙刑事シャイダー』の本編を見た人にとっては自明のことではあるのだが。
こんなものがよく商業誌に載ったものだと思うが、しかも私が読んだのは『宇宙刑事ギャバン・シャリバン・シャイダー トリロジーBOX』(2002年)に再録されたものである。その際に文章を手直しすることもなく、こんなものが残ったらプロの文筆家として恥ずかしいという感覚すら上原氏は持つことはなかったようだ。
結局のところ、この小説も単に当時のアニーの人気に便乗しただけの企画であって、しかもその人気というのもアニーというキャラクターに対するものではなく、単にパンチラに対するものでしかなかったと、私は疑わざるをえないのである。
収穫が全くなかったわけではない。鳥山劣(現・横井孝二)氏の挿し絵はかわいかった。宇宙スケバン刑事が活躍するのは第四話(嘘)。
幻のアンヌ隊員? 誰よそれ
ウルトラセブン幻のアンヌ隊員と再会
ひし美ゆり子氏というのは『ウルトラセブン』(1967年)で友里アンヌ隊員役を演った人だが、そのトークイベントが4月11日に神戸で行なわれ、そこに豊浦美子氏が出席したらしい。豊浦氏というのは当初アンヌ役に内定していた女優のことである。ひし美氏が代役であったということは、ファンにとっては有名な話ではあるのだが(隊員服のサイズが合わなかった云々)、しかしこのニュースを聞いて、ひし美ファンというのは本当に訳の分からない人たちだと思った。
豊浦氏の話なんか聞いて、一体何が嬉しいのだろうか。『セブン』とは何の関係もない話ではないか。
当日は豊浦氏は「“こっちに出てれば”って思うことはありますね」などと発言したらしい。私が仮にひし美氏のファンで、そのイベントに出席していたら、「ふざけんな! 帰れ!」と叫んでいたことであろう。心の中で。
友里アンヌというキャラクターが大きな成功を収めたのは、ひし美ゆり子が演じたからである。豊浦氏なんかが演じていたら、きっと大失敗になっていたに違いない(と思うのがファン心理ではないのか)。豊浦氏の「こっちに出てれば」などという発言には、「私が出てたとしても同じように(あるいはそれ以上に)アンヌ隊員は人気が出たはずだわ」などという思い上がりが潜んでいる。
あるいはこれは豊浦氏の負け惜しみの発言なのであろうか。『セブン』を蹴って別の映画に出演するなどという愚かな決断をした豊浦氏を嘲笑うためにファンが集ったイベントだったのだろうか。しかし、豊浦氏の詳しい活動履歴は詳しくは知らないが、仕事がなくなって引退に追い込まれた、というのではないように思える。多分結婚退職だろう。女優という職業に大した執着も未練もなく、あっさり引退を決めた可能性は大きい。
そして今は何不自由のない生活を送っていて、そんな人が過去を振り返って「こっちに出てれば」なんて言ったとしたら、それはそれで不愉快な話だ。
こんなことを書いているのも、私が偏屈だからなのだろうか。しかし、『ウルトラセブン』は五十年近く昔の作品である。そんな昔にヒロインに恋い焦がれ、その思いをいまだに抱き続けている人であれば、偏屈でないほうがおかしくはないか。まあ私は『ウルトラセブン』はあまり面白いとは思わないし、その中でも比較的面白いと思ったのが第11話と第13話だったりするんだが。
21日・23日に補足
女性アクション映画(大人向け)のお寒い状況(中)
(前回からの続き)戦うヒロインのピンチが、レイプをイメージしていることについては、今さら言うまでもない。
「エロと暴力」。キャラクターに実在感を吹き込む二大強力ツールである。しかし子供向け番組でそんなもん露骨に出すわけにはいかない。だから仄めかしという形で行なう。苦痛の喘ぎ声もセックスの喘ぎ声も、聞いている分には似たようなものである。正義のヒロインが敵の攻撃を受けて悶え苦しんでいるのを見て、ひとたび敵の手に落ちれば、女の戦士は男の戦士よりもはるかに酷い目にあわされるであろうことを、視聴者の子供たちは漠然と感じるのである。であればこそ、なぜ女が戦うのか、その理由についてしっかりと作中で描くことが求められる。筋力や体格では男に比べて圧倒的に弱い女の身でありながら、一体どのような経緯で正義の戦士となる決意したのかということを。
実際、戦隊シリーズにおいては「強化スーツ」が常連アイテムである。これを装着することによって、女であっても十分なパワーを持つことができる(ただし男と完全に同等ということはない)。またそのスーツを着るための適合性というものがあって、特殊な家系の出身であるとか、未知のエネルギー波を浴びたとかいう設定がある。子供向け番組だと侮っている人には信じられないことばかりであろうが。
戦いは男の仕事だと一般には考えられている。そしてその考えを容れた上で、自分は女であることを捨てて戦士としての道を歩む決心をしたのか、それとも「戦いは男の仕事」という考え自体を否定するのか。設定がきちんとしているからこそ、そのヒロインの心理について緻密な考察を行うことができる。
ところが大人向けの作品であれば、そんな仄めかしに留めておく必要はない。もう最初からエロ全開である。そしてこんなエロエロな姉ちゃんがなんで刑事とか隠密とかになって、危険な任務についているのか、何の説明もない。お約束で済ます。そんな説明なんかする暇があれば、この半裸や全裸の姉ちゃんを一秒でも長く見たいというのが見る側の欲求である。
ただし、そういうピンキー・バイオレンスと称される路線ばかりではない。大人向け女性アクション映画にはやり方はもう一つある。(続く)
女性アクション映画(大人向け)のお寒い状況(前)

四方田犬彦・鷲谷花(編)『戦う女たち――日本映画の女性アクション』
『華麗なる追跡』(1975年、主演・志穂美悦子)という映画がある。正義のヒロインが悪党の屋敷に乗り込んだものの敵に捕らわれ鎖で縛られ、天井から吊るされてムチで打たれるんだか、そのシーンで敵のボスのセリフが
そのうち裸にひんむいて犬にしてやる。鎖を引きずってな。永遠にこの屋敷で家畜となって生きるんだ。「そのうち」って何よ……。
自分の命を狙いに来た女武道家を、あっさり始末するのでは面白くない、生かしておいて家畜として調教しよう、まあここまでは理解できる。だったら今すぐ裸にひんむいて、自我崩壊まで屈辱を与えるべきだろう。なんで着衣のままムチで打っているのだろうか。というか、この映画じたい何がしたいのか全然分からない。見終わって五分も経てば、どんな筋だったかも思い出せない、そういう映画である。
志穂美悦子と言えば日本のアクション女優の最高峰である。顔、アクション、演技力のいずれも申し分なし。しかしその彼女の主演映画にはろくなものがない。別に脚本も演出も凝る必要なんかなくて、素直に彼女の女優としての魅力を引き出す画を撮ればいいだけの話だ。しかしそれすらできていない。まだ十分人気がありながら、1987年にあっさり引退しちゃったというのも、なんか分かるような気がする。
女性アクション映画というジャンルがある。緋牡丹博徒シリーズ(主演・藤純子)、女囚さそりシリーズ(梶芽衣子)、女必殺拳シリーズ(志穂美悦子)と、全部東映だったりする。スーパー戦隊シリーズが魅力的なヒロインを次々と輩出することができたのも、その系譜を受け継いでいるからではないか、そういう方面からの分析も試みる必要がある……と思って何作か見てみたら、まったくの時間の無駄だった。話にならない。「子供だまし」という言葉があるように、一般的に大人向け作品よりも子供向け作品のほうが程度が低いと思われている。しかし、少なくとも女性アクション映画に関してだけは、子供向け作品のほうがずっと緻密な作りになっている。何なんだろうこの逆転現象は。
やはりそこには「性」の描き方に対する姿勢の違いが関係しているような気がする。(続く)
もういいでしょ、星光子さん……
別に私は星光子ファンではない。しかし気になってずっと注目していた。『ウルトラマンA』の南夕子役を降板したことについて、自分から降りたと言ったり、降ろされたと言ったり、発言がコロコロ変わったことについても。
そして2014年6月6日の『爆報! THE フライデー』に出演、そこでまた『A』について語るということがあったのだが、その数日前の星氏のブログにこのような記載がある。
ゴールデンタイムのバラエティ番組なので、少し誇張した表現になっているかも知れませんが、番組サイドの制作上の狙いもありますのでご理解ください。これを読んだ時、もう心底ウンザリした気持ちになった。
私はその番組は見ていないのだが、見た人によれば、星さんが涙ぐむ一幕もあり、違和感を覚えた人もいたらしい。要するに、カメラに向かって涙ぐんでくださいとディレクターに言われ、それに応じて演技をしたということか。女優であればお手のものというわけだ。
星さんの発言の変転については、咎める人もいるようである。だがそもそも人間には記憶違いというものもあるし、過去の思い出にいまだ整理をつけられず、自分を繕ってしまうということもある。もしそれが事実と異なっていたとしても、それが彼女にとっての正直な心境であり、一種の真実であることに変わりはない。しかしそれが、テレビ的演出のために事実を曲げるとなると話は全然別である。もうこの人の発言には今後一切の信用を置くことはできない。たとえば毎日どんな心境で撮影所に通っていたかということをインタビューでしゃべったりしても、それは悲劇のヒロインを気取ろうとして、計算して行なった発言としか受け止められない。
しかも、あれは演出ですよということまで自分のブログで明らかにするなんて、いったいこの人はなにがしたいのか。もう何がなんやら。
よくよく考えると、『A』で南夕子の降板がなく、最後まで演り通していたらどうなっていたか? ウルトラヒロインのワンオブゼムにしかならなかっただろう。不本意な途中降板があったからこそ、かえって伝説になったようなものである。「夕子に会いたい」というファンの声に背を向けて、長らく姿を現すことがなかった星光子。その時期こそが、ファンにとって最も幸福な時期だったのだろうなと、今にして思う。
森永奈緒美の復活に泣く

「え、こんなかわいい人だったの!?」と、特撮ヒロインの写真集に載ってる森永奈緒美さんのスチル写真を見てびっくりしたことは、今でも覚えている。
というのは、『宇宙刑事シャイダー』の本編でのアニーが、大してかわいくなかったからだ。いや、そう思って改めて本編を見返すと、確かに時々ものすごく魅力的な表情を見せていた。しかし彼女のそういう素質を伸ばそうとすることに、監督陣は全然熱心ではなかった。彼らは彼女の顔を撮ることよりも、彼女のパンツを撮ることに何倍もの熱意を示していた。……今さら言うまでもないことではあるが。
かてて加えて、脚本家の上原正三氏。アニーを魅力的なキャラクターとして描こうという意欲を見せていたのは序盤の数話だけ。故郷の星を失った悲しみも、シャイダーとの関係も、早々に全然掘り下げられなくなった。その上、全話執筆なんて余計なことをやる。たとえ一本でも他の脚本家、たとえば鷺山京子氏とかが書いていれば、どんなアニーが見られたのだろうかと、今でも思うことがある。
『シャイダー』という作品は、森永奈緒美という女優の可能性をつぶし、「ああ、パンチラの人ね」という形でしかファンの記憶に残らないようにした――という言い方が妥当かどうかについては異論もあろう。もともとつぶすほどの才能もなかったのだ、それを「パンチラの人」という形でファンの記憶に残るようにしてやったんだから有り難く思え、という反論が返ってくるかもしれない。どっちが正しいかなんて、今さら議論しても仕方がないという気もする。
彼女自身、丈の短いスカートでのアクションを面白く思ってなかったということは、円谷浩氏(シャイダー役)も証言しているし、いくら東映が図々しい会社であっても、彼女にまた何かに出てくれなどと申し出ることもあるまい。森永さんにはこんな番組に出たことは忘れて、今は一般人として幸せな生活を送っていることを祈る……。
などと思っていたら、このニュースである。
なんでこんなもんに出んの!?
記者会見で、「パンチラはないんですか?」などと質問した馬鹿がいたらしい。森永さんも、いきなり洗礼を浴びせられるとは思わなかっただろうが、ま、こういう世界だということは百も承知で戻ってきたんですよね。だったらもう何も言いませんわ。
友里アンヌのファンはおかしい

切通理作『怪獣使いと少年』から
アンヌは『セブン』の中で、常にダンの心の支えのようなヒロインとして描かれていた。恋の告白やラブシーンなどは一回もないのにもかかわらず、視聴者の子どもたちはダンの恋心をよくわかっていた。「零下140度の対決」で、雪の中に倒れたダンは、アンヌが基地でいれてくれる「あったかいコーヒーとスチームが僕を待っている」と自らを奮い立たせる。僕にはこのセリフは「あったかいコーヒーとアンヌ(原文では傍点)が待っている」と、ずっと聞こえていた。おい。
妄想を根拠に論を組み立てるな。
『ウルトラセブン』は古典だから、教養として身につけておかなくてはと思って第1話から見始めたんだが、あんまり退屈なんで途中でギブアップしてしまった。『セブン』ファンには悪いが、「今見ても面白い」とか言う人は、“思い出補正”で目が曇っているとしか思えない。
私は当然友里アンヌに注目して見た。第26話「超兵器R1号」。超兵器計画にはしゃぐウルトラ警備隊(アンヌ含む)、一人だけ暗い顔をしてつぶやくダン、「血を吐きながら続ける、悲しいマラソンですよ」。第42話「ノンマルトの使者」。本当の地球の原住民は誰なのか苦悩するダン、「人間が人間のことを考えるのは、当然のことじゃない。海底は私たちにとって、大切な資源よ」とアンヌ。
「常にダンの心の支えのようなヒロインとして描かれていた」? 嘘をつくな。アンヌが何かしゃべって、ダンの孤独はいっそう引き立つ、そんな描写ばっかりだぞ。
途中をすっ飛ばして最終二話「地上最大の侵略」を見たら、これはよくできていた。で、この回のアンヌに深い感動を覚えた視聴者が、これまでずっとアンヌがダンを支えてきたかのように錯覚したんだな。
女のほうは、別に男に尽くしたいとか全然思っていないにもかかわらず、男のほうは勝手に今まで自分がそうされていたと思い込む。現実にはよくある話である。こじらせるとストーカーになったりする。
しかし現実の女性相手ならともかく、テレビの中のヒロインに対してそんな感情を抱くのは、気持ち悪いからやめたほうがいいと思う。
星光子のファンであることの大変さ
星光子氏の公式サイトに日参していたことがある。
別に私は星氏のファンではないのだけれども、『ウルトラマンA』(1972年)の途中で突然ヒロインが降板したのは有名な話で、その南夕子役の女優であるし、その三年後に芸能界を引退してからは一切メディアへの出現を拒み、ファンにとっては消息を知りたくても知れない二大特撮人気ヒロインみたいな言われ方をしていて興味を持った。(ちなみにもう一人は大川めぐみ氏。桃園ミキ役。)
2004年にDVDの発売を機に、メディアに登場するようになるのだが、そこで降板の真相をファンから聞かれて「納得のいく演技ができないので自分から降板を申し出た」と言っていた。だから、2005年9月10日に公式サイトが更新され、降りたのではなく降ろされたのだという内容の記事がUPされたとき、私も星光子ファンと共にその衝撃を味わうことになった。
私は別にファンではないから、同情する気もないのだが、それより感動したのはファンの反応である。今はブログも始まって、ファンもコメントをつけられるようになっているのだが、そこで「じゃあなんで嘘ついてたんですか」と聞いてるやつが一人もいない。
星氏にしてみれば『ウルトラマンA』なんてのは昔の話だし、すべてをありのままファンの前にさらけ出すつもりなんか全然なく、ただ思わせぶりなことを書いて同情してもらいたいだけだということは、ブログを読んでいれば容易に分かる。そしてファンも、自分たちが彼女の愚痴を聞いておれば、彼女の昔の心の傷を少しでも癒すことになると思って、聞き役に徹しているのである。彼女が自分たちファンに心を開く気など全然ないということを承知の上で。
三十年間待ち続けた結果がこれである。
特撮番組に出ていたヒロインに恋をするということは、現実に恋をすること以上に苦くて切ない思いをすることもあるのだ。
アニメやマンガのキャラに萌えたとか言ってる人には、こういう感覚というのは分かるのだろうか。
沈黙を破って以降の星氏が、映画にも出演しさまざまなイベントに出たりと急激に露出を増やす一方、二大ヒロインのもう一方はというと……。
いやこの話はいいや。
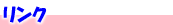
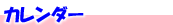
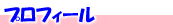
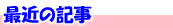
- フェミニズムに媚びる杉作J太郎 (07/18)
- ひし美ゆり子に対する疑念(後編) (06/10)
- ひし美ゆり子に対する疑念(中編) (06/08)
- ひし美ゆり子に対する疑念(前編) (06/06)
- 幻のアンヌ隊員? 誰よそれ(再再) (04/23)
- 幻のアンヌ隊員? 誰よそれ(再) (04/21)
- 素人小説『アニーの大冒険』(上原正三)を読む (04/18)
- 幻のアンヌ隊員? 誰よそれ (04/15)
- 女性アクション映画(大人向け)のお寒い状況(中) (02/26)
- 女性アクション映画(大人向け)のお寒い状況(前) (02/24)
- もういいでしょ、星光子さん…… (10/01)
- 森永奈緒美の復活に泣く (09/11)
- 友里アンヌのファンはおかしい (02/22)
- 星光子のファンであることの大変さ (03/04)
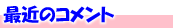
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ percetakan jakarta (04/20)
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
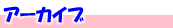
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)