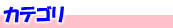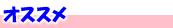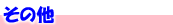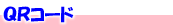仮面ライダーの人気低下は本当か
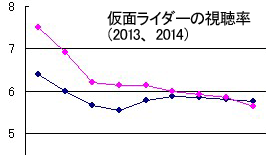
「仮面ライダー」人気低下か?クリスマス商戦で不人気ぶりが話題 アマゾンで投げ売り状態
アナウンス効果というものがある。仮面ライダーの人気は下がっていると、大した根拠もなく言い続けていると、本当に下がってしまう。そういう現象というのは実際に存在する。こういう記事が出て以来、さっそくネットのあちこちで「仮面ライダーのくせにバイクに乗らないのがいけない」とか「二話完結が飽きられた」などと百花斉放である。そしてそういうのに影響されて見なくなる人というのは確実にいる。
東映は抗議したっていいくらいのものだ。
だいたい元の記事だって、今年は仮面ライダーの玩具に品薄感がないという、そんなことを根拠に人気低下とか言うのも無茶な話である。個人的にツイッターとかやっているプロデューサーも多いんだから、反論すればいいのに。なぜしないのか。できないんだろうな、やっぱり。
だいたい玩具の売り上げというのは作品の人気に正比例するわけではない。玩具そのものの出来というのもあるし、いかに視聴者の購買欲を刺激するか、その戦略にも左右される。今年は『妖怪ウォッチ』の影響もあるだろう。それに『ドライブ』の売り上げが良くないといって、毎年200億売ってるのが今年は150億しか行かなさそうだ、という程度のものじゃないのか。そんだけ売れりゃ、スポンサーだって文句はつけられない。しかしネットの上では、玩具の売り上げ高が高ければ高いほど良い作品だ、とみなす風潮が猖獗を極め、前の年から一円でも下げれば失敗作呼ばわりされる。そもそもこんな風潮を作ったのは誰か。東映のプロデューサー自身である。昔は、たとえ口先だけでも、子供に夢や希望を与える番組を作りたいと言っていた。最近はもう露骨に金の話ばかりして恥じない人が多い。そしてその結果として、あやふやな根拠をもとにして仮面ライダーが不人気だという記事が出たところで反論もできない。自業自得である。
それにしても、『鎧武』で仮面ライダーシリーズ史上最低視聴率を記録し、『ドライブ』ではそれをさらに下回った(9話時点)。仮面ライダーの人気低下についての記事だというのに、視聴率については一切触れないとは。この記事を書いたのは、どんな書き方をすれば東映が困るか、知り尽くしている奴に違いない。
特撮技術の進歩は何のため?

佛田洋『特撮仕事人』
戦隊ロボの在り方を見ても、昔は1年に1体のロボットでやっていて、それがだんだん2号ロボ、3号ロボと増えていって、そういう進化がシリーズの面白さや発展に繋がったんだけど、以前に比べてロボに乗ることのありがたみが薄れてる気がするというか。昔は、“このロボがやられたら大ピンチなんだ!”という緊迫感があったけど、今は“やられても、また次のロボが出るんだろ”みたいな。(佛田洋『特撮仕事人』p.178〜179)断っておくと、佛田氏は別に今の東映の商法に対して批判的なわけでは全然ない。ただ戦隊シリーズの初期からスタッフとして関わり、『地球戦隊ファイブマン』(1990年)からはずっと特撮監督を務めている佛田氏が私と全く同じことを考えていたので、都合のいい部分だけ抜書きして、虎の威を借る狐をやろうと思った次第である。
私は『超新星フラッシュマン』の第15話をリアルタイムで見ているが、フラッシュキングの腕がもげ、火花をまき散らしながら倒れたシーンの衝撃は今でも忘れられない。なにしろ巨大ロボがシリーズ史上初めて敗北した回なのである。目の前で何が起こっているのか、理解するのにしばらく時間がかかった。今の若い人たちには、戦隊シリーズを見てこれほどの衝撃を味わうことなどないであろう。――なんて書き方をしたら自慢みたいに思われるだろうか。
また、この本では、佛田氏を筆頭とする特撮班が、面白い映像を撮るためにどれほど粉骨砕身しているかも書かれているのだが、会心の画が撮れたからといって、おもちゃの売り上げに結びつくとは限らないらしい。それよりも、たくさん出すことのほうが重要だと(p.165〜166)。売り上げのためには、質を高めるよりも量を増やすほうが効果的、そして量を増やすことは質の低下につながりやすい。
だからといって、じゃあ今からロボの数を減らせば、一体一体に対する子供たちの愛着が以前のように増すかといったら、それも無理だろう。単に物足りなく思われるだけだ。今の若い人たちに、『フラッシュマン』の第15話を見せたところで、衝撃なんか感じるとはとても思えんし。結局このまま物量作戦を続けていくしかないのだろうか。
昔はCGなんかなかったし、ミニチュア感丸出しの特撮や、不自然なオプチカル合成とかもあった。イラストがそのまま出てくることも。それでも別に大した不満はなかった。今は昔に比べて技術は格段に進歩し、にもかかわらず、子供たちが番組から感じる興奮や感動が、昔に比べて劣っているとしたら、いったい何のための技術の進歩なんだろう。
『ジェットマン』の価値を貶めるのはやめろ
東映YouTubeで『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)が今配信中なのだが、コメントとか見てると、つくづく誤解されている作品だなあと思う。戦隊シリーズの中でも比較的知名度があって人気の高い作品にしてこうだ。先入観に基づいたイメージばかりが行き渡っていて、正しい評価がなされていない。怒りすら感じる。
当時は戦隊シリーズは打ち切りの危機にあって、どうせ打ち切られるのなら好き放題やってやれと大胆な作風を持ち込んだら結果的にそれがヒットした、という説が結構広まっているけど、「スーパー戦隊シリーズの視聴率」でも書いたが、これ絶対に嘘だと思う。なんでこんなことを私が力説しているかというと、それが前作である『ファイブマン』(1990年)に対する侮辱であるというのみならず、『ジェットマン』に対する侮辱でもあるからだ。
『ジェットマン』を見た人なら誰でも同意することだとは思うが、結構戦隊の型にはまっている部分も大きいのである。それは悪いことではない。戦隊シリーズの方針は「不易流行」である。型を守る部分と、型を破る部分、この二つのバランスが重要なのであり、『ジェットマン』もまた例外ではない。もしも本当に好き放題にやった結果として『ジェットマン』程度にしかならなかったとしたら、井上敏樹氏が相当貧困な発想の持ち主だったということになる。いいのかそれで。
成功の可能性など考えず、ただひたすら好き放題やったら、それが既成の固定観念を打ち壊して大ヒットした、というほうが話としては面白いのであろう。だが、そんなんで成功作が生まれれば苦労はしないのである。「怪我の功名」なんて言葉もあるが、それも成功に対する緻密な計算があった上で、トラブルを成功に変えることに成功したケースを指すのであって、単に珍奇なことをして成功作が生まれるなんてことは絶対にない。
そういえば昔『新世紀エヴァンゲリオン』(1995年)というアニメがあった。時間が足りなくて無茶苦茶な最終回を放映したらそれがかえって人々の好奇心をかきたて結果的に大ヒットした、なんて言われているが、あれも嘘。時間がなかったというのは事実だし、だから全部セリフで説明したわけだけど、そのセリフの一つ一つに作り手が必死の情熱を込め、その結果として視聴者の心をつかむことに成功したということは、ちゃんと見た人には分かったはず。『エヴァ』にとってあれ以上の最終回はありえなかった。それは、その後の劇場版、および新劇場版のグダグダを見てりゃ納得できるっしょ。
デンジピンクは一体何を牽引したのか

小熊英二『〈民主〉と〈愛国〉』
『電子戦隊デンジマン』のデンジピンク・桃井あきらに関しては、悪く書いてはいけないみたいな意識が自分にはあり、そういうのもよくないと思って、今回「戦隊ヒロイン列伝」を書きなおしていたら、桃井あきらに関しては前に比べて思い切っきり評価が辛くなってしまった。その弁解をする。
私は『デンジマン』はリアルタイムでは見ていない。だから、見ていた人から「当時はすごく人気があった」と言われたら、どうしてもそこには圧迫の構造が生じる。『スーパーヒロイン画報』(1998年)にも「特撮ヒロインブームを牽引(した一人)」なんて書いてあり、こういうことを書いてある本は他にも多い。しかしそれは、単にその執筆者があきらのファンで、自分が感じたことを当時の人間すべてが感じたことのように書いているだけなのではないか。今回「謎なぞ七色レディ」をあらためて見て、こんなにつまらない話だったのかと愕然とした。
当時の雑誌とか色々調べているのだが、あきらがそんなに人気が出たなんて資料はいくら探しても見当たらない。そんなに人気が出たのなら、次作の『太陽戦隊サンバルカン』でなぜ女戦士がいなかったのか。また小泉あきら氏もこの番組の後は二度と女優はやっていない。彼女の魅力はあくまでもモデルとしてのものであって、女優としてのものではないことは明白である。特撮ヒロインブームの牽引車はやはり桃園ミキだと考えるのが妥当であって、彼女が人気が出ることによってそれ以前の戦隊ヒロインにもスポットライトが当たるようになった、と考えたほうが辻褄の合うことは多い。
「体験」とか「実感」というものに基づいた証言などに重きを置くものではない。それを許せば、結局は声のデカいもの勝ちになってしまう。昨今の憲法九条をめぐる動きを見ていると、日本の戦後の反戦平和運動の限界もやはりそのへんから来ているのではないか。などと書くと急に話がでかくなって申し訳ないが、「戦争体験の悲惨さを語り継ぐ」という形でしか国民の反戦意識をかきたてる手段を持たなかったがため、「戦争中が暗かったというのはサヨクの嘘っぱちであって、米英撃滅・聖戦完遂のために国民の心は一つで意気は高く明るかった。自分はそのように体験した」などと言う奴が出て来ると、対抗手段がなくなってしまうのである。ま、そういう「体験」を語る人というのは、戦中世代といっても深刻な飢餓や空襲にあうことのなかった、比較的恵まれた立場にいた人に決まっているんだけど(と、小熊氏の本に書いてあった)。
誰が石川大我の足を引っ張るのか
最初に断っておくけど、私は社民党についても、その社民党から東京比例区で立候補した石川大我氏についても、何の興味も関心もないのだが、選挙戦を終えて、政治家石川大我へのメッセージというtogetterを読んでいたら、あまりにも酷すぎるので一言言いたくなった。戦隊シリーズとも関係のない話ではないし。
石川氏というのはれっきとした社民党の党員である。社民党の理念に共鳴し、その組織に所属して立候補したのである。129,992票というのは石川氏という個人に対して投じられた票と、社民党という政党に対して投じられた票の合計であり、それが少なかったから落選したのである。で、その石川氏の支持者が、落選が決まった途端に社民党の悪口を言いまくっているのである。石川氏は素晴らしい人なのに社民党の連中はやる気がなかったので負けたとか、その証拠に石川氏個人の支持者に比べて社民党の党職員の悔しがり方が少ないとか、あげく石川氏は他の党から出たほうが良かったとか言う奴まで出る始末。
こいつら政党というものを何だと考えているんだ。
社民党を批判している連中の、その「組織よりも個人が大事」というスタンスが、まさに社民党的なのである。だから社民党の国会議員なんかは、ちょっと嫌なことがあったらすぐに離党するでしょ。そして散り散りになる。団結の力も何もあったもんじゃない。同じような政策をかかげる党でありながら、今回の選挙で共産党が躍進した理由を少しは考えてみるがいい。もちろん共産党の「個人よりも組織が大事」という気風に問題がないとは言わんが、ただその中央集権的な組織運営のおかげで意思決定が迅速に行われるというメリットもある。北朝鮮の拉致問題への対応でグズグズして傷を深めた過去をお忘れか。
個人と組織の関係について、少しでもまともに物事を考えたことがあるのだろうか、この人達は。
「戦隊史学基礎」で私は、個人と組織の関係についての議論を展開した。戦隊シリーズなどという、世間からは幼稚な子供番組だと思われているものを題材にこっちはこんなに真剣な議論をしている一方で、国政選挙に興味があるような、意識の高いであろう人達が、こんなに幼稚な議論ををやっているのを見ると、自分は一体何をやっているんだろうと無性にむなしい気分になってくる。
プロレスと同じ道をたどる特撮ヒーロー
「プロレスの試合に筋書きがあることくらい、ファンは昔から知っていた。知った上で楽しんでいたんだ」
プロレスファンはだいたいこういうことを言う(小林よしのり『ゴーマニズム宣言』2巻とか)。
嘘をつくな。
少なくとも力道山の時代には、観客は真剣勝負だと思って見ていた。だからレスラーも、観客に見破られまいと、体を鍛え、技を磨き、必死になって迫真の勝負を演出していた。時代が下るにつれ、プロレスにブックがあるという事実が知れ渡ってくると、技をかけられる側も協力しているということが素人目にも分かるような、不自然な技を出すことにも躊躇を感じなくなってゆく。昔と今とでどちらのほうが試合に迫力があり、ファンもドキドキしながら見ていたか、言うまでもなかろう。
プロレス人気の凋落に従い、「嘘と分かってだまされてあげる、それがプロレスの見方。まことにプロレスは奥が深い」などという、ひねくれた言い方で弁護する連中が現れ始める。ナマの現実の感動と、つくりものの感動と、どちらが優れているか、言うまでもないだろう。
で、それがどうも現在の特撮ヒーロー番組の置かれた状況に重なって見えて仕方がない。
昨今の、スーパーヒーロー大戦系のヒーロー総出演映画で、ストーリーの辻褄が合っていないとか、キャラクター改変だとかに対して批判が起こると、それに対する弁護の仕方は決まって「細けえことはいいんだよ」「どうせお祭り映画なんだし」「子供向け番組に何目くじら立ててんの」。
『スーパーヒーロー大戦GP』の発表を受け、「仮面ライダー3号とは何者だろう」とワクワクと議論にいそしんでいる人たちのネット上での書き込みを見ていると、衰退に向かっていた時期のプロレスファンと雰囲気がそっくりなんだが。そういえば、特撮ファン全体、作品に対して真剣に怒って批判している人も、その批判に対して真剣に擁護しようとする人も、一時期に比べてずいぶんと減っているような気がする。
1980年代と言えば軽薄短小の時代として知られるが、まさかそんな時代の亡霊と今になって邂逅を果たすとは、ちょっと信じられない気分である。そういえば、白倉伸一郎氏も、1980年代に青春時代を送った世代なんだっけ。関係しているのか……?
誰がスーパーヒーロー大戦を批判できるのか

レッカ社「語ろう! クウガ アギト 龍騎」(2013年)
『スーパーヒーロー大戦GP 仮面ライダー3号』の制作が先日発表になったというのに、今年はあまり批判の声に勢いがないような気がする。こんな映画は過去のヒーローを貶めるような内容になるに決まっているのだし、もう濫発はやめろという声が湧き上がるのが毎年恒例のはずなのだが。
この『語ろう』という本にも、宇多丸氏による『仮面ライダーディケイド』劇場版「オールライダー対大ショッカー」(2009年)の批判が収録されている。東映の特撮ヒーロー大集合系の映画に対する批判の典型的なものであり、内容自体は全くの正論である。だが、こんな批判のやり方には何の有効性もないし、共感の輪が広がることもありえない、という理解がファンの間にも浸透したということだろうか。遅まきながら。
この本の最大の目玉は、高寺成紀氏という人がここまでイタい人だということを明らかにしたことである。『仮面ライダークウガ』を、自分一人だけの力で成功させたと思っているプロデューサー、という噂は前から聞いていた。しかし『宇宙刑事』だの『仮面ライダーBLACK』だの、子供だましの作品ばっかり作って活気を失っていた当時の東映特撮を、『クウガ』が全部変えたという話が出てくるに及んでは、読んでいて開いた口がふさがらなかった。
宇多丸氏を含めた他の六人は、さすがにここまでイタいことは言ってはいない。だが、『クウガ』およびそれに続く平成仮面ライダー初期作品は、従来の東映の特撮ヒーロー物とは違っていたがゆえに素晴らしく、またヒット作になったのだ、という認識は、多かれ少なかれ全員に共通しているように見受けられる。新しい世代が新しいものを付け加えた、というのは事実である。しかし昭和ライダーのブランドの力がなければそもそも企画自体が存在せず、また戦隊やメタルを作り続ける中で維持されてきたノウハウがなければ、『クウガ』を完成させることもできなかった、という認識が余りにも薄い。
先輩たちに対する感謝の念を忘れ、全部自分たちの功績だとうぬぼれていた連中が、今度は自分たちが先輩の立場になったとき、後輩からどのような扱いを受けることになるのか。
『クウガ』や『アギト』、『龍騎』が成功したおかげで平成仮面ライダーは今なお続いている。それは事実である。そしてその恩を忘れ、その平成初期作品が持っていた志も魂も踏みにじり、過去のライダーたちを十把一絡げに扱った映画が毎年濫発されている。だがそれに対して怒る資格は誰にもない。それは「報い」というものだ。
戦隊にオーディションは必要か?(後編)
ダイヤの場合は、磨く前に「これはダイヤの原石だ」ということくらいは分かっていなくてはならない。だから人間の場合でも、才能の有る無しを見極める、指導者の眼力なんてものが持てはやされたりする。しかしその「眼力」って、本当に存在するのだろうか?
たとえばプロ野球では、毎年たくさんの新人選手が入団する。そしてそのほとんどが、何の実績も残すことなく数年後に退団する。ごく一部だけが一流選手への道を駆け上がり、そして一流選手になった後で、スカウトや入団当時のコーチが「一目見た時から、こいつはダイヤの原石だということが分かっていました」なんてことを言う。それだけの話じゃないのか?
磨く前に、才能があるかないかが分かるのであれば、なんで毎年あんなに大量の選手を入団させて退団させるなどという、非効率なことをやる必要があるのだろうか。マニュアル化してもっと効率よくできるはずではないのか(いよいよ内田樹氏みたいになってきた)。
戦隊に話を戻すと、まあ確かに基礎も全然出来てない人くらいの見分けはつくから、オーディションでの篩い落としに全然意味がないわけではない。十人よりも二十人、三十人の中から選ぶほうがいいに決まっている。しかし何百人ともなると、果たして意味があるのかどうか。
「眼力」などという不確かなものを当てにして、キャラクターに合わせて役者を採用し指導するよりも、むしろ、役者に合わせてキャラクターを作るほうが確実だ。つまり、数話ぶんの撮影が終わった時点で、こいつは二枚目の役をやらせるつもりで採った、しかし三枚目の役をやらせたほうが、この役者の魅力はより引き出せる、そのことに気がついた。その場合に監督や脚本家が、柔軟な対応ができるのかどうか。できないのであれば、オーディションの倍率の高さを誇るなど全くの無意味な行為といえる。それは単に力を入れるべきところで入れず、入れても意味のないところで入れてるだけだ。
そういうふうに考えると、1982年の『大戦隊ゴーグルファイブ』は撮影開始直後にトラブルが発生して、ゴーグルピンク・桃園ミキ役に予定していた女優が急遽降り、やむを得ず慌ただしい雰囲気の中で別の人を起用することが決まったわけだけど、その結果としてそれが大人気となり、戦隊ヒロインの概念を一変させてしまったというのも、偶然がもたらした奇跡とか天の配剤とかというものではなく、むしろ順当な結果だったのではなかろうか、という気がしてならない。
戦隊にオーディションは必要か?(前編)
最近の戦隊のオーディションというのは、どのくらい人数が集まっているんだろうか……と思って調べていたら、二千人とか五千人とか、すごい数字が出てくる。合格者は五人だから、倍率は何百倍ということになる。そんな難関をくぐり抜けた者のみが、戦隊のヒーロー・ヒロインになれるわけか。
すごいなあ。
それで、あの程度のしか出てこないのか。
いや、断っておくけど、昔は良かったとか言いたいわけではない。昔も今もレベルは大して変わってないと私は思う。それが問題でしょ。昔に比べて今のほうが、はるかにハイレベルでないとおかしいんだから。理論的に考えて。
昔なんかやってることは無茶苦茶で、スポンサーとか東映の上層部の人とかが、こいつを使えと言ってきたり、相当ひどいゴリ押しとかもあったようだ。『太陽戦隊サンバルカン』のバルパンサー・豹朝夫役の小林朝夫氏なんて、どう考えてもコネ採用なわけで、その小林氏と、最近の何百倍もの難関を突破した今の若い人たちが、大してレベルの違わない演技やってるって、どういうことなんよ。
しかも、役者に対する世間の注目度も昔とでは段違い。放映中だってのに写真集やらDVDやらバンバン出るし、メジャー俳優へのステップボードと見なされて久しい。有力事務所は有望な若手を送り込みたがるし、役者の方だって死に物狂いで演技に打ち込んでいるはずだ。昔は別にジャリ番なんかでいくら人気が出たところで、次の仕事につながる可能性の保証なんて全然なかった。俳優としての野心に乏しい人が起用されることもあったらしい。
それで、ねえ……。
別に熟練の演技力を見せろなんて言っているわけではない。戦隊の役者は原則として新人か準新人。都会育ちの女の子に、純朴な田舎娘の演技をしろと言っても無理な話だ。だから、本物の田舎娘をキャスティングすりゃいいではないか。何百人もの人間から一人を選ぶんだから、イメージぴったりの人間を探すなんて大したことではないはずだ。それなのに、キャラと役者が合っていないケースが見られたりする。そんなんでオーディションの倍率を誇られても困る。
最近の監督やプロデューサーの、ダイヤモンドの原石を見極める眼力が昔に比べて落ちているのか、それとも原石は見極めているんだが、それを磨く現場の力がないのか。しかし、どうも私には、オーディションというやり方自体に問題があるような気がする。
なんて言ってると、内田樹氏の教育論みたいになりそうな予感。(続く)
東映ほどファンを大切にする会社はない(悪い意味で)

スーパーヒーロー大戦系の、戦隊・ライダーが大集合する映画のあまりの濫発ぶりに、東映というのはファンの気持ちを大切にしない会社だ、という声が巷に満ちている。しかしそれは言いがかりであると、声を大にしていいたい。
そもそも、柳の下にドジョウがいれば、十匹でも二十匹でも捕りつくさずにはおれない、それが東映魂である。それが顰蹙を買いトラブルの種をまき「義理欠く恥かく人情欠く」の三かくマークと陰口をたたかれる原因ともなる一方、大衆の求めるものは何かと常に血眼になって探しまくる、そのバイタリティが映画作りの原動力になっていたのもまた事実である。
こういう考えに私が至ったのも、東映の歴史についての本を最近ずっと読みあさっていたからである。時代劇もヤクザ映画もポルノも、ずっとそういう姿勢で作り続けてきたわけだ。そして今の戦隊・ライダーもまたその東映の血を濃厚に受け継いでいることは明らかである。ただし、ずっと小粒化した形で。
最近で言えば『仮面ライダー大戦』(2014年)。ファン投票をするとか言い出した時に、非難や落胆の声が上がったのは、手口の余りのセコさからだ。これが昔の東映であれば、昭和ライダーと平成ライダーが最後の一人になるまで徹底的にブチ殺しあう、それくらいのことはやっていたはずだ。今のサラリーマンプロデューサーにはそんな決断なんか下せるわけがない。適当に両者に花を持たせるような結末は、最初から目に見えていた。こんな安っぽい手口に食いつくのはネットイナゴくらいのものだろう。そんなに客を呼びたいのなら、吉永小百合を悪の女幹部役で呼ぶくらいのことはしたらどうなのか。嗚呼、豪放磊落、破天荒の伝統はどこに行った!
1980年代の戦隊ヒロインがあれほどまでに輝いていたのは何故か。女の人も男に守られているばかりではなく、きちっと戦っていくという所を子供たちに見せたい、などという思いがあったのは事実である。しかしそれは一面であって、女の子にミニスカはかせてキックさせたいとか、縛られて地面にのたうち回ってヒィヒィ悲鳴をあげる女の子を撮りたいとか、そういうギトギトした欲望が裏になかったとは言わせない。上品さと下品さは表裏一体のものだ。今じゃ坂本浩一程度で「エロ監督」とか呼ばれてるんじゃなあ。
エロだろうがグロだろうが、大衆はこういうものを求めてるんだと思えば何でもかんでもガツガツ喰らいつき、骨までしゃぶる。かつて東映が持っていた猥雑で下品なパワーはすでになく、かといって高尚な芸術理論なんかもともと持ってる会社ではない。ファンの期待に応えねばという気持ちだけは依然として旺盛だから、結局やってることがどんどんチマチマしてくる。
二度死んだ熊野大五郎
「爆報フライデー」の話をこのブログでするのは二回目である。前回は『ウルトラマンA』のヒロインだったが、先日(2014年12月5日)の出演者は『秘密戦隊ゴレンジャー』の二代目キレンジャー・熊野大五郎役のだるま二郎氏だった。
この手の番組のコンセプトは、かつて華やかなスポットライトを浴びていたスターが、今は落ちぶれて惨めな生活をしている姿をさらし、視聴者に優越感を感じさせるという下衆なものであるが、テレビとは元々そういうものなのだし、批判したって始まるまい。宮内氏たちにしたって、現在困窮している昔の職場仲間を気遣うのであれば、さっさと電話でもすりゃいいのであって、なんでわざわざテレビカメラの前で「感動の対面」なんかしなきゃならんのか。わざとらしい演出にも程がある。
私が怒りを感じるのは、こんな番組にノコノコと出てきただるま氏の方だ。
実際だるま氏の現在の生活の悲惨さというのも、テレビ的な演出をこらされたものであることは一目瞭然である。食うや食わずの生活をしているわけではない。病気も家族との別居も確かに大変だろうけど、「僕は今こんなに哀れな生活をしているんですよ」とテレビを通して全国の視聴者にアピールするほどのものなのか。
ヒーローならば、人前でみっともない姿を見せるなと、先輩やスタッフから教えられはしなかったのか。
しかしよく考えたら、だるま氏が『ゴレンジャー』に出たのは全84話中13話だけなのか。キレンジャーは確かに人気があったが、それも畠山麦氏の演じた初代のほうであって、単にピンチヒッターでしかない二代目の方はキャラもそれほど立っていなかったし、人気もあったとは思えない(このへん「爆報」でも意図的にごまかしていた)。だるま氏にヒーロー魂が受け継がれていないのも、仕方ないといえば仕方ないか。
かつてはチビッコたちの憧れの的であったヒーローが、今は落ちぶれて無残な生活をしているという絵をテレビ局は欲したのだろう。しかし仮にも一年間ヒーローを演じ通した俳優であれば、そんな要求は拒絶するに決まっている。自分に対して夢や憧れを抱いたファンの思いは裏切れない。たとえ今はどんなに貧乏な生活をしていても、今は明るく楽しく生きていますという姿を、やせがまんをしてでも見せようとするだろう。それではテレビ番組としては絵にならない。そこで白羽の矢が立ったのが、だるま氏だったというわけか。
熊野大五郎は黒十字軍との戦いで戦死した。ヒーローになれなかった男である。そして今回こんな低俗番組に出たことによって、もう一回ヒーローになりそこなったのである。そういえば「爆報」に出て、番組の要求に従って大げさな演技をしてみせた星光子氏もまた、途中降板した人だったっけ。
イケメン特撮ブームの裏で何が進行しているのか
12月1日のエントリの続き。竹熊健太郎氏のツイート「女性が見る特撮は私にとって特撮ではない。特撮魂が曇る。」について。この発言自体は擁護のしようもないが、それを叩いて正義感に浸っている人たちも、事の深刻さが分かっているとは思えない。
「子どもと一緒に番組を見ているお母さんたちは、亭主よりもかっこいいイケメンが出ているのなら、抵抗なく、応援してくれるものです(笑)。だから、以前の仮面ライダーを演じる俳優は、アクションが似合う武闘派のイメージがある、武骨なタイプが多くて、年齢も高めでしたが、平成仮面ライダーでは若いイケメン系の俳優を起用して、若々しいキャラクターにしました。初期の仮面ライダーにあった改造人間という暗く陰のある部分も描くのをやめて、変身した後もナマっぽい生物的なスタイルから時代を引っぱるクールなデザインに変えて、子どもや女性が見やすいライダーにしました」(なぜ「仮面ライダー」で若手俳優は成長するのか 輝く男の発掘・育成法(2))なんか無茶苦茶である。仮面ライダー1号・本郷猛役の藤岡弘氏だって、若い頃はさわやかなイケメンだった。年をとってから渋みのある顔になったのである。それに昭和の仮面ライダーも言われているほど暗くはない。むしろ平成のほうが「同族殺し」という、仮面ライダー本来のテーマと真剣に向かい合っている、という人もいるくらいである(見たことないから知らんが)。
いったい誰がこんなことを言っているのか。
東映の鈴木武幸専務である。
鈴木氏と言えば、スーパー戦隊シリーズのプロデューサーを十五年も連続して務めた人である。しかし平成仮面ライダーにはほとんどタッチしていないはずだ。確かに『クウガ』のプロデューサーではあった。途中からだが。管理職の人がそれほど現場の実務にコミットしていたとは思えない。そしてググってみると、平成仮面ライダーの成功は、自分の手柄だと思い込んでいるような発言も多々出てくる。
これはかなり深刻な事態である。女性の視聴者を獲得するためには、ぬるめの話にする必要があるのだ、という先入観を持っている人間が、上の方に居座っているということだ。こういう管理職の連中が現場に口出しをしてきたら、一体どういうことになるのか。
竹熊健太郎などという一編集者の戯言なんかとは比較にならない。
それにしても、この記事、この後で戦隊シリーズでは仮面ライダーほど役者がブレイクしていない、という話になるのだが、その理由の分析は読んでいて「なるほど」と思わせる。十五年も戦隊の現場に関わってきたのは伊達ではないということか。
だったら戦隊の話だけしてろよ。
鈴木武幸氏という人は、私の尊敬する人の一人である。戦隊シリーズ第一期は、女戦士は男たちのオマケという雰囲気を、完全に払拭するには至らなかった。払拭できたのは、鈴木氏がチーフプロデューサーに就任してからである。女の人もきちっと生きていける、そういう時代の理想の女性像を示していきたい、と言っていた鈴木氏である。その人が今じゃあ、女の人に見せるには、暗くて陰のあるものじゃダメ、どうせ顔しか見てないんだし、なんてこと言ってるのか。
東映の拝金主義と『がんばれ!! ロボコン』
1〜26話 一期生編 70点
27〜50話 二期生加入編 80点
51〜72話 大山美容院編 60点
73〜94話 三期生編(前) 20点
95〜118話 三期生編(後) 20点
「したがって、総合評価、『がんばれ!! ロボコン』50点」
「えーっ! なんでなんで!? 超合金もたくさん売れたし、ポピーさんを大儲けさせたんだよ!」
「キャラクタービジネスに関しては100点だった。
しかし、人気が出たために番組の引き伸ばしを図ろうと無理をしたため、二年目以降になるとマンネリの話が続出した。それにロボコンが成長してしまうと物語が終わってしまうという制約から、ロボコンを同じ失敗ばかり繰り返している、向上心のないロボットであるかのように描かざるをえなくなってしまった。
たまにロボコンが活躍しても、無理矢理に減点の種を見つけてハートマークをとらせないという姿勢もあからさますぎた。
それに超合金を売りたいがために、次から次へと新しいロボットを登場させる。三期生になると全然キャラが立っておらん。ロボメロなどロボペチャの下位互換にしかなっていない。
その上、マンネリを打破しようと焦って、ロボチャンなんかを出し、ご都合主義的なストーリーのためにロビンまでものすごく間抜けなキャラクターにしてしまったではないか。
何よりいけないのは、おもちゃの売上を伸ばすことに目的を特化させ、視聴者の子供たちを楽しませるという本来の任務をおろそかにしたことだ。この番組がなまじ成功してしまったがために、東映の姿勢が完全に固まってしまい、これが二十一世紀になってもなお続いているんだぞ!
したがって50点減点。50点だ」
「うららぁ〜」
東映特撮YouTubeで『がんばれ!! ロボコン』全話視聴完了。これを見ると、東映の拝金主義的な姿勢ってのは最近になって始まったことではないんだなあ、とつくづく思った。義理欠く恥かく人情欠くの東映三かくマークは伊達じゃない。
ただ昔は才能のあるスタッフもたくさんいた。職人魂と商人魂がガッチリと組み合わさって、ヒット作をたくさん作ることもできた。その後職人としての腕は落ちる一方なのに、商人としての才は健在なままだから、ゼニゲバ体質だけが目立ってしまうということなのだろう。
ちなみに職人魂だけがあって商人魂がなかったのが円谷プロ。
美人の女優を目当てに見る特撮
前回に続き、竹熊健太郎氏のツイート「女性が見る特撮は私にとって特撮ではない。特撮魂が曇る。」について。
これ自体は単なる差別発言だから論じるまでもないが、イケメン俳優目当てに特撮を見る女性に対する侮蔑感情は、ある程度の広がりを持っているように思われる。つまり、ああいう女どもは話の筋にも映像の面白さにも興味はなく、単に顔の良い俳優が出さえすれば満足なのであり、そんな女どもに媚びれば特撮が衰退の道をたどるのは必至である、という決めつけのことである。
それが当たっているかどうかは、私は今の特撮には詳しくないから判断できないが、過去においては確かにそういう事態はあった。ただし男女逆だが。今、「戦隊ヒロイン列伝」を書き直している途中だが、戦隊シリーズの歴史においても、なぜこんな女優が起用されたのか、不可解というケースが何度かある。つまり、演技やアクションがうまいわけでもなく、その女優の持っている雰囲気が作品の雰囲気に合っているかどうかも関係なく、とにかく美人を出しさえすれば大きなお友達が食いついてくるだろうという、安直な考えをスタッフが持っていて、そのために起用されたのではないかと思われるケースが。
1980年『電子戦隊デンジマン』のデンジピンク・桃井あきらについても、その一人であったとしか思えない。
デンジピンクのベスト・エピソードといえばもう誰が見たって第18話「南海に咲くロマン」である。この回の桃井あきらは本当に魅力的なキャラクターだった。序盤は一向に定まらなかった彼女のキャラは、この回を境に固まるかと思われた。しかしその後もキャラのブレは続き、あげく第43話「謎なぞ七色レディ」である。「桃井あきら」には何の興味もない、「小泉あきら」にしか興味がないという人のために作ったような話であった。『スーパーヒロイン画報』(1998年)なんかは、これをベスト・エピソードに挙げている。ふざけんな!
竹本弘一監督は、小泉あきら氏のことを非常にかわいがり、目をかけていたという。その割には、彼女に魅力的な演技をさせることに、何の興味もなかったのだろうか。厳しい指導も何もなかったという話もまた聞く。
小泉あきら氏は現在店をやっており、しかしデンジピンクのファンが来店することをあまり快く思ってはいないらしい、ということを前に書いた。彼女自身『デンジマン』に対して忸怩たる思いを抱いているという可能性も、ひょっとしたらあるかもしれない。『デンジマン』自体は名作なだけに……。
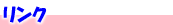
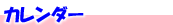
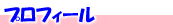
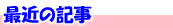
- 仮面ライダーの人気低下は本当か (12/31)
- 特撮技術の進歩は何のため? (12/29)
- 『ジェットマン』の価値を貶めるのはやめろ (12/27)
- デンジピンクは一体何を牽引したのか (12/24)
- 誰が石川大我の足を引っ張るのか (12/21)
- プロレスと同じ道をたどる特撮ヒーロー (12/19)
- 誰がスーパーヒーロー大戦を批判できるのか (12/16)
- 戦隊にオーディションは必要か?(後編) (12/14)
- 戦隊にオーディションは必要か?(前編) (12/12)
- 東映ほどファンを大切にする会社はない(悪い意味で) (12/10)
- 二度死んだ熊野大五郎 (12/07)
- イケメン特撮ブームの裏で何が進行しているのか (12/05)
- 東映の拝金主義と『がんばれ!! ロボコン』 (12/03)
- 美人の女優を目当てに見る特撮 (12/01)
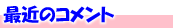
- スーツアクターという難題
⇒ Manju (10/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19)
- スーツアクターという難題
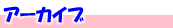
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)