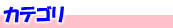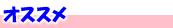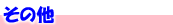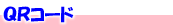女性アクション映画(大人向け)のお寒い状況(後)
(前回からの続き)もう一つのやり方は、清純派アイドル映画にしてしまうことである。実際、当時の志穂美悦子には当時そういうイメージがあったし、女性ファンの方が多かったくらいである。エロな雰囲気を作品内に持ち込んだりしたら、そっちのほうが総スカンをくらったこともある。ところがアクション映画である限り、「エロと暴力」のうち、前者はともかく後者については当然のことながら排除することはできない。ヒロインが敵にとらわれ逆さ吊りにされ痛めつけられているにもかかわらず、敵の男のうち誰一人としてヒロインを裸にしようともしない、それどころか性的な視線を浴びせることすらしないという、ものすごく不自然な事態が出来する。もちろんそれを「お約束」だとして了解した観客にとっては十分に楽しめる映画なのだろうけど、戦う女性の抱く心理の綾や襞の描写に何の期待も持てないことについては、ピンキー・バイオレンスと何の違いもない。
と、そのように考えた場合、かつて戦隊シリーズがなぜかくも魅力的なヒロインを毎年毎年送り出すことができたのか、分かるのではないか。要するに、ここは「エロと暴力」の邪悪さ渦巻く世界だということを、あからさまではないにせよ、ほのめかすような描き方をすることによって、なお正義のために生きるヒロインは、その気高さと清らかさが引き立てられたのである。そして最近の戦隊シリーズにおいて、まともなピンチシーンが描かれなくなっていったことと、ヒロインの魅力が少なくなっていったことは無関係ではないだろう。
さて、冒頭にかかげたのは『戦う女たち』という本である。これは日本の女性アクション映画についての、八人の論客による論考集である。そして編者は、戦隊ヒロインについて、一章を割こうという発想もなかったようだ。「ジャリ番」としか思っていなかったからだろうけど。そしてその結果として、資料的価値は別にして、考察や論考という点に関しては、何一つ読む価値のない本が出来上がったわけである。戦隊ヒロインをずっと見続けてきたような人間にとっては、だが。
高尚な文芸作品よりも、大衆に寄り添った低俗な作品のほうこそが映画の王道だ、などと言う評論家や研究者は最近多い。女性アクション映画などという、それ自体いかにも低俗という雰囲気の漂うジャンルを扱った本が出版されるという事実がそれを裏付ける。しかしそういう人たちですら、子供向け特撮ヒーロー番組なんてのは、視野の外にあるようだ。
デンジピンクは一体何を牽引したのか

小熊英二『〈民主〉と〈愛国〉』
『電子戦隊デンジマン』のデンジピンク・桃井あきらに関しては、悪く書いてはいけないみたいな意識が自分にはあり、そういうのもよくないと思って、今回「戦隊ヒロイン列伝」を書きなおしていたら、桃井あきらに関しては前に比べて思い切っきり評価が辛くなってしまった。その弁解をする。
私は『デンジマン』はリアルタイムでは見ていない。だから、見ていた人から「当時はすごく人気があった」と言われたら、どうしてもそこには圧迫の構造が生じる。『スーパーヒロイン画報』(1998年)にも「特撮ヒロインブームを牽引(した一人)」なんて書いてあり、こういうことを書いてある本は他にも多い。しかしそれは、単にその執筆者があきらのファンで、自分が感じたことを当時の人間すべてが感じたことのように書いているだけなのではないか。今回「謎なぞ七色レディ」をあらためて見て、こんなにつまらない話だったのかと愕然とした。
当時の雑誌とか色々調べているのだが、あきらがそんなに人気が出たなんて資料はいくら探しても見当たらない。そんなに人気が出たのなら、次作の『太陽戦隊サンバルカン』でなぜ女戦士がいなかったのか。また小泉あきら氏もこの番組の後は二度と女優はやっていない。彼女の魅力はあくまでもモデルとしてのものであって、女優としてのものではないことは明白である。特撮ヒロインブームの牽引車はやはり桃園ミキだと考えるのが妥当であって、彼女が人気が出ることによってそれ以前の戦隊ヒロインにもスポットライトが当たるようになった、と考えたほうが辻褄の合うことは多い。
「体験」とか「実感」というものに基づいた証言などに重きを置くものではない。それを許せば、結局は声のデカいもの勝ちになってしまう。昨今の憲法九条をめぐる動きを見ていると、日本の戦後の反戦平和運動の限界もやはりそのへんから来ているのではないか。などと書くと急に話がでかくなって申し訳ないが、「戦争体験の悲惨さを語り継ぐ」という形でしか国民の反戦意識をかきたてる手段を持たなかったがため、「戦争中が暗かったというのはサヨクの嘘っぱちであって、米英撃滅・聖戦完遂のために国民の心は一つで意気は高く明るかった。自分はそのように体験した」などと言う奴が出て来ると、対抗手段がなくなってしまうのである。ま、そういう「体験」を語る人というのは、戦中世代といっても深刻な飢餓や空襲にあうことのなかった、比較的恵まれた立場にいた人に決まっているんだけど(と、小熊氏の本に書いてあった)。
立花レイが欠いていたもの
『科学戦隊ダイナマン』の立花レイというキャラクターには何が足りないのだろうか、ということをずっと考えていたのだが、やっと気がついた。レイが仲間の男たちの指示に逆らうようなシーンが一回もないのだ。
もともと特撮ヒーロー物は男の世界である。女戦士はあくまでも異物であった。だから、戦隊においては仲間の男たちの足手まといになることもあったが、それと同時に、男どもが四人がかりで思いつきもしなかったような方法で局面を打開しようとするようなこともあった。ところが戦隊シリーズも第七作目ともなれば、女戦士も特殊な存在ではなくなった。女ならではの特質を、男のほうが取り込んでしまったからだ。ジョーカー的な存在であることをやめ、単に戦隊の一員となってしまっては、女にとっては旗色が悪い。力では男にかなうわけがないからだ。
じゃあその「女ならではの特質」ってなんだ、と言われれば、やっぱりそれは「やさしさ」ということになるのではないか。
といっても、ヒーローがくじけそうになったり迷ったりしたときに、ヒロインのやさしい笑顔に励まされ、ヒーローは再び戦うための勇気を取り戻す――などという限定的なイメージで「やさしさ」をとらえてはならない。
どんなに強い力を持っていても、それをどの方向に向かって振るえばいいのかが分からなくては意味がない。ヒーローは、弱い人たち、苦しんでいる人たちに共感し、彼らを助けたいと思うことによって、その力をどっちにむけて振るえばいいのかを知る。強さのないやさしさ、やさしさのない強さ、いずれも意味がない。このような認識に立って初めて強さとやさしさが同等の重みを持つ価値観であることが理解できようというものだ。
レイは別にやさしくなかったわけではない。ただそれまで戦隊シリーズがずっとやってきた「女の子だからやさしい、男たちに比べて特にやさしい」という描き方をやめて、ただ普通にやさしい女の子として描いただけだ。そしてダイナレッド・弾北斗はというと、強さとやさしさの両方をそなえたパーフェクトなヒーロー。これじゃあレッドの指示に反した行動などとれるはずがない。
この事態は、今度は女のほうから逆に「男ならではの特質」を取り込まんとすることによって打開が図られた。単に女だからやさしいというのではなく、理性を伴ったやさしさを持つ必要性。それを実現させたのがシリーズ第九作『電撃戦隊チェンジマン』ということになるのだろうか。
立花レイ論
渚さやか・翼麻衣論
立花レイ論(続)・夢野博士にはなぜ美人の秘書がいないのか
『ゴレンジャー』 加藤陽子(007)、林友子(008)、中村春子(009)
『ジャッカー』 〈後半〉林恵子(7号)、山本純子(8号)、飯島佳子(9号)、10号
『バトルフィーバー』 青葉ミドリ、中原ケイコ、上野トモコ
『デンジマン』 松尾千恵子
『サンバルカン』 嵐山美佐
『ゴーグルファイブ』 若木みどり、山本さゆり
『科学戦隊ダイナマン』は、味方に女性のレギュラー・準レギュラーのいない、初の作品となった(子供はのぞく)。
戦隊シリーズ初期において、女戦士はあくまでも「男の役割をする女」であった。だから「女の役割をする女」が別に必要だったのだ。ところが『大戦隊ゴーグルファイブ』で桃園ミキが、一人で両方の役割を完璧にやってしまったもんだから、じゃあ次からは一人で済まそう、ということになったのは当然の成り行きといえる。
戦隊シリーズの黎明期においては、ヒロインはどんなに辛くても弱音を吐くことなど許されなかった。たまに吐くことはあったが、それは、自分は戦士として劣った存在ですと白状するも同然の行為とみなされた。ヒロインはあくまで「男」でなくてはならなかったのである。それを改めたのが多分『ダイナマン』ということになるのだろう。第51話(最終話)でレイが弱音を吐いて弾に叱られるというシーンがサラッと描かれることによって、ようやく戦隊内における男と女の関係は、普通の人間のものになったと言える。
戦闘能力という点で男が女よりまさっているのは生物学的事実なのだし、男が女をリードしたり守ってあげなくてはと思ったりすることは、何でもかんでも差別だと決め付ける煽動家の言うことに耳なんか傾ける必要はないのだが、特撮ファンの中でもフェミニズムを中途半端にかじった連中がそんなことを真に受けたりしているみたいで、困ったものだ。(もちろん、フェミニズムを本格的に学習した人間はそんなことは言わない。)
男が女を守りたいと思うことと、対等の相手とみなすことは絶対に両立し得ないものではない。
萩原佐代子氏はブログをなさっておられるが、昼飯に何を食ったとか、どうでもいいことばかり書いてばかりいないで、立花レイについて何か書いてくださらないものか。実際に演じた人が語る言葉ほど、参考になることはないのに。
桃園ミキについては贔屓しすぎたかしらん。書き直す予定。
桃園ミキ論
立花レイ論
戦隊ヒロイン列伝の方向性
どうも方向性を誤っているような気がしてならぬ。
これではまるで、私が作中でのジェンダーの描かれ方だけに興味を持って戦隊シリーズを見ているみたいではないか。これではフェミニズム批評がやってることとあまり変わらない。
たとえば立花レイについては問題点ばっかり書いてしまったが、これは、レイが魅力的なキャラクターであることは自明の前提だと思ったからこういう書き方をしたのだ。ところが、これを読んで今の若い戦隊ファンが、昔のヒロインは問題点が多かったのだなあ、なんて思ったらどうしよう。
立花レイがどんなふうに魅力的であったか、それが今の若い戦隊ファンにも伝わるような文章を書けと言われたら、まあ、私は書ける。だけどそういうのってレイのファンがやるべきことなんじゃないのか。なんでやらないのか。まとまりのない感想文をダラダラとあげてるブログはいっぱいあるけど。まあその程度のファンしか生み出せなかったということなんだろうが。
私自身はレイは魅力的なヒロインであるとは思うが、特に思い入れはない。レイの魅力について書くのはレイのファンにまかせておいて、私はジェンダー論に特化したサイトにしていけばいいやと思って始めたことだ。しかし実際そういうことやってるレイファンなんぞ一人もおらんという状況では、こっちとしても考え直さなくてはならん。
あ、あとイラストについては無茶苦茶手抜きしたことは認めます。すみません。
戦隊ヒロイン列伝
立花レイ論
馬鹿フェミニズムと特撮評論
『バトルフィーバーJ』の第26話「包帯男の仮面報告」。
『電子戦隊デンジマン』の第18話「南海に咲くロマン」。
『太陽戦隊サンバルカン』の第29話「美剣士白バラ仮面」。
戦隊シリーズ初期作品の、それぞれのヒロインベストエピソードを選べと言われたら、このへんは鉄板ではないか。
共通しているのは、いずれもヒロインが仲間の男たちの指示に逆らって行動するという点だ。こういうことを書くと私自身がフェミニストみたいだが、そうではない。筋力や体格には性差というものがあり、女は男に戦闘能力という点では劣る。だから女が男の指示に従うのは当たり前。そしてそのような前提があった上で、女が男に逆らうからストーリーが面白くなるのだ。それを何か勘違いして、女が強ければ強いほど面白くなると思ったのだろうか、その後の戦隊シリーズは、普段どんな弱い人間でも強化スーツを着用すればたちまち無敵の超人と化すような話になっていき、結果男も女も戦闘能力の差はなくなっていった。そこで女が男に対して対等な口をきいたところでそんなものは当たり前すぎて、面白くもなんともない。かえって空しいだけだ。
たとえば文芸評論の分野では、これは女を弱く描いているからダメな作品だ、女を強く描いているからイイ作品だ、なんてことを言ってるやつはいない(まあたまにいるが)。人間というものは多面的なものであって、一つの物差しだけで作品の評価を決めることはできない。だが特撮ではこういう単細胞的な評論がまかり通り、斎藤美奈子氏の『紅一点論』みたいな愚劣な本がもてはやされたりしている。
マンガやアニメの評論も、昔はひどかったが、最近はちゃんとしたのが出てきている。こんなところでも特撮は差をつけられている。なさけない。
ちなみに、先にあげたエピソードに共通していることがもう一つあって、すべて脚本がサブライターである曽田博久氏によるものである。
曽田氏がメインライターに就任した最初の作品である『大戦隊ゴーグルファイブ』で、戦隊ヒロイン人気の大爆発が起こったのは、まあ当然の結果だ。
ダイアン・マーチン、汀マリア論
桃井あきら論
嵐山美佐論
「女リーダー」というまやかし
『忍者戦隊カクレンジャー』を見返していてつくづく思ったのだが、ニンジャホワイト・鶴姫ってのは本当に名目だけのリーダーだったのだな。
男四人は昨日今日戦士としての使命に目覚めた連中ばかりである。だから、カクレンジャーのリーダーとしての使命を代々受け継いできた家系の出身である鶴姫が、引っ張っていかなければならないはずなのだが、体力は仕方ないとしても忍術の腕前、さらに判断力や統率力といった面でもサスケに劣るのはどうしたことだ。実質的なリーダーは最初からサスケである。白面郎登場以降はもう論外。いったいなんのためのリーダー設定だったのやら。
『未来戦隊タイムレンジャー』のリーダーがタイムピンク・ユウリなどと言い出したのは誰だろうか。作中ではそんなことは一言も言われていない。第30話では五人の意識ではリーダーは決まっていないと描かれているし、実質チームを束ねているのはタツヤである。ユウリは人付き合いが苦手なタイプである。そこがユウリの魅力なのだが、しかしそんなタイプにリーダーがつとまるわけないだろう。
戦隊シリーズは男社会である。そういう批判をされることがある。だからそれをかわし、いや女がリーダーをつとめた作品もありますよ、などという姑息な言い訳をするために、無理矢理ユウリがリーダーだったことにされているような気がする。
だが、戦隊が男社会なのは当たり前ではないか。子供番組的オブラートにつつまれてはいるが、あくまでも戦隊は「軍」なのである。男社会でない軍などあるわけがない。
戦隊内における男女関係とはどうあるべきかについて根源的な考察もなく、単に世の母親やフェミニストに媚を売って批判をかわそうということしか考えていないから、こういう変なことになる。
そういえば昨年度は『侍戦隊シンケンジャー』で女レッドの登場が騒ぎになっていたけど、あれはどうなったのだろうか。(実はまだ見ていない。)
昔のヒロインの似顔絵を描くことの困難さ
最近のヒロインだと、すぐに写真集が出る。その写真というのは、専門のカメラマンがその女優が最もかわいく見えるようにプロのテクニックを用いて撮ったものである。その中から適当に一つ選んで(まあできるだけ描きやすいのがいい。左斜め三十度なんてのがあれば最高だ)、それを見ながら描けば、まあかわいい絵が描ける。楽なもんである。
しかし昔のヒロインだとそうはいかない。
たとえば、カレン水木にはロングヘアのイメージを持っている人も多いと思うが、全35話のうちロングだったのは最初の8話だけである。「これは似合わない」ということに作っているスタッフもすぐに気づいたということなのだろう。(ちなみにジャッカー電撃隊キャスト鼎談によれば、あれはカツラらしい。)
じゃあなんでロングのイメージがあるのかというと、歴代戦隊のヒロインの写真集が出るとき、その時期の写真しか載ってないからだ。私はそんな絵は描きたくない。やはりそのヒロインが最もかわいい髪型をしていた時期のを描きたい。だから映像を見て描くことになる。そのヒロインがもっとも魅力的に映る角度、もっとも魅力的に映る表情はどれか。そういうのも全部自分で判断して描くことになる。
非常にめんどくさい。
汀マリアも前髪おろしていた時期のほうがかわいいと思うんだが、これも写真集への収録は絶望的ときている。
昔はろくにスチル写真なんか撮ってなかったからな。特撮ヒロインなんかで商売になるなんて発想自体がなかったし。
よく、掲示板とかブログとかで、歴代戦隊ヒロインの容姿の品定めをし、ランクつけたりしている人がいる。
大いに結構だが、やるのなら同じ条件でやれよな。
強すぎたがゆえに……(カレン水木論)
朱に交わっても赤くなるとは限らない(ダイアン・マーチン、汀マリア論)
ぶかぶかのゴレンジャースーツの性能は
ゴレンジャースーツは今見ると「ぶかぶか」という印象がある。
スーパー戦隊シリーズで、強化スーツに光沢がつき、体にピッチリと張り付くようになったのは『科学戦隊ダイナマン』(1983年)からであるが、この材質の変化は意外と大きな影響をシリーズに与えたのではないか。いかにも世界最高の科学技術を用いて作られた、ハイテクスーツという印象。しかもデザインもスマートでシャープ。運動神経ゼロの人間でも、このスーツを気さえすれば五倍十倍のパワーが出、無敵のスーパーヒーローとなれると言われても全然おかしな感じがしない。
『ダイナマン』以降も変身前アクション重視の姿勢は変わらなかったが、見ていて「あんなすごいスーツを持っているんだから、敵に遭遇したらさっさと変身したらいいのに」という印象を持たないわけにはいかなかくなった。90年代なかばあたりから、役者のアクションはほとんどなくなる。そして、特に強い体力も精神力も持っていない人間でも、強化スーツさえ身にまとえば安心して戦士になれるんだという路線が主流になっていく。光沢のある材質はその下ならしをしたと言えるのではないか。
ちなみに『ゴレンジャー』の劇中では、強化スーツの性能や原理について、詳しい説明は一切なされていない。石森章太郎によるマンガ版では少し詳しく描かれていて、パワーアップは1.5〜2倍だそうだ(図参照)。あのもっさりした、ぶかぶかのスーツの性能はそんなもんだろう。
そしてそんな程度の性能しか持っていない強化スーツを着て、凶暴な敵が待ち構えている戦場へと女の子がおもむくのを、視聴者はハラハラドキドキしながら見つめていたわけである。
こういう感覚というのは、最近の若い戦隊ファンとかには分かってもらえるのだろうか?

性能の低さが生んだリアリティ ペギー松山
戦隊ヒロインはお茶くみを拒否する
『天装戦隊ゴセイジャー』はまだ見ていないなのだが、第4話の大掃除のシーンがちょっとした話題になっているみたいなので、そこだけ見てみた。
部屋がおおかた片付いたので、モネは自分と自分の兄貴であるアグリの二人のためだけにコーヒーをいれる。
ハイド「あれ、俺のは?」
モネ「え!? 自分でやればあ?」
コミカルな芝居を挿入しようとしたが演出に失敗して、単に険悪なだけの展開になってしまったのではと、推測している人もいる。しかし、ひょっとして作り手は意図的にモネをそういうキャラクターにしたかったのではないか。
コーヒーを五人分いれるのも二人分いれるのも、大した手間の違いはないだろう。しかし、女にしてみれば、好きでもない男のためにコーヒーを入れるなんて一滴たりともイヤだ。イヤなものはイヤと言う。普段職場で心ならずもお茶くみをさせられている全国のOLはこのシーンを見て溜飲が下がるはず……。
戦隊ヒロインの歴史を見てみると、仲間に対する思いやり、気配りという点では昔のほうが圧倒的に上である。仲間がケガをすれば心配し、率先して包帯を巻く。それが女の役目だというふうに。別に好きでやっていたかどうかは分からない。心の中では女性差別だと思っていたかもしれない。しかし相手は地球の平和を守るために、命をかけて共に戦う仲間である。チームの雰囲気を常に良好な状態に保っておくことは戦士にとって最も優先されるべきことであって、仲間に包帯を巻いてもらいたがっている奴がいれば巻く。そういうものだ。
時代が下がるにつれ、女性差別と指摘する声に従ったのか、そういうシーンはなくなっていった。かといって男が包帯を巻くようになったわけでもない。包帯を巻くシーンそのものがなくなっていったのだ。そして戦隊メンバーの人間関係はどんどん希薄になっていき、ともに命をかけて戦う仲間だという意識も年を追って減少する。
モネのお茶くみ拒否も、そういう流れの上にあるのであろう。
ペギー松山論 あるいは変身前アクションの必要性
近日中に大幅にリニューアルして、戦隊ヒロイン全般について取り扱うサイトにしようと思っているのだが、その第一弾としてペギー松山論をUPするつもりである。しかしこれが全然筆が進まない。
特撮ヒロイン史上におけるペギー松山の位置づけについてなら、いくらでも書ける。最近の戦隊しか見たことがないという人でも、彼女の偉大さについて異論をさしはさむことはできまい。というか、既に「特撮ヒロインの女性学」ですでに書いたしそれに付け加えることもないのであるが、そうではなくて、ペギー松山自体の魅力についてだ。
書けば書くほど近年のヒロインの批判になってしまう。
彼女が持っていた魅力というのは、すべて最近のヒロインが失ってしまったものだからだ。
時代の流れに従って戦隊ヒロイン像も代わり、新しい魅力を加えた結果として古い魅力を捨てた、というのではない。単なる劣化である。
たとえば、最近の戦隊でも、一年に一度くらいは、変身前アクションがある。
変身すれば強いんだから、変身して戦えばいいんでないの? なんで変身前アクションなんかする必要があるの? 最近のファンならそう思うかもしれない。だが、一見ムダに思えるようなことが、作品の強度を支えていることはよくあることだ。だから、昔みたいにやるのは無理でも、せめて一年に一度くらいは、と思ってやらせているのだ。
作り手の側はそのことは分かっている。
一年に一度やる程度のことで何が変わるものか、と思う人もいるかもしれないが、私はその作り手の心意気は買う。
分かってないのは見ている側だ。
昔の戦隊なんか観たことない連中が、昔の戦隊について勝手なイメージを抱いたまま、ブログとか掲示板とかでデタラメなことを書いていても、まあ仕方ないなあとは思う。しかしかなりの高齢者のはずなのに、そういうことを書いてる連中がいる。
やっぱり老人になると記憶もぼけ、感性も磨耗するんだろうか。ああはなりたくない。
とにかく、今後歴代戦隊ヒロイン全員について書くつもりなのだが、ペギー松山の魅力について論じることができなければ、何も始まらない。
さとう珠緒「オタクはキモイ」発言の真相
『超力戦隊オーレンジャー』でオーピンク・丸尾桃を演じた珠緒(現在は改名してさとう珠緒)氏が、「オタクはキモイ」とかいう趣旨で何か言っているらしいというので読んでみた。
私、昔からオタク系からは好かれないんです。グラビアっぽいことをしていても、そういうファンがつかなかったんです。戦隊モノやっていたのになあ。歴代ピンクは人気あったのになあ。私だけダメだったみたーい。でも、秋葉系の人たちは見る目があるって証拠ですよね。
それ、オタクは関係ないから。
戦隊ファンというのは何か特殊な価値基準を持っているということにしたいみたいだが、そんなことないって。普通に脚本や演出や役者の演技力を見て作品の出来不出来を判断している。歴代の戦隊ヒロインで人気があったのはいずれも役者に魅力があり、いい脚本や監督に恵まれた人たちばかりであって、オーピンク・丸尾桃の人気がなかったとしたら、まあ、そゆこと。
『オーレンジャー』に関しては、一番の問題は脚本であろう。シリアスで行くのかコミカルで行くのか最初から迷走状態。さとう氏自身は悪くはなかったと思うが、しかし今やタレントとして幅広く活動している彼女にしてみれば、たかが一年やそこらで芸能界から消えてしまったような連中よりも、自分の方を下に評価する連中が存在しているなどということ自体、我慢がならないことと見える。だから戦隊を見てる連中というのはオタクであり、つまり社会不適応者で女に幻想を抱くキモイ男のことで、そういう連中に媚びるように演じるのでなければ人気は出ないのだと、どうもそういうことにしておきたいらしい。
そういえば最近、超力戦隊の制服を14年ぶりに着て『ゴーオンジャー』の劇場版の舞台挨拶に行ってきたとかいう話があったが、いい年して何やってんだか。そんなことしたってオーピンクの評価が上がるわけないし、歴代戦隊ヒロインの輝く星々の列に今さら加われるはずもない。しかしあんたは現実にタレントとして今成功しているんだから、そんなものに敵愾心なんか燃やしてどうするんだ。大人げない。
オタクは世界に誇る日本の文化だと主張している人がいる一方で、とにかく自分にとって都合の悪い連中を一括りにしてレッテル貼りする言葉としても通用している。この議論の行く末は一体どっちだ。
ジェンダーフリーとスーパー戦隊
謀巨大掲示板に「目立たない戦隊ヒロイン!サヤ・大河冴・樹らんる」などというスレが立ったことがあった。その後宇崎ランが加わって、近年のキャラ立てに失敗した戦隊ヒロイン四天王みたいな言われ方をしているが、彼女たちを見るにつけ、東映はジェンダー理論も知らないで戦隊シリーズを作り続けているんだなあと思うと溜息が出る。(知っててあんなの作ったというのなら、処置なしだが。)
昔は五人の戦士の中に女一人だけといったら、もうそれだけで自動的にキャラ立ちしていた。それは、女は女らしくするのが当然だったからだ。男にはない優しさ、可憐さが魅力のポイントになっていた。
問題がないわけではない。一つの型にはめるわけだから、毎年同じようなタイプのヒロインになってしまう。女二人を出したら、二人とも同じようになる。昔の紅二点戦隊でヒロインの差別化に失敗したのが多いのはそれが理由である。
だからその後、「女なんだから女らしく」という性別役割分業イデオロギーを否定する流れでキャラクター作りが行なわれるようになったのは、まあ当然といえる。ではどうするのか。ムードメーカーをやるのか生真面目なタイプにするのか、男どもを引っ張ったりするのか。どういうタイプにするのか大して詰めずに今までのクセを引きずって、女一人だけだから自動的にキャラ立ちするだろうと甘い考えのままテレビ画面に送り出されるヒロインが続出することになった。
1998年以降の紅一点ヒロインで成功したといわれているのは、そういうかつての性別役割分業を受け入れた『救急戦隊ゴーゴーファイブ』のマツリと、そういう性別役割分業を敢えて否定するスタンスをとった『未来戦隊タイムレンジャー』のユウリだけだ。女らしいのか女らしくないのか中途半端にやり過ごそうとした者は枕を並べて討ち死にである。紅二点戦隊のほうがまだ成功率は高い。
「女は女らしく」という概念は女性の生き方を縛り自由を奪うものである、という主張は確かにその通りである。では拘束から解き放たれた女性はその後いかに生きるべきか、それに関して明確なビジョンも持たず、ただ闇雲に性別役割分業を否定した先には何があるのか。それを戦隊シリーズは教えている。
戦隊シリーズにおける戦士の役割分担(理論編)
戦隊シリーズにおける戦士の役割分担(実践編)
戦隊ヒロインのアイドル化と純朴幻想
「べつに女優なんてなりたくないし。地味で真面目な仕事のほうが好きだし向いてるし」
『魔法戦隊マジレンジャー』第8話「君こそヒロイン」での小津麗の台詞に、思わず噴いてしまった。
最近は戦隊ヒロインのオーディションも無茶苦茶倍率が高いそうで、その難関をくぐりぬけたということは、「なんがなんでもこの役を射止めてやる!」というギラギラした野心の持ち主にちがいなく、そこでこういう台詞をしゃべれと言われた彼女は一体どんな心境だったのだろうかと想像してしまった。
とまれ、このエピソード、アイドルという存在のすごく鋭いところをついた話ではあった。
やっぱりみんな、純朴な女の子が好きなのである。
アイドル界は昔から、そういう女の子を発掘せんと血眼になっていた。しかしそうなればなるほど、そこから遠のいてしまうという矛盾。
1980年代ごろまでの戦隊ヒロインはどうであったか思い出してみると、やはりガツガツした上昇志向の持ち主もたくさんいたかもしれないが、歌手とか普通のドラマとかに比べれば、子供向け特撮ヒーロー番組なんてのはアイドル界にとっては僻地も同然だったし、こんなところで人気が出たところで次の仕事につながる可能性なんてなかったし、だから視聴者には、この女の子たちは自分の野心のためではなくて純粋に子供たちの夢のために演技をしているのだと勝手に思い込んで、純朴さを見出し夢中になっていた。(まあ錯覚だったかもしれん。)
彼女たちのほとんどは、番組が終われば速攻で芸能界から消えていったが、そのことによって彼女たちに対するファンの幻想はますます強化された。
そうこうしているうちに特撮番組に対する世間の注目度が増し、ヒロインのオーディションの倍率が上がり、現実に成功した女優を輩出するにしたがって、純朴さのレベルはどんどん落ちていくことになる。まあ言っても仕方のないことではあるのだが。
ちなみに、ヒロインが芸能界にデビューするエピソードであるにもかかわらず、荒川稔久氏の脚本ではないという珍しい回。(横手美智子氏である。)
アイドルファンでないほうが、アイドルのツボをかえって知っているのかもしれん。
女レッドがそんなにイヤか
「あんな女レッドはイヤ」なのではない。
「女レッドはイヤ」ということらしい。
女がレッドをつとめること自体が許せない、女が男の上に立ったり、男に命令したりすること自体が気に食わない……そういう意見が出てくるんじゃないかと思ってシンケンジャーのブログとか掲示板とかいろいろ見てまわったら、案の定である。(そういうことを堂々と書いたりしたら女性差別だと糾弾されるので、「だって、男の子はそういうのイヤでしょ、現にうちの甥っ子が……」などと姑息な言い訳をしている人もいる。)
最終回を迎える目前の『侍戦隊シンケンジャー』に、女のレッドが出てきたらしい。「らしい」というのは私は見てないからだが、見てる人たちは大騒ぎらしい。そして上記のような意見も出てきている、と。
一体戦隊シリーズはこの三十年以上もの間、何をやってきたのだ。
女は男に従属すべきものである。そういう考え方はそういう考え方としてありだ。世間の多数派かもしれない。もっともそれは、男は女を守って戦わねばならないという義務とセットになった上での話だが。
女を守る義務は負いたくないが、女が男より上に立つのも許せない、なんてのはただの虫のいい話だ。保守的な考えというのですらない。
戦隊シリーズは、男も女も区別なく、ともに命をかけて戦うというところからスタートしたはずだ。それがいつのまにか、オタクどもに甘ったれた夢を与えるだけの話に変質してしまったのか。
なさけない。
それとも、残りの四話で、そんなオタクどもに冷や水をぶっ掛けるような展開になるのだろうか。いや、ぜひともそうなってほしい。
西堀さくらが りりしくない理由
戦隊シリーズの歴史をひもとくと、やはり昔は女の地位は低かった。1980年代半ばまでは男は姓で、女は名で呼ばれていたなんて、今の感覚からすれば相当変である(戦隊における人間関係と呼称)。
だがいったん戦いが始まれば事情は一変し、「レッド」「ピンク」と完全に対等な呼称を用いる。戦場においては男も女も関係ない、自分たちは互いに命を預けあった仲間だ、という意識がここに現れている。「死ぬも一緒、生きるも一緒」の間なのだ。
時代下がって『ボウケンジャー』(2006年)では逆だ。「ミッション中はコードネームを用いる」という規則になっているのだが、それはつまり明石だけは「レッド」ではなく「チーフ」、他は全員色で呼べということである。といってもメンバーには全然身についた規則ではなくて、普通に姓名で呼んだりする。そしてそのたびに注意が飛ぶ。勝手な呼称を使うな、明石だけを特別扱いする決められた呼称体系を用いなさい、と。
注意をとばすのはポウケンピンク・西堀さくらの役である。
もしさくらが男だったら、すごく嫌な奴のはずだ。
あんまり嫌な奴に感じられないのは、女だからだ。女が男の前でへりくだっても、当然という意識が視聴者の側にあるからだ。
これはつまり、女に対する差別意識が昔に比べて進んでいるということであろうか?
そうではあるまい。
それは多分、自分たちは昔の戦隊とは違って、互いに命を預けあったりしてるわけではありませんよ、そこまで深い絆はないですよ、という意識があるからなのであろう。
最近の戦隊は全然見ていなかったのだが、療養中は浴びるほど見た。いろいろ発見があっておもしろい。
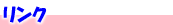
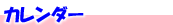
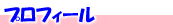
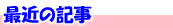
- 女性アクション映画(大人向け)のお寒い状況(後) (02/28)
- デンジピンクは一体何を牽引したのか (12/24)
- 立花レイが欠いていたもの (07/07)
- 立花レイ論(続)・夢野博士にはなぜ美人の秘書がいないのか (06/21)
- 戦隊ヒロイン列伝の方向性 (05/20)
- 馬鹿フェミニズムと特撮評論 (05/07)
- 「女リーダー」というまやかし (04/26)
- 昔のヒロインの似顔絵を描くことの困難さ (04/19)
- ぶかぶかのゴレンジャースーツの性能は (04/05)
- 戦隊ヒロインはお茶くみを拒否する (04/01)
- ペギー松山論 あるいは変身前アクションの必要性 (03/25)
- さとう珠緒「オタクはキモイ」発言の真相 (03/15)
- ジェンダーフリーとスーパー戦隊 (01/31)
- 戦隊ヒロインのアイドル化と純朴幻想 (01/24)
- 女レッドがそんなにイヤか (01/12)
- 西堀さくらが りりしくない理由 (01/11)
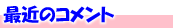
- スーツアクターという難題
⇒ Manju (10/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19)
- スーツアクターという難題
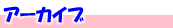
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)