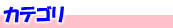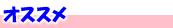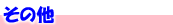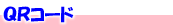『キャプテン・フューチャー』の勧善懲悪
火星人だの金星人だの冥王星人だの、太陽系9惑星(当時)にそれぞれ住民がいるという世界、主人公キャプテン・フューチャーは太陽系を股にかけて活躍する。1940年代に書かれたスペース・オペラを、この21世紀になって東京創元社から全集として復刊しようなどという大それた試みに、これは是非とも読んでみなくてはと前々から思っていたのだが、先日全巻読破したところ。
小説の出来じたいにはおおむね満足した。
読んでる最中は、本当に太陽系9惑星に住民がいるという、こっちの世界の方が正しくて、ボイジャーのほうが間違っているのではないかと一瞬思いそうになったくらいのものだ。
しかしどうにも読後感がすっきりしない。
作者のエドモンド・ハミルトンはSFとしての面のほうに精根を傾けたがっていたようで、だから中盤の『輝く星々の彼方へ!』や『惑星タラスト救出せよ!』になると、ヒーロー物としての面がおざなりになってくる。「この人たちを苦しみから救いたい」「悪を許してはおけない」とキャプテンがなぜ思ったのか、それを読者に対して丁寧に説明しようという作者の熱意がどんどん減っていくように思える。
勧善懲悪のヒーロー物なんてのは単純でくだらない読み物であって、そんなものを作るのは簡単であると思っている人は多い。しかし、勧善懲悪だろうがなんだろうが、ちゃんと読者が感情移入できるような物語を書くのは、大変難しいことのはずではないのか。どうもハミルトンですら勧善懲悪をナメていたのではないかという感じがぬぐえない。
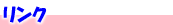
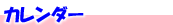
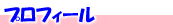
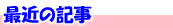
- 『キャプテン・フューチャー』の勧善懲悪 (05/09)
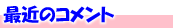
- 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ percetakan jakarta (04/20) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ percetakan jakarta timur (04/20)
- 友里アンヌのファンはおかしい
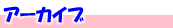
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)