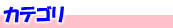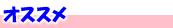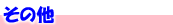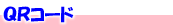ジェンダーフリーとスーパー戦隊
謀巨大掲示板に「目立たない戦隊ヒロイン!サヤ・大河冴・樹らんる」などというスレが立ったことがあった。その後宇崎ランが加わって、近年のキャラ立てに失敗した戦隊ヒロイン四天王みたいな言われ方をしているが、彼女たちを見るにつけ、東映はジェンダー理論も知らないで戦隊シリーズを作り続けているんだなあと思うと溜息が出る。(知っててあんなの作ったというのなら、処置なしだが。)
昔は五人の戦士の中に女一人だけといったら、もうそれだけで自動的にキャラ立ちしていた。それは、女は女らしくするのが当然だったからだ。男にはない優しさ、可憐さが魅力のポイントになっていた。
問題がないわけではない。一つの型にはめるわけだから、毎年同じようなタイプのヒロインになってしまう。女二人を出したら、二人とも同じようになる。昔の紅二点戦隊でヒロインの差別化に失敗したのが多いのはそれが理由である。
だからその後、「女なんだから女らしく」という性別役割分業イデオロギーを否定する流れでキャラクター作りが行なわれるようになったのは、まあ当然といえる。ではどうするのか。ムードメーカーをやるのか生真面目なタイプにするのか、男どもを引っ張ったりするのか。どういうタイプにするのか大して詰めずに今までのクセを引きずって、女一人だけだから自動的にキャラ立ちするだろうと甘い考えのままテレビ画面に送り出されるヒロインが続出することになった。
1998年以降の紅一点ヒロインで成功したといわれているのは、そういうかつての性別役割分業を受け入れた『救急戦隊ゴーゴーファイブ』のマツリと、そういう性別役割分業を敢えて否定するスタンスをとった『未来戦隊タイムレンジャー』のユウリだけだ。女らしいのか女らしくないのか中途半端にやり過ごそうとした者は枕を並べて討ち死にである。紅二点戦隊のほうがまだ成功率は高い。
「女は女らしく」という概念は女性の生き方を縛り自由を奪うものである、という主張は確かにその通りである。では拘束から解き放たれた女性はその後いかに生きるべきか、それに関して明確なビジョンも持たず、ただ闇雲に性別役割分業を否定した先には何があるのか。それを戦隊シリーズは教えている。
戦隊シリーズにおける戦士の役割分担(理論編)
戦隊シリーズにおける戦士の役割分担(実践編)
島本和彦氏よ、お前もか
『週刊少年サンデー』1984.1.5増刊号に掲載された「島本先生 あこがれの大川めぐみちゃんとデート」という記事は、大川めぐみ氏(桃園ミキ役の女優)の大ファンであるマンガ家の島本和彦氏が、彼女に会わせろと編集部に頼んで実現した企画だと思われるが、そこの対談で、なんで子供番組なんか見ていたのかという大川氏の質問に対して、島本氏がこう答えている。
友だちに、ああいう特撮モノのフアンがいたんです。それで、『ゴーグルV』に出てる女の子がカワイイって教えてくれて、それでボクも観て
嘘をつくな!
いや嘘はついてないか。しかしこれではまるでその友だちとやらが、自分と特撮モノの接点だったみたいな言い方だ。自分自身が「特撮モノのファン」であることを隠そうという意図がない限り、こんな答え方はない。ちなみに島本氏は当時『宇宙刑事ギャバン』(同じ年だ)にハマっておられたはずである。
隠すのは仕方がない。それは咎められない。当時は大人になってアニメだの特撮ヒーロー物だのを見ていたら世間から気違い扱いされる時代だったから。自分たちは『大戦隊ゴーグルファイブ』なんか見たくて見ているわけではなくて、このかわいい女の子を目当てに見ているだけだと、みんな自己正当化に躍起になっていた。顔がかわいいから見てるだけなんだと。大川氏にしてみれば、自分の演技を通して視聴者に何らかのメッセージが伝わればと思って彼女なりに一生懸命桃園ミキを演じていたはずだ。そして我々はそこから逃げていたのだ。(私もその一人だったわけだが。今こんなサイトをやっているのは、その償いである。)
月日は流れて、オタクは今や世界に誇る日本の文化だそうである。島本氏も今やラジオで堂々とアニメや特撮の話を熱っぽく語っておられたりする。さて昨年『少年サンデー1983』という本が出た。昔の『少年サンデー』の誌面を復刻したものだが、そこでくだんの大川めぐみ氏とのデートの記事がちょっとだけ触れられてある。それに対して、島本氏はブログで
カラーグラビアなんかは過去の[漫画家にとって]いやなものを引っ張り出してきて…まんが家いじめだ(笑)。
この記事で島本氏は、当時連載中であった『風の戦士ダン』のコスプレをやっている。あこがれの大川めぐみさんに会いたいんです、そのためにはどんな恥ずかしい格好だってしますと、編集部にかけあって企画を実現させたんじゃないのか。燃えるマンガ家にとっては、これは青春の勲章ではないのか。今では「いやなもの」なのか。「ボクは、いつまでも、あなたのフアンです」と言っていた、若き日の自分のに対して言うことがそれか。
また逃げるのか。
久しぶりに桃園ミキの絵
療養中はずっとペンも握れなかったから、画力も相当落ちているはず。けれども久しぶりに桃園ミキを描いてみたら、できあがった絵を見てびっくりした。大きくてつぶらな瞳も、可憐さの中に秘められた精悍さも、スレンダーな体型も、こんなにミキをかわいくかけたのは初めてだ。私は何かをつかんだらしい。
昔は今みたいに写真集やらDVDやらが出ることはなかったから、「もっといろんな彼女をみたい」という気持ちを満足させようと思ったら、自分で描くしかなかった。絵心なんか全然なかったし、絵なんてどうやったら上達するかも全然知らなかった。ただひたすら描いて描いて描きまくるだけだった。そしてようやくここまで来たのだ。
今なら歴代の戦隊ヒロインの全員のイラストも描けそうな気がする。
♪誰が殺したクックロビン〜

戦隊ヒロインのアイドル化と純朴幻想
「べつに女優なんてなりたくないし。地味で真面目な仕事のほうが好きだし向いてるし」
『魔法戦隊マジレンジャー』第8話「君こそヒロイン」での小津麗の台詞に、思わず噴いてしまった。
最近は戦隊ヒロインのオーディションも無茶苦茶倍率が高いそうで、その難関をくぐりぬけたということは、「なんがなんでもこの役を射止めてやる!」というギラギラした野心の持ち主にちがいなく、そこでこういう台詞をしゃべれと言われた彼女は一体どんな心境だったのだろうかと想像してしまった。
とまれ、このエピソード、アイドルという存在のすごく鋭いところをついた話ではあった。
やっぱりみんな、純朴な女の子が好きなのである。
アイドル界は昔から、そういう女の子を発掘せんと血眼になっていた。しかしそうなればなるほど、そこから遠のいてしまうという矛盾。
1980年代ごろまでの戦隊ヒロインはどうであったか思い出してみると、やはりガツガツした上昇志向の持ち主もたくさんいたかもしれないが、歌手とか普通のドラマとかに比べれば、子供向け特撮ヒーロー番組なんてのはアイドル界にとっては僻地も同然だったし、こんなところで人気が出たところで次の仕事につながる可能性なんてなかったし、だから視聴者には、この女の子たちは自分の野心のためではなくて純粋に子供たちの夢のために演技をしているのだと勝手に思い込んで、純朴さを見出し夢中になっていた。(まあ錯覚だったかもしれん。)
彼女たちのほとんどは、番組が終われば速攻で芸能界から消えていったが、そのことによって彼女たちに対するファンの幻想はますます強化された。
そうこうしているうちに特撮番組に対する世間の注目度が増し、ヒロインのオーディションの倍率が上がり、現実に成功した女優を輩出するにしたがって、純朴さのレベルはどんどん落ちていくことになる。まあ言っても仕方のないことではあるのだが。
ちなみに、ヒロインが芸能界にデビューするエピソードであるにもかかわらず、荒川稔久氏の脚本ではないという珍しい回。(横手美智子氏である。)
アイドルファンでないほうが、アイドルのツボをかえって知っているのかもしれん。
『シンケンジャー』からの宣戦布告
本当は他の作品の批判なんて、あんまりしたくはないのである。
たとえば『轟轟戦隊ボウケンジャー』は「30戦隊大全集」というミニコーナーを設け、「俺たちの前のたくさんの先輩たち」の紹介をやっていた。これを見て、今の子供たちが旧作に興味を持ったりするかもしれない。こんなことをやられたら、『ボウケンジャー』の批判は口にしにくい。
東映としては、新作のファンに対しては「旧作も面白いよ」、旧作のファンに対しては「新作も見てみなよ」という態度を一貫して取り続けてきたはずだ。双方、言いたいことは多々あれどグッとこらえて、新作が好きな人も旧作が好きな人もお互いを尊重し批判を手控えるのが双方の利益にかなうことだと言われれば確かにそうである。
「昔はよかった」などと書こうものなら即座に「回顧厨」などとレッテル貼りをしてブログを荒らして回る連中がいるが、ああいう手合いに来られるのもイヤだし。
などと考えていたのだが、最近ちょっと考えを改めることがあった。
たとえば『東映ヒーローMAX』という雑誌で、過去の作品について特集をするときなど、問題点・反省点なんか全然載らないから、読みごたえの全然ないスカスカの文章だらけだ。
批判をしないなどというのは欺瞞である。つまらない作品に対してはつまらないと言わなければならない。意見があれば堂々とぶつけあうべきである。批判のないところには進歩も発展もない。
そして先日、『侍戦隊シンケンジャー』の東映公式サイト、その第三十四幕の分に、1984年まで戦隊シリーズは衰亡期にあった、という意味の文章が載ったのを発見した。
非常に微妙な、遠まわしな書き方がしてあるのは、やはり過去の作品をおおっぴらに批判することに対するためらいがあったのであろうか。「中興の祖」などという難しい言葉を使って文章の真意をカモフラージュしようという意図も感じられる。
とにかく、東映の公式サイトが以前のような馴れ合いの態度をかなぐり捨てた以上、正々堂々とこの挑戦を受けてたつべきであると考えた。
ただ、一つ困ったことが起きた。以前は一つの作品について三十話も見れば十分だろうと思っていたのだが、批判するからにはちゃんと全話を見なくてはなるまい。だいたい十話も見れば、傑作か駄作かくらいは分かる。駄作と知りつつ五十話も見るのがどれほどの苦痛か。こちらとしてはそれだけ腹をくくって批判をするつもりであるので、それを承知の上で私を「回顧厨」と呼びたい人は、好きなだけ呼んでいただきたい。
荒川稔久氏は本当にアイドル好きなのか
『ダイレンジャー』第33話「アイドル初体験」、『ギンガマン』第14話「二人のサヤ」、『ハリケンジャー』第30話「アイドルと友情」、『ボウケンジャー』第37話「憧れの芸能界」、『ゴーオンジャー』第31話「歌姫デビュー」と、戦隊ヒロインがアイドルデビューするような話が多いなと思っていたら、それが全部同一脚本家によるものであると知って二度びっくりした。
一体この人は、こんな話を誰のために書いているのだろうか。
地球の平和を守るために戦っている女戦士が、アイドルになってしまう話の面白さが分からないのか、だって?
分かってるよ。
分かるもなにも、それは我々が1982年に現実に体験したことなんだから。
当時はどんなに熱烈なアイドルファンも、特撮ヒーロー番組なんか絶対チェックしていなかったし、子供と特撮マニアと、あとはたまたま見た者だけが、彼女を見つめていたのだった。「特撮ヒーロー番組なんかに、こんなにかわいい女の子が出ていることを知っているのは、我々だけだ」と思いながら。
そしてそれがきっかけとなって、特撮ヒロインはアイドルの一分野になっていった。
1982年に戦隊ヒロインの人気が爆発したのは、メインの脚本家をつとめた曽田博久氏の功に負うところが大きい。
男と対等に戦うヒロインの魅力を最初に描いたのは、もちろん『ゴレンジャー』のメイン脚本家の上原正三氏だが、そこにサブとして参加した曽田氏の脚本は、さらにその先を行っていた。『バトルフィーバー』第26話「包帯男の仮面報告」、『デンジマン』第18話「南海に咲くロマン」など名エピソードを書き、それが評価されてかどうかは知らんが、メインに就任する。そしてそこにサブとして参加した鷺山京子氏がさらにその先を……。
彼らは戦隊ヒロインを、現実にアイドルにした。
荒川氏は戦隊ヒロインを、作中でアイドルにして満足している。
アイドル好きの人間として、くやしくはないのか。
人を守るのがそんなにイヤか
『獣拳戦隊ゲキレンジャー』(2007)は当初の「楽しみながら強くなる」路線を第20話あたりから修正し、「人を守りたいと思う気持ちが己を強くする」とかなんとか言い出してから、多少は話も順調に転がりだし持ち直すのであるが、そのおかげで、最近(ここ十年くらい)のスーパー戦隊の致命的な問題点について気づかされた。
ストーリーもアクションもソツなくこなされていて、だけど見ていて全然面白くない話が最近になって急に増えてきたような気がするのはなぜか。
話がうまく転がらないのなら、とりあえず主人公に「俺は人を守るために戦う!」と叫ばせておけ、そうすればうまく行く……そういう作り手の意識が透けて見えるのである。
人を守りたいという使命にめざめることによって、ヒーローがパワーアップしても、確かに文句はつけにくい。
でもそれは、人を守って戦うことの大切さを子供たちに訴えたいという、作り手の願いの込められたものではなくて、しぶしぶやっているものだから、熱血しているのはうわべだけで、脚本も演出も役者の演技も非常に薄っぺらに見える。
もしも本当に「俺は世のため人のために戦うなんてウンザリである、俺は自分自身のために戦うのだ」というヒーローを生み出したいというのであれば、それはそれでおもしろそうだ。『轟轟戦隊ボウケンジャー』(2006)の明石が仮に、俺は冒険が好きだ、冒険してワクワクを楽しむためならば世界がどうなっても構わない、そんなキャラのまま最後まで突っ走ったなら、世間からは「あんなものはヒーローではない」「戦隊ヒーローの風上にも置けない」と非難ゴーゴー戦隊になっていたであろうが、私は新しいヒーロー像の出現と称えるつもりでいた。ところがやっぱり商品展開の都合からか、正しい魂がどうのこうのと、しらじらしいヒーローへと成り下がっていった。
スーパー戦隊シリーズが30年以上もの長きにわたって蓄積してきたフォーマットは、ヒーローは人を守るために戦うということを前提にして作られてきたものだ。そんなに人を守るヒーローが嫌いなのなら、新しいフォーマットを自分たちで一から作ってみたらどうなんだ。そんな面倒なことはしたくない、楽をしたい、でも「人を守るために戦う」というテーマと真正面から格闘するのもイヤ。その結果、既成の枠組みを形だけなぞった、薄っぺらな作品が作られ続けることになる。
東映としては、玩具が売れさえすればスポンサーさまに喜んでもらえるし、スタッフもそれでいいと考えているのだろうか。
だけど本当にそれでいいのか。
ヤマトにはなぜ女が一人しか乗っていないのか
この齢になって初めて『宇宙戦艦ヤマト』(1974年の第一作・テレビ版)を見た。とても感動した。そこでさっそくジェンダー分析をやる。
宇宙戦艦ヤマトの女性乗組員は森雪一人だけである。これは非常に奇妙な設定である。女が十人ぐらい乗っている、あるいは一人も乗っていない、というのなら分かる。しかし一人だけって。
このことについて何か筋の通った説明をひねり出すことは不可能だし、意味もない。問題にするのは背後にある思想だ。
最終回では、彼女は古代進の命を救いたい一心で、コスモクリーナーDを起動させたということになっている。文献でそう書いている人も多いし、劇中での描写も確かにそのような感じである。
しかし、そもそも森雪はヤマトの乗組員に選ばれるくらいのであるから、使命感も旺盛で勇気のある女性のはずだ。実際の描写もそんな感じである。ヤマト乗組員全員の福利厚生のために働き続けた生活班のチーフである。艦内に放射能ガスが満ちようとしたとき、だから艦を救うため、地球の未来を救うために我が身を犠牲にして放射能除去装置を作動させたとしても、なんら不自然なことはない。それをなんか無理矢理、艦を救うためではなく、古代進一人を救うために命を落としたということにして話を進めようとしているように見える。
「女が英霊になったら困る」という思想が見え隠れする。
男は「公」、女は「私」に生きるべきものである。かりに女が男以上にヒロイックな行動をとったとしたら、いやあれは公的ではなく私的な動機によって行動したのだと無理矢理にでも解釈する、そうやってヤマトは男の船である、男のロマンであるという観念をなにがなんでも守らねばならぬ。
主人公は古代進である。あくまで古代の視点で物語は展開されなくてはならない。そうである以上、女性乗組員が「私」から「公」へと越境しようとしたとき、それをすかさず引き止めるためには、その女は古代とプライベート上の深い関係性を持っていなくてはならぬ。要するに恋愛関係のことだが、古代がドンファンではない以上、限度は一人である。
とまあここまでくれば謎は解けたも同然であろう。
女レッドがそんなにイヤか
「あんな女レッドはイヤ」なのではない。
「女レッドはイヤ」ということらしい。
女がレッドをつとめること自体が許せない、女が男の上に立ったり、男に命令したりすること自体が気に食わない……そういう意見が出てくるんじゃないかと思ってシンケンジャーのブログとか掲示板とかいろいろ見てまわったら、案の定である。(そういうことを堂々と書いたりしたら女性差別だと糾弾されるので、「だって、男の子はそういうのイヤでしょ、現にうちの甥っ子が……」などと姑息な言い訳をしている人もいる。)
最終回を迎える目前の『侍戦隊シンケンジャー』に、女のレッドが出てきたらしい。「らしい」というのは私は見てないからだが、見てる人たちは大騒ぎらしい。そして上記のような意見も出てきている、と。
一体戦隊シリーズはこの三十年以上もの間、何をやってきたのだ。
女は男に従属すべきものである。そういう考え方はそういう考え方としてありだ。世間の多数派かもしれない。もっともそれは、男は女を守って戦わねばならないという義務とセットになった上での話だが。
女を守る義務は負いたくないが、女が男より上に立つのも許せない、なんてのはただの虫のいい話だ。保守的な考えというのですらない。
戦隊シリーズは、男も女も区別なく、ともに命をかけて戦うというところからスタートしたはずだ。それがいつのまにか、オタクどもに甘ったれた夢を与えるだけの話に変質してしまったのか。
なさけない。
それとも、残りの四話で、そんなオタクどもに冷や水をぶっ掛けるような展開になるのだろうか。いや、ぜひともそうなってほしい。
西堀さくらが りりしくない理由
戦隊シリーズの歴史をひもとくと、やはり昔は女の地位は低かった。1980年代半ばまでは男は姓で、女は名で呼ばれていたなんて、今の感覚からすれば相当変である(戦隊における人間関係と呼称)。
だがいったん戦いが始まれば事情は一変し、「レッド」「ピンク」と完全に対等な呼称を用いる。戦場においては男も女も関係ない、自分たちは互いに命を預けあった仲間だ、という意識がここに現れている。「死ぬも一緒、生きるも一緒」の間なのだ。
時代下がって『ボウケンジャー』(2006年)では逆だ。「ミッション中はコードネームを用いる」という規則になっているのだが、それはつまり明石だけは「レッド」ではなく「チーフ」、他は全員色で呼べということである。といってもメンバーには全然身についた規則ではなくて、普通に姓名で呼んだりする。そしてそのたびに注意が飛ぶ。勝手な呼称を使うな、明石だけを特別扱いする決められた呼称体系を用いなさい、と。
注意をとばすのはポウケンピンク・西堀さくらの役である。
もしさくらが男だったら、すごく嫌な奴のはずだ。
あんまり嫌な奴に感じられないのは、女だからだ。女が男の前でへりくだっても、当然という意識が視聴者の側にあるからだ。
これはつまり、女に対する差別意識が昔に比べて進んでいるということであろうか?
そうではあるまい。
それは多分、自分たちは昔の戦隊とは違って、互いに命を預けあったりしてるわけではありませんよ、そこまで深い絆はないですよ、という意識があるからなのであろう。
最近の戦隊は全然見ていなかったのだが、療養中は浴びるほど見た。いろいろ発見があっておもしろい。
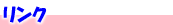
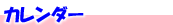
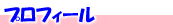
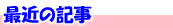
- ジェンダーフリーとスーパー戦隊 (01/31)
- 島本和彦氏よ、お前もか (01/29)
- 久しぶりに桃園ミキの絵 (01/26)
- 戦隊ヒロインのアイドル化と純朴幻想 (01/24)
- 『シンケンジャー』からの宣戦布告 (01/21)
- 荒川稔久氏は本当にアイドル好きなのか (01/19)
- 人を守るのがそんなにイヤか (01/16)
- ヤマトにはなぜ女が一人しか乗っていないのか (01/14)
- 女レッドがそんなにイヤか (01/12)
- 西堀さくらが りりしくない理由 (01/11)
- 再開 (01/09)
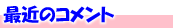
- スーツアクターという難題
⇒ Manju (10/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19)
- スーツアクターという難題
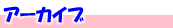
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)