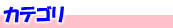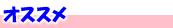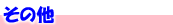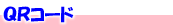平成仮面ライダーの幼稚さ
苦情殺到の『仮面ライダー ディケイド』「続きは映画で!?」の真相を直撃!
――(仮面ライダーシリーズの)ヒットとロングランの秘訣は何でしょうか? やはり手を替え品を替え、戦略的に緻密に計算されていたわけですか?
白倉 逆にそうせざるを得なかったんですよ。ヒットの法則なんてあればいいですよね。レンジャーシリーズみたいに「とりあえず5人の戦士がいて最後に大悪党を倒して終わり」的なものが、実は仮面ライダーシリーズにはないんですよ。
白倉伸一郎氏も東映の特撮スタッフなんだから、「戦隊シリーズ」という名前も言えんのか。なんだよ「レンジャーシリーズ」って。「戦略的に緻密に計算」する必要がある、高尚なる仮面ライダーシリーズとは違い、「とりあえず5人の戦士がいて最後に大悪党を倒して終わり」さえすればいいだけの戦隊シリーズなんて、正式名前を覚える必要もない、ということをわざわざ言いたかったのか。
子供みたいな人だな。
まあ子供番組を作ってる人が子供じみた精神構造を持っていても何も不思議なことはないのだが、そういう人たちに限って、子供だましの戦隊シリーズとは違い、仮面ライダーシリーズは高尚なドラマ性を持った大人向けの番組なんですよとか言いたがる。
こういう幼稚な人たちが作っているのが平成仮面ライダーシリーズというわけだ。
ペギー松山論 あるいは変身前アクションの必要性
近日中に大幅にリニューアルして、戦隊ヒロイン全般について取り扱うサイトにしようと思っているのだが、その第一弾としてペギー松山論をUPするつもりである。しかしこれが全然筆が進まない。
特撮ヒロイン史上におけるペギー松山の位置づけについてなら、いくらでも書ける。最近の戦隊しか見たことがないという人でも、彼女の偉大さについて異論をさしはさむことはできまい。というか、既に「特撮ヒロインの女性学」ですでに書いたしそれに付け加えることもないのであるが、そうではなくて、ペギー松山自体の魅力についてだ。
書けば書くほど近年のヒロインの批判になってしまう。
彼女が持っていた魅力というのは、すべて最近のヒロインが失ってしまったものだからだ。
時代の流れに従って戦隊ヒロイン像も代わり、新しい魅力を加えた結果として古い魅力を捨てた、というのではない。単なる劣化である。
たとえば、最近の戦隊でも、一年に一度くらいは、変身前アクションがある。
変身すれば強いんだから、変身して戦えばいいんでないの? なんで変身前アクションなんかする必要があるの? 最近のファンならそう思うかもしれない。だが、一見ムダに思えるようなことが、作品の強度を支えていることはよくあることだ。だから、昔みたいにやるのは無理でも、せめて一年に一度くらいは、と思ってやらせているのだ。
作り手の側はそのことは分かっている。
一年に一度やる程度のことで何が変わるものか、と思う人もいるかもしれないが、私はその作り手の心意気は買う。
分かってないのは見ている側だ。
昔の戦隊なんか観たことない連中が、昔の戦隊について勝手なイメージを抱いたまま、ブログとか掲示板とかでデタラメなことを書いていても、まあ仕方ないなあとは思う。しかしかなりの高齢者のはずなのに、そういうことを書いてる連中がいる。
やっぱり老人になると記憶もぼけ、感性も磨耗するんだろうか。ああはなりたくない。
とにかく、今後歴代戦隊ヒロイン全員について書くつもりなのだが、ペギー松山の魅力について論じることができなければ、何も始まらない。
『サイボーグ009』とポリティカル・コレクトネス
島本和彦『アオイホノオ』の主人公は、大学生時代の作者がモデルである。1980年ごろのアニメとかマンガとかの話が出てきて面白いのだが、『サイボーグ009』の二度目のアニメ化(1979年)が始まった時、主人公がそのオープニングを見て大感激をするというシーンがある。サイボーグ戦士が一人ずつ画面に出てきてはその能力を見せるのだが、それがいかに素晴らしいセンスで演出がなされていることかについて事細かく延々と力説する主人公。しかし私は003のくだりで噴き出してしまった。

みもふたもないことを。
やっぱりみんな003のことをマスコットヒロインだと思っていたんだな。戦士じゃない。
『ジャッカー電撃隊』と『サイボーグ009』は、どちらもサイボーグ戦士団の戦いを描いた、石ノ森章太郎の作品である。片や打ち切り、片や石ノ森の代表作扱い。ずいぶんと差がついたものである。
ところが、『ジャッカー』の流れを汲むスーパー戦隊シリーズは、男と対等同格の女戦士を登場させ、戦士としての強さと女の子としてのかわいらしさの両方の魅力を持ったヒロインを打ち出し、大きな成功をおさめた。それに対して女の子としてのかわいらしさしか持たされなかった『009』の003は、言っちゃ悪いが、今見ると大して魅力的なヒロインではない。
2001年には三度目のアニメ化となった『009』だが、他のサイボーグたちは大岩を軽々とジャンプする一方で、いちいち男たちに手を引っ張ってもらわないと岩も登れない003は、はっきり言って変すぎる。なんで一人だけ性能がこんなに違うの。
『009』の原作が初めて世に出たのが1964年である。今読めば、偏見や差別と受け止められる可能性を持つ箇所も多い。それがリメイクのたびに問題になる。原典のままにするのか、修正するのか。適宜判断していくしかないだろう。しかし2001年版のアニメは、人種・民族に対しては、神経過敏と言ってもいいくらいの修正を施しながら、性に対してはほったらかし。
石ノ森プロの問題意識って一体どうなってんのよ。
特撮ヒロインの女性学 第二章
オタクの旗は降ろせ! 非実在青少年規制問題について
東京都の「青少年健全育成条例」改定案問題については竹熊健太郎氏のブログで知ったのだが、継続審議になったことは、とりあえず目出度いことではある。しかしそれはあまり知られないうちにコッソリ通してしまおうという敵のやり口に反発してこその世論の盛り上がりであり、また、今回は時間があまりにもないので小異を捨てて大同についたが反対運動の進め方には違和感を持っている、なんて言ってる人もいる。条文が拡大解釈されて言論の自由のない社会が到来するのでは、という恐怖心から反対運動に馳せ参じた人は多いだろうが、「でも何らかの規制は必要では?」と漠然と思っている人もやっぱり多いだろうし、そういう人たちを説得するような理論を、次に議会が開かれる六月までに構築できるのだろうか? 中には、説得どころか、そういう規制の必要を感じている人たちを上から目線で馬鹿にすることしか考えてない人のブログなんかもあって、そういうのを見るにつけ非常に不安になる。
それはそうと、こういう動きが起こるたびに思う。いいかげんオタクの旗は降ろしたほうがいいのではないか。
「オタク」というのはもともと蔑称である。それを逆手に利用し、オタクは素晴らしい、世界に誇る日本の文化だ、とアピールしてきたつもりが、世間様のほうはというと、一体どのような土壌があってこそのオタク文化が花開いているのかについて、全く理解なさっていないし、なさろうともしていない。有益なものも有害なものも含めて文化なのであり、有害なものだけ取り除いて有益なものだけ育てようとしても枯死するだけだ、ということが全然分かっていない。
そういうことを今回の動きであらためて知らされた。
二次元のキャラクター相手に恋をする、そんなことは普通のことである。すぐれた創作作品にはそれぐらいの力があって当然だ。ところがそれをわざわざ「オタク」だの「萌え」だのと、何か特殊な概念であるかのように命名し、その結果どうなったか。自分たちがすぐれた存在であるかのようにアピールしたつもりかもしれんが、世間様からは、ああいうのは特殊なメンタリティを持っている人間なのだ、というぐらいの認識しかされていない。
特殊な人間だから規制したって構わない、と思われるのだ。
弾圧の呼び水になっているとしか私には思えん。
さとう珠緒「オタクはキモイ」発言の真相
『超力戦隊オーレンジャー』でオーピンク・丸尾桃を演じた珠緒(現在は改名してさとう珠緒)氏が、「オタクはキモイ」とかいう趣旨で何か言っているらしいというので読んでみた。
私、昔からオタク系からは好かれないんです。グラビアっぽいことをしていても、そういうファンがつかなかったんです。戦隊モノやっていたのになあ。歴代ピンクは人気あったのになあ。私だけダメだったみたーい。でも、秋葉系の人たちは見る目があるって証拠ですよね。
それ、オタクは関係ないから。
戦隊ファンというのは何か特殊な価値基準を持っているということにしたいみたいだが、そんなことないって。普通に脚本や演出や役者の演技力を見て作品の出来不出来を判断している。歴代の戦隊ヒロインで人気があったのはいずれも役者に魅力があり、いい脚本や監督に恵まれた人たちばかりであって、オーピンク・丸尾桃の人気がなかったとしたら、まあ、そゆこと。
『オーレンジャー』に関しては、一番の問題は脚本であろう。シリアスで行くのかコミカルで行くのか最初から迷走状態。さとう氏自身は悪くはなかったと思うが、しかし今やタレントとして幅広く活動している彼女にしてみれば、たかが一年やそこらで芸能界から消えてしまったような連中よりも、自分の方を下に評価する連中が存在しているなどということ自体、我慢がならないことと見える。だから戦隊を見てる連中というのはオタクであり、つまり社会不適応者で女に幻想を抱くキモイ男のことで、そういう連中に媚びるように演じるのでなければ人気は出ないのだと、どうもそういうことにしておきたいらしい。
そういえば最近、超力戦隊の制服を14年ぶりに着て『ゴーオンジャー』の劇場版の舞台挨拶に行ってきたとかいう話があったが、いい年して何やってんだか。そんなことしたってオーピンクの評価が上がるわけないし、歴代戦隊ヒロインの輝く星々の列に今さら加われるはずもない。しかしあんたは現実にタレントとして今成功しているんだから、そんなものに敵愾心なんか燃やしてどうするんだ。大人げない。
オタクは世界に誇る日本の文化だと主張している人がいる一方で、とにかく自分にとって都合の悪い連中を一括りにしてレッテル貼りする言葉としても通用している。この議論の行く末は一体どっちだ。
大川めぐみ「ポルノ志願」発言はデマ
大川めぐみ氏(桃園ミキ役の女優)が、ポルノに出たいと発言したのを雑誌で見たことがあるとか、プロフィールにそんなことが書いてあったとかいう情報がネットで出回っている。そのもとになった発言が載った雑誌をつきとめた。どう見てもポルノの話はもののたとえだとしか読めない。曲解しようという意図でもない限り、ポルノを志願したというような読み方はできない。
いかげんにしてくれ。
匿名なのをいいことに、ネットでデマをばらまいている連中はまとめて地獄へ落ちてくれないかな。
それにしてもなあ。
萩原佐代子氏(ダイナピンク)のファンはいいよなあ。
彼らがきらびやかなイベントに行って「お会いできて感激」などとはしゃいでいる一方で、この俺はというと、薄暗い図書館の片隅で、すえた匂いのする古い雑誌の一頁一頁をめくりながら目当ての記事を探し、やっと探し当てたと思ったら、ほんの小さな記事で、しかもそれが、芸能界でもっともっと大きくはばたきたいという夢に目をきらきら輝かせている大川氏の笑顔の写真が載っていたりなんかすると、こっちとしてはその夢は結局かなえられなかったことを既に知っているから、やるせない気持ちで一杯になる。
大川氏について調べるのはいつも精神的ダメージが大きい。
大川めぐみ資料庫
クラリスは現実に存在するか?
オタクは世界に誇る日本の文化だ、と言いたがる人たちの心の支えになっているのが宮崎駿監督である。
アニメなんか子どもの見るものであり、大人になってアニメなんか見ているのは幼稚な連中だと、世間から迫害されてきた、しかし今や見返してやる時が来たのだ、と。日本のアニメは今や世界から高く評価されているのだ。賞もたくさんもらっているではないか。
ところがその宮崎氏のほうはというと、オタクを毛嫌いする発言をしょっちゅう繰り返している。自分の作っているアニメは、オタクどもが好むアニメなんかとは格が違うんだと思っておられるに違いない。
しかし、どう違うというのだろう?
クラリスにしろナウシカにしろ、宮崎作品に出てくる女の子なんて、現実にいそうにもないタイプばかりではないか。
実際そんなふうに直接言われたこともあるそうで、それに対する宮崎監督の答え。
「現実にいますよ」
物語のキャラクターは当然架空の存在だが、ゼロから作り上げるわけではない。現実の人間を元に抽象化・理想化して作るものである。その抽象化の度合いが高すぎれば、物語の受け手にとっては「現実にいそうもない」「現実味がない」という感想を抱くことになる。作り手にとっては現実にしてキャラクターを創造しているつもりであっても、そんなふうに受け手に思われたということは、それは作り手の力量不足の現れであって、だからクリエイターとしては、反論なんかしているヒマがあるのなら、反省してもっと現実感のあるキャラクターを創造するよう努力しなければならない。
しかしここに一つ問題がある。
クラリスみたいな女の子が現実にいるわけねーだろと言っている人たちが、同時に『カリオストロの城』は日本アニメ映画史上の最高傑作だ、などと言うのである。
リアリティなんか必要ない、私たちは架空の人物を架空の人物として愛することができるのです。こんなふうに言われたら、作家としては立つ瀬がないではないか。
だから宮崎氏としては、こういう連中は物の価値の分からない馬鹿どもだ、オタクはこれだからダメなんだと、罵倒し軽蔑するしかない。
最近の宮崎監督は「悪人をやっつければ世界が平和になるという映画は作りません」なんて発言をしてたりして、これって明らかに『カリオストロの城』等、オタク受けをした自分の作品を否定したいという意志の現れなんじゃないか。
もっとも、現在の宮崎氏の作っている作品にリアリティがあって、見る人に現実の手触りを感じさせるような出来に果たして仕上がっているのかというと、それは……。
宮崎氏に限らず、作り手の側は「オタク」という言葉を劣ったものとして使用する人が多い。
星光子のファンであることの大変さ
星光子氏の公式サイトに日参していたことがある。
別に私は星氏のファンではないのだけれども、『ウルトラマンA』(1972年)の途中で突然ヒロインが降板したのは有名な話で、その南夕子役の女優であるし、その三年後に芸能界を引退してからは一切メディアへの出現を拒み、ファンにとっては消息を知りたくても知れない二大特撮人気ヒロインみたいな言われ方をしていて興味を持った。(ちなみにもう一人は大川めぐみ氏。桃園ミキ役。)
2004年にDVDの発売を機に、メディアに登場するようになるのだが、そこで降板の真相をファンから聞かれて「納得のいく演技ができないので自分から降板を申し出た」と言っていた。だから、2005年9月10日に公式サイトが更新され、降りたのではなく降ろされたのだという内容の記事がUPされたとき、私も星光子ファンと共にその衝撃を味わうことになった。
私は別にファンではないから、同情する気もないのだが、それより感動したのはファンの反応である。今はブログも始まって、ファンもコメントをつけられるようになっているのだが、そこで「じゃあなんで嘘ついてたんですか」と聞いてるやつが一人もいない。
星氏にしてみれば『ウルトラマンA』なんてのは昔の話だし、すべてをありのままファンの前にさらけ出すつもりなんか全然なく、ただ思わせぶりなことを書いて同情してもらいたいだけだということは、ブログを読んでいれば容易に分かる。そしてファンも、自分たちが彼女の愚痴を聞いておれば、彼女の昔の心の傷を少しでも癒すことになると思って、聞き役に徹しているのである。彼女が自分たちファンに心を開く気など全然ないということを承知の上で。
三十年間待ち続けた結果がこれである。
特撮番組に出ていたヒロインに恋をするということは、現実に恋をすること以上に苦くて切ない思いをすることもあるのだ。
アニメやマンガのキャラに萌えたとか言ってる人には、こういう感覚というのは分かるのだろうか。
沈黙を破って以降の星氏が、映画にも出演しさまざまなイベントに出たりと急激に露出を増やす一方、二大ヒロインのもう一方はというと……。
いやこの話はいいや。
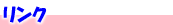
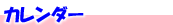
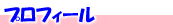
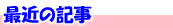
- 平成仮面ライダーの幼稚さ (03/28)
- ペギー松山論 あるいは変身前アクションの必要性 (03/25)
- 『サイボーグ009』とポリティカル・コレクトネス (03/22)
- オタクの旗は降ろせ! 非実在青少年規制問題について (03/20)
- さとう珠緒「オタクはキモイ」発言の真相 (03/15)
- 大川めぐみ「ポルノ志願」発言はデマ (03/11)
- クラリスは現実に存在するか? (03/07)
- 星光子のファンであることの大変さ (03/04)
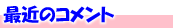
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ percetakan jakarta (04/20)
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
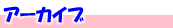
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)