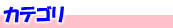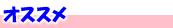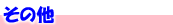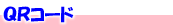勧善懲悪で何が悪いのか?(前編)
戦隊シリーズのファンが、ウルトラマンや仮面ライダーのファンと異なっている最大の点は、勧善懲悪をくだらないものと決めつける風潮が希薄なことではないかと思う。
ウルトラシリーズの名作エピソードを挙げろと言われたら、大抵の人は「故郷は地球」「ノンマルトの使者」「怪獣使いと少年」あたりを挙げる。理由は「勧善懲悪でないから」。勧善懲悪はくだらないもの、劣ったものであるというのが説明不要の前提みたいな扱いになっている。
だったら、『ウルトラマン』の全話が「故郷は地球」みたいな話だったら、もっと名作になっていただろうか? んなわけないだろう。
仮面ライダーシリーズにおける「正義」に関して平山亨氏が二枚舌を駆使していることについては、このブログでも何度も触れたから繰り返さない。
だいたい、勧善懲悪というのは本当にくだらないものなのだろうか。
そしてそんなくだらないものであるなら、なぜこれほどまでに人気があるのだろうか。
山の中で迷子になったとする。
山と行っても道もなく、原生林の茂った人跡未踏の地である。地図はない。視界も悪い。ただし、コンパスだけはある。そういう状況に陥ったと想像してみよう。自分ならどうするだろうか。
闇雲に歩きまわっても麓にたどりつける可能性は低い。こういう時に誰もが考えるのは、北なら北と方向を決めて、一方向に向かって歩き続けることである。そうすれば必ずいつかは山から降りられるはずだ。ただ、その行く手には崖や沼があり、進めなくなるかもしれない。崖はよじ登り、沼は泳いで渡り、あくまでも一直線に突き進むというのも一つのやり方ではあるが、途中でどうしても突破できずに力尽きて倒れる可能性も大きい。やはり険しい道は避けて進むべきではなかろうか。ただしあまりにも歩きやすい道ばかりを選んで歩いていると、同じ所をぐるぐる回っていつまでたっても脱出できない可能性も考える必要が出てくる。(続く)
「デカレンジャー 10 YEARS AFTER」に思う
「特捜戦隊デカレンジャー 10 YEARS AFTER」に関する、さいねい龍二氏のブログ。
先日監督と話した時に、vsマジもゴーカイもデカとは違う時間軸のパラレルワールドの話なんで忘れてね、なんて話してました。今さらカマトトぶる気はないんだけど、戦隊のスタッフやキャストの間で「パラレル」という言葉がこれほど気安く使われているという事実には、多少の失望を感じないわけでもない。
もっともこういう、キャラクターに対する愛情のなさという問題は今に始まったことではない。というか昔のほうがひどかった。昭和の仮面ライダーシリーズに参加した脚本家によれば、「次はV3の客演回ですから」とプロデューサーに一言言われるだけ、V3に関する資料なんか渡してくれることもない。そうやってV3の出てくるシナリオを書いていた。そういうことをインタビューで、大して悪びれることもなくしゃべっていたりする。
そんないいかげんな仕事が通用したのも、当時一般家庭に録画機器なんかなかったからであろう(あったとしてもビデオテープがものすごく高かった)。一人称が「ぼく」だろうが「おれ」だろうが、一般の視聴者にはそもそも分からない。偏屈なマニアが目くじら立てたくても立てるすべがないという状況。
科学技術が発達し経済的に豊かになり、今では過去作の第○話を見たいと思えばいつでも見られるようになった。情報量は以前に比べれば圧倒的に多くなりマニアの目も肥え、それに対して作り手の側の意識は以前のまんまときている。話のつじつまが合わないとかキャラクターの性格が似てないとか指摘されても「パラレルですから」と言い訳すればそれ以上の追及を免れると思ってる。便利な言葉だ。
科学の進歩は必ずしも人間の生活を豊かにするとは限らない。「3・11」以降そういうことを言い出す奴が急に増えたが、仮面ライダーや戦隊のファンからしてみれば、何を今さらという感じがする。
道化を演じる元特撮俳優たち
爆報フライデーの話を書くのはこれで三度目である。
といっても星光子やだるま二郎とは違って、特に問題のある番組構成だったというわけではない。2012年3月23日に『超電子バイオマン』(1984年)のピンクファイブ・桂木ひかるを演じた牧野美千子氏が築地で佃煮屋をやっているのを、ちょっとだけ紹介しただけである。しかし、「変身ポーズをとってください」と言われたのでとってやった場面で、なんでそこでゲラゲラ爆笑する音声をかぶせるのか。
基本的にこういう低俗バラエティ番組は、人を小馬鹿にして笑いを取るものだから、いちいち腹なんか立ててもいられない。腹が立つのは、こんな番組に出たがる方だ。やっぱり牧野さんも芸能界に未練があるのだろうか。やれるだけのことはやった上で引退したわけではないからなぁ。親の反対がなければ今頃は……などと後悔の念に苛まされながら毎日生きているとしたら辛い話だ。だからテレビに出られるのなら何でもいいと思って飛びついたのだろうか。
だったらもっと実のある話をしてくれればいいのに。
イエローフォーの話とか。
さすがにそれはマズイだろうけど、でも矢島由紀氏の降板の経緯の一部についてバラしたのは牧野さんだ(2010年のトークショーでの話)。それまでは当時のキャスト・スタッフが、降板について触れること自体がタブーだった。牧野さん、後で東映から厳重注意くらったのだろうか。
とにかく、元特撮俳優で当時の話を色々しゃべりたがっている人は多い。ファンも知りたがっている人は多い。にもかかわらず、そういう人たちのブログやツイッターでは、当り障りのない話しか出てこない。上のほうで監視している人がいるのだろうか。実際、当時のことを書いたツイートを後で削除した人を私は知っている。問題になりそうなツイートでは全然なかった。名前は書かないでおくが。
そして一方でこんな低俗番組なんかに出演して道化を演じている人がいる。このミスマッチ、なんとかならないのだろうか。
なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その4=完結)

(承前)『劇画・オバQ』という作品がある。
『新オバケのQ太郎』の最終回でオバケの国へと帰ったQちゃんが、十五年ぶりに人間界へやって来て、大人になった正ちゃんと再会する。テーマは「子供時代との訣別」。しかし、大人といっても、素敵な大人もいれば、つまらない大人もいるはずだ。一体ここまで正ちゃんをつまらない大人にする必要があったのだろうか。あまりにも夢のない話になっていて、ファンの中には「これを正式な後日譚とは認めたくない」と言う人もいるらしい。気持ちは分かる。
大人になるということは、悪いことばかりではないはずだ。しかし藤子F先生にはそんな話は描けなかったのだろうか。
もし当初の予定通りの『チンプイ』の最終話を描いておれば、同じようになっていた可能性は高い。しかし描かなければ「もし描いていれば感動的な最終回になっていたかもしれない」という言い訳の成り立つ余地がある。実際ネットで『チンプイ』ファンの声を拾っていると、その作戦は成功したように見える。かくして名声に傷がつくのは避けられた。
藤子F先生は『チンプイ』という作品に愛着がなかったわけではないだろう。ただ利害打算がそれを上回っただけの話である。
「『ドラえもん』をやめさせてくれないんだ」
生前、藤子F先生は家族に向かってそういう愚痴をこぼすことがあったらしい(ソースは『藤子・F・不二雄SF短編PERFECT版 7』収録の藤本匡美「父の持論」)。といっても別に小学館から暴力的な恫喝を受けていたとかいう話ではあるまい。自分はもう財産も名声も十分に得た、あとは本当に自分の好きな仕事だけをしたい、というふうに腹をくくったなら、編集者だって無理じいは不可能だったはずだ。ということは、それほど切実な苦悩でもなかったのだろう。
そして『ドラえもん』の原稿を描きながら机に突っ伏して死んだ。
藤子・F・不二雄はまぎれもなく日本史上屈指の偉大なクリエイターである。その人ですら、カネや名声のための仕事か、本当に自分のやりたい仕事か、どっちかを選ばねばならない時にどっちを選んだかを考える時、仮面ライダーやスーパー戦隊シリーズに関する今の東映の拝金主義を強く批判する気にはどうしてもなれないのである。
なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その3)

氷室冴子(作)/山内直実(画)『なんて素敵にジャパネスク』より
(承前)「玉の輿に乗りたくない」というのは少女マンガにおける一つのパターンとして確立している。財産も地位も何になろう、女の子にとって本当の幸せは愛し愛される人との結婚である。『ジャパネスク』の瑠璃姫など、それらのヒロインには一つの共通点がある。いずれも強い意志の持ち主だということである。
毎回毎回「マール星の科法の世話になんかなりません!」と言いながら結局は世話になっているエリは明らかにこの系列から外れている。
なぜエリは科法の世話になることに抵抗があるのか。チンプイもワンダユウも別に恩に着せるわけではない。それが却って「借りの感情」をエリの心の底に少しずつ少しずつ積もらせていく。また科法のもたらす便利さ・快適さに一度慣れてしまったら、そこから抜け出せなくなるのではという恐怖もある。そして毎回誘惑に屈し、結局は科法の世話になるということが示唆するのは、妃殿下なんかになりたくないというエリの意志がそれほど強いものではないということである。
エリは内木くんのことが好きである。ではどの程度の「好き」なのか。内木くんと結婚できさえすれば他には何も要らない、たとえ将来食うや食わずの極貧生活を送ることになっても、愛さえあれば耐えていける――と思うほどなのかというと、別にそういうわけではない。というか、十二歳でそんな具体的なことまで考える女の子は普通いない。内木への恋心はいかにも子どもじみた、たわいのないものである。その一方内木はというと、もうエリのことを単なる友達としか思っていない。
理屈はともかくとして、エリが妃殿下になったら結局は夢のない話になるのではないか、と思う向きもあるだろう。そういう人には『ローマの休日』を見ることを勧める。あれは、最後に王女が自発的に大使館に戻るから感動的な話として成り立っているのである。最後にエリが妃殿下になる決意をし、それを美しく感動的な話として描く余地は十分にあったはずだ。ではそれが執筆されるに至らなかった理由はなにか。(続く)
なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その2)

藤子・F・不二雄『チンプイ』「殿下に負けないで」より
(承前)では『チンプイ』はどんな結末を迎えるはずだったのか。それについて論じる前に、まず「エリのクローンを作ってマール星へ行ってもらう」説を片づけておく。
といっても、「クローン人間はコピー人間ではない」という事実を指摘しておくだけで十分だろう。一卵性双生児は性格までそっくりと勘違いしている人も多いようだが、そんなことはない。エリのクローン人間を作ったとして、性格も知力体力も音楽の趣味も、全く異なる人間ができあがる。これでは解決にはならない。
それともマール星の科法は、単なるクローン人間ではなく、精神まで完璧にそっくりにコピーする技術を有しているのかもしれない。しかし、人間の心だとか人格だとか、そんなものまで自由自在に操れる技術があるのであれば、もう何だってアリだろう。さっさとエリを洗脳してマール星へ連れて行け。一体ワンダユウは何を苦労しているのだろうか。
人の心は自由にはならないという制約があるからこそ、人の世にドラマは生まれるのである。
しかしこのクローン人間説の最大の問題は、その発想の貧困さにある。読者の願いは、エリが幸せになることである。しかし「エリが幸せになる」ということと、「エリの欲求が通る」ということは別のことのはずだ。なぜ、エリの気が変わる可能性は絶対にないということを前提にする必要があるのか。
エリはルルロフ殿下のお妃になんかなりたくないと言っている。しかしエリのその気持の根拠は相当薄弱なものだ、という描き方は第一話から一貫している。エリはルルロフ殿下やマール星について十分な知識を持っていないし、持とうと思うことすらない。とにかく嫌なものは嫌だと言っているだけである。虫歯になった子供が歯医者に行くのを嫌がって駄々をこねているのと大して違いはない。
チンプイの立場に立って考えたい。ワンダユウがマール星本位の考えをエリに押し付けようとする傾向があるのに対して、チンプイはエリのことが純粋に好きである。そのチンプイが、エリにマール星に来て妃殿下になってほしいと言っている。それがエリにとっても幸せなことだという強い確信があるからである。そしてエリの側は、マール星なんかに行きたくないという自分の気持ちを相手に分からせるには、どういう言い方をすればいいのだろうか、と考えてみようとすら思わない。結末は最初から目に見えている。(続く)
なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その1)
『チンプイ』は藤子・F・不二雄に見捨てられた作品である。
などと書いたらムキになって反論してくる人もいよう。F先生は完結に執念を燃やしていたのだが、病魔に倒れ無念にも果たせなかったのである、とかなんとか。しかし『チンプイ』の雑誌連載が終わり、少しだけ描き足して完結させますというアナウンスが出てから、F先生が病没するまで五年以上。体調は良くなかったと聞くが、それでも『大長編ドラえもん』のほうはちゃんと仕事をしていたではないか。『チンプイ』はメジャーな作品ではない。エリちゃんに幸せな結末を迎えてほしい、というファンの痛切な願いに応えるより、億単位のカネの動く『ドラえもん』の映画のほうが大事だったのだろう。
もっとも、金儲け主義の犠牲になって『チンプイ』が未完のまま終わったなどという事実は藤子プロにとっても体面の悪いことではあるらしい。当時の編集者やらアニメ関係者やらは、最終回についてF先生から構想をうかがったことがあるとか、思わせぶりなことをやたら口にしたりしている。しかしシチュエーションが不自然な割には中身のある話はゼロときている。そんなので読者が騙されるとでも思ったか。ふざけんな!
もっとも、『チンプイ』を虚心に読めば、どのような結末に向けて話を進める予定であったのかは明白であって、議論の余地などないはずだ。ただしそれはF先生のファンにとっては受け入れがたいことのようだ。彼らは一様に、F先生は読者に対して誠実であろうとしたがために却って未完になってしまったのだ、などという無理のある前提をもとに推論を組み立てる。だから、最終回はエリのクローンがマール星へと旅立つなどという珍説が生まれたり、そしてそれが支持を集めたりする。これは人様のブログだが
「チンプイ」未完結の理由を考察私は別に商業主義を悪と思っているわけではない。それはこのブログでも何度も書いてきた。しかし商業主義であるにもかかわらず、いやこれは商業主義に走った結果ではない、読者・視聴者のことを真に思ったがゆえだと言いくるめる手法、そしてそれにまんまと乗せられるファン心理は、いずこも同じのようだ。東映特撮に限った話ではないらしい。(続く)
「チンプイ」未完結の理由を考察 の補足
あらためて「チンプイ」
あしたのジョー、男塾、御都合主義
刷り上がった『少年マガジン』を読んで梶原一騎は頭を抱えた。矢吹丈よりも一回り大きな体格の男として力石徹の登場が描かれてあったからである。ボクシングには体重別の階級というものがあることを、ちばてつやは失念していたのだった。これでは二人をリングで戦わせることができない。力石の過酷な減量物語は、実は二人の作者の行き違いが生んだのである……。
『あしたのジョー』のファンなら誰もが知っているエピソードである。ところがこの話を聞いた時、私は意味が分からなかった。そんなの、力石が威圧感でジョーの目には大きく見えた、ということにしておけば済む話ではないか。そして次からは、普通にジョーと同じ体格の男して描く。マンガ家なら誰もがやっていることだ。『魁!! 男塾』というマンガでもそういうことをやっていた。
そう、誰もがやることを、敢えてやらなかった。『あしたのジョー』だって御都合主義が絶無なわけではない。その場その場の盛り上がりを優先させるために、辻褄が合わなくなってしまったことも確かに色々ある。それでも、これだけは絶対に譲れないという一線があり、それを最後まで守り通した。それが、一流のマンガ作品である『男塾』と、超一流の作品である『あしたのジョー』を分かつものであった。
さて、仮面ライダーの春映画と言えば、もう辻褄なんか無視することが慣例になっている。整合性のつく説明を求めるようなファンがいれば、むしろ野暮呼ばわりされる。細けえことはいいんだよ、どうせお祭り映画なんだから、と。
『仮面ライダー』といえば、藤岡弘の事故が有名である。そしてなんとか辻褄を合わせようと、スタッフ一同必死で智恵を絞っていた時点では、仮面ライダーシリーズも超一流の作品となる可能性を持っていた。一体どこで道を踏み外したのだろうか。多分、死んだはずのライダーマンを、何の説明もなく再登場させた時点ではなかったかと思う。
高寺成紀の復活はもうないのか

・『東映ヒーローMAX』Vol.39(2011年12月)、Vol.40(2012年3月)
・『語ろう!クウガ・アギト・龍騎』(2014年7月)
一体この二年間の間に高寺成紀氏に何があったのだろう。両方とも高寺氏のインタビューが載っていて、しゃべっている内容もほぼ同じ。それなのに語る口調がまるで正反対。もちろん人間なのであるから、考えが変わるということはありうる。人生上り調子の時は天狗になり、下り調子の時は落ち込む、それが普通である。しかし、高寺氏の場合は、2010年の『大魔神カノン』の評判が芳しくなく、その後も『ガメラ』の新作を任されたとかいう話が出た割には目に見えた進展は何もない。にもかかわらず増長の度が増しているのは一体どういうことなのか。
だいたい一年間のテレビシリーズなどというものは、一人の人間の力で出来るものではない。大勢の人間が力を合わせて作るものである。その一方で『クウガ』の手柄を独り占めにしたいという思いもあるのであろう、だから2011〜2012年でのインタビューでは、結局何が言いたいのかよく分からないことになっている。インタビュアーが切通理作氏だから仕方ないと言えば仕方ないのだが、この時点ではまだフタッフに対するリスペクトを語ったりもしている。それが2014年の時点では、もうはっきりと自分以外のスタッフは全員無能という考えを隠そうともしていない。
プロデューサーとして一番大切な仕事は、人を動かすことである。だから、たとえ本心はどうあれ、口先だけでも「このような素晴らしい作品を作れたのは、大勢の優秀なスタッフに恵まれたおかげです」と言う。そうでなければ人はついてこない。
とすると現在の高寺氏は心境はどうなっているのか。答えは一つしかあるまい。もう現場復帰はあきらめたということだろう。
ゴーグルファイブ同窓会にむけての提起
最初に断っておくと、これは義務感で書いたものである。
「言い出しっぺがやるべきだ」という反応が返ってくることは目に見えているし、実際その通りだとは思う。しかし一人ではやりたくない。なにしろ大川めぐみさん一人に会いに行くだけで心臓飛び出る思いをしたのだし、あと四人に対して同じことしろと言われても気が進まないというのが正直なところである。一緒にやろうと申し出てくれる人がいれば話を進めたいが、そうでなければ終わり。
『東映ヒーローMAX』なんかではよく戦隊OBがインタビュー受けたり座談会やったりしている。そして昔のキャストやスタッフと何十年ぶりに再会して、涙がでるほど感激したとかしゃべったりしている。まあ普通はそうだろう。懐かしい青春の思い出である(もちろん例外の人もいるだろうけど)。しかしそういう人達も、別に自分のほうから会うことを働きかけたわけではない。まあ普通そうだろう。照れや気恥ずかしさがある。第三者がセッティングの労をとらなければ実現することもなかったわけだ。
で、ゴーグルファイブの五人もそのように思っている可能性は大いにある。その場合、どっかの編集部とかがセッティングしてくれることを期待することはできない。ゴーグルファイブってそういう点では妙に冷遇されているのだな。要するに、ゴーグルファイブの五人が再会するような機会が得られるとすれば、それはファン自身の手によって実現させなければならないということである。それはファンにとっての責務ともいえる。
今のところ五人のうち消息不明なのはレッドだけだ。しかしそれだって八方手を尽くして調べた結果として不明なわけではない。調べてないだけだし。
自らの業績に泥を塗る東映プロデューサー

大下英治『日本(ジャパニーズ)ヒーローは世界を制す』(1995年)という本は、東映テレビ番組のキャラクタービジネスの歴史についての本であるが、公平な視点から書かれた本ではないということは、一読してすぐに分かる。重大な決断はすべて渡邊亮徳という人間によって行なわれ、他の人間はその指示に従って行動しただけという書き方で貫かれているからである。他の人間が重大な決断をする際は、固有名詞が出てこない。2014年にこの本の増補改訂版が『仮面ライダーから我狼へ』という題名で文庫化された際、「渡邊亮徳・日本のキャラクタービジネスを築き上げた男」というサブタイトルがついたのは、さすがに中立を装うのにも限度があることを知ったからだろう。
こんな本の間違いをいちいち指摘するのも面倒なだけだから、『がんばれ!! ロボコン』(1974年)に関して記述が一切ない、という一点を指摘するにとどめておく。人気が大変高かったというだけではない、ビジネスモデルを確立したという点においても、重要な作品である。『ロボコン』の超合金に触れないで日本のキャラクタービジネスの歴史を語るということなど絶対にありえない。なぜ触れなかったかというと、渡邊氏の汚点だからである。平山亨氏がロボットコメディ物の企画書を出したら渡邊氏にボツにされ、平山氏はそれを大切にとっておいたら数年後にテレビ局の人の目に止まり、実現させたら大ヒットになったという経緯があったからである。
渡邊亮徳という名前は、平山氏の本の中や吉川進氏のインタビューにもしばしば出てくる。尊敬する上司として。大きな功績のある人だということは確かなのだろう。しかしそれも、こんな本を出した時点で全部台なしである。自分たちの仕事の正確な記録を残すよりも、自分の手柄を誇大に見せかけることのほうが大事だ、という風潮は、今後も東映のプロデューサーに受け継がれていくのだろうか?
それにしても。
人間には誰でも名誉欲というものがある。だったら、どうしてこんなチンピラのライターを使ったのだろうか。ヨイショ本であることを容易に見破られてしまわないような、巧みな文章を書ける腕のいいライターを使おうとは思わなかったのだろうか?
「戦隊シリーズの生みの親」はなぜ四人もいるのか

『ドラえもん』10巻「見えなくなる目ぐすり」より。藤子・F・不二雄氏は自分一人で描いた作品をも、A氏との合作であったかのように描いていた。こういう人は珍しい。逆はよくあるが……。
というわけで、「戦隊シリーズの生みの親」に関する議論。今までの整理も兼ねて。
石ノ森(石森)章太郎
スーパー戦隊シリーズ第一作『秘密戦隊ゴレンジャー』の原作者――といっても名義上のものだし、本人にとっても気に入った作品ではなかったようである。『バトルフィーバーJ』以降のスーパー戦隊に自分のテイストが受け継がれているなどという主張をしたこともない。しているのは石森プロだけ(2月9日のエントリ参照)。
渡邊亮徳
『ゴレンジャー』製作時の東映テレビ部部長。大下英治『日本(ジャパニーズ)ヒーローは世界を制す』1995年(2014年に増補改訂版『仮面ライダーから牙狼へ』)という本は、『ゴレンジャー』が大ヒットしたのはすべて渡邊氏の手柄であり、平山氏も吉川氏も、単に渡辺氏の素晴らしいアイディアを実行に移すだけの手足という書き方をしている。んなわけあるか。次のエントリで詳しく論じる。
平山亨・吉川進
両名とも『ゴレンジャー』のプロデューサー。企画書を書いたのは平山氏だが、病気療養ということもあって、実際の制作の指揮をとっていたのは吉川氏、ということでいいんではないか。二人とも自分が生みの親だという主張をしているが(それぞれ2014年11月15日と7日のエントリ)、『東映ヒーローMAX』Vol.29(2009年6月発行)のインタビューで吉川氏は、はっきりと平山氏の名前を出し、自分と平山氏との考え方の違いについて具体的に述べている。それに対して平山氏に対してこの点を深く突っ込んだインタビュアーは見たことがない。この問題に関しての決着はついた、と言えるかな。
ちなみに『東映ヒーローMAX』のインタビュアーは切通理作氏。この人もなあ、やればできる人なんだけどな……。
内田有作はなぜ東映を首になったのか

東映の拝金主義的体質は別に最近になって始まったことではない。
ということをこのブログでもさんざん書いてきたわけだが、2010年ごろから仮面ライダーやスーパー戦隊の映画の粗製濫造が限度を超え、ファンの批判的な目が向きはじめただけのことである。「昔は良かった」というわけではない。本当は大切にすべきものを、目先の利益優先で使い捨てにする。昔からそうだったし、そして厄介なことに、そのような社風が『仮面ライダー』のような大ヒット作を作る原動力にもなっていたのだから、一概に否定することもできない。問題なのは、時代が変わって昔からのやり方が通用しなくなり、近年は大ヒット作も作れなくなったのに、社風は依然として昔のままだということである。
「本当は大切にすべきもの」。その筆頭はなんといっても人材であろう。
『東映ヒーローMAX』Vol.40(2012年3月発行)は、東映生田スタジオの所長を務めた内田有作氏の追悼ということで特集が組まれている。
その記事によれば、厳しい条件の下で予算やスケジュールを管理する制作者としての手腕、映画界での幅広い人脈、スタッフを惹きつける素晴らしい人柄。『仮面ライダー』の大ヒットは内田所長の手柄に帰す部分が非常に大きいということになっている。
そんな有能な人が、なんで生田スタジオの赤字の責任をたった一人に押しつけられる形で所長を解任されたりしたのか。
内田氏はウィキペディアに項目もないし、ネットで調べてもよく分からない。退職金も出なかったというのは本当だろうか? 東映を辞めた後の晩年の人生も、映画人として満足のいくものだったとは思えない。
しかしこの記事を読んで一番不気味に感じたことは、内田氏に対する東映の仕打ちに誰一人憤るわけでもなく、まるで「男の生きざま」みたいな美談仕立てにしていることである。一体これのどこが美談なのか。それとも労働者の仲間を裏切ってスト破りした男の末路はこんなものなのだろうか?
『東映ヒーローMAX』なんて雑誌は、東映の大本営みたいな雑誌である。そんな雑誌を読んで、東映という会社の闇の深さを印象づけられるというのも妙なものだ。別に私はこれ以上追及する気はないんだけど。
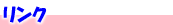
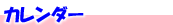
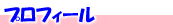
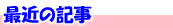
- 勧善懲悪で何が悪いのか?(前編) (05/30)
- 「デカレンジャー 10 YEARS AFTER」に思う (05/28)
- 道化を演じる元特撮俳優たち (05/25)
- なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その4=完結) (05/22)
- なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その3) (05/20)
- なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その2) (05/18)
- なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その1) (05/16)
- あしたのジョー、男塾、御都合主義 (05/14)
- 高寺成紀の復活はもうないのか (05/11)
- ゴーグルファイブ同窓会にむけての提起 (05/09)
- 自らの業績に泥を塗る東映プロデューサー (05/05)
- 「戦隊シリーズの生みの親」はなぜ四人もいるのか (05/03)
- 内田有作はなぜ東映を首になったのか (05/01)
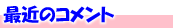
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ percetakan jakarta (04/20)
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
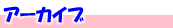
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)