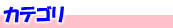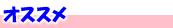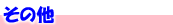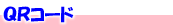「ゴレンジャー同窓会」という詐欺事件(後編)
(承前)ツイッターを見ていると、「四人に会えただけでも感激」と喜びのツイートを上げている人がたくさんいる。最初から正直に「四人しかそろいません」と宣伝しておけば、誰もが満足するイベントになったことだろう。なぜそうしなかったのか。五人がそろうと言わなければ、5,550円のチケットが売れ残ると思ったのだろうか。
たったそんなことのために、そんな端金のために、ファンからの信頼を永久に失うという危険をこの人達は冒したのだろうか。しかも、その詐欺がバレないように周到な用意をするわけでもなく。
彼らは別にわずかな金に目がくらんでファンを裏切ったのではない。ファンを裏切るのは悪いことだという認識そのものが、最初から欠如しているのだ。そうとしか思えない。
26日に「前編」を上げた際、私はこのイベントの主催者を鈴木美潮氏であると書いた。その直後の28日に鈴木氏がイベントの報告レポをアップ、そこではイベントの主催責任者は自分ではなく宮内洋氏であるということを、しつこくしつこく強調して書いてある。
事実であるならば、訂正でも謝罪でもしよう。しかしだとすると、イベントの主催責任者は誰かということすら明示しないまま、チケットを売ってイベントを開催していたことになる。これはもう最初からファンをあざむく気満々だったとしか思えない。追及の火の手が上がった場合、責任の所在をあいまいにして追及をかわそうというつもりで。ちなみに伊藤幸雄氏が最初にこのイベントに対して不信感を持ったのは、主催者の名前がなかったからだという(10月8日のフェイスブック)。
たとえ鈴木氏の言い分を100%信じたとして、主犯ではないというだけであって、犯罪行為の片棒を担いだ疑いは全く晴れていない。そして文面から判断するに、チケットを買ってくれた客の期待を裏切る結果になったことについて、申しわけなかったとも何とも思っていないようだ。
そして鈴木氏によって主催責任者と名指しされた宮内氏のほうはというと、何の声明も出す気はないらしい。(公式サイトは10月28日の更新で何の言及もなし)。
特撮イベントの周辺というのは、これほどまでに倫理観の低い世界なのか。
だとすれば、もうこれ以上の追及は糠に釘だ。こんなやり方が常態化しているというのであれば、我々ファンとしては、食い物にされぬよう自衛するまでのことである。この手のイベントには近づいてはならない。
本当に会いたい人がいるならば、直接行くべきだ。
「ゴレンジャー同窓会」という詐欺事件(中編)
(承前)「5人そろって同窓会」へ実際に参加した人の報告ルポがネット上に上がり始めたが、それを読むと、この手のイベントの主催者や出演者の間には随分といびつな、もとい、一般のファンとはかけ離れた常識が蔓延している様子が浮きぼりになってくる。
最も驚いたのは、このツイート。イベントが始まってからもなお宮内洋氏は携帯電話で伊藤氏に連絡をつけようとしたらしい(つながらなかったが)。
伊藤氏が断ったのは、主催者に対する不信感もあったが、第一の理由は仕事が忙しかったからである。伊藤氏のフェイスブックによれば、9月11日(イベントの告知日)以降も主催者サイドは引き続き伊藤氏にメールや電話をしていたそうだが、どうしても五人そろえたかったのであれば、伊藤氏の都合のいい日をあらためて聞くべきだった。しかし10月24日という日付を変更する気は最初からなかった、ということは、仕事なんか放ったらかしてイベントの方に駆けつけろと呼びかけていたことになる。
今の仕事に力を尽くすことと、昔の思い出話に花を咲かせることと、この人達は一体どっちが大事だと思っているのだろうか?
一般的な常識からすれば、当然前者である。俳優をやめて今は別の仕事についている人に対して、ファンが望むことは何か。今の仕事で活躍をすることである。忙しく、充実した生活を送り、その結果としてこんなイベントに出る暇なんかなくなったとして、それこそがファンにとって最もうれしい事である。
しかし主催者や出演者らの考えは違うらしい。
宮内氏らの行為については、二通りの解釈が考えられる。
一つは偽装である。イベントの紹介文にはこういう一文がある。
※出演者は予告なく変更する場合があります。つまり、主催者サイドとしては五人揃うように努力はしましたと形だけでも整えることによって、もし金返せという声がファンから沸きおこったとしても、それを押さえつけやすくしようという、そのための工作だったということである。
もう一つは、……これはちょっと考えたくないことではあるのだが、現在の仕事よりも過去の思い出のほうが大事だと、本気で思っているということである。そしてこんなイベントの運営手法が定着しているということは、先日のイベントは特殊なケースではなかったということなのだろうか?(続く)
「ゴレンジャー同窓会」という詐欺事件(前編)
(9月21日のエントリのコメント欄からの続き)
10月24日に新宿ロフトプラスワンで行なわれたイベント「5人そろって同窓会」が詐欺であることについては何の弁解の余地もあるまい。
出演が告知されていたゴレンジャーの五人のうち、ミドレンジャー・明日香健二を演じた伊藤幸雄氏が当日姿を現さなかったのは、直前になって緊急の仕事が入ったわけでも急病になったわけでもない。イベントの告知が行なわれたのは9月11日であるが、もうその時点で伊藤氏の欠席は確定していた。にもかかわらず「多忙な5人のスケジュールが奇跡的に合いました」などという虚偽の宣伝文句とともにイベントの周知が行なわれ、チケットが売られ続けたのである。その一方で伊藤氏は自分のフェイスブックで、9月12日、21日、10月8日、24日と自分は出ないと宣言し続けるという、異様な状態が続いていた。
伊藤氏が出席を断ったのは、仕事の都合であるが、無理して休みをとるという選択肢もなかったわけではない(その場合は色々なところに迷惑をかけることになっただろう)。しかし、そんな無責任な主催者によるイベントとあっては、たとえその後事情が変わってヒマになったとしても、再考の余地などありえなかっただろう。
ツイッターでは、「五人そろわなかったのは残念だが、四人に会えただけでも良かった。ありがとう」という感謝の思いを綴っている人も多くいるようだ。しかしそれは、五人全員がそろうイベントにするべくスタッフ一同が力を尽くし、結果として揃わなかったと思い込んでいる人たちだ。真相を知ればどう思うだろうか。まさに Ignorance is bliss.
これは明らかに犯罪行為である。
チケット代が5550円で、会場の収容人員が約150人。場所代だの機材費だのを差し引いて、この手のイベントにどれほどの利益が出るのかは知らない。しかし問題は金額ではない。主催者である鈴木美潮氏(*注)は、特撮のイベントに十年以上も関わり続けている人である。シロウトではない。そして大勢の特撮のスタッフやキャストからも厚い信頼を寄せられている。そういう人が、ファンの気持ちをあざむくことに何の痛痒も感じない種類の人間であるということは、いったい何を意味するのか。特撮界全体にいったい何が蔓延しているのか?(続く)
* 主催者は鈴木氏ではないという説もあって、「後編」で詳述した。10月31日追記。
「アンケート至上主義」についての誤解
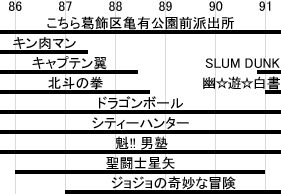
『週刊少年ジャンプ』の「アンケート至上主義」については勘違いしている人も多いように思われる。
それは決して「目先の売り上げのことしか考えない」という意味ではない。いやもちろんそういう傾向はある。しかしそれと同時に中長期的な戦略をも編集部は併せ持っていたし、であればこそ1990年代に650万部などという驚異的な売り上げを記録することもできた。そしてそのバランスが崩れた時に、『ジャンプ』の低迷が始まったのである。
短期的な視野しか持っていなかったことが『ジャンプ』の黄金時代をもたらすと同時にその後の低迷期をももたらした――と思いこんでいる人が多いみたいだが、それは間違い。
諸星大二郎と星野之宣が『ジャンプ』でデビューしたということを知らない人も多そうだ。
この二人の作風が『ジャンプ』向きではない、ということを編集部は分かっていた。分かっていた上でチャンスを与えたのである(ソースは失念)。当時はこういうことをよくやっていた。なぜかというと、雑誌の作風の幅を意図的に広げようと常に努力しておかないと、あっという間に同じようなマンガばっかりになってしまうからである。まあ結局はそうなっちゃったんだけど。そうなると、常に変化する大衆の嗜好に機敏に対処できなくなる。そして転落が始まる。
つまり、長期にわたってヒット作をコンスタントに送り続けるためには、短期的視野と長期的視野の両方を持つ必要がある。よく考えたら当たり前のことなんだけど。しかし『ジャンプ』から間違った教訓を引き出す人もいて、「短期的視野しか持たなくてもソコソコ成功しうるが長続きしない」と考えたりする。そうではない。短期的視野しか持たなければ、ソコソコ成功することすら出来ないのである。
さて戦隊シリーズに話を持って行くと、雑誌とかでスタッフのインタビューを読んでいたら、作品の成功・不成功を、単に玩具等のグッズの売り上げだけでしか判断しようとしない発言が最近になって急に増えてきているような印象がある。シリーズの作風の幅を広げるということに全然関心を持っていないかのようにも思える。
大丈夫なのか。
戦隊シリーズ打ち切りの危機と功名心と
過去に戦隊シリーズの打ち切りの危機があったかどうかについては、今も資料を集めて調査中。今回は中間報告をやる。真相の究明を困難にしているのは、関係者がインタビューで必ずしも本当のことを言うとは限らないことだ。どいつもこいつも自分の手柄を大きく見せかける方向でしゃべりたがる。だから辻褄が合わなくなる。
では、プロデューサーを連続して十五年間も担当した、スーパー戦隊シリーズの最大の功労者ともいえる鈴木武幸氏はどんな発言をしているだろうか。まずは『スーパー戦隊画報』掲載のインタビューから。
『ジェットマン』では思い切って恋愛ものの要素を入れました。これは企画側や現場にあった「戦隊は毎年あって当たり前だ」という緩みだした空気を改革したくて入れた要素でした。周囲の反対もありましたが、結果的に振り幅を広くしたことで翌年の『ジュウレンジャー』につながっていきました。緩んでたのかよ!
雨宮慶太監督の言っていることと随分話が違うではないか。1991年に『鳥人戦隊ジェットマン』で恋愛要素をぶち込んだのは、当時は戦隊シリーズが打ち切りの危機で、それを打開するための乾坤一擲の賭けだと思い込んでいる人は多い。なんか随分とイメージが違うぞ。
もう一つ。『スーパー戦隊戦士列伝 赤の伝説』から。
今だから言えますが、シリーズ終了が具体化しそうになったこともあります。何年のことかは、このインタビューからは全く読み取れない。「具体化しそうになった」ということは、「具体化した」わけではないということか。終了の危機といっても大したことではなかったみたいだ。
鈴木氏というのは、自分の手柄を大きく見せかけるような発言はあまりない。今まで戦隊シリーズは打ち切りの危機を何度も何度も迎え、そのたびに自分の素晴らしいアイディアのおかげでそれを乗り切ることができた、とかいう話を作っても良さそうなのに(いや良くないけど)。
鈴木氏は謙虚で誠実な人なのであろうか? そーゆーのとも違うような気がする。特撮畑出身のプロデューサーというのは、なぜかみんなあまり出世しない。平山亨氏のように、自分から降りた人もいる。その中で、鈴木氏は今や専務取締役。結局の所みんな、出世したくてもできない鬱屈を、インタビューなどで自分の功績を誇大にしゃべることで解消しているのだろうか。なんか書いてて虚しくなってきた。
『仮面ライダークウガ』第25・26話の幼稚さ
もし自分の小学生のときに神崎みたいな先生が担任だったら、確実に学校嫌いになっていただろうなあ。
というのが『仮面ライダークウガ』の第25・26話を東映YouTubeを見て真っ先に思ったことである。なんでオマエがそんなもん見てるんだ、仮面ライダーには(昭和も平成も)関心ない、などと言っていたくせに――と言われそうだが、まあ無料だし、後学のためにとも思って見始めたら、刑事ドラマの部分は割と楽しめているが、しかし人間ドラマの部分がちょっとひどすぎるのではないか。
小学生だって決まりきった日常がイヤになって、ある日フッと電車に乗って遠くに行きたくなることくらいあるのではないか。しかし東京行きの電車に乗った直後にはもう目撃者から教師に報告が行き、その教師が東京在住の元教え子に電話、そして早々に身柄確保。いくらなんでも早すぎだろう。それとも栃木県というのはそれほどまでに相互監視の網の目が隅々にまで張り巡らされた、ガチガチの管理社会なのか? 普通ドラマでこういう話をするんだったら、自殺をほのめかすような書き置きを残しているとか、夜の十時になっても家に帰らないとかにするだろう。
ポレポレでは神崎先生が、子どもたちのことが分からなくなったと愚痴るのも意味不明のシーンだ。どうもこの先生、教師は生徒のことを100%理解していなくてはならないと思い込んでいるかのようだが、神崎先生って勤続何十年という設定じゃなかったのか? 普通こういうのって新任教師がするような勘違いだぞ?
夏目教授の娘の時も思ったが、なぜ五代のところに人生相談ばっかり舞い込んでくるのだろうか。とにかく作り手は彼を誰からも好かれる完璧超人にしたいように思える。どんなに深い悩みを抱えている人間でも、五代と接すればたちどころに固く閉ざした心を開く、とでもいうような。そのためには話の展開の不自然さなどどうでもいいと思っているのではないか。
これが、リアリティにこだわった作品ねえ……。
まだ折り返し時点であるから、これから挽回して面白くなることを祈ろう……と言いたいところだが、プロデューサーとか主演俳優とか、『クウガ』の作り手ってやたらと幼稚な言動を繰り返している人間が多い。彼らの自己投影が五代雄介というキャラクターだとするならば、あまり期待しないほうがいいのだろうか。
全話視聴完了後の感想
『ガッチャマン』を無視する戦隊シリーズ

石森章太郎(石ノ森章太郎)『秘密戦隊ゴレンジャー』より。どれが誰のセリフなんだろう。
「パクリとオマージュ」に関する議論というのは、どうしてかくも不毛なのだろうか。
おそらく「独創性」に関する間違った観念が横行しているからであろう。似たようなアイディアを持った作品が以前に存在していたということは、決してその作品の価値を落とすことにはならない。しかし落とすように感じる人は多い。そして騒ぎ立てる。
スーパー戦隊シリーズでいえば『科学忍者隊ガッチャマン』(1972年)の存在がある。
戦隊シリーズの歴史について書かれた書籍では、このアニメ作品の名前が挙がることは絶対にない(多分)。そして、ヒーローは一人で戦うのが当たり前だと考えられていた時代にあって、五人でチームを組んで戦うヒーローがいかに斬新なアイディアであったかとくどくどと説くことから話を始めるのが普通である。んなわけないって。もちろん、集団ヒーローいうアイディア自体はそれほど革新的なものではない、と書いてある本もある。しかしその場合、先行作品というのが真田十勇士とか南総里見八犬伝とか白浪五人男とか。そこまで遡らんでもいいだろう!
『秘密戦隊ゴレンジャー』は『ガッチャマン』を参考にしたということに言い逃れの余地はない。なぜなら石森章太郎のマンガ版の存在があるからである。これ、五人のキャラクターの分け方がまるっきり『ガッチャマン』なのである。そして石森章太郎は名義上の『ゴレンジャー』の原作者。影響を受けていないなどと言い張るのは無理がありすぎる(ちなみに「原作者」というのも実態ではないのだが。これも大人の事情がからんでいる)。
そういえば、『鳥人戦隊ジェットマン』はガッチャマンと鳥の種類が全部同じというのはやはり、『ガッチャマン』へのオマージュだったのだろうか(生物分類学上ではタカとワシ、フクロウとミミズクは区別しない)。偉大なる先達に対して、さりげない形でリスペクトを捧げようして仕込んだような気がする。それとも単に、勇猛さとか素早さとか、プラスのイメージを伴う鳥類限定で、なおかつバラエティに富ませようとしたら必然的にこの五つになる、というだけの話なのだろうか。スズメやハトの戦士なんて確かにイヤだし。
謎は尽きない。
トキワ荘の真の敗残者は誰か

伊吹隼人『「トキワ荘」無頼派――漫画家・森安なおや伝』
今の東映の拝金主義はけしからんと批判するだけなら簡単なのである。
映画人として、いい作品を作りたい、見てくれる人の精神の糧になるような物を作りたいと全く思わない人などおるまい。しかし映画というのはとにかく金がかかる(特撮ならなおさら)。「いい作品」よりも「金になる作品」を作らねばならない、という彼らに対する圧力もまた相当のものである。である以上、軽々しい気持ちで批判することもまた慎まねばならない。
その点、映画よりはずっと製作費が安くつくマンガの場合はどうなのだろうか。
「森安なおや」というマンガ家の生涯は、実態以上に不幸で惨めだったというふうに脚色され世間に流布されているようだ。なんのためにというと、もちろんマンガ界の伝説、「トキワ荘グループ」の輝かしい成功者である藤子不二雄(F・A)・石ノ森章太郎・赤塚不二夫らを引き立たせるためにである。ドキュメンタリーやら映画やらでも敗残者扱いが定番。森安氏が死んだのは急性心不全だが、アパートで一人暮らしだったから遺体の発見は二日後になってしまった。しかし近所に住む家族とは行き来もあったし友達もいた。それが「孤独死」なんてことにされてしまう。
マンガ家という職業を選んだ人間にとっての最大の苦悩は、なんといっても「描きたいもの」と「売れるもの」との食い違いである。両立させられればいいが、それでもどっちかを選ばなければならないとなった時、前者を選んだのが森安氏で、後者を選んだのが藤子・F氏らである。どっちが幸福かは、軽々しく結論の出せる問題ではない。にもかかわらず、前者を選んだ者の悲惨さや無残さだけが特に強調され、マスコミを通じて拡散していく。(ということは、逆の方も疑う必要があるということだ。藤子・F先生の生前の知り合いは皆、口をそろえてF先生が充実した悔いのない人生を送ったかのようなことを言うが、果たしてどこまで本当なのか。)
財産や名声を得たからといって幸福とは限らない。俺は俺の描きたいものを描きたいときに描きたいだけ描いたのだから、俺の人生に満足している――と本人は思っていても、世間の誰も耳を貸してくれない可能性がある。そして実態以上に無残な人生を送ったかのように言われる。
勇気の要ることだ。
藤子・F・不二雄作品の主人公の顔
藤子・F・不二雄先生の批判ばっかり書いてると、ファンから恨まれるんじゃないかと内心ビクビクしていたんだが、ファンの方がよっぽど辛辣のようだ。こんなもん見つけた。
【効き藤子F主人公クイズ!】 主人公の顔を画像から選べ基本的に藤子・F先生のマンガは日常と非日常の出会いから話が始まる。非日常サイドの主人公のほうは、いずれもユニークなデザインで魅力的なキャラクターばかりなのに対して、日常サイドの主人公のほうは手抜きがすごい。顔がほとんど一緒だ。顔だけではなく、中身も同様。これといった特徴なく、魅力の乏しい平凡人が多い。
いやこれは本当に手抜きだろうか。平凡なほうが読者としても感情移入しやすいと思ってワザとそうしているのではないか。確かにそういうセオリーはある。それが勘違いであることは、藤子・F先生の大ヒット作品がここに一つも入っていないことからも明らかである。大原正太、須羽みつ夫、野比のび太と、いずれも平凡なだけのキャラクターではない。ま、木手英一やつづれ屋21エモンのように、特徴のある顔で大ヒットしなかったのもあるが。あと、佐倉魔美や春日エリのように、主人公が女性の場合は方針が違うらしい。
以前藤子・F先生はインタビューで、のび太のことを「どこにでもいる、ごくありふれた男のコ」などと言ったことがある(大全集『Fの森の大冒険』に収録)。んなわけあるか! たとえば学校の成績にしたって、0点が普通なんてのは、のび太くらいのもんだろう。藤子Fワールドにおける日常サイドのキャラクターと非日常サイドのキャラクターの関係が、『ドラえもん』だけが他の作品と違って特殊だということは、愛読者なら誰もが知っていることであって、それを作者が把握していなかったなどということは、ちょっと信じがたいんだけど。
そういえば大原正太というのはA先生のキャラクターなのだった。『オバケのQ太郎』が藤子不二雄にとっての初の大ヒット作になったのは、そのことが大きいのかもしれない。その後はなぜか合作はやめてしまうのだが、続けておれば、もっとたくさん大ヒット作を生み出していたのだろうか。
マニュアルで創作は可能か

沼田やすひろ・金子満『「おもしろい」映画と「つまらない」映画の見分け方』『「おもしろい」アニメと「つまらない」アニメの見分け方』
5月5日のエントリのコメント欄で勧められた本をようやく読んだ。確かに創作の理論書としては優れている。映画とか小説とかマンガとかを見て「つまらないなあ、どうしてこんなにつまらないのだろう」と思った時、この本を読むとよい。「13フェイズ構造」に照らし合わせてみて、なるほど第7フェイズが弱いからつまらないのだなあ、と納得できる。そういう本である。
しかしこのような優れた理論書が発売されている一方で、どうして巷間にはつまらない作品があふれているのだろうか。映画を作るのであれば、まず脚本が上がった段階で、面白い作品になりそうかならなさそうか、この理論を使うことによって判定できるはずだ。にもかかわらず、何億という製作費をかけた、面白くもなんともない作品が毎日生み出されているのは、どういうわけなのだろう。不思議だ。
スーパー戦隊シリーズの場合、つまらない作品は13フェイズのうちどれに問題があるかというと、断然第7フェイズ「転換」である。戦隊シリーズの場合、ある日道を歩いていたら突然声をかけられて秘密基地に連れて行かれ、戦士に任命された、というケースが多い。まあ、最初はだいたい運命の渦に巻き込まれるような形で戦士になる。そして途中で転機が訪れ、平和と正義を守る戦士としての使命に目覚め、自発的な意志で戦うことを決意する。それが第7フェイズである。そこをきちんと描かなければ、主人公は人から戦えと言われたから戦っているだけでしかなく、そんな主体性のない存在に視聴者が満足できるわけがない。(そういう意味で、『鳥人戦隊ジェットマン』なんてのは話の構造自体はものすごく王道である。)
どうしてこの程度のことがうまく出来ないのだろうか。
創作という神聖な行為は、「これを表現したい」という、本当に心の底から沸き上がってくる熱情に突き動かされてこそ出来上がるものであって、マニュアル化できるようなものではない、という思い込みでもあるのだろうか。しかしそういうのは歴史に残る名作を生み出すような人が言うことだ。今のニチアサにそんなもん求めてる人なんかいるのだろうか?
『ニンニンジャー』へのジライヤ出演に思う

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「影とりプロジェクター」。郷ヒデキ、といっても帰ってきたウルトラマンとは無関係(多分)。
『手裏剣戦隊ニンニンジャー』10月18日放映に『世界忍者戦ジライヤ』のジライヤが出るらしい。まともに批判する気にもなれないので、今回も『ドラえもん』の話をする。
今でこそ批判的なことばかり書いてるが、私も子供の頃は『ドラえもん』が大好きで、てんとう虫コミックスの19巻が出た時は息せき切って本屋に駆けつけたものだが、「影とりプロジェクター」を読んだ時の気持ちは今でもはっきりと思い出せる。意味が分からない。分からないなりに心に引っかかるものがあったかというと、そんなこともない。単なる意味不明の話である。そこに出てくる女性アイドル「星野スミレ」とやらが『パーマン』に出てくるキャラクターだということを知ったのは十年以上経ってからだが、それを頭に入れた上で読み返すと、それはそれでやっぱり面白くもなんともない話である。
藤子・F・不二雄先生は何を考えてこんな話を描いたのだろう。1968年に連載終了した『パーマン』に未練があることのアピールだったのだろうか? 人気が高いうちに連載が終わったのは色々商売上の理由があったらしいが詳しくは知らない。そのアピールの甲斐があったのかなかったのか、1983年に連載再開、そしてそれ以降は『ドラえもん』に星野スミレがチョイ役として出てくることすらなくなった。気が済んだのだろう。
つまらない話だという感想は今でも変わらないが、別に腹が立つわけではない。自分の作ったキャラクターを、自分の作品の中で、自分の責任で出したのである。仮にその話の内容がファンの思いを傷つける結果となり、「こんなのはスミレちゃんじゃない」という声が沸き起これば、責任は全部自分で負う、という覚悟でやっていることである。「パラレルですから」と言い訳さえすれば何をやっても許されると思っている(そして実際許されている)某映画会社とはそこが違う。
星野スミレは「めだちライトで人気者」で再び『ドラえもん』に登場し、「オンボロ旅館をたて直せ」ではつづれ屋が、「なんでも空港」ではQちゃんやデンカが出てくる。これらはいずれも1980〜81年。この頃から急につまらなくなっていったような気がする。
藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(後編)
(承前)このような問題は子ども向け作品に限った話ではない。映画『二十四の瞳』(1954年)などに対してもついても同様の批判が存在している。しかし子ども向け作品の場合は事情はより切実だ。子どもは大人に比べればさらに理解力は低い。戦争だとかエコロジーだとか真の友情とは何かとか、重いテーマを作中で取り上げようと思えば、程度を落として描かざるをえない。子どもの頃に意味が深いと思いながら見ていたマンガやテレビ番組も、大人になってから見るとどうしても批判的な部分に目がいく。
そしてそういう見方をされることこそが、子ども向け作品にとっての名誉ではないかと思う。
「程度を落とす」と言えば聞こえは悪いが、しかし『ドラえもん』を読んだ子どもがそれをきっかけにして日本の戦争について興味を持つようになり、中学生・高校生へと成長するに従って年齢に応じて程度の高い本を読むようになれば、それは素晴らしいことである。重いテーマにそもそも触れないような作品は、子どもの頃にどんなに大好きであっても、大人になってから見返してみた時に単に懐かしさ以外の感情が沸き上がってくることはないし、議論する気にもならない。程度を落とさずに扱えば、そもそも子どもには理解できないから心にも何も残らない。程度を落としすぎず落とさなさすぎずという困難を達成した作品は名作と呼ばれるべきである。
もちろん、子どもの頃に感動し、大人になってから見返しても子供の頃と何一つ変わらぬ感動を与えてくれる作品、という名作もないわけではない。しかしそれは単にその人間が子供の頃から成長していないだけではないのか。
さて話は最後に戦隊に戻るが、戦隊に出演した俳優で、サイトやらブログやらをやっている人はいっぱいいるが、自分の出演した作品を本当に名作だと思い、出演を誇りにしている人は、批判的な目で自分の出演した作品について語るのではないだろうか。しかしそんな人は滅多にいないのである。
なぜフニャコフニャ夫はFよりA似なのか

左から順にフニャコフニャオ67年/フニャコ・フニャオ68年/フニャ子フニャ雄70年/フニャコフニャオ71年/フニャ子フニャ夫74年/フニャ子フニャ雄77年/フニャコ82年/フニャコフニャオ89年
いまだに「F」だの「A」だのと言った呼び方に慣れない。
そりゃ確かに合作していたのは『オバQ』までで、その後は二人とも別々に描いていたというが、「僕たちは二人で一人だ」という意識が藤子不二雄の作風を規定していたのは間違いなく、それを今さら「これはFの作品、これはAの作品」とか言われてもハイそうですかと受け入れる気になれない。「不二」は「二つではなく一つ」という意味だ。
象徴的なのがフニャコフニャ夫という存在である。
F先生のマンガに出てくるキャラクターである。常に締め切り追われているマンガ家。F先生とA先生の似顔絵を混ぜて更にブサイクにしたような顔をしている……と言われている割には、どう見てもA成分のほうが圧倒的に大きい。普通こういうのって逆にしないか。と思って抜き出して年代順に並べてみたのが上の図である。
こうして見ると、最初は確かにFA半々だったのが、徐々にFもAも抜けていって、普通のマンガ家というキャラになっていくのが分かる。そしてフニャコフニャ夫が最も大きな活躍をしたのが『ドラえもん』の「あやうし!ライオン仮面」(1971年)である。
F先生のトレードマークは何といってもベレー帽とパイプである。だから潰れた目・タコみたいな口・メガネ・低い背と、全体的にはA先生を踏まえていても、ベレーとパイプさえ描いておけばFA半々といった趣になる。しかし「あやうし!ライオン仮面」では飛んだり跳ねたりわめいたりの大暴れだから、口に何かをくわえさせるのは無理があった。A成分はまだまだ残ったまま、F成分はベレー帽だけという、その時点でのフニャコフニャ夫で世間一般のイメージが定着した。
結果として、自分より自分の友だちのマンガ家をネタにしたキャラクターが大暴れして、「あやうし!ライオン仮面」は『ドラえもん』の中でも屈指の爆笑回になったわけだが、これが果たして最初から二人別々のマンガ家という意識のもとで執筆されていれば、これほど面白い話になっていたかどうか。

藤子・F・不二雄『ウメ星デンカ』「スイカとギャング」にも、ものすごくヒドい役でA先生が出演。
藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(中編)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「階級ワッペン」より。この見方も単純過ぎる。
(承前)平和と繁栄を謳歌している21世紀のトーキョー。しかしその高度な科学技術文明も、設定によれば、人類が自力で築き上げたものではなく、地球に来訪した宇宙人から与えられたものである。それが、純粋な善意によるものなのか、それとも地球に利用価値があったからなのかについては、よく分からない。一つだけ確実なのは、地球にとって宇宙人の指導を受けるか受けないかの選択の余地などなかったということである。
年表によれば、1983年ごろに第三次世界大戦の危機があり、そして人類はそれを自力で解決できず、宇宙人が介入してくれたおかげで防ぐことができたという。そしてその後、地球は星間連盟に加入し正式に宇宙人との交流が始まったが、こういう経緯がある以上、地球に自治権が認められたとは考えにくい。
二人連れの客が「地球を地球人の手に取り戻せ」と演説をぶちあげたのは、そのような事情が背景にあったと思われる。
そしてその主張に対して、21エモンは何の関心も示さない。
21エモン、そしておそらくは他の圧倒的多数の地球人にとっても、豊かで安全な生活が保証されてさえいれば、独立の気概とか地球人としての誇りとかどうでもよい、と考えられているようなのだ。まさに鼓腹撃壌。
これが戦後日本の似姿であることは言うまでもない。藤子F先生が何を考えてこんな話を書いたのか、ちょっとよく分からない。F先生といえば1933年生まれ、生まれた時から戦死こそ名誉と周囲の大人たちから叩きこまれ、それがある日いきなり引っ繰り返った。この世代の人間には、だから深刻なトラウマを抱えた人もいる一方で、大多数は大した苦悩も葛藤も経ず、自分たち庶民は悪い指導者にだまされて戦争に協力させられ犠牲を強いられていたのだとみなし、アメリカのような優れた文明国の指導を新しく受けることになったことを光栄に感じたのだった。
それは同時に日本人に対して、戦争というものは、するもしないも決めるのは上のエライ人たちであって、我々庶民はそれに振り回されるだけの存在なのだ、という考えを植え付けた。『ドラえもん』において語られる大東亜戦争も、それは我々日本人が日本国の名のもとに戦った戦争であるという意識が極めて薄い。それは後続世代にも受け継がれることになった。しかしそんな戦争観が国際社会で認められるはずもないのである。(続く)
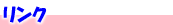
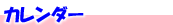
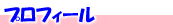
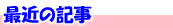
- 「ゴレンジャー同窓会」という詐欺事件(後編) (10/31)
- 「ゴレンジャー同窓会」という詐欺事件(中編) (10/28)
- 「ゴレンジャー同窓会」という詐欺事件(前編) (10/26)
- 「アンケート至上主義」についての誤解 (10/24)
- 戦隊シリーズ打ち切りの危機と功名心と (10/22)
- 『仮面ライダークウガ』第25・26話の幼稚さ (10/19)
- 『ガッチャマン』を無視する戦隊シリーズ (10/17)
- トキワ荘の真の敗残者は誰か (10/15)
- 藤子・F・不二雄作品の主人公の顔 (10/12)
- マニュアルで創作は可能か (10/10)
- 『ニンニンジャー』へのジライヤ出演に思う (10/08)
- 藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(後編) (10/06)
- なぜフニャコフニャ夫はFよりA似なのか (10/03)
- 藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(中編) (10/01)
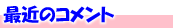
- スーツアクターという難題
⇒ Manju (10/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19)
- スーツアクターという難題
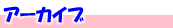
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)