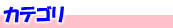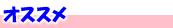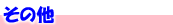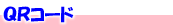スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その4=完結)
(承前)別にそれでも構わない、というのが一つの考え方としてある。演劇というのは役者の魅力を見せるのが第一であって、ストーリーなどどうでもよい。もう一つはやはりストーリーを重要とする考え方であり、その場合は当初の構想に反する五人の役者が集まったのなら、その時点であらためてストーリー自体を練り直し、しかるのちに五人のキャラクターを練り直す、という一段階多いプロセスを経る。
年内に戦隊マップを完成させたかったのだか「戦隊マップの作り方」はなんとか完成させられたようなので、まあよしとしよう。
戦隊を分類するにあたって注目すべきなのは「準備」である。つまり第一話で敵と初めて戦うという時点において、準備万端で敵を迎え撃つのか、それとも出たとこ勝負の戦い方を挑むのかである。戦士にふさわしい人間を探し、訓練を施し戦術を与える、つまり「発掘と育成」にどれほど手間を掛け、そして成果を上げたか。それは「無限に時間があれば」と仮定して、それと比較して算定する。ここで注意すべきなのは、後者が前者より劣った戦い方ではないということ。
そして次に、その準備がチーム本位でなされたものなのか、それとも個人単位なのかである。どのような戦法で戦うかが最初に決まっており、それに適合する五人を選ぶのか、それとも優れた能力を持った五人の戦士を探すのが先決であり、戦術は後で決めればよいとするのか。たとえば『超新星フラッシュマン』では五人は別々の星で育てられ訓練を受けたということになっているが、見過ごされがちではあるがこれは極めて重要な設定である。もちろん最低限の情報の交換はなされていたに違いない。
さてネットを色々見て回っていると、「戦士はどのように選ばれるのか」に着眼して戦隊シリーズを分析しようと試みている人は、私以外にも大勢いるようだ。心強いことである。ただやはりそこで(私を含めて)つまずきの石になっているのが、そもそも理由なんかなくて戦士に選ばれてしまったケースをどう考えるかである。典型的なのが『救急戦隊ゴーゴーファイブ』において、なぜ家族だけで戦うということになったのか、明確な理由はどうも存在しないようだ。家族だけで戦いたいから家族だけで戦っているようであり、それは1970〜80年代のスーパー戦隊の感覚からは決して読み解けないものである。
スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その3)
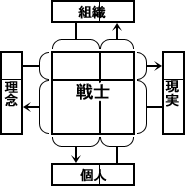
(承前)比喩がコロコロ変わって申し訳ないが、今度は演劇を例にとる。主役はこういうキャラクターなので、それにピッタリのイメージを持った役者を探したがなかなか見つからない、ということがある。時間がないので仕方なく、八割くらいイメージが合致している人で間に合わせることにした。そして逆に、その役者にピッタリに合うように脚本と演出プランを修正。そしたら最初の構想よりも、もっと素晴らしい劇になった――というケースがある。
つまり、役に役者を合わせるのも、役者に役を合わせるのも、優劣はないのである。合ってさえいればよい。後者の効果を最初から狙い、時間がたっぷりあるにもかかわらず、役にピッタリの役者を探す努力を適当に切り上げることすらある。まあその場合、脚本家と演出家に皺寄せがくるが。
さて、話をスーパー戦隊に戻すと、ある人が戦士に選ばれたとして、その理由は二つに分けられる。一つは理念先行現実追随の理由、もう一つは現実先行理念追随の理由である。知力や体力、精神力に秀でた者を戦士に選びたい、という理念が最初にあるとする。しかし、敵の襲来が予想より早く、戦士の選考に十分な時間をかけることができなかったらどうなるか。その場合は「たまたま近くにいた」というのが戦士に選ばれた理由ということになる(つまりそれが「現実先行」)。場合によっては、十分な時間があるにもかかわらず、ベストでない者を選ぶこともありうる。
さて、理念先行と現実先行の理由の比率は、どのようにしたら算定できるであろうか。「時間が無限にあったら」という仮定を設けると分かりやすい。現実先行的理由がゼロになって、理念先行的な理由だけで戦士の選考が行なわれたとしたならば、一体どのようなチームができていただろうか。そしてそれと比較することによって、この戦隊は理念何%現実何%と同定できる。
しかし果たしてそういうやり方で、ちゃんと戦闘能力を発揮できるのかという疑問もある。話を演劇に戻すと、もともとのプランでは、ヒロイン二人は対照的な性格をしており、それがストーリーに味わいを加えるはずであったのが、役を役者に合わせた結果としてどっちも同じような性格になってしまった、なんてことになったらどうすればいいのだろうか。つまりここでは「理念と現実」の関係と全く同じ構造が、「個人と組織」の関係についても成立していることが分かる。(続く)
何が戦隊シリーズを25分に削ったのか(後編)
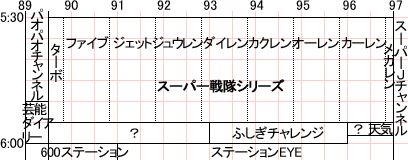
(承前)1983年の4月から戦隊シリーズが5分短縮になった原因として考えられるのは二つ。
(1)ANNニュースレーダーの5分繰り上げ
(2)藤子不二雄劇場を10分→15分へと拡充
恐らく正解は(1)であろう。「ドラハッパ」などと呼ばれ、藤子不二雄原作のアニメが当時人気絶頂だったとはいえ、月曜から土曜まで毎日放送していた帯番組に15分はいくらなんでも長すぎではあるまいか。
テレビ番組の移り変わりを調べていて思うのは、番組にも「格」というものがあるということである。それは必ずしも視聴率を反映したものではない。テレビ局にとってもっとも格上である報道番組が、ジャリ番の都合で時間帯が変更させられるなど考えられないことである。
当時は、同じ6時30分から日本テレビもTBSもニュース番組をやっていた。そこでテレビ朝日としては他の局よりも5分早く始めることによって、視聴率競争に打ち勝とうという魂胆だった、そう考えるのが妥当であろう。
しかしそれはそれで随分とセコい話ではある。あまり体面のいい話ではない。スーパー戦隊シリーズに関する書籍は多いが、どれも25分になった理由について説明していないのは、それで説明がつく。
1987年10月からはニュースレーダーに代わってANNニュース&スポーツが始まると、6時55分から7時までは、本当にどうでもいい5分間だけのミニ番組が始まるが、戦隊は依然として25分のままである。
1989年10月からは金曜日へと移行、この際に30分へと戻さなかったということは、もう当時は本気でシリーズ打ち切りが視野にあったと思う。ここでも6時からはNHK、日本テレビ、TBS、フジテレビがニュース番組をやっていたが、その空いた5分間を利用してテレビ朝日だけ早く5分ニュースを始めるということもなかった。ちなみに1996年10月からは、2分間だけ早く始めるなどというセコいことをやっていた。半年だけ。
1997年4月からは戦隊シリーズはめでたく日曜早朝へ移行しそれに伴い30分番組へと復活する。これは、テレビ朝日が改心し、今後は戦隊シリーズを大切にする決心をしたということであろう。あるいは単に、日曜早朝は、あまり視聴率競争にとって大して重要でないと思われていただけかもしれない。日曜早朝が「子供にとってのゴールデンタイム」と呼ばれるようになるのは、それからしばらくたってからのことである。
何が戦隊シリーズを25分に削ったのか(前編)
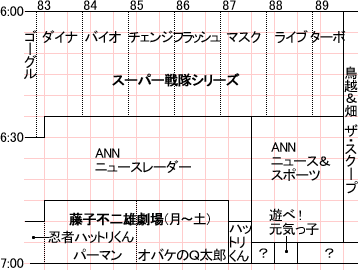
戦隊シリーズが25分番組だった時期がある。
1983年4月から1997年の3月まで。作品名で言うと『科学戦隊ダイナマン』の序盤から『電磁戦隊メガレンジャー』の序盤まで。今は戦隊シリーズに関する書籍も多く出ているが、なぜかどの本もその理由について触れていない。では自分で調べてみるかと思ったら、たちまち行き詰まってしまった。
その5分間に何を放映していたのだろう、ということが追跡できたのは最初の四年半だけで、その後は番組名すら分からない。一応当時の新聞縮刷版と『日本民間放送年鑑』に当ってみたのだが、新聞には「スター」「芸能」「遊び」「ふしぎ」「キッズ」などという文字があるだけで、何の略かも不明。ラテ欄は夕刊ではスペースに余裕があって、あと五文字くらい入るのにもかかわらず、こんな表記である。『放送年鑑』には、その年の開始番組と終了番組が載っているのだが、そこにも載っていないということは、よっぽどどうでもいい番組だったのであろう。何しろ5分間のミニ番組だし。
ここで私がプロのライターであれば、テレビ朝日の内部資料を手に入れようとするのだろうが、別にそんなことをしなくても、もう謎は解けたも同然である。
この時期の戦隊シリーズについて、よりスピーディになってテンポが良くなったなどと書いてある本もある。しかし展開がせわしないのは見ていて瞭然だし、実際当時の監督にも、もっと時間があればドラマが深く描けるのになどと発言していた人もいた。時間短縮は明らかに戦隊シリーズにとってマイナスだった。テンポ云々は、そのマイナスを最小限に食い止めたということに過ぎない。
少なくとも最初の四年間に関しては納得できる。テレビ局にそういう事情があったのなら5分削られたのも止むを得ない。しかしその時期を大過なく乗り越えてしまったがために、「戦隊なんか25分番組で十分だろう」と局に思われてしまった。戦隊シリーズなんてその程度の番組でしかなかったのである。
スーパー戦隊シリーズは来年で四十作目を迎える。多くの人たちの理解と協力があってこその記録であり、テレビ朝日もまたその一員であることには違いない。過去にはジャリ番だと思ってぞんざいな扱いをしてきたこともあったが、そんな過去をいまさらネチネチとほじくり返すのも、大人げない態度である。(続く)
スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その2)
(承前)1997年の『電磁戦隊メガレンジャー』が、戦隊の歴史において特筆すべき作品であるなどと評価されることは滅多にない。
確かに、敵の襲来が予想よりも早かったために、仕方なく五人の高校生を戦士に選んだ、という設定自体はよくあるものである。しかし久保田博士は決してこの五人を、当初の予定に比べて劣っていると考えてはいなかった。彼らの若さの可能性に賭けると、第2話で言明している。だから、久保田は彼ら五人を教え導く立場にありながら、逆に彼らから教えられることも多かったのである。
翌年の『星獣戦隊ギンガマン』になると、戦士としての実力は明らかにヒュウガがリョウマより上とされている。ヒュウガが復帰してもなおリョウマは戦士を続けたいと言ったことに、何か合理的な根拠はない。「俺は戦いたいんだ」、それだけである。従来の作品であれば、「潜在能力ではリョウマの方が上かもしれない」などと匂わすような描き方をしたであろうし、そうしていれば『ギンガマン』は本当にただの凡作になっていたことは間違いない。
つまりそれまでは、理念が先にあって、現実はそれに従うべきものであった。こういうやり方で敵と戦う、という戦法が先に決まり、それに適合するような能力を持った人間を選んで訓練を施して戦士にするのである。逆のケースも場合によってはあったが、それは止むを得ない事情の結果であった。しかし『メガレン』『ギンガ』を経て、戦隊シリーズにおいて「理念→現実」と「現実→理念」は全く対等のものとなったといえる。
比喩を用いれば、理念がレシピで現実が食材である。食事を作ろうと思ったら、カレーの作り方しか知らないのに、冷蔵庫の中にはダイコンやチクワしかない。解決法は二つ。一つは今から買い物に行ってカレーの材料を買ってくることであり、もう一つはダイコンやチクワに合う料理(おでん等)の作り方を今から習うことである。レシピに合わせて食材を調達するか、食材に合わせてレシピを調達するか。
料理に喩えれば、別にどちらが上ということはないということは容易に理解できる。ところが日本人は「一つの不動の信念を貫く」と言うと、なんかものすごく立派なことのように考える風潮があり、それが冷静な議論を困難にしている。それが単に「レパートリーの少ない料理人」と同じようなものでしかなくても。(続く)
スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その1)
ウィキペディアを見ていると、なんかやたら「シリーズではこの作品が初」みたいな記述が目につく。革新的なのはなんでもかんでも良いことで、保守的なのはなんでもかんでも悪いことという決めつけでもあるのだろうか。『鳥人戦隊ジェットマン』も単に新しいだけの作品ではない。絶対の正義を信じて戦うという、旧来ヒーロー像の残滓を引きずっているところもあり、それがまたこの作品の魅力の一つでもあるはずだ。
『ジェットマン』ではバードニックウェーブが、バイラムに対抗して人類を守る唯一の力、という設定になっている。いや、なんとなく雰囲気的にそういうふうに話が進んでいるだけであって、よくよく考えてみると、「唯一」なんて作中では誰も言っていない(ナレーション含む)。だいたいバードニックウェーブは人類が研究室で作ったものであって、別に神秘的な設定があるわけでもなし。
にもかかわらず、竜以外の四人は「しかたなく戦士に選ばれた者」ということになっている。事故が起こって、当初の構想とは食い違ってしまったという理由で。だが果たして本当に彼らは劣っているのだろうか?
それ以前の作品でも、『デンジマン』ではデンジ星人の末裔としての力が、『チェンジマン』ではアースフォースが……というふうに、それがそれぞれの作品世界において絶対的に信頼できる力が一つだけあるという設定になっている――ように見える。しかし正確に言うとそれは「唯一の力」ではなくて、「今のところ知られている唯一の力」にすぎない。他にも方法はあるのかもしれない。と考えると、第二話であきらが戦士になることを拒む場面についての解釈も大きく変わってくる。もっとも『デンジマン』のファンでもそこまで突っ込んで考察している人というのは見たことないが。
『ジェットマン』に話を戻すと、第40・41話に出てきたネオジェットマンは、そういう意味では作品のかなり深いところを突いていたと言える。当初の構想に近いのはネオジェットマンの方であり、それは果たして竜たちのジェットマンに比べて優れていると一概に言えるのか。もっともこの問題も、あまり掘り下げられることはなかったが、掘り下げられていれば『ジェットマン』がさらに深い作品になったかどうか。意見が別れるところであろう。ちなみにこの回の脚本を書いた荒木憲一氏、メインライターでない人である。(続く)
ゲゲゲの正義漢

水木しげる『ゲゲゲの鬼太郎』「海座頭」。悪い妖怪をやっつけるだけのワンパターンになっていったことに対する自虐ネタ?
『藤子・F・不二雄大全集』をほぼ読み終わったので、先日から『水木しげる漫画大全集』を読み始めたら、その矢先に水木先生の訃報。
その追悼記事や追悼番組で、「水木作品の素晴らしいところは、単なる勧善懲悪ではないところである」という表現を何度目にしたかしれない。確かにそうかもしれない。とすると、将来「水木しげる論」が書かれるであろう際に、『ゲゲゲの鬼太郎』はどういう扱いになるのかが気になる。なぜなら、水木先生が生涯描いた莫大な数の作品の中で、ダントツの人気と知名度を誇るのが『ゲゲゲの鬼太郎』であり、そしてそれが大ヒットしたのは、単純な勧善懲悪物にしたからである。
実際、『ゲゲゲの鬼太郎』って確かにあまり面白くない(もちろん「水木作品の中では」という意味だが)。これのヒットで水木先生は貸本漫画時代の極貧生活から抜け出すことができたのであって、いかにも編集者から「売れるためにはこういう描き方をしなさい」と言われて素直に従って描いた作品という感じがする。しかしそのことが却って良かったようにも思える。めちゃくちゃ面白い作品ではないが、読んでて不愉快になる作品でもない。水木先生の作品に対する思い入れのなさを反映してであろうか、鬼太郎もまた妖怪を退治して高揚感なく、淡々と事務的に作業を進めているようにも見える。おかげで正義のヒーローにありがちな傲慢さや独善さを作品から感じることが少ない。
さて、1970〜80年代のスーパー戦隊シリーズが今見てなお面白いのは、作り手が本気で正義を信じていたからである。正しい科学の発展が、いずれ人類を理想の世界へと導くであろうと本気で思っていたからである。今この2010年代に、そんな作品を作るのはどう考えても無理だし、だったら無理して熱血漢を演じるより、いっそのこと鬼太郎みたいな眠たそうな目つきをしたヒーローを復活させてみるのも手ではないかと割と本気で思う。そうすれば戦隊の人気も少しぐらいは回復するんじゃなかろうか。
心の奥底では正義を信じていないにもかかわらず、信じているふりをして(あるいは本人も信じているような気になって)、正義の名のもとに暴力をふるう。世の中にこれ以上不愉快なことはない。
バンダイを「悪の財団」と呼ぶのは誰か

小野塚謙太『超合金の男 ―村上克司伝―』
ウルトラシリーズやガンダムシリーズのファンの中には、バンダイを悪の財団とか金の亡者のように思い込んでいる人もたくさんいるようだ。その背後には、作家というものは好き勝手やらせれば素晴らしい作品を作るものであり、それを玩具会社が資本主義の論理で押しつぶす、みたいな単純極まりないイメージがある。それに対して仮面ライダーシリーズと戦隊シリーズのファンの間には、そのような風潮は薄い。その両シリーズのファンには賢い人が多いからではない。東映がバンダイ以上に拝金主義的な体質を持った会社だということを、知っているからである。
なにしろこの本によれば、村上克司氏すら今のスーパー戦隊シリーズはおもちゃの数を出しすぎることに対する違和感を抱いているくらいなのだから。もちろん「個人的な意見」と断ってはいるが、バンダイのキャラクタービジネスを長らく牽引してきたその張本人の口からすらそんな言葉が出てくるということは、今のスーパー戦隊をめぐる事態は相当深刻なように思われる。
富野由悠季氏との間のバイク戦艦をめぐるやりとりについては巷間で色々言われてはいるが、スポンサーとして商品が売れなければ文句をいうのは当たり前だ。金が湧いてくるわけじゃないんだから。しかしそれは、「売れない商品」に対してばかりではなく、「売れそうに思えない商品」に対してまで口出しするようにエスカレートする危険性をはらむ。そして既成概念にとらわれない斬新なアイディアを持った作品を生むことを妨げる要素にもなりかねない。そのような懸念は今やあっちこっちで見聞きする。
バンダイが悪の帝国で、村上氏がその首領であるかのような誤解を抱かれることに、村上氏に責任が全くないわけではない。2000年くらいまでずっと戦隊のマスク、スーツやマシン、ロボットをデザインし続けるという、多大な貢献をしてきた人であるにもかかわらず、クレジットに決して名前を出さないからである。マニア向けの書籍や雑誌にすら、デザイナーの名前が伏せられていた。これは、玩具会社サイドの人間が、制作に関わっているということは色々な誤解を招くという配慮からだというが、そんなことしたら余計に誤解を招くだろ。
荒木飛呂彦が『サザエさん』を語る

荒木飛呂彦『荒木飛呂彦の漫画術』
最初に断っておくと、大していい本ではないです。「秘伝の公開」とか言っている割には、「マンガの描き方」といった類の本に既に書かれているようなことばかりだし、文章も下手だし(無理もない)。だが、中には鋭いことも書いてあって、
アニメの『サザエさん』がなぜ何十年も続いているかと言えば、その時その時で新しく作ったエピソードを加えて、現代風にアップデートし続けているからで、つまり一連のエピソードからなるストーリーによってリニューアルしているのです。作家として一流の人は評論家としても一流のようだ。
『サザエさん』こそは理想のコンテンツ、十年一日で同じことやってるだけで人気が維持できるんだから――なんてことを仮面ライダーシリーズのプロデューサーが言ったりしているが、こういうこと分かった上での発言なんだろうか。冷静に考えれば、莫大なエネルギーを注ぎ込むことなしに、何十年も人気を維持し続けることなど出来るわけがない。時代に合わせて少しずつ少しずつ変えていっているから気づきにくいだけであって、実際、長谷川町子の原作の方は、今読んで大して面白いものではない。――ということを、荒木氏がものすごく遠回しに書いているのは、やっぱりハッキリと書いたら色々差し障りがあるんだろうか。
『水戸黄門』が終わったのも、多分そこを見誤ったからなのであろう。
それにしても、世の中にはマンガやアニメの批評や分析をしている人というのはたくさんいるが、アニメの『サザエさん』についてそういうことをやっている人というのは見たことがない。いるかもしれないけど、まあやったところで労が大きい割には報いも少なそうだ。カツオの性格の変遷について、本格的に研究なんかすれば、戦後の日本の世相の変化についての貴重な資料になりそうな気もするんだけど。
真に偉大な作品ほど、批評や研究の対象になりにくい。
そしてスーパー戦隊についても事情は同じだ。戦隊史について研究しています、なんて言ったら世間からは冗談としか受け取ってもらえないことは間違のないところだ。
『ゴーカイジャー』の視聴率を下げたのは誰か
スーパー戦隊シリーズの第40作目の記念作となる『動物戦隊ジュウオウジャー』に関する情報も出回り始める季節になったが、案の定というか、歴代戦隊とつながったストーリーや、オリジナルキャストの出演を期待する声が上がり始めている。
五年前にもそういうことをやって、視聴率を前年から0.5ポイントも下げたことを『海賊戦隊ゴーカイジャー』の関係者がどういうふうに総括しているのか、ちょっと聞いてみたいところではある。
特に俳優。
当時の雑誌記事を調べていると、宇都宮孝明プロデューサーによれば、当初はオリジナルキャストを出すにしても近年の作品だけで、昔の人など呼ぶ予定はなかったらしい。そしたら「俺も出せ」と逆オファーをしてくる俳優がわらわらと出てきて、その声に押されたのか、それとも別の理由があったのかはよく分からないが、とにかく予定を変更して戦隊OB・OG大量投入ということになった、そしてその結果が視聴率の大幅下落というわけである。
もっともこんな結果は宇都宮P以下のスタッフにとっては最初から分かりきっていたことであった。戦隊シリーズのメイン視聴層は子供である。子供は昔の戦隊なんか知らないし興味もない。またそれに代わって高齢の視聴者の関心を引くようなトピックがあったわけでもなし。だいたい1970年代や80年代の戦隊シリーズをリアルタイムで視聴し、当時の作品に深い思い入れを持っているファンにしてみれば、今の戦隊なんかとても見るに耐える代物ではない。
もっとも東映の上の方の人にとっては、『ゴーカイジャー』は成功作だそうだ。理由はレンジャーキーがバカ売れしたから。もう完全に30分の玩具CM扱いだ。だったらなおのこと、過去の作品のオリジナルキャストを出して後日譚みたいなことをやる意味がない。ゴーカイチェンジで十分だろう。
東映の公式サイトを見ていると、当時としては古巣に対するうるわしい愛情のつもりだったのだろうが、今読むと善意の押し売り感が漂う。今はどう思っておられるのであろうなあ、西村和彦さん。
東映公式サイト・『海賊戦隊ゴーカイジャー』第30話「友の魂だけでも」
橋下徹と土井たか子は似ている
いちおー戦隊に関係した話です。
今の日本の政治は急速に劣化しているとか、反知性主義の跋扈とか、盛んに言われているが、絶対に嘘だと思う。橋下徹氏率いる維新の会に対する熱狂は、1989年に起こった日本社会党委員長の土井たか子ブームとソックリだ。こんなことを言ったら両方から「一緒にすんな!」と叱られそうだが。
維新の党に対する国民の支持なんて、ほとんどが橋下徹個人に対する人気によるものであって、それは党分裂後の世論調査からも明らかである。にもかかわらず、分裂前の国会議員が51人中25人、半分も押さえられなかった。よっぽど人望のない人らしい。この「人気は高いが人望は低い」という点で思い出すのが土井委員長である。1989年の参院選で日本社会党を大勝ちさせながら、その後の党内で何のリーダーシップも発揮できかった人である。もっとも彼女の場合は、建設的なビジョンなど最初から何一つ持っておらず、単に女の政治家であるというだけで、男社会をぶっ潰してくれるであろうという期待を担わされただけの話ではあったのだが。
その「女−男」を「大阪−東京」に置き換えて、25年後の今また同じことをやっているだけとも言える。
さて、以前このブログでは「スーパー戦隊シリーズは時代を映す鏡である」ということを書いたが、訂正をする必要を感じる。少なくとも1980年代くらいまでは、スーパー戦隊は単に戦うだけの存在ではなかった。人類の素晴らしい未来を切り開くという最終的な目標があり、それを阻む敵をやっつけるために、毎週毎週新たに出現する怪人と戦っていた。90年代に入ると段々とそんな壮大な夢や理想を持つことが難しい世の中になって行き、それでもなんとか「正義とは何か」という難問と格闘しながらスタッフは番組を作り続けてきた。それに対し現実の方ではこの25年間、この国の政治の世界で長期的なビジョンが力強く打ちだされたことなど一度もなく、政治家は単にその時その時の「敵」を見つけてはぶっ倒せと叫ぶだけだった。
これは、現実の世界は夢も理想もないものであるから、せめて子どもたちの前だけでは希望ある未来を語っておきたい、とこの国の大人たちが考え続けてきたことの現れだったのだろうか。そんなふうに考えると、それはそれで情けない話ではある。
なぜ大葉健二を叩かないのか
2013年の『スーパーヒーロー大戦Z』におけるギャバン・一条寺烈の扱いについて、『宇宙刑事ギャバン』のファンが怒ったのは当然である。もっとも、その怒りに対して共感を寄せる気など、まったく起こらなかったが。
私が不可解だったのは、この映画が公開された当時、インターネットの掲示板などで一番叩かれていたのが白倉伸一郎プロデューサーだったということである。白倉なんか叩いたってしょうがないだろ! ファンの思い入れよりも金のほうが大事というのは東映という会社が長年かかって築き上げてきた社風であって、氏は単にその伝統に従って仕事をしただけである。個人でどうにかなる問題ではない。他にも脚本の米村正二氏と監督の金田治氏が叩かれていた。
だったらなぜ大葉健二氏を叩かないのか?
それこそが「鎖の最も弱い環」だろう。
だいたい白倉氏という人は、敵が多いほどうれしくなるというか、いくら叩いたところで蛙の面に小便というか、そーゆー人だというのはもう周知の事実ではないか。それに比べて俳優はイメージが大事である。叩いて叩いて叩きまくって、ノイローゼにしてやったらよかったのだ。そして、自分がこんな糞映画に出演し、一条寺烈役を演じたことによって、どれほどファンの気持を傷つけてしまったかということを、大葉氏に骨身にしみるまで分からせてやるべきであった。大葉氏もまた被害者である、などという弁明の成立する余地は一切ない。ギャラを受け取った以上は。
しかしファンは過激な行動に出ることもなかったし、そしてそれ以降も東映は懲りることなく、往年の俳優を起用して同じような糞映画を作り続けている。
要するに、ファンはナメられているのだ。どうせあいつらはそんな大それたことをするだけの智恵もなければ行動力もない。そのように白倉氏に見透かされているのだ。そうである以上今後もやりたい放題は続くだろう。
ところで、『仮面ライダークウガ』の主演を演じたオダギリジョー氏は、こちらのほうは理由はよく分からないが『クウガ』ファンからよく叩かれる人である。先日放送された『高寺成紀の怪獣ラジオ』では、「今後、五代雄介を演じることはありえますか」と質問されて、それに対する答えが「脚本次第」。
ヒーローの魂を持った俳優は一体どっちだろうか。
平成の次に来るヒーロー?(後編)
(承前)最近のスーパー戦隊を見て感じる最も大きな違和感は、ヒーローたちがまるで好きで戦っているかのように見えることである。
戦わない、という選択肢は初めからない。人類の生存を脅かす敵が、週に一体のペースで次から次へと襲ってくる世界である。死にたくないと思えば戦う以外ない。そうやって毎週戦い続けることが、やがては地上に理想の世界を実現させることにつながると思えばこそ、ヒーローたちはいかなる困難さにも耐えることができた。かつては。では現代のように理想を口にすることが難しい時代において、人は一体いかなる動機で戦い続けることができるのだろうか? 賽の河原ではないのか。
そこでその動機の不足を補うべく考えだされたのが、戦いそのものを楽しむことである。確かにこれはうまい手である。
ただ、「戦わねばならないから戦う」と「戦いたいから戦う」のハイブリッドの時代を経て、その傾向がさらに亢進すると、ヒーローたちはまるで後者が戦うことの動機の全てであるかのような様相を呈し、そうすると問題が露呈し始める。
そんな戦いを、なぜ視聴者が応援しなくてはならないのか。
もともと争い事が好きな性格ではなく、しかし、人々が安心して平和に暮らせるような世の中を作るためには、誰かが戦いを引き受けなくてはならない、そのような思いを胸に戦いに立ち上がった主人公というのであれば、もうそれだけで視聴者としては応援する気にさせられるのに十分である。しかし、好きで戦っているのであれば、まあ頑張ってちょうだいと思うだけである。ラストニンジャになりたい? 勝手になれば?
クリエイターにとって、自分のために戦う主人公を描くのは、他人のために戦う主人公を描くのに比べてはるかに難度が高い。視聴者を惹きつけるためには、ラストニンジャになることが、主人公たちにとってよっぽどの切迫感のあることだというふうに描く必要がある。どうもこの5年ほどのスーパー戦隊を見ていると、戦いの目的は昔と違ってきているのに、ヒーローの描き方は昔のままをやっているような気がする。
それとも今は過渡期であって、新しいヒーロー像を生むための苦しみの時期なのだろうか?
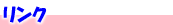
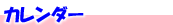
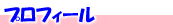
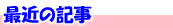
- スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その4=完結) (12/31)
- スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その3) (12/28)
- 何が戦隊シリーズを25分に削ったのか(後編) (12/25)
- 何が戦隊シリーズを25分に削ったのか(前編) (12/23)
- スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その2) (12/21)
- スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その1) (12/19)
- ゲゲゲの正義漢 (12/17)
- バンダイを「悪の財団」と呼ぶのは誰か (12/14)
- 荒木飛呂彦が『サザエさん』を語る (12/12)
- 『ゴーカイジャー』の視聴率を下げたのは誰か (12/10)
- 橋下徹と土井たか子は似ている (12/05)
- なぜ大葉健二を叩かないのか (12/03)
- 平成の次に来るヒーロー?(後編) (12/01)
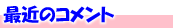
- スーツアクターという難題
⇒ Manju (10/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19)
- スーツアクターという難題
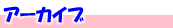
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)