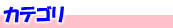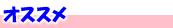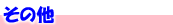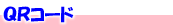スーツアクターという難題

鴬谷五郎編著『東映ヒーロー仮面俳優列伝』
スーツアクター二十人にインタビューした本。
二階建ての家の屋根から落ちるとか(下はマット一枚)、炎の中や水の中でアクションをしたら息ができなくなって死にそうになったとか、そういう話が普通のこととして出てくる。安全管理をおろそかにしているわけではないとは思うが(多分)、危険が多いのはやむをえないことではあるし、そうやってアクションに文字通り命を懸けている人たちに支えられて、スーパー戦隊シリーズや仮面ライダーシリーズは続いているのだ――と素直に感動しておけばいいのであろうが、しかし釈然としないものも残る。
アクションパートがこれだけ高いプロ根性によって支えられている一方で、プロデューサーや脚本家や素面の役者のあの意識の低さはなんなのだろう?
どうも最近のこのプログ、キャストやスタッフが雑誌のインタビューで喋ったこととかブログに書いたこととかに対して、やたらと怒っているような気がするが、これは別に誰か問題発言をしていないかと意識的に探してやっているわけではない。特に何もしなくても普通に目に入ってくるんである。おかげでブログのネタに事欠いたためしがない。
そもそもスーツアクターというのは報われない職業である。どんなに頑張っても子供に人気が出ることはない(というかむしろその存在を悟られないことこそが勲章である)。重労働で危険性大、そしてそれに見合うだけの給料が出るわけでもないらしい(というようなことはこの本には載ってないが)。
モチベーションは一体どこから湧いてくるのだろうか?
子供たちに夢を与えたい、子供たちに少しでも質の良い作品を見てもらいたいという情熱が彼らのアクションを支えているのだ、と言えば模範回答になるのだろうが、だったらプロデューサーや脚本家も、彼らのそのような命懸けの思いに感化されて自分たちもしっかりしたストーリーを作ろうとか、そういうことを少しは思ってもよさそうなものだ。
というか、そもそもこの本自体、スーツアクターの人たちの、自分のアクションを素晴らしい物にしたい、自分の演じるキャラクターを魅力的なものにしたい、という気持ちがひしひしと伝わってくる一方で、作品を良い物にしたいという思いは全然出てこない。自分に与えられた仕事だけに全力を尽くし、それ以外には無関心、それこそが真の職人魂ということなのだろうか。しかし本当にそれでいいのか?
仮面ライダーは面白くなければいけないのか
白倉伸一郎氏はアンチも多いがファンも多い。自分は生産者の側の人間なのだから当然生産者の立場に立つ、消費者の立場は二の次である、とはっきりと宣言していることが、一種の清々しさを感じさせるからであろう。『仮面ライダー1号』公開を記念した井上敏樹氏との対談では、
仮面ライダーっていうのは「あって当たり前」、よくも悪くも、っていうのは一つのゴールなんですよ。なんか変なことやってるなっていうことじゃなくて「あって当たり前」っていうふうになっててほしい。でも、ま、見ていて面白いかどうかは(以下笑い声が起こって聞き取れず)笑い声が起こったのは、話の流れから、そんなものが見ていて面白いものではないことは分かりきっているからである。分かっていて、作る側の都合として、そうしたいと言っているのである。
「スーパーヒーロー大戦」のパンフレットで、自分の仕事は劇場に足を運びたいと客に思わせることであり、その客が満足して家路につくかどうかには関心がないかのような発言をしたこともある。
たとえて言えば、ビール会社の社長が、私はビールの味には関心がない、関心があるのは広告とかがうまくいって売れるかどうかだけだ、とあたり構わず公言しているようなものである。
その社長が、ある日突然「みなさん、うちの会社のビールはおいしいと思いますか? 私は最近おいしいと思ったことがない」などと言い出したらどうか?
消費者としては戸惑うだけだ。「あんたに酒の味なんか分かるの?」と。
『仮面ライダーアマゾンズ』の制作発表会で、白倉氏が「最近の仮面ライダーを面白いと思ったことがない」などと言ったことが、大して話題になっていないということは、多分そういうことに違いない。
『ドライブ』や『ゴースト』といった最近の仮面ライダーをつまらないと思っていた人たちの間からは、この発言を歓迎する向きも見られる。ライダーシリーズを安定して続けるためには『サザエさん』化する以外になく、実際そうしてきたが、それは地上波の制約があったからであって、動画配信ならもっと思い切ったことができるはずだ――とでも思っているのだろうか。しかし、今まで「仮面ライダーは面白くある必要はない」と言っていたまさにその当人の口から、「次からは本気を出す」みたいな言葉を聞かされても、なにをどう期待しろというのか。
とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
炎上商法の達人の名をほしいままにしてきた東映の白倉伸一郎プロデューサーも、さすがに最近は疲れているようだ。
三月十八日に行なわれた『仮面ライダーアマゾンズ』の制作発表会では例によってとんでもない発言をやらかしたのだが、ツイッターでも反応は鈍い。飽きられた、というのもあるだろうが、どうも発言の真意が理解されていないようにも見受けられる。
東映の取締役という偉い立場にいながら「最近の仮面ライダーは面白くない」などと、懐古厨みたいなことを言ったもんだから、もっと騒ぎになってしかるべきだが。ただソースによって微妙に発言内容が違っている。マイナビニュースでは「牙を抜かれた仮面ライダーに牙を」、アニメイトTVでは「トゲを抜かれた仮面ライダーにトゲを」。これは瑣末な問題としても、前者にだけあるのが
関わる人が増えた分、やれることが制限されて丸まってしまっている。後者にだけあるのは
『仮面ライダークウガ』や『仮面ライダーアギト』でやれたようなことが今は出来ない。つまり後者のソースでは、理由も言わずに最近の仮面ライダーはつまらん、それに比べて自分が手がけていた頃のはよかった、という老害丸出し発言をしたということになる。
特撮ファンとしては、そんなの相手にしようもない。
しかし白倉発言で本当に問題にすべきなのは、四十五年の仮面ライダーシリーズの歴史において、いまだ『アマゾン』以上の異色作を生み出すことができていない、と言ったことの方である。
2000年に『仮面ライダークウガ』が始まった時には「こんなものは仮面ライダーではない」とずいぶん言われた。そしてそれ以降も、野心的な挑戦作と世間で騒がれた作品がけっこう作られたような気がする。しかし白倉氏に言わせれば、そんな挑戦など昭和ライダーである『アマゾン』にも及ばないらしい。平成仮面ライダーは、仮面ライダーというヒーロー像の枠を一ミリも広げられなかったと言ったも同然である。
このところ白倉氏は、平成ライダーの価値を下方修正する発言が続いている。
氏は平成ライダーの発展拡大に寄与してきたと、誰もが認める人であるから、一連の発言は謙遜からきたと解釈できないこともない。ただ『クウガ』ファンだけは、この発言に少しくらいは怒ってもいいのではないか。『クウガ』は白倉氏の作品ではないんだから。
誰が橋本環奈を殺したのか?(後編)
(承前)『セーラー服と機関銃 -卒業-』に関するレビューを集めていたら、「アイドル映画だからストーリーは要らない」という意見のあまりの根強さに暗澹たる気持ちになった。
要らんわけないだろう!
一般映画には一般映画の文法があるように、アイドル映画にはアイドル映画の文法というものがあるのだ。それは一般映画の文法(起承転結とか)とは違っているから、見慣れていない人からは意味不明なことをやっているようにも見える。しかし本当にすぐれたアイドル映画を作るのは、難度の高い作業である。すぐれた一般映画を作るのと同様に。
美少女がいる。その資質を見極め、どのようなコンテキストに置けばその美少女を最も美しく光り輝かせることになるのかを考え、そしてそれを元にストーリーは作られねばならない。『セーラー服と機関銃』の旧作もまさにそのような映画である。しかし現状は美少女が顔アップでカメラにニッコリ微笑んでさえいればファンは満足するだろうとしか考えていない連中によって現場は占められているし、そして実際ファンもそれに満足している。
橋本環奈氏は、当初はあどけなくかわいい女組長を無難に演じることを期待されていたに違いない。ところがいざ撮ってみれば牝虎だった。ファンとしても期待の外のことであっただろう。まあそれはそれで「環奈ちゃんはこんな演技もできるんだ」という楽しみ方をすればよい。しかしその牝虎は、悪党どもの喉笛を次々と食い散らかしていくわけではないらしい。千年に一人の逸材だというのが本当だったとしても、その「怪演」を見るためだけに、退屈なストーリーは我慢しろというのであれば、ファン以外の人間にとっては観に行きたくなる気持ちなど起きるはずもないのだ。
アイドル映画をなめるんじゃない。
ヤクザの組長がハマっている十七歳の美少女。例のレビューが本当だとすれば、なんと希少な資質ではないか! そんな類まれな才能を持った少女を、そんなもったいない使い方をしているのか。面白いドラマチックな話がいくらでも作れるだろうに。
え、そんな資質、普通のドラマじゃ使いようがないって?
だったら特撮によこせ。いや、来てください。お願いします。
誰が橋本環奈を殺したのか?(前編)
角川映画40周年記念映画『セーラー服と機関銃 -卒業-』が大爆死らしい。
今年は東映特撮にとってもメモリアルイヤー、仮面ライダー45周年とスーパー戦隊40作目の年ということで色々控えているというのに何と不吉な。プロデューサーの名前を見たら井上伸一郎、って『キカイダーREBOOT』の人か! こっちの伸一郎は大丈夫だろうな。
別に興味もない映画のことではあるが、「「セーラー服と機関銃 -卒業-」をすごく観たくなるレビュー」というのがたまたま目に入ったら、観たくなるどころか怒りがフツフツと湧いてきた。だいたい関係者でもなければプロの映画評論家でもない、一介のファンの書いたレビューが話題になるということ自体、常軌を逸している。
そもそも『セーラー服と機関銃』は、フツーの女子高生がある日いきなりヤクザの組長になってしまうという、そのミスマッチの妙が売りの作品である。ところがこのレビューによると、主演の橋本環奈氏がヤクザにハマリ役だったらしい。それは一周回ってミスキャストじゃないか。
そういえば公開前も、橋本氏の十七歳とは思えぬ肝っ玉の座った態度と高いプロ意識が記事になっていた。小学校三年生から芸能界の水に浸かってきたというのであれば、そういうこともあるかもしれない。しかし、十七歳にしてもう初々しさがないというのは、アイドルとしては致命的な欠点だぞ。彼女が『セーラー服と機関銃』には合っていないのは、もう最初から関係者には分かっていたんじゃないのか。
ダイヤモンドの原石を、どのような磨き方をすれば最も光り輝くだろうかと検討に検討を重ねた結果として『セーラー服と機関銃』が選ばれた、というのではあるまい。薬師丸ひろ子も演じた往年の名作であれば、スポンサーも見つけやすいし、マスコミも好意的な記事を書いてくれるに違いないという計算先にありきだったことは容易に想像がつく。過去作に依存した安直な商売をやっているのは我が東映特撮の専売特許ではないようだ。まあ、橋本氏が本当にダイヤの原石かどうかは分からないし、ただの石ころだったのかもしれないが、ちょっと磨いてみて光らなかったらすぐに捨て、また新しい原石を拾いに行く、そういうことを日本の芸能界はずーっとやってきたわけだし、今さら腹を立てるようなことでもない。
腹が立つのは、「アイドル映画」を一般映画に比べて程度の低いものだとみなす考えのほうである。(続く)
高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(後編)
(承前)『カーレン』『メガレン』『ギンガ』の三作は、戦隊シリーズとしては理想的な成功を収めた作品であったといえる。ところがそのチーフプロデューサーを務めた高寺成紀氏は、『語ろう』本に載ったインタビューなどから判断する限り、不本意な失敗作と思い込んでいるようだ。
スーパー戦隊シリーズがかくも長きにわたって成功を続けてきたその秘訣は、保守と革新のバランスにある。伝統的なノウハウをおおかた受け継ぎつつ、時代の変化に応じて少しずつ古いものを捨てたり新しいものを付け加えたりしていく。「この作品から戦隊の歴史は変わった」というような急激な変化は必要ない。必要なのは、時流とともに徐々に変わり続けることであり、それはまた難度の高いことでもある。そして上記の三作品は、確かにそれをクリアしている。
ところが高寺氏は、自分の手がけた作品は100%革新的なものでなければならない、と思い込んでいるように思われる。
もちろんそれは勘違いなのだが、その思い込みが奇跡的にプラスの方向に働いたことがある。『仮面ライダークウガ』(2000年)である。仮面ライダーシリーズ十年ぶりのテレビ放映とあっては、さまざまな想定外の事態が次から次へと降りかかったことであろうし、それを乗り切るためにはバランス感覚よりも、思い込みが生み出す突進力のほうが、役に立ったのかもしれない。
そして平成仮面ライダーも作品数を重ね、安定期に入ることが望まれるようになった時、そのような手法は仮面ライダーシリーズからは不要になったのである(もちろん2005年の『仮面ライダー響鬼』のことである)。
高寺氏がプロデューサーとして有能な手腕を持った人であることは疑いえない。実際戦隊シリーズで実績を上げた。そしてそんな人材を、映画やテレビ番組制作の現場はいつでも喉から手が出るほど欲している。ところが高寺氏の思い込みが、氏に働き場所を与えない。だいたい『クウガ』にしたって東映の血を受け継いでいる部分も決して小さくはないのだが。しかし『クウガ』は非東映的な作品なんだ、100%革新的な作品なんだという思い込みを、氏は近年ますます強めていっているような気がする。
なんか色々もったいないことである。
高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
自分が心の底から好きなものを貶されて怒らないのなら、その人は本当のファンではない。
高寺成紀氏が例によって宇宙刑事をディスるツイートをしているのだが、それに対して憤慨しているファンを見ない。
【ビバ怪】今思えば「宇宙刑事」シリーズのフォーマット主義に、円谷教徒であるが故に不信感を抱いていた自分からすると「ああいうやっつけ的な作品をルーティンで撮ってる大人は、他人に興味のない冷たい人達なんだ」と思い込んで、研修に臨んでいた気がします(2016年2月26日)ちなみにその後考えを改めたという話ではない。
怒らない理由は想像がつく。この高寺氏の指摘は半分は当たっているからだ。そして半分は当たっているという事実を認めたくないから無視する以外にないのである。
だいたい高寺氏にしろ、また宇宙刑事シリーズのファンにしろ、彼らの頭のなかにあるのは、極めて単純幼稚な図式である。
革新=良いもの
保守=悪いもの
人間というのは元来保守的なものである。なにかやってうまく行けば、それに縛られ、新しいことにチャレンジすることに臆病になる。だから必要以上に「革新」へと急き立てる必要がある。しかしだからといって、革新的でさえあれば何でもかんでも良い作品、保守的なら何でもかんでも悪い作品というわけでもなかろう。温故知新。要はバランスである。
『宇宙刑事ギャバン』(1982年)もどちらかと言えば保守的な作品である。斬新であったと言えるのは銀ピカのヒーローというデザインワークだけで、脚本や演出法にそれほど新しいものはない。だからダメな作品だというのが高寺氏であり、それに反駁するために、革新的な作品だとこじつけてでも言い張ろうとするのが宇宙刑事ファンである。そして間違っているのは両方である。
そういう意味で不思議なのが、なぜ高寺氏は戦隊シリーズを悪く言わないのであろう。だいたい東映のプロデューサーの間には、仮面ライダーをスーパー戦隊より格上だとみなす風潮がある。ところが高寺氏にはそういう発言は見当たらない。1996年から1998年、三年連続して戦隊シリーズのチーフプロデューサーを務めたことがトラウマになっているのだろうか。『カーレンジャー』『メガレンジャー』『ギンガマン』、いずれも評判の良い作品である。そしてその評判の良さがほろ苦い体験になっていることは容易に想像がつく。(続く)
『仮面ライダー1号』、井上敏樹、「七光」?

竹中清・井上敏樹『伊上勝評伝』
井上敏樹×白倉伸一郎 緊急対談「変身し続ける男たち――映画〈仮面ライダー1号〉公開記念特別番組」で、井上氏に脚本を依頼した理由を聞かれた白倉氏の発言
なんだかんだいって、伊上さんというメインライター、仮面ライダーの、血筋を継ぐ、じゃないけれど、という方でもあるじゃないですか。それは他の誰にも持っていない、血筋、なんですよね。そこ、運命的なものがあるんじゃないのかなあという気がしますよね。言うまでもないことであるが、井上氏が脚本を依頼されたのは、優れた力量を持ったプロであり、作風も今回の企画に合っているからであって、それが伊上勝氏の息子だったというのは単なる結果である。いくら東映が出鱈目な会社とはいえ、血筋が理由でスタッフの起用が決まることなどありえない。
ただこの発言で気になるのは、初代『仮面ライダー』のメイン脚本家を務めた人間の息子が今回脚本を担当するということが、この映画にとってセールスポイントになるとプロデューサーの白倉氏が本気で考えている、ということである。実際ツイッターなどでの反応を見ると、その判断は当たっているようにも思える。
井上敏樹という人は親孝行な人である。『伊上勝伝評伝』という本への寄稿文からも、業界の偉大な先輩として尊敬し、また父親として深い愛情を持っていることがひしひしと伝わってくる。それが、白倉氏のこんな発言を放置しておいていいのか。超売れっ子脚本家であった伊上氏が、なぜかくも急に没落していったのか、その有り様を至近距離で見つめていた井上氏はその理由が誰よりも分かっているはずだし、そしてそれが自分の作風にも影響を及ぼしていることの自覚がないわけがない。「伊上勝の息子だから」などという期待を抱いて映画館に足を運ぶ人たちの期待に沿うことは自分にはできないし、沿ったりするような本を書いたりしたら大コケになるのが確実なことは分かっているはずだ。なぜそこで白倉氏の発言を咎めもせずニヤニヤしながら聞くだけだったのか。
ひょっとしたら、親孝行な井上氏のこと、どうせ今の東映に大した映画が作れる力量がないのは分かりきっているし、自分が脚本を書くことでわずかでも話題性が上がれば、今となってはほぼ忘れ去られた親父の名前に再びスポットライトが当たると思ったのかもしれない。
「七光」というのは普通子供が親の恩恵を受けることだが、その逆は何と言うのだろう?
水木しげるは本当に「反戦」と言わなかったのか(後編)

水木しげる『決戦レイテ湾 第六部 壮絶 特攻』
(承前)水木しげるの貸本劇画時代の戦記物からは、戦争の格好良さを感じる部分がなくもない。
などと言ったら確実に怒る人が出てくるだろうけど、しかし戦争の悲惨さと格好良さというのは本来なら表と裏の関係のはずだ。桜は散るから美しい。その後水木しげるは自らの従軍体験をもとにした作品を発表するようになり、そこでは悲惨さや愚かしさ一辺倒の描き方になっていく。
いったん戦争が始まれば、平時の常識は戦時の常識に取って代わられる。それは平時の感覚からしてみれば、おぞましく、しかし同時に魅力的なものでもある。そのような異世界の存在を垣間見たいという欲求をかなえてくれるものとして、サブカルチャーにおける戦争を扱った作品は存在していた。それが機能しなくなったのは、いつ頃からなのだろうか?
仮面ライダーやスーパー戦隊に代表されるヒーロー番組もまた同じ流れにあった。
『仮面ライダークウガ』を見て驚いたのは、そこでの人々の生活が、視聴者である我々の生活と何一つ違った所がないということである。人々は毎日会社や学校へ通い、警察はマニュアルに従って出動する。暴動が起きることもないし政府の内部で不穏な動きが出るということもない。わずかにポレポレで、最近は外出を控える人も減ったなあという会話が一度出たきり。
案外これがリアルなのかもしれない。正体不明の生命体が頻繁に出没し、何千何万という単位で人が殺さる事件が続いている、にもかかわらず人々は整然と平時と何も変わらない生活を営んでいる、というのは。
「異世界を覗き見るような興奮」を、かつての仮面ライダーシリーズが十分に描いていたとは思わない。とりあえずものすごく理不尽な運命を背負わされた主人公というのだけ出しておいて、あとは視聴者の想像に任せていた。しかしリアルさを求める風潮の高まりの前には、理不尽なものを理不尽なまま視聴者の前にポンと出すという手法も、単なる手抜きとしか受け取められなくなる。
最近のヒーロー番組は昔に比べて緊張感がなくてつまらない、という主張がある。敵は恐ろしくなく、それをやっつけるヒーローの活躍にも爽快感がない。原因として挙げられるのは、テレビ局の規制なのか自主規制なのかは知らないが、人が死んだり残酷なシーンを滅多に出せなくなったことである。しかし問題はそんなところにはないような気がする。
水木しげるは本当に「反戦」と言わなかったのか(中編)
(承前)『超電子バイオマン』(1984年)のエンディングから
命それより大切なこんな深刻な歌詞を、明るくポップな曲調に乗せて歌っているのを今聞くとシュールな気分に陥る人もいるかもしれない。しかしこれが1980年代の普通の感覚であった。
ものがオレにはあるからさ
命より重いものはない、というのはあくまでも平時の常識である。殺人事件が起きるたびにいちいち人命の価値について議論なんかしていたのでは裁判所は大変だ。何人殺したら量刑はどれだけと事務的に決めておく、それが法律というものであり、通常はそれで社会は運営されている。そしてそんなルールが吹き飛ぶのが戦争である。平時には平時の常識があるように、戦時には戦時の常識がある。そこでは人命もまた一銭五厘で補充可能な消耗品としてしか扱われなくなる。いいとか悪いとかいう問題ではない。戦時の常識を平時の常識を基に批判しても無意味であるし、平時の常識を総動員したところで戦争の抑止力にはならない。
もちろん子ども向け番組であるから、いったん戦争になったら人の命なんか全然重いものではなくなると真正面から描くわけにはいかない。しかし、子どもたちの日常生活を普段支配している、学校の先生や親から教えられるようなことが、一切通用しなくなるような瞬間が訪れることは世の中にはありうるし、そのような世界を垣間見せるような役割を果たしていたからこそ、子どもたちは夢中になって番組を見ていたのではないか。そこでは大きな使命のためには自らの命を喜んでなげうつ戦士の存在は不可欠である。
ヒーロー番組といえばPTAによって昔から目の敵にされていたのも、それが理由の一つではなかったか。そしてイケメンヒーローブームを経て、財布を握っているお母様方の歓心を買うのも玩具販促にとって重要な課題となった今となっては、もはやヒーロー番組の描く世界もまた平時の常識の枠内から出られなくなったような感じがする。
そこで思い出すのは『仮面ライダークウガ』(2000年)についての議論である。リアルさを描いたという声も聞くし、リアルを期待して見たらがっかりしたという声も聞く。恐らく『クウガ』が描いたのは、平時のリアルである。警察は出てくる、しかし自衛隊は出てこない。それほどの大事件ではないからである。そして古参のライダーファンが期待していたのは、戦時のリアルではなかったか。(続く)
水木しげるは本当に「反戦」と言わなかったのか(前編)

水木しげる『カランコロン漂泊記』より
雨宮処凛がゆく!「水木しげるさんの死〜なぜ「戦争反対とは決して言いません」だったのか。の巻」そうかぁ?
「決して言わなかった」ってことはないだろ。
かりに言わなかったとして、それが大した意味を持っていたとも思えない。『カランコロン漂泊記』で小林よしのりの『戦争論』を批判したことがあった(ものすごく遠回しな言い方だったが)。そこで言ってることは反戦平和と何も違いはない。「日本はペコペコ国でいいんだ」とまで言っている。というか、むしろマスメディアでデカい面して「反戦平和主義者」を自称している連中のほうがこういうことを言わない。言明を避ける。しかし「私は最も正しい戦争よりも、最も不正な平和を選ぶ」と堂々と言えずして何が平和主義者か。そしてそんな口先だけの自称平和主義者たちと一緒にされたりしては水木しげるの商品価値が落ちてしまうと考えて、マネージャーさんはそういうことを言ったに違いない。賢明な判断である。
水木しげるの思想は「反戦」という括りに入れられるほど単純なものではない。しかし同時に「反戦ではない」という括りに入れられるほど単純なものでもない。そんなことくらい作品を読んでりゃ自明だろう。戦争体験の悲惨さを語り継いでいくことと、戦争に反対するのとは全く別の概念だ。もちろん、戦争の実態がいかに悲惨なものなのかを知らないまま、やたら勇ましいことを呼号する愛国者気取りというのはいつの時代にもいるが、ああいうのは論外だから処置なし。戦争が悲惨なのは自明のこと、議論の前提である。悲惨ではあるが、民族の独立と誇りを守るためにはやむを得ないと思う者によって世界中で戦争は絶えることなく行なわれているのである。「悲惨だから戦争はやめよ」なんて言ったところで何の説得にもならない。
いついかなる場合においても戦争に反対するのか、それとも正義の戦争と不正の戦争の区別はあって後者にだけ反対するのか。日本の戦後の平和運動はずっとその点を曖昧にしてきた。そのツケを今まさに払わされている。学者や評論家や政治家の偉い人達が幼稚な議論にうつつを抜かしている間に、戦争について最も真摯な姿勢で取り組んできたのがサブカルチャーの分野であるというのはつとに指摘されていることであり、水木マンガも当然ここに入る。スーパー戦隊シリーズを含めたヒーロー番組もまたその一翼を担う。もちろん正義の戦争はあるという立場で。そこで長年かけて培われてきた議論が現在全く生かされていない。歯がゆいばかり。(続く)
シャーロック・ホームズと仮面ライダーの差

アンソニー・ホロヴィッツ『シャーロック・ホームズ 絹の家』(原書2011年)
昔のキャラクターを利用して新作を出すという商売は全世界のどこでも行なわれているが、その中で最も活動が盛んなのは間違いなくシャーロック・ホームズ物であろう。コナン・ドイル没後も世界中でホームズの冒険譚は絶え間なく作られ続けており、この『絹の家』もまたその一つである。ただ、ミステリーとしてよく出来ているとか、ホームズやワトソンのキャラクターの再現度も高いとか評価されている一方で、話が暗くて爽快感が少ないという批判にもまたさらされている。おそらく書いた人の志が高すぎたのであろう。
『絹の家』のホームズは単に犯罪捜査を行なうのみならず、より巨大な社会悪に戦いを挑む。ということは、ドイル自身によって書かれた、いわゆる「正典」においては、ホームズはその社会悪に対して見て見ぬふりをしていた、いやそれどころか加担者ですらあったという事実が読者の前に浮き彫りになる。
これは明らかにホームズに対する批判である。
コナン・ドイル財団も、よくぞこんな小説に公認を与えたものだと思う。
その試みは必ずしもうまくいっているとは思わない。二十一世紀的な価値観で十九世紀の人間の行動を裁くという無理もなくはない。ただ、ホームズを完全無欠のスーパーヒーローのように思い描いていたファンにとっては幻滅であるのは事実である。作者は、無難なパスティーシュを書くことを自分に許さなかったのだ。シャーロック・ホームズの名はこれからの時代も永久に輝き続けるものでなくてはならない。そのためには現代の価値観でホームズはどのように見られるかに無頓着であることは許されず、たとえ「正典」を傷つける結果になろうとも、それを避けて通ることはできなかったのだ。
さて本題である。世界的な名キャラクターであるホームズと比べるのもどうかとは思うが、少なくとも平成ライダーが始まった当初は、そこには同じような志の高さもまた存在していたように思われる。そして、新しい時代の価値観に即した仮面ライダーを新たに作るということは、旧作もまた無傷のままでいられる保証はない。平成ライダーに対して「こんなのは仮面ライダーではない」と抗議の声を上げた人たちは、おそらくそのことに気づいていたのだろう。
時代は移り、かつては新作が作られるたびに聞かれた「こんなのは仮面ライダーではない」という批判の声は、近年はもうさっぱり耳にしなくなった。理由については書くまでもない。
原点が頂点ならば、その後はずっと下り坂
白倉伸一郎センセイの悪口を言うのはもう一生やめよう。
今春公開予定の映画『仮面ライダー1号』のキャッチコピーが「原点にして頂点」だと知った時、そう思った。
原点が頂点ということは、つまり後はずっと落ちっぱなしということである。ガンダムやゴジラに対してそう言ったところで、文句を言う人はいない。第一作だけが伝説的名作であり、そのブランドバリューだけでシリーズが延々続いているというのは誰もが認める事実だから。別に恥ではない、シリーズとは元々そういうものだ。
仮面ライダーシリーズはそれらとは違う――はずだった。
たとえば脚本家の會川昇氏は『語ろう!』シリーズの本でこんなこと言っていた。
僕はね、平成ライダーは昭和ライダーより優れている点がいっぱいあると思うんですよ。というよりも、僕は平均的には平成ライダーの方が優れていると思ってます。多数派というわけではなかったが、極端に変わった意見でもなかった。仮面ライダーシリーズは一度は終わったコンテンツだった。それがよみがえったのである。新しい時代にふさわしい価値観をまとって。平成仮面ライダーは「平成仮面ライダー」というブランドなのであり、昭和仮面ライダーの養分に寄生しているのではない――そのような主張が一時期は大真面目に存在していたのである。
その栄光を全部捨てる気らしい。
白倉センセイだって取締役にまで出世したんだし、「平成仮面ライダーをここまで大きく育て上げた男」という勲章も得たのだから、後は会議室でふんぞり返っていればいいのである。そして「今の若い人たちにはもっと頑張ってもらわなくては」などと偉そうなことを言っていれば万事収まる。しかしこの人は自分の勲章を自分の手でむしりとってしまった。もちろんそこには、「平成ライダー初期」なんか持ち上げたところで今後の商売にとっては有利にはならず、昭和ライダーを持ち上げたほうがいいという冷静な計算に基いているのであろうが、商人根性もここまで徹底していればもう敬服するしかない。
「平成ライダー初期」を持ち上げていた人たちには気の毒ではあるけれど。
平成仮面ライダーは「恩返し」をしたのか
「一体これのどこが『仮面ライダー』なんだ?」
東映YouTubeで『クウガ』が終わったので引き続いて『アギト』を見ている。確かに面白いことは面白いが、番組の名前に「仮面ライダー」と付いている理由が分からない。
……などということを、十五年前の視聴者は熱っぽく議論していたのだろうか。今となってはもはや話し相手になってくれる人などいない。「そんなもん、商売の都合に決まっているだろ」。これで議論はオシマイになる。
平成仮面ライダーが始まった2000年頃は、「こんなもの俺は『仮面ライダー』とは認めない」などと言う人もいたらしい。老害だの懐古厨だのと言われていたようだが、しかし十五年経った今となっては、結果的に彼らの言い分の方が正しかったと言わざるをえない。なぜなら結局のところ「恩返し」がなされなかったからである。
昭和仮面ライダーの築き上げたブランドバリューの恩恵を平成仮面ライダーが受けていることについては異論の余地はあるまい。しかし時代の流れに合わなくなった部分も出る。それを切り捨て、新しいものを付け加え、今の時代にふさわしい仮面ライダー像を更新する。そしてそれを次の世代へと手渡す。それを「恩返し」というのである。もちろん平成仮面ライダーのスタッフも、当時はそういう気概も持っていたとは思う。だが結果的に彼らは次の世代に何を残したというのか。昭和の仮面ライダーを見て育った世代は、『クウガ』が始まった時、番組名に「仮面ライダー」という文字が入っているというだけの理由で見始めた人がたくさんいただろう。しかし「仮面ライダー」という文字は、単に商売の都合だけでつけているということが天下周知の事実となってしまった今となっては、『クウガ』や『アギト』を見て育ったからといって、番組名に「仮面ライダー」という文字が入っているというだけの理由で『鎧武』や『ゴースト』を見始める人が一体どれだけいるだろうか。
いやそういうことを言うのであれば、『V3』以降の昭和ライダーも全部そうじゃないかと言われるかもしれない。確かに仮面ライダーブランドを築いたのは初代『仮面ライダー』だけで、あとはずっと遺産の食いつぶしをし続けていただけとも言える。そして今春『仮面ライダー1号』の映画公開。同族争いだの親殺しだの事故否定だの、ゴチャゴチャと理屈をこねまわしていた白倉伸一郎プロデューサーも、ついに自分たちは何も新しいものを生み出すことがなかったことを、正直に認める気になったのだろうか。
平成宇宙刑事とは何だったのか(後編)

(承前)宇宙刑事シリーズというと、東映特撮ヒーローのピンチを救った作品だと思っている人は多い。実際書籍にもそんなことが書いてある。たとえば吉川進プロデューサーは『宇宙刑事大全』(2000年)で
『ギャバン』が始まる直前の81年というのは、東映ヒーロー存続の大ピンチだんたんですよ。私が東映テレビ部のキャラクター作品を担当する企画営業第二部部長に就任したのは78年なのですが、その後、東映ヒーロー危急存亡の危機が2回ありました。「だんたんですよ」というのは原文ママ。ところが同じ吉川プロデューサーが、以前は全く異なる発言をしていたことを知っている人は少ない。『宇宙刑事ギャバン(ファンタスティック・コレクションNo.41)』(1984年)では
1回目は78年の末。〔中略〕そして2度目が81年というわけです。
このようにいつも、悲愴な感じで、背水の陣の中で東映キャラクター路線の命脈を保ってきたのですが、それらの場合〔75年と78年の危機のこと〕と大きく違って製作本数が一本増えるという、積極的にして、前向きの考え方のなかに、〔「ギャバン」の〕企画が成立したのです。78年が危機というのは事実。75年が危機というのも意味不明。
「ゴレンジャー」や「スパイダーマン」が、あとのない厳しい環境で製作した作品であるとするならば、「宇宙刑事ギャバン」は、日本晴れの青空の環境で製作された作品であると言えます。
実のところ『ギャバン』はそれほど大した作品ではない。少なくとも東映としての認識はそうである。ただ東映特撮としては戦隊と仮面ライダーの二つだけに頼りっきりというのも心もとないし、宇宙刑事シリーズをプッシュしようという動きが間歇的に出てくる。しかしハッキリ言って『ギャバン』にはそれほど画期的なインパクトがあったわけではないから、その結果宇宙刑事が東映特撮ヒーローの危機を救ったという歴史が捏造されたのである。
宇宙刑事ファンは、宇宙刑事シリーズが不当に低く扱われているかのように思っている人もいるようだが、そんなことはない。現状の扱いは妥当である。そして東映が商売の都合によって持ち上げたり下げたりし、その度にファンは付き合わされ一喜一憂させられる。そういうのをずっと繰り返してきた。
こんな歴史はいいかげんに断ち切られるべきではないか。
平成宇宙刑事とは何だったのか(前編)
渡洋史氏は『宇宙刑事シャリバン』(1983年)でシャリバン・伊賀電を演った人であるが、『宇宙刑事シャリバン Next Generation』(2014年)にも出演し、その際に、ブログにこんなことを書いていた(2014年6月5日)。
そして今回ヒットになれば次回はまた劇場版やテレビシリーズに繋がるかもしれませんので、是非ともDVDをレンタルではなくお宝物として皆さんの手元に置いておいて頂けたら幸いです。で、その後何の新しい動きもないところを見ると、結局売れなかったのか。だったら報告ぐらいすればいいのに。目標とする売り上げはどれだけで、実際売れたのはどれだけか。それがファンに対する礼儀ではないかと思うが、まあどうせ売れるなんて最初から本気で考えていなかったんだろうけど。
こういうのを見ると、宇宙刑事ファンには本当に同情する。
冷静に考えれば、そんなに無茶苦茶売れるような内容でないことは最初から明らかだった。ただ、万一の可能性を前にすれば冷静さを失うからこそ「ファン」というのだし、彼らはここ十何年もの間ずっと、その手の生殺しの目にあわされ続けてきた。
だいたい第一作である『宇宙刑事ギャバン』(1982年)からして、ヒットはヒットでも大ヒットではない。これをシリーズ化するにしても三年がせいぜいと思った当時の東映スタッフの判断は妥当なものだった。現状、東映特撮ヒーロー物としては仮面ライダーとスーパー戦隊の二大シリーズが盤石の地位を占め、それよりはるかに格下にキカイダーや変身忍者嵐があり、宇宙刑事を含むメタルヒーローがいるのもまたそこだ。ただ東映としてはライダーと戦隊だけというのは不安ではあるし、だから時々思い出したように宇宙刑事、あるいはメタルヒーローをプッシュする。そして口先では1980年代のヒーロー物の金字塔だとかなんとか麗々しく言葉を飾って持ち上げはするものの、内心では単なる補欠としか思っていないし、ちょっとやってうまくいかなければじゃあ次はキカイダーのリブートでもやるかという具合。
糠喜びをさせられてはガッカリさせられるの繰り返し。ファンは本当に気の毒である。
だから『スーパーヒーロー大戦Z』でも、宇宙刑事ファンが怒るのは当然ではあるが、だからといってそれ以外の人々に共感が広がるわけでもない。冷酷かつ無能な上司の役というのが、今の宇宙刑事ブランドの価値からしてみれば、相応の扱いというわけだ。(続く)
平成仮面ライダー、昭和に膝を屈する
仮面ライダーシリーズ45周年記念の第一弾として今春公開される『仮面ライダー1号』については、例によって白倉伸一郎プロデューサーが、ファンの予想の斜め上を行く出来事を用意していますよと、ツイッターなどを通じて必死に煽ろうとしているが、さすがにファンの方でも学習能力があるわけで、今さら何をやろうが驚くようなことなど残っているものかと、冷笑的な雰囲気が漂っている――と思っていたら、その『仮面ライダー1号』のバレ情報を見て驚いた。
平成ライダーの意義全否定か。
なんと仮面ライダー1号というのは全仮面ライダーのリーダー的存在で、45年もの間ずっと悪の秘密組織と戦い続けてきたという設定らしい。その全仮面ライダーというのは当然平成ライダーも含まれていることであろう。
世界征服を目指す悪の秘密組織などというものがリアリティを持っていた時代は終わった、これからは新しい時代にふさわしい新しい仮面ライダー像を、自分たち新しい世代が作っていくのだ、という意気込みのことに作られたのが平成仮面ライダーではなかったのか。そしてそれは人気を得て順調に作品を送り続けてきた。白倉氏は平成仮面ライダーは昭和よりもすぐれている、石ノ森章太郎が仮面ライダーに込めた思いを忠実に継承しているのはむしろ平成の方である、などという発言すら行なってきた(「仮面ライダーの敵」『朝日新聞』2013.4.12)。
全部撤回するということでよろしいか。
さすがにこれは予想の斜め上だ。
一番立場を失うのは、『仮面ライダークウガ』のファンだな。
『クウガ』が好きな人もそうでない人も、『クウガ』に対してはリスペクトを払わなければならないと思ってきた。仮面ライダーシリーズの新しい潮流を作ろうとしたパイオニアだからだ。しかしそんな試みなどなかったのだ、ということにするのであれば、もはや『クウガ』はシリーズのたくさんの作品の中の一つでしかなくなる。
まあ『クウガ』は正直いって今見てあまり面白い作品ではないから、それはそれでいいか。それを言うのなら初代『仮面ライダー』だって今見てあまり面白いものではない、と言われるかもしれない。さすがに45年も前の作品であれば、テンポが今とは違いすぎる。にもかかわらず、初代のほうは永久に偉大な作品として語り継がれることだろう、仮面ライダーシリーズが続く限り。『クウガ』とは違って。
ヒーロー番組に残虐描写は必要か(後編)
(承前)『仮面ライダークウガ』を通して見て、私の場合は未確認生命体に恐怖感や緊迫感を感じたのは前述の二話しかなかったのだが、その理由について色々考えていたら、あのテロップがよくなかったのではないか。「荒川区 11:28 p.m.」とか画面にしょっちゅう出てくる、あのやつ。
あのテロップが画面に出てくるたひに、ああこれは東京の話なのだ、東京以外の人間にとっては関係のない話なのだ、と無意識に刷り込まれていたような気がする。
現実の話、シリアやイラクでは毎日何百人という単位で人が殺されている。しかしそんなことは日本ではニュースにもならない。ところがそこに日本人が一人でも含まれていれば、上を下への大騒ぎだ。自分にとって何の接点もない人間が百人殺されることよりも、接点のある人間一人が殺されることのほうが激しい興奮を呼び起こす。いいとか悪いとかいう問題ではない、人間とはそういうものである。
現実に起こっている殺害事件ですら赤の他人の興味を引くのは簡単なことではないのに、ましてやテレビドラマで殺されるのは架空の人物である。実在感を視聴者に対して感じさせるのは、口で言うのは簡単だが、要求される技術の難度は非常に高い。
『クウガ』は一体何を考えてあんなテロップをいれたのだろう。
日本国民は誰でも東京に興味を持つのが当たり前とか考えていたのだろうか。
私とて決してテレビの表現規制の問題を軽く考えているわけではない。ただ問題にするからにはフェアな態度で取り組まねば説得力はない。たとえば鈴木美潮氏という人も、最近のヒーロー番組については不満を感じているらしくて、著書でもそのことに一章を割いている。しかし最近のヒーロー物がつまらないとしたら、それは外部的要因と内部的要因があるはずだし、外部的要因、つまりテレビの表現規制やスポンサーによる過剰な販促要求については饒舌に語っておきながら、内部的要因、つまりスタッフやキャストの技量や情熱が昔に比べて落ちている可能性については触れもしないというのでは、説得力も何もない。
「昔は良かった」などというと、たちどころに「懐古厨」などとレッテル貼りをして意見を封殺しようなどという風潮もある中で、「現場の末端のスタッフは一生懸命頑張っているんだ、悪いのはテレビ局やスポンサーのお偉方の連中だ」という言い方は確かに受け入れられやすい。しかしそれはそれで狡いやり方ではないのか。
ヒーロー番組に残虐描写は必要か(前編)
「最近の仮面ライダーは昔に比べて面白くない」と唱える人の根拠の一つとなっているのが、残虐描写に対する表現規制の問題である(鈴木美潮氏など)。
人が殺される場面など滅多に出てこない。そのためにストーリーに迫力が生まれない。これはテレビ局の放送コードだけの問題ではなく、あまり怖くしすぎて子どもたちに避けられて視聴率が下がっては困るという自主規制も含む。
にわかには賛成できない意見である。
今のヒーロー番組が以前に比べて緊迫感を欠いているという点には同意するが、それは別に規制の問題ではなくて、他の理由、たとえば脚本家や監督の技量が落ちているために視聴者をハラハラさせるドラマを作ることができないのを、他に責任をなすりつけているだけのようにも思える。昭和時代のヒーロー物だって、それほど簡単に人が死んでいたわけではない。富士山を噴火させ日本列島を真っ二つにするなどという壮大な作戦を立てては正義のヒーローに阻止されるばかりで結果として人一人殺せない悪の組織であったとしても、それでサスペンスがなかったなどとは言わせない。
この問題でよく引き合いに出されるのが『仮面ライダークウガ』(2000年)である。しかし、私は先日全話視聴したばかりなのだが、人がいっぱい死ぬからといって、それが作品の緊張感に結びついていたとは到底思えなかった。緊張感を最も味わったのは、第24話で桜子が襲われた時と、第27話でプールに行ってきたおやっさんたち一行が未確認とニアミスをした時である。どこの誰とも分からぬ人が百人殺されるよりも、レギュラーキャラが殺害現場の近くにいたという、ただそれだけのことのほうに見ていてヒヤリとさせられた。
人が一人殺されたとする。その人にも生活があり、家族や友人、将来の夢といったものがあった。それを視聴者に対して実在感があるように描くのでなければ、死の重みも生まれてこないし、百の死体を出したところでストーリーに緊張感が増すわけでもない。むごたらしく殺された死体を出せば視聴者の気を引けると考えているとすれば、安直にもほどがある。
ところで、ここまで書いたところで念のためにと調べてみたら、第24話も第27話もどっちも脚本が井上敏樹氏の回だった。別に私は熱烈なファンというわけでもないんだけど、それともメインライターが下手すぎなのか。(続く)
『仮面ライダークウガ』は過去の作品である(その4=完結)
(承前)『クウガ』の鈴木武幸プロデューサー(途中参加)は、後年インタビューでこのようなことを言っている。「こんなものは仮面ライダーではないと言われた時、『クウガ』の成功を確信した」と(ソースは失念)。
当時の仮面ライダーシリーズは確かに先細りの袋小路にはまっていたし、シリーズを再び活性化させるためには、今までの流れを断ち切った、大胆な発想に基づいた新しい仮面ライダー像を作る必要があった。
『クウガ』がその期待に応え、新しい時代の仮面ライダーのスタンダードを示すことのできた作品であったか、それとも単に目新しさが受けただけの作品だったのかは、歴史の審判に委ねられることになろう。
新しいことに挑戦する。それが新鮮さゆえにヒット作になる。ここまではいい。その結果、柳の下のドジョウを狙った作品が次々と作られ、あっという間に鮮度が落ちる。それは仕方ない。その新鮮さを差し引かれて、なおどれだけの魅力がその作品に残るか。それが名作かそうでないかの分水嶺となる。十五年は判断を下すのに十分な時間であろう。
東映としては『クウガ』をどういうふうに扱いたがっているのだろうか。最近の動きを見ると、昭和と平成の断続性を強調したいようにも見えるし、連続性を強調したいようにも見えて、よく分からない。前者であれば、『クウガ』を平成ライダーの原点としてプッシュしていくだろうし、後者であれば、単なるワンオブゼムにすぎなくなる。『クウガ』に限った話ではないが、商売上の都合で、とっくに寿命のつきた作品を「いつまでたっても色褪せない不朽の名作」などと作り手の側が持ち上げることなどよくある話だし、当然その逆もある。
もっともそのような小細工、見抜くのもそんなに難しいことではないのだが。
どんな作品でも、作られた時代の刻印を穿たれている。そして時間の経過に従って、評価も当然変わっていく。そして「今まであまり指摘されてこなかったが、この作品の魅力はこの点にある」という批評の言葉が時代の変化に従って常に新しく生み出されるようであれば、それこそ真の名作と呼ばれるに値する作品である。同じようなことばかり言われ続けるような作品は、もう寿命が尽きていると判断して差し支えない。
『仮面ライダークウガ』は過去の作品である(その3)
(承前)映画『七人の侍』は、侍たちが村を去る場面で幕を閉じる。そこには、彼らに手を振って見送ったりする村人は一人もいない。
田植えで忙しいからである。
人々を守るために命がけで戦うヒーローに対して、人々が抱く感謝の念をあまりくどくどと描かない、というのはヒーロー物の伝統である。薄情に見えることさえある。しかしそれにはちゃんとした理由があるのだ。
一般の人々にとっては、超越的な力の持ち主という点では、ヒーローも敵も同じなのである。自分たちとは異なる世界の住人なのだ。今はたまたま味方である者が、明日には敵に変わらないという保証はない。ヒーローに対して一般人は敬意や感謝の念と同時に、恐怖心もまた抱いている。ヒーロー番組にとってこのジレンマは昔からずっと議論され続けてきたものであって、たとえば『伊上勝評伝』という本にも井上敏樹氏が似たような内容の文章を寄せている。
理不尽と言えば理不尽である。ヒーローにしてみれば、自分のことを心から信頼し尊敬してくれるわけでもない人々を守るために、命をかけて戦わねばならないのだから。敵を全滅させ人々が笑顔を取り戻した瞬間、自分は不要の存在へと転落する。そして、そんな日が一日でも早く来ることを願って、ヒーローたちは戦い続ける。
だから、一般人から何の疑念も持たれることなく、心からの信頼を寄せられながら戦うヒーローも見てみたい、という欲求が出てくるのも当然のことであろう。それのみならず、武器を開発したり古代言語を解読したり健康診断をしてくれたり、ヒーローが大勢の人々の協力を得ながら戦うのであれば言うことなしだ。しかし、それを「リアル」と呼んでいいのであろうか。「第4号」がどんどん力をつけていくことに、他の人達は脅威を感じることはなかったのだろうか?
正義のためにふるう暴力も、暴力の一種である。このテーマについて、昭和の仮面ライダーやスーパー戦隊が真剣に格闘してきたとは言いがたい。スポンサーやテレビ局がいい顔をしないからである。かといって、おろそかに扱ってきたわけでもない。深入りしない、というのも一つのやり方である。誠実な態度とも言える。深入りしたあげく安直な結末をつけるのに比べれば。(続く)
「スーパーヒーローイヤー」? なにそれ?
白倉伸一郎センセイがまたなんかやらかしたらしい。(togetterまとめ)。
『スター・ウォーズ』をdisったのが発端らしいのだが、氏の一連の発言の中で、私が気になったのはこのツイート。仮面ライダーシリーズの話らしいのだが
「原点回帰」「完全新生」等々、なぜ先達はいちいち過去との断絶を宣言する? …とか悩んでいた頃、初代からやってる某Pに呼びだされ、「お前、そんなのは『流派の違い』だ!」と一喝された想い出がありまして。この発言がほとんど問題になっていないのを見ると、白倉氏を叩いている人も、褒めそやしている人も、仮面ライダーシリーズの歴史についてよく分かっていないんじゃないかなあ、という気がする(もちろん白倉氏本人も)。
仮面ライダーシリーズで「完全新生」なんて、ほとんど言ってなかったでしょ(『響鬼』くらい?)。それに比べて「原点回帰」、これはもう昭和の頃からしょっちゅう言ってた。
昭和ライダーは、前作に比べて視聴率で上回る作品を、ただの一つも生まなかった。縮小再生産の袋小路にはまっていたのは明らかだった。石ノ森先生が死んで、過去と断絶することによってシリーズは息を吹き返したのであるし、それは平成ライダーの自慢していいところだ。もっともその後は断絶しすぎが逆に問題になっていくんだが。
「某P」というのが誰を指すのか知らないが(見当はつくけど)、認識が間違っているとしか思えない。
ちなみに戦隊シリーズの方はというと、「原点回帰」だの「完全新生」だの、そんな宣言聞いたことないでしょ。もともとこの二つのシリーズは歴史も違うしファンの意識の土壌も違う。「ニチアサ」などと同じ括りに入れられたのは、ごく最近の話だ。
今年は「仮面ライダー45周年、スーパー戦隊40作目」のスーパーヒーローイヤーだそうだ。頼むからスーパー戦隊を巻き込まないでほしい。もともと戦隊シリーズにはアニバーサリーを大々的に祝う習慣はない。仮面ライダーとは違う。やりたいのなら仮面ライダーだけでやってくれ。
もっとも、仮面ライダー45周年だけでは盛り上げる自信がないので、スーパー戦隊には名前だけでも貸してほしい、というのであれば協力してあげてもいい。去年の春映画がそうであったように。
『仮面ライダークウガ』は過去の作品である(その2)
(承前)昭和の仮面ライダーシリーズでは、警察や自衛隊は出てこない。なぜなら、出てきても役に立たないからである。
ショッカーにしろデストロンにしろ、その技術力は人間の科学をはるかに上回っている。その陰謀を阻止できるのは、やはり人間の科学を超越した力を持った仮面ライダーのみ。ということは、もし仮に警察が仮面ライダーの戦いに協力し、そしてそれが結構役に立ったりすることがあれば、その敵はショッカー等に比べてずっとグレードダウンしたものであるに違いない。
実際『クウガ』の作中人物に、未確認生命体の出現によって人類の生存が脅かされている、などという認識を持っている人は皆無である。たとえば栃木県の住民には、「東京の方では物騒なことが起こっている」という程度の認識しかない。
昭和時代の悪の組織は、口先では人類絶滅だの世界征服だの大きなことを言っている割には、東京で町内一つ占拠できない。やろうとするたびに、たちどころにライダーに阻止されてしまう。それを変といえば変ではある。その点『クウガ』の未確認たちは、もう最初から東京でチョコチョコと事件を起こすことを目的にしている。それをリアルというのであれば、確かにリアルではある。しかしそれは随分と後ろ向きな話ではないのか?
『クウガ』の放映開始は2000年。忘れた人も多いだろうが、20世紀の人間にとって「21世紀」という言葉は、輝かしい理想の未来か、それとも破滅的な災厄か、どっちかというイメージだった。新世紀を迎えるまでに、何か劇的な変化が世の中に起こるに違いない、という漠然とした雰囲気が社会を覆っていた。結局何も起こらず、その反動として今度は、もはやこれからは劇的な社会変化なんて絶対に起こらないのではないか、かわりばえのない日常が永久に続くのではないか、という雰囲気が蔓延する。今まで人類の自由と平和を守るために戦ってきた仮面ライダーを、「人々の笑顔を守る」などというスケールの小さな戦いへと送り込んだスタッフは、自分たちが時代の最先端を行っているつもりだったに違いない。その後、貧困・格差問題の台頭、新冷戦の危機、原発事故。ドラスチックな社会変化は少し遅れてやってきた。「終わりなき日常」なんてもはや誰も言わない。
『クウガ』は時代をつかんだつもりで、ババをつかまされたような気がする。(続く)
『仮面ライダークウガ』は過去の作品である(その1)
去年の10月19日に書いたように、東映YouTubeで『仮面ライダークウガ』を見ていた。それが全話完了したのだけれども、なんか頭に浮かんでくるのは戸惑いの感情だけだ。
わけがわからない。
「みんなの笑顔を守る」? そんな理由で戦う正義のヒーローなんてあるのか?
ナチスだって、ドイツに巣食う劣等民族どもを皆殺しにすれば、みんなが笑顔になれると信じて戦ったのだ。少なくとも主観的にはそうである。
極論を言うなと言われそうだが、しかし、正義とは何か、ヒーローはなぜ戦うのか、というテーマは昭和の御代から連綿と続いてきた議論である。そして「みんなを守りたいから」というだけでは理由としては不十分であるというのは、とっくの昔に決着のついた議論ではなかったのか。ではその不足分を何で補うのか。簡単に答えの出せる問題ではない。だからこそ、ずっとヒーロー番組は暗中模索試行錯誤を続けてきたのだ。それを、いきなり時計の針を逆に回し、そしてそれが「革新的」な作品として評価されているって。
なにがなんやら。
「みんなの笑顔を守りたい」? 結構な話ではある。ではその「みんな」には誰が含まれ誰が含まれないのか、そしてそれを決めるのは誰か。その議論をすっとばしたら、単に「自分にとって大切な人みんな」の笑顔を守るため、それ以外の人たちをブチ殺しますというだけの話に過ぎなくなる。そこで話はナチスに戻る。
ショッカーにしろデストロンにしろ、何か目的を持ち、それに従って行動しているということは、第一話の段階で視聴者の前に明らかにされていた。そしてそんな目的は許せないと思って仮面ライダーは戦っていた。その点、『クウガ』における「未確認生命体」たちは、一体どんな目的や信念を持っているかも、最後までよく分からなかった。五代雄介もまたそのことに大して関心を持っているようでもない。ただあいつらは、我々人類とは異なる存在であり、我々人類の生命と安全を脅かす敵なんだ、という決めつけがあるのみ。ひょっとしたら彼らは地球の先住民族であり、我々人類のほうが加害者なのかもしれない、などという発想は逆さに振っても出てこない。別にそんな話が見たいわけではないが、「私が『クウガ』を作る以前の東映は子供だましだった」なんていう大言壮語は、それくらいの作品を作ってから言え。(続く)
なぜ大葉健二を叩かないのか
2013年の『スーパーヒーロー大戦Z』におけるギャバン・一条寺烈の扱いについて、『宇宙刑事ギャバン』のファンが怒ったのは当然である。もっとも、その怒りに対して共感を寄せる気など、まったく起こらなかったが。
私が不可解だったのは、この映画が公開された当時、インターネットの掲示板などで一番叩かれていたのが白倉伸一郎プロデューサーだったということである。白倉なんか叩いたってしょうがないだろ! ファンの思い入れよりも金のほうが大事というのは東映という会社が長年かかって築き上げてきた社風であって、氏は単にその伝統に従って仕事をしただけである。個人でどうにかなる問題ではない。他にも脚本の米村正二氏と監督の金田治氏が叩かれていた。
だったらなぜ大葉健二氏を叩かないのか?
それこそが「鎖の最も弱い環」だろう。
だいたい白倉氏という人は、敵が多いほどうれしくなるというか、いくら叩いたところで蛙の面に小便というか、そーゆー人だというのはもう周知の事実ではないか。それに比べて俳優はイメージが大事である。叩いて叩いて叩きまくって、ノイローゼにしてやったらよかったのだ。そして、自分がこんな糞映画に出演し、一条寺烈役を演じたことによって、どれほどファンの気持を傷つけてしまったかということを、大葉氏に骨身にしみるまで分からせてやるべきであった。大葉氏もまた被害者である、などという弁明の成立する余地は一切ない。ギャラを受け取った以上は。
しかしファンは過激な行動に出ることもなかったし、そしてそれ以降も東映は懲りることなく、往年の俳優を起用して同じような糞映画を作り続けている。
要するに、ファンはナメられているのだ。どうせあいつらはそんな大それたことをするだけの智恵もなければ行動力もない。そのように白倉氏に見透かされているのだ。そうである以上今後もやりたい放題は続くだろう。
ところで、『仮面ライダークウガ』の主演を演じたオダギリジョー氏は、こちらのほうは理由はよく分からないが『クウガ』ファンからよく叩かれる人である。先日放送された『高寺成紀の怪獣ラジオ』では、「今後、五代雄介を演じることはありえますか」と質問されて、それに対する答えが「脚本次第」。
ヒーローの魂を持った俳優は一体どっちだろうか。
平成の次に来るヒーロー?(後編)
(承前)最近のスーパー戦隊を見て感じる最も大きな違和感は、ヒーローたちがまるで好きで戦っているかのように見えることである。
戦わない、という選択肢は初めからない。人類の生存を脅かす敵が、週に一体のペースで次から次へと襲ってくる世界である。死にたくないと思えば戦う以外ない。そうやって毎週戦い続けることが、やがては地上に理想の世界を実現させることにつながると思えばこそ、ヒーローたちはいかなる困難さにも耐えることができた。かつては。では現代のように理想を口にすることが難しい時代において、人は一体いかなる動機で戦い続けることができるのだろうか? 賽の河原ではないのか。
そこでその動機の不足を補うべく考えだされたのが、戦いそのものを楽しむことである。確かにこれはうまい手である。
ただ、「戦わねばならないから戦う」と「戦いたいから戦う」のハイブリッドの時代を経て、その傾向がさらに亢進すると、ヒーローたちはまるで後者が戦うことの動機の全てであるかのような様相を呈し、そうすると問題が露呈し始める。
そんな戦いを、なぜ視聴者が応援しなくてはならないのか。
もともと争い事が好きな性格ではなく、しかし、人々が安心して平和に暮らせるような世の中を作るためには、誰かが戦いを引き受けなくてはならない、そのような思いを胸に戦いに立ち上がった主人公というのであれば、もうそれだけで視聴者としては応援する気にさせられるのに十分である。しかし、好きで戦っているのであれば、まあ頑張ってちょうだいと思うだけである。ラストニンジャになりたい? 勝手になれば?
クリエイターにとって、自分のために戦う主人公を描くのは、他人のために戦う主人公を描くのに比べてはるかに難度が高い。視聴者を惹きつけるためには、ラストニンジャになることが、主人公たちにとってよっぽどの切迫感のあることだというふうに描く必要がある。どうもこの5年ほどのスーパー戦隊を見ていると、戦いの目的は昔と違ってきているのに、ヒーローの描き方は昔のままをやっているような気がする。
それとも今は過渡期であって、新しいヒーロー像を生むための苦しみの時期なのだろうか?
平成の次に来るヒーロー?(前編)
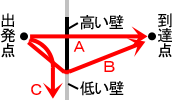
A:昭和 B:平成 C:平成の次?
「平成仮面ライダーの初期作品は素晴らしかった。それに比べて最近のは……」
という声が上がるのに接すると、かつて昭和ライダーのファンを懐古厨と呼んでバカにしていた連中が、今度は呼ばれる側になったのか、と感慨にふけりたくなってくる。しかし話はそれほど単純でもないようだ。
昭和/平成(より正確に言うと改元より少し後の1990年代前半)を境にした、ヒーロー像の変化というのは確かにあった。中断期間がない分だけ、ライダーよりも戦隊の方で傾向の違いは明瞭なのだが、具体的に言うと、かつてヒーローはいかなる高い障壁をも乗り越え、到達点まで一直線に突き進むべきものであった。実際は迂回することもあったが、それは力が足りなくて止むをえずそうしていただけである。それが社会の変化に従って、「巨大な悪」がリアリティを失うとともに、「高い壁は迂回し、低い壁は乗り越える」のも決して仕方なくやっているのではなく、それこそが正義のために戦う者が歩むべき道だというふうに変化していった。
この「到達点」が何を指すかというと、もちろん「戦いのない世界」である。ヒーローにとって戦いはあくまでも手段であって目的ではないのだから、「ヒーローたちが戦うのは、戦いが必要とされない世界を作るためである」というのも別に逆説的ではない。もちろんそんな境地に「達する」ことが簡単にできるわけではない。肝心なのは「近づく」ことである。
だが、最近の戦隊を見ていると、そのような目標とすべき到達点そのものを、持っていないようにも見える。
戦隊マップの現実/理念の対立で言えば、A(昭和)が理念型、B(平成)が現実・理念の混合型ということになる。とすれば、いずれはCの現実型へと移行するのは理の必然ともいえる。それが今だということになるのだろうか。そう考えると、1990年代前半にも比肩するような、大きなヒーロー像の変革が、今まさに進行中のような気もしてくる。しかし、25年前はソ連の崩壊があり冷戦が終結し、日本の社会は1945年の敗戦以来の大激動期を迎えていた。最近それに匹敵するような大事件って何かあっただろうか……?(続く)
特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(後編)
(承前)先日の「ゴレンジャー同窓会」でもそうだったが、戦隊の作品に出演した俳優が集まるイベントが執り行われた際、主演だった五人のうち四人しか集まらないことがある。その場合、あろうことか、残りの一人に対して非難の矛先を向ける声がネットで上がったりする。来たくなかったから来なかったのか、それとも来たかったのに仕事が忙しくて来れなかったのかもお構いなし。彼らの頭中では、とにかくこういうイベントに出てくる人はファンを大切にする人であり、出てこない人はファンを大切にしない人だという決めつけがある。
そういうのが現実に多数派か少数派か分からないが、とにかく声の大きいほうがファンの代表的な意見であるとしてまかり通ったりするのは困ったことである。
ところで、私も特撮出演俳優に会いに行ったことがある。その人はイベントなんかには全然出てこない人であるが、理由を聞いたら、俳優の才能はないと思ってさっさと引退した自分のような人間に、会いたいファンがいるとは思わなかったからだそうである。だからこっちから居場所を突き止めて押しかけていった。それでどうだったかというと、あまり詳しくは書く気がしない。なぜならイベントのような金銭を介在させた出会いとは違って、個人的なことをあまり大っぴらぴらにするものではないと思うからである。行ってよかったと思えるものであったとだけ書いておく。同様のことをした人は他にもいるであろう。多分みんなそんな感じに違いない。
だったらなんでオマエはこんなブログを書いているんだと言われそうだが、黙っていて、イベントに出てこない奴は特撮番組に出演したことを黒歴史にしているなどと見なす空気がさらに支配的になったりしては困るからである。そして出てこない人に対して心理的圧力がかかり、「やっばり出たほうがいいのだろうか」と嫌々出席するような事態が生じたりすることを懸念するからである。私とて、わざわざ人が楽しんでいることに対して、ケチを付けるような真似はしたくないのであって、やむをえず書いたのである。
特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(中編)
(承前)カドの立たないような言い方はないかとずっと考えていたのだが、結局ないようなので、もうはっきり書くことにする。
俳優として大成できなかったにもかかわらず、ファンから金を巻き上げることに精を出す姿は見苦しい。
別に他人が何をやろうと自由である。そしてその行為について、他人が感想を述べるのもまた自由である。別に止めろと言っているわけではない。
だいたい芸能界というのは、毎年膨大な数の人がデビューする。そして同じ数だけの人が消える。テレビ番組で一年間レギュラーの役を務めはしたものの、それ以外はあまりパッとすることもなく引退した俳優など星の数ほどもいるだろう。彼らは引退すれば即座にファンの記憶から消えてゆく。ところが特撮に出てヒーロー・ヒロインを演じた人たちに限ってはそうではない。引退して何年も経ってから、イベントに呼ばれて当時の思い出話をするよう求められたりすることがある。そして特に面白い話が出るわけでもない、冬の撮影は寒かったとか、どうでもいい話が聞けるだけのイベントのチケットに、五千円以上もする値段がつけられたりするのである。
もちろんそのような商売は、特撮ファンの勘違いの上に成立している。ファンは望んで勘違いをしているのだし、だから別に俳優は何か悪どいことをしているわけではない。
勘違いというのは具体的に言うと、「役と役者の混同」のことである。
特撮ファンが憧れの感情を抱く対象は、あくまでもヒーローであって、ヒーローを演じた役者ではない。しかし混同は容易に生じる。劇中でカッコいいヒーローを演じた役者は、役者自身も普段からカッコいい人だとファンは誤解する。ヒーローがカッコいいのは、もちろん役者の演技力もあろうが、プロデューサーや脚本家や監督や、その他大勢のフタッフの努力の結果である。それを、まるで自分一人の実力によってカッコいいヒーロー像を作り上げたかのように勘違いした俳優が、そのイメージを利用してファンから金を巻き上げる行為に加担し、その上ファンに幻滅を味わわせるような行為を働いたりする。これを見苦しいと言わずして、何を見苦しいと言うのか。(続く)
『七人の侍』は本当に名作か
娯楽作品というものは芸術作品よりも低く評価されるのが普通である。
しかるに、『七人の侍』はなぜかくも高く評価を受けているのだろう。不思議だ。日本映画オールタイム・ベストを選ぶという企画があればほぼ確実に一位。今さら言うまでもないことであるが、『七人の侍』は純然たる娯楽作品である。もちろん、娯楽作品としては超一級の作品であることには間違いはないが、娯楽作品としての限界もまた存在している。だから1954年に公開された当初は、批判的な評もあった。それがベネチア映画祭で銀獅子賞をとったら賛美一色になったらしい。いかにもこの国にありそうなことだが。
どんな批判かというと、さんざん語られ尽くして今さら書くまでもないのだが、要するにこの映画には侍・百姓・野伏せりの三種類の人間が出てくるのだが、それが完全に固定化されてしまっているということである。現実は、人間は誰でも気高き侍にもなりうるし、卑小な百姓にも残虐凶暴な野伏せりにもなりうる。秀吉の刀狩り以前という時代設定を考えれば、考証的にもおかしい。
そしてそのように人間の複雑さを切り落として単純な図式に落としこんだからこそ、世界中で大ヒットしたのである。
実際、2015年の現実を生きている我々には、たとえ娯楽映画といえども正義や悪というものをそんな単純な図式で描いていいものであろうか、という意識がちらつく。にもかかわらず『七人の侍』を見ると、理屈抜きにぐんぐんと画面に引き込まれてしまうのである。これはやはり黒澤明を筆頭とする当時のスタッフや俳優がよっぽど偉大だったのか、それとも以後の日本映画のシステムがどんどんダメになっていったということの証左なのか、邦画界のことについてはよく知らないが。
さてスーパー戦隊でも仮面ライダーでも、「大人の鑑賞に堪える」なんてことがよく言われる。単純な勧善懲悪もいいが、人間の複雑さを描いてこそ、見ている子どもたちの心に後々まで残る作品が出来上がる、とか。しかし『七人の侍』のような単純な作品が今なお名作と称えられている現状を鑑みると、問題はそれほど簡単ではないように思える。私自身も1970〜80年代のスーパー戦隊を今見ると、価値観が古いと感じぬわけでもない。それでも今の作品よりは見ていてワクワクする。これを単に懐古厨の戯言と片づけて良いものかどうか。
特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(前編)
最初に、好きなものを好きと言うのならともかく、嫌いなものをわざわざ嫌いと言うことに何の意味があるのか、という批判に対する反論。
好きなものに対しては好きと言う、嫌いなものに対しては嫌いと言わない。それが普通の生き方だとは思う。しかし世の中そんな人間ばっかりになってしまったら、「俺のやっていることは、誰からも好かれているのだ」などと勘違いする人が続出する。星新一の『妖精配給会社』の世界。だから誰かが言う必要があるのだ。
どうもこのブログも最近はネガティブなことばかり書いているような気もするし、コメント欄でもそのことを指摘されたばかりであるが、書いてる当人の心持ちは至ってポジティブである。
特撮に出たことのある俳優は、そのことを一生の宝物として誇りに思うはずである、などという思い込みは、特撮ファンの間に相当広く浸透しているように思われる。そういう人達は、一生の宝物というほどではないが大切にしている人もいる、ということが理解できない。オダギリジョーは『仮面ライダークウガ』に出たことを黒歴史にしているけしからん奴だ、という噂もそこに由来する。オダギリ氏はこの前ラジオに出て、自分は黒歴史にしたことなど一度もないと、きっぱりと否定していたが、それで噂が消えるものかどうか。
しかしなんでそんな誤解が浸透しているのだろうか。俳優がそういうことを言うからである。イベントとか、インタビューとか。本心からか、リップサービスからかは知らないが、そういうことを言ったらファンが喜ぶだろうと思って言う。しかしそんなファンばかりではない。もちろんファンとしては、特撮番組に出たことを大切な思い出として持っていて欲しいとは思う。しかし大切に思えば思うほどよい、というわけでもない。一生の宝物とまで思ったりする人は嫌だ、というファンだっている。そういうファンはわざわざそんなことを口にはしない。イベントにも行かない。無視するだけ。
そして俳優の方はますます勘違いしていくのである。(続く)
ギャバンとアトムと維新の党
維新の党の分裂騒ぎを見ていると、頭の中で『宇宙刑事ギャバン』の「チェイス!ギャバン」が延々と鳴り響いて困る。
敵が多いほど うれしくなるのさいやもちろんそういう意味じゃないってことは分かっているんですが。
強いやつほど 大歓迎
「敵を作る」というのが今の日本の政界において最も手っ取り早く有権者の歓心を買う手段になってから久しい。「守旧派」だの「抵抗勢力」だの「既得権益層」だの、とにかく敵認定してレッテルを貼るテクニックだけが大流行して、壮大な理想を語る人が誰もいなくなってしまった。でもそんなやり方は期限切れも早い。人気を維持しようと思ったら、絶えず敵を作っては叩き作っては叩きを繰り返す必要がある。
また思い出すのが、手塚治虫が『鉄腕アトム』を嫌っていたという話である。初の国産テレビアニメであり、スケジュールの逼迫度は想像を絶するものがあったようだ。一話一話じっくりと時間なんかかけておられず、そうするとどうしても悪いロボットを出してそれをアトムがやっつける、という話ばっかりになってしまう。勧善懲悪というのは作るのが一番手っ取り早いらしい。ソースは当時虫プロで絵コンテを描きまくっていた富野由悠季氏の自伝『だから僕は…』。
1981〜95年の15年間連続でスーパー戦隊シリーズのプロデューサーを務めた鈴木武幸氏が、以前こんなことを誇らしそうに言っていた。昔は子供がヒーロー物なんか見ていたら、親は顔をしかめていたものだが、今はそんなことはない。我々の努力が実を結んだ結果だ、と。素直に喜んでいいのだろうか。昔も、勧善懲悪物それ自体が教育に悪いと考えられていたわけではない。しかし、子供が勧善懲悪物だけを見ていたら、味方でないものは敵、敵でないものは味方という、きわめて単純な善悪二元論的なものの考え方しかできない大人になるのではないかという懸念があった。そしてそんな子どもたちが今や大人になって親となり、彼らは誰もそのような懸念を口にすることはない。多分、かつての懸念が的中したのだろう。
オダギリジョーはいったい何をバカにしたのか?(後編)
(承前)「自分は『クウガ』を黒歴史にしたことなど一度もない。にもかかわらずそのように言われる」
というようなことを「高寺成徳の怪獣ラジオ」2015年10月31日放映分でオダギリジョー氏自らが言っていた。もちろん原因は思い込みの激しいファンの方にあるのだが、オダギリ氏に責任が全くないわけでもない。
オダギリ氏は『クウガ』の主役に決まった時、自殺を考えたという。冷静に考えれば、そんなことがあるわけがない。イヤなら断ればいいのである。しかし純情なファンはこんなことを本気にしたりする。そして、結局はオダギリ氏は五代雄介役を引き受けたということは、まさに命がけの覚悟でこの『クウガ』という作品に臨んだということだ。しかるに、『クウガ』が終わった後も、オダギリ氏は特撮ヒーロー物なんてあんまり好きじゃないなどという発言を続けている。ああ、やっぱりオダギリ氏は『クウガ』なんか演じたことを後悔しているのだ、黒歴史にしているのだ……。まあそういう流れである。
私もそのラジオを聞いたんだが、オダギリ氏の口調から判断するに、やはり『クウガ』は大切な思い出の作品ではあるが、自分にとっての一番大切な作品というわけでもない、今までこなしてきた数多くの仕事の中の一つである、まあ多分そんな感じである。そりゃそうだ。仕事を一つ引き受けるたびに、いちいち命がけの覚悟なんかしていたら体がいくつあっても足りない。だからこの場合、勘違いするファンが悪いのである。しかしファンをそのような勘違いに仕向けたのもオダギリ氏である。
じゃあ、最初から正直に、僕は今回この役を引き受けましたが、単なる仕事と思ってこなします、などと言えばよかったのか。それはそれでマズイだろう。芸能人というのは幻想を売るのが商売なのだから。芸能人とファンの関係というのは恐ろしく複雑微妙な構造の上に成り立っているのであり、特撮ファンというのは、その中でも特に思い込みが激しい人が多い。オダギリ先生は、今回のラジオ出演で誤解が払拭されることを望んでいるようだが、そんなに都合よくいくまい。現に、オダギリ氏の「特撮物は好きじゃない」という発言を、「あれは『クウガ』を除く特撮物は好きじゃないという意味なのだ」などと勝手な解釈をし、掲示板荒らしをしている『クウガ』ファンがさっそく見られる。
オダギリジョーはいったい何をバカにしたのか?(前編)
オダギリジョーといえば、『仮面ライダークウガ』(2000年)の主演俳優であり、戦隊シリーズを侮辱するような発言をしている人である、と聞いていたので、いずれは筆誅をくわえてやらねばと前々から思っていたら、2015年10月31日の「高寺成徳の怪獣ラジオ」を聞いたら、どうもこの人は単に見栄を張って話を盛っているだけのような気がしてきた。そんな人を叩いたってしょうがない。
オダギリ氏は、『クウガ』の前年に『救急戦隊ゴーゴーファイブ』のオーディションを受けた際に特撮ヒーローをバカにするような発言を審査員に向かって行ない、つまみ出されたということで有名な人である。
僕が俳優の勉強をしているのは、リアルな芝居をやりたいためであって、変身とかヒーローとか、そういうものになるつもりはありません。変身ヒーロー物のオーディションをわざわざ受けに行って、こんなことを言ってきたというんだから、痛い人だと思われるのも当然だ。本人によれば、事務所に行けと言われて仕方なく、受かりたくもないオーディションに行ったという。どうも信じられない。そんな奴が最終選考まで残ったりするのだろうか? 審査する方の目だって節穴ではないだろう。
本当は受かりたくて受かりたくてたまらなかったんだけど、場の空気を読み違えて盛大にスベり、審査員を怒らせる結果になった。しかしそんな失敗談はみっともない。だから見栄を張って、最初から落とされるつもりだったんだ、みたいな話に作り変えた。真相はそんなところだろう。イソップにも確かそんな話があったような気がする。
そう考えていくと、翌年に『クウガ』の主役が決まった時だって、本当は天にも昇るような心地だったんだけど、素直に喜んだら自分を安っぽく見せてしまうことになるから、真剣に悩んだことにしておこうとしたとか、そういう可能性もある。「自殺を考えた」なんてのは明らかに誇張だろうけれども。
だいたいオダギリ氏が今回「怪獣ラジオ」という番組に出た目的の一つは、『クウガ』という作品に対する自分の思いが曲解されてファンの間に広まっており、それを払拭することであったという。しかしなあ、俳優にとって自分のありのままの本心をファンの前にさらさない権利があるのなら、ファンも俳優の発言をありのままに受け取らない権利があるのですよ。(続く)
作品を作ることの喜びと悲しみと

藤子・F・不二雄『未来の想い出』
ふええ、藤子・F先生もこんなこと考えてマンガ描いてたのか、晩年の作品のマンネリっぷりは本人も自覚していたんだなあ……などと勘違いしてはいけません。まあ、このコマだけ取り出して見せられたら勘違いして当然だけど(ごめんなさい)。
『未来の想い出』(1991年)はエッセイマンガではなくて、純然たるフィクションである。主人公の納戸理人はマンガ家だが、戦後生まれで出身は山梨。自伝的な要素はない。ただ、主人公の顔は作者の自画像の流用。それでこんなセリフをつぶやいてるんだから、読んでる方は当然ギョッとする。
日本一のマンガ家になるぞと青雲の志を立てて上京し、数多くの苦難を経てようやっと花開いた才能、そして大ヒット作家へ……と思ったその時点で既にマンガを描く喜びは消えていた。それだけでも悲劇だが、その上さらに悲劇的なのは、その悲劇を悲劇と感じる感覚すら麻痺してしまっているということだ。普通のマンガ家は、自分は今マンガを描いていて幸せなのだろうか、などと自問することすらない。
「ものを作る喜び」というのは、それほど簡単に消えるものらしい。それに代わって作家を突き動かす原動力となるのは、金や名声に対する執着心である。そっちの方はずっと強力で長続きする。というようなことを石ノ森章太郎も『マンガ家入門』(1965-66年)で書いていた。超一流の作家だけが気づく悩みというものがあるようだ。『未来の想い出』の安直な結末も、逆に現実の厳しさを浮き立たせているようで、かえって切ない。これが『ドラえもん』を除く最後の連載作品になる。
さて東映特撮の話だが、雑誌のインタビューとかを読んでいると、現代において仮面ライダーを作ることの意義はなにか、ということを熱っぽく語っている人が、別の所では、商品の売上高とか興収とか、まるで金のことにしか興味がないかのようにしゃべったりすることがある。どっちが本心なのだろうか。多分どっちも本心なのだろう。藤子・Fや石ノ森などには及ぶべくもないが、プロとして食っていくことに不自由はしないだけの才能はあるクリエイターにとって、「ものを作るということ」は、そういうことであるに違いない。
『仮面ライダークウガ』第25・26話の幼稚さ
もし自分の小学生のときに神崎みたいな先生が担任だったら、確実に学校嫌いになっていただろうなあ。
というのが『仮面ライダークウガ』の第25・26話を東映YouTubeを見て真っ先に思ったことである。なんでオマエがそんなもん見てるんだ、仮面ライダーには(昭和も平成も)関心ない、などと言っていたくせに――と言われそうだが、まあ無料だし、後学のためにとも思って見始めたら、刑事ドラマの部分は割と楽しめているが、しかし人間ドラマの部分がちょっとひどすぎるのではないか。
小学生だって決まりきった日常がイヤになって、ある日フッと電車に乗って遠くに行きたくなることくらいあるのではないか。しかし東京行きの電車に乗った直後にはもう目撃者から教師に報告が行き、その教師が東京在住の元教え子に電話、そして早々に身柄確保。いくらなんでも早すぎだろう。それとも栃木県というのはそれほどまでに相互監視の網の目が隅々にまで張り巡らされた、ガチガチの管理社会なのか? 普通ドラマでこういう話をするんだったら、自殺をほのめかすような書き置きを残しているとか、夜の十時になっても家に帰らないとかにするだろう。
ポレポレでは神崎先生が、子どもたちのことが分からなくなったと愚痴るのも意味不明のシーンだ。どうもこの先生、教師は生徒のことを100%理解していなくてはならないと思い込んでいるかのようだが、神崎先生って勤続何十年という設定じゃなかったのか? 普通こういうのって新任教師がするような勘違いだぞ?
夏目教授の娘の時も思ったが、なぜ五代のところに人生相談ばっかり舞い込んでくるのだろうか。とにかく作り手は彼を誰からも好かれる完璧超人にしたいように思える。どんなに深い悩みを抱えている人間でも、五代と接すればたちどころに固く閉ざした心を開く、とでもいうような。そのためには話の展開の不自然さなどどうでもいいと思っているのではないか。
これが、リアリティにこだわった作品ねえ……。
まだ折り返し時点であるから、これから挽回して面白くなることを祈ろう……と言いたいところだが、プロデューサーとか主演俳優とか、『クウガ』の作り手ってやたらと幼稚な言動を繰り返している人間が多い。彼らの自己投影が五代雄介というキャラクターだとするならば、あまり期待しないほうがいいのだろうか。
全話視聴完了後の感想
特撮ヒーローへの「誇りの強要」(補論)

『東映ヒーロー悪役列伝』(2006年12月30日)
特撮ヒーローへの「誇りの強要」への補論
特撮ヒーロー番組に出演し、誇らしい思い出として持っている人は、当然そのように言う。イベントにも出るしインタビュー記事にもなる。しかし嫌な思い出しか持っていない人も当然いるはずで、そのような人は黙っている。わざわざファンの夢を壊したいと思う人はいない。その結果として、ヒーロー番組に出たらそれを誇らしく思うのが当たり前である、などという勘違いが生まれる。
ところが、「嫌な思い出しかない」ということが、いろいろな偶然が重なって公になることもある。故・曽我町子氏にとっての魔女バンドーラ(『恐竜戦隊ジュウレンジャー』)がそうである。この本に掲載された曽我氏のインタビュー記事は、ヘドリアン女王をはじめとする戦隊悪役への出演について熱く語りながらバンドーラについての言及が一切ない。そして編集部からの追記がある。ちなみにその本の発売時点で曽我氏は故人。
編集部としては、当然この作品についてもうかがい、曽我さんから熱いコメントをいただいたのですが、後日、その内容に関して、ご本人から「話した内容をそのまま載せると一部の関係者の方に迷惑がかかる。かと言って、『ジュウレンジャー』について自分が語るのなら、先日あなた方に話した内容しかない」という旨の連絡を受けました。わざわざこんなこと書くなよとは思うが、書かなければファンから「なぜ触れられていないのか」という問い合わせがうるさいから書いたそうだ。
しかしこんな思わせぶりな書き方をしても、曽我氏が『ジュウレン』出演でどんな不快な思いをしたかなどという話は、ネットで調べれば出てくるわけですよ。ただそのネットの情報だけでは、どの程度の不快さだったのか分からない。両方の情報を組み合わせることによって、もう本気で腹を立てていたということが分かる。
もっともそのネット情報を読む限りにおいては、曽我さんのほうが誤解しているんじゃないかなあ、と思う部分もある。しかし曽我さんも、曽我さんが腹を立てた相手も故人となった今となっては詳しい事情が発掘される可能性は限りなく低い。
もし仮に、『ジュウレンジャー』の良い思い出も悪い思い出もフランクに話せるような風潮があったなら、その過程で曽我さんの誤解が解かれる可能性があったかもしれない(誤解だったとしてだが)。そしてバンドーラを演じて良かったと考えを改める機会を持つことができた可能性もある。もっとも「ファンの夢を壊すな」というのも一つの考えではあるから、どっちがいいと一概に言えない。
特撮ヒーローへの「誇りの強要」(後編)
(承前) 鈴木美潮のdonna 「赤祭」に戦隊の歴史支えた20人、「ムネアツ」超える感動!(2015年9月4日)についての続き。
今年も「激しい爆発シーンで、1年間の放送期間中に何度も爆風で飛ばされた」「ロープが切れて崖から落ちたのにその事故映像がそのままオンエアで使われた(もちろんDVDにもなっている)」「崖から落ちて肋骨を折ったが撮影はそのまま続行された」などのすさまじいエピソードが飛び出した。この手の、昔はこんなに危険な思いをして撮影をしていたんですよ(それに比べて今は……)、というような自慢話については、素直に感心できないところがある。
もちろん当時の撮影の現場に、いい作品を作りたい、迫力のある画を撮りたいという情熱がみなぎっていたというのは事実であろう。それが彼らを命知らずのアクションへと突き動かしていたとすれば、それ自体は非常に素晴らしいことである。しかし色々調べていていくと、それは単に安全管理に対する意識が低かっただけではないのかという疑念もぬぐえない。
平山亨氏や吉川進氏の回顧録を読んでも、東映という会社自体にジャリ番を差別する雰囲気があり、予算やスタジオの使用順位といった面で不遇を味わっていたという。それで現場だけが高い士気を維持していたという話を額面通りに受け取っていいのかどうか。危険な撮影も、監督に怒鳴られるのが怖くて嫌々やっていたけど、年を取れば若いころの苦労も懐かしく、記憶を美化してしゃべっている人もいるだろう。その一方で辛い思い出は辛い思い出のまま、という人もいるに違いなく、そういう人はイベントに出ることもなければインタビューを受ける機会もない。
実態はどうであったかは、簡単に結論が下せるような問題とは思えない。特撮ヒーロー番組に出たことを、誇りに思う人もいれば、思っていない人もいるはずで、それを一方的に誇りに思うのが正しく思わないのが間違っていると決めつけるような風潮には、はっきりと異議を唱えておきたい。
それはそうと、今の番組が昔ほどの迫力がないのは、命がけでやっていないからだ、という意見がある。しかしその迫力とやらが、スタッフや役者の人命に対する軽視ゆえに生み出されたものであるならば、そんなものはもう見たいとは思わない。CGで我慢する。一生障害が残るような大ケガをした人もいるし、あるいは死人だって出ていたのではないか。表沙汰になっていないだけで(別に事件を隠蔽したというのではなく、単にニュースバリューがなくて)。
補論あり
特撮ヒーローへの「誇りの強要」(前編)
鈴木美潮のdonna 「赤祭」に戦隊の歴史支えた20人、「ムネアツ」超える感動!(2015年9月4日)
まして、ヒーロー番組が「ジャリ番」と呼ばれ、今よりその地位がずっと低かった時代である。きっと、皆さんが胸を張ってヒーローを演じたことを語り出すまでには、長い時間が必要だったと思う。しつこいようだけど、鈴木美潮という人の、特撮ヒーロー番組に出た人は、その出演歴を誇りに思うはずである、思わなければならない、という決めつけは、一体どこに由来するのだろうか。この前出た本でもそうだったが。
私も以前、元特撮ヒーローの俳優がやっている店に行ったことがある。そのことを別に売りにしているわけでもなく、かといって隠しているわけでもない店である。ファンだと言って話しかけたら、普通に喜んでくれた。特撮ヒーローを演じたことを、特に誇らしく思っているわけでもないが、かといって恥と思っているわけでもない。しかし若いころの辛くも楽しい思い出となれば自然に話も弾みがつく。たっぷり話ができて満足だった。
こういうものだろうと思う。
特撮以外の元俳優でも、元スポーツ選手でも元マンガ家でも、事情はみんな同じようなものではないのか。
ネット上では、ヒーロー番組に出た俳優は、ヒーロー番組に出た俳優であることを誇りに思うか恥と思うかのどちらかしかない、と決めつけるような風潮が存在しているようで、イベントに出てこなければ「黒歴史にしている」と速攻でレッテル貼りだ。実際に人とふれあったこともなく、ネット上で人の品定めばかりしている人が、自分の頭で物を考える術をなくしたとしても不思議はないが、しかし鈴木氏は長年イベントを開催し、大勢の特撮番組のスタッフやキャストと交流を持っている人である。それがなんでこういうことになるのだろうか。それとも読売新聞の政治部に入って官邸や自民党の担当に配属されたら、こんなふうになるのだろうか。
コナン・ドイルがシャーロック・ホームズを嫌っていたというのは有名な話ではあるが、しかしそんな事実はホームズファンにとってはどうでもいいことである。同じことはモンゴメリの『赤毛のアン』についても言える。(続く)
仮面ライダーと日本国憲法

白井聡『永続敗戦論』。特に目新しいことが書いてあるわけではないが、こういう本が売れるということは、その程度には日本人の意識も変わりつつある?
ショッカーによって力を与えられた主人公が、その力を使ってショッカーと戦うという『仮面ライダー』の構図は、日本国憲法と似たところがある。
日本国憲法がアメリカによる押しつけ憲法だというのは、いやでも認めざるをえない事実である。井上ひさしや鶴見俊輔といった人たちの本を読むと、学者や知識人は皆そのことを分かっていた。そして分かっていたからこそ、守る価値を見出していたのだった。一言で言えば「敵の武器を奪って使う」。アメリカから与えられた憲法を盾にして、アメリカの言いなりから脱しようという戦略がここにはあった。そのためには、それが元々は敵製の武器だったということ、つまり我々は自力で武器を調達することすらできない情けない国民なのだという屈辱を、国民一人一人が直視する必要があった。しかしその戦略は結局は実を結ばなかった。
現実問題として政治の世界で力を持つためには、選挙で勝たねばならない。難しい話では大衆の理解も得にくいし票にもならず、だからもっと単純明快でわかりやすいスローガンが必要だった。だから護憲政党は、日本国憲法は世界にさきがけて人類の未来を照らす理想をうたったものだとかなんとかキレイ事で主張を塗り固め、その甲斐あって常に国会で三分の一強の議席を占めるほどの勢力は保ち、自民党が対米従属一辺倒に走るのを牽制する程度の役割は務めたものの、結局は政権につくこともなかったし、情勢が変わってアメリカから集団的自衛権を認めるよう本気で迫られれば、ひとたまりもなかったのである。
そしてそれは、敵の力を使って戦うという設定を持った『仮面ライダー』が、早々にテコ入れをされ、明るく単純な勧善懲悪劇へと作風を変化させていく中で大ヒット番組になったという事実とかぶって見える。「同族殺し」「改造人間の悲哀」という重苦しいテーマは、商業作品として人気を得るためには障害にしかならず、かといって石森章太郎先生から授かったテーマを粗略に扱うわけにもいかず。密教顕教の二重構造は解消されぬまま今に至っている。
あるいは平成仮面ライダーというのは、それを解消しようという試みだったのだろうか?
なぜ元ヒーローのブログは恥ずかしいのか
先日、何気なくある戦隊ヒーロー俳優の名前で検索をかけていたら、なんかものすごく恥ずかしい物を見つけてしまった。
佐村河内守・交響曲1番「HIROSHIMA」(2012年11月10日)佐村河内守氏のゴーストライター騒動は2014年2月である。その時、それまで佐村河内氏の音楽の素晴らしさを称えるような記事を載せていたブログは、当該記事を一斉に抹消した。まるで、自分は今まで佐村河内氏の音楽を称えたことなど一度もありませんよ、とでも言うかのように。それはそれで卑怯な態度だとは思うが、しかし記事を上げたことを忘れ、放ったらかしにする人もいることを思えばまだ随分とマシという気がする。
それにしても、かつてヒーローを演じたことのある俳優がやっているブログやツイッターやフェイスブック等々は、なぜああも恥ずかしいのだろうか。
現在俳優を続けている人はいい。今は別の職業についたり、何か社会的な活動をやっていて、その内容を報告するという明確な目的を持っているブログも同様である。それ以外の人のやっているブログは、恥ずかしいエントリを上げたから恥ずかしいとかいうのではなく、もう存在そのものが恥ずかしい。
いや、そもそもブログとはそういうものであって、元ヒーローのブログが特に恥ずかしいわけではない、という反論があろう。昼飯は何を食ったとかいう、どうでもいいような身辺雑記を延々と続けたり、普段から本なんか全然読んでいないくせに政治について語ったりするブログなんてのがよくある。それを無名の人間がやっているのであれば、別に恥ずかしくはない。平凡な人間が、自分は昼飯に何を食ったかという情報すらニュースバリューが生じるほどのVIPだと勘違いする。単によくある話である。
しかし元ヒーローの場合、俳優業を引退して何年経とうが、ファンにとっては雲の上の存在である。もちろんそんな幻想につきあう義務があるわけではない。自分は今は普通に社会人やってます、という態度をとるならとるで構わない。そして、そういう人のブログの中味が身辺雑記や床屋政談だったりする。
カッコいい人間であることを求められている人が、カッコいい人間であろうと努め、結果それが傍目に全然カッコよくない。この三拍子がそろうことは滅多にあるものではない。
『ウルトラマンメビウス』の大迷惑
私自身はウルトラシリーズのファンではないし、ウルトラシリーズが何をやろうが文句をつける筋合いはない。ただ、『ウルトラマンメビウス』(2006年)を感動的ともてはやすような風潮が、戦隊シリーズにまで伝播してきたりしたら大変なことになる。両シリーズの土壌の違いを無視して同じようなことをやったら無残な結果になることは目に見えていると、注意を促しておいたほうがいいのだろうか。あまり気の進まぬことではあるが。
『メビウス』の中で特に話題になったのは、『A』と『80』に関するエピソードのようだ。この二作品に共通しているのは、当時「投げっぱなし」をやったという点である。『A』では南夕子、『80』では教師設定。目先の数字、つまり視聴率とか商品売り上げに目を奪われ、小さなファンたちの心を踏みにじった。その投げっぱなしにした設定を回収し、きちんとした決着をつけ、ファンは感涙にむせんだ――どうもそういうことらしい。過ちは償わないよりも償ったほうがいい。しかしだったら最初から過ちをしなければ、もっとよかったはずだ。
その点戦隊シリーズは、投げっぱなしというのは余りやらない。ファンの思い入れを大切にしないという点では、東映だって決して人後に落ちないはずだが、なぜか最終回の決着だけはきちんとつけることが多い。きれいに終わった話には、後日譚は作れない。無理して作っても蛇足になることは確定的だし、それでもなんとか頑張って、作品に対する愛情と優秀な技量を持ったスタッフをかき集めて全力投球したところで自ずと限界はある。
それにしても、円谷プロだって別に改悛したわけではないだろう。商売の都合で状況によってクルクル方針を変えているだけで、ファンもよくこんな筋の通らない掌返しを許す気になれるな。その「おおらかさ」こそがウルトラファンのいいところなのだ、と言えば聞こえはいいが、それが頑固さとか、筋を通すことを軽蔑する風潮にもつながっているんじゃないの。そしてそれは、篠田三郎氏を大した根拠もなく裏切り者呼ばわりする人たちが、決して多数派ではないにせよ根強く存在していることと、無関係ではないような気もするけどね。
鈴木美潮という特オタ女の勘違い(補論)
8月14日の記事への補論
鈴木美潮『ヒーローたちの戦いは報われたか』は、論ずるに値する中味など何もない本ではあるが、第七章「ヒロイン、前線に立つ」については少しだけ引っかかることがあった。
しかし、この「紅一点」モデルの定着は罪でもあった。戦隊などで女が一人だけ入っていることについて何か言いたいらしいのだが、そもそもモモレンジャーに対する「男並みに働く女」という認識自体が恐ろしくステロタイプである上に、驚いたことに、この筆者は自分のことをモモレンジャーに重ね合わせているらしい。
男並みに働くとができるうえに女らしさも兼ね備えているスーパーウーマンしか、男性と平等に働くことはできない、という誤った固定観念を、筆者を含め多くの女子の胸に刻んでしまったからだ。
アメリカの大学に入って修士号を取得、読売新聞社に入社して政治部記者としてエリートコースを歩み続け現在はメディア局編集委員。うらやむべき経歴である。男社会の中で「男並みに働く女」であろうと必死に頑張ってきた人なんだろうなというのは容易に想像がつく。そして男社会に馴化適応していく中で、自分というものを失っていったことについても。政治部記者として、なにかユニークな記事を執筆して注目されたとか、スクープをものにしたとか、そういう話はなさそうだし。
それは仕事の上のことだけではない。自分の大好きな(はずの)特撮ヒーローについての本を出したら、それは既に今まで特撮ファンであればどこかで見聞きしたようなことのツギハギしかない本の一丁上がり。著者の独自視点は何一つない。特撮ファンの世界自体が男社会なのだから、確かに平仄はあっている。
「女の特オタなんてのは、イケメン俳優の顔しか見ていない」ということを言う人が時々いる。そういう人たちは、こういう「名誉男性」が書いた本についてはどういう評価を下すのだろう?
ちなみにこの本のこの箇所、竹信三恵子『女性を活用する国、しない国』を参考にしたらしい。しかしこれは日本社会の構造を分析した本だ。それを特撮ヒーロー番組に機械的に当てはめる奴があるか。耳学問ここに極まれりだ。ちなみに竹信氏というのも新聞記者。朝日だけど。
鈴木美潮という特オタ女の勘違い

鈴木美潮『ヒーローたちの戦いは報われたか』 オビの推薦文には藤岡弘、、佐々木剛、宮内洋、水木一郎の名前が並ぶ
書き手の「熱」というものを、これほど感じさせない特撮本というのも珍しい。
よく調べてあるなあとは思う。作品についてもその時代背景についても。ただしそれだけの本。
一例だけ挙げると、p.56には仮面ライダーがなぜ正義のために戦うヒーローではないのかについての分析が載っている。おい、仮面ライダーが劇中で「正義」という言葉を使いまくり、挿入歌でも歌詞に「正義」が頻繁に出てくることを知らんのか。
仮面ライダーが戦うのは正義のためではない、というのは平山亨プロデューサーが生前常々言っていたことである。インタビュイーは常に本当のことを言うとは限らない。その発言の中から何が真実で何が嘘かを見極める目が必要なのだ。言われたことをそのまま受け取る奴があるか。よくこんなんで政治部の新聞記者が務まるな、と思ったら、読売だった。読売なら仕方ないか。
自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で感じたことを自分の言葉で綴った本ではない。作品に関する分析も、その背景にある社会情勢に対する考察も、すべてどこかからの受け売りばかり。
なんでこんな本が出たのだろう?
逆のパターンはよくある。事実関係については間違いだらけなのだが、筆者の特撮に対する熱い思い入れがほとばしっている本。そういう本は少なくとも読んでて退屈はしない。この本はひたすら退屈なだけだ。
おそらく、この著者が女性であるということと無関係ではないと思われる。
特撮オタクにとって女性は稀少である。だからイベントなんかの場でさんざん「美潮ちゃん、そんなことよく知っているね」「美潮ちゃん、よくそんなことに気がついたね」などとチヤホヤされてきたことは容易に想像がつく。それはもちろん言っている方は「女の子にしては」という前提つきなのだが、言われた方は、自分が本当に一家言の持ち主としてみんなから認められたと勘違い、その結果がこの本なのだろう。
特撮界ではいまだに、女にゃ分からぬ男の世界、という風潮が根強くある。作品の作り手の側からも、女性蔑視的な失言が途絶えないのはそういうことだ。この本が、そのような特撮界の偏見を一層助長することにならないことを願う。
8月21日に補論
炎上商法をナメるな――『進撃の巨人』をめぐって
8月1日に公開された映画『進撃の巨人』は炎上商法をやっているのではないか、という噂が立っている。
というのは公開日を前後して、町山智浩、西村喜廣、樋口真嗣、福田裕彦と、制作スタッフあるいは彼らのお友達が、ファンの神経を逆撫でるような発言を次から次へと行なったからである。こんなに失言が矢継ぎ早に出るのも不自然ではないか、あるいは話題作りのためにワザとやっているのではないか……。
ハッキリ言ってやる。こんなものが炎上商法のワケがない。真面目に炎上商法をやっている人に対して失礼である。
炎上商法の達人として、今の日本映画界において第一に指を屈するのは東映の白倉伸一郎氏である。
白倉氏という人も毀誉褒貶の激しい人である。しかし、自分のプロデュースした作品をヒットさせるためならば、どんな汚い手を使うことも厭わないという、その姿勢に対しては一種の敬服の念を持たざるをえない。氏のすごいところは、どんなクソ映画を作っても、素晴らしい傑作ができましたと、記者会見の場でぬけぬけと自信たっぷりに言い放つことである。だから怒る人も出る代わりに、だまされたと思ってちょっと行ってみるかという気にさせられる人も出るのである(そして見終わってから怒るのである。後の祭りである)。
ひるがえって『進撃の巨人』の連中はどうか。原作厨だとか、冷笑家だとか、ハリウッド厨だとか、この映画を見て楽しめない人がいるとすれば、問題はそいつの方にあると決めつけるようなことばかり言っている。予防線を張るのは作品の出来ばえに自信がないことの現れだというのが透けて見える。それが劇場に足を運ぼうという気を萎えさせる。制作スタッフ自身が客を減らすような真似をしてどうするのだ。
『進撃の巨人』のスタッフは白倉伸一郎氏に土下座して、炎上商法のノウハウを教えてもらえ。もう遅いか。
小谷野敦の本はなぜ売れるのか(後編)
(承前)『ドラえもん』の劇場映画はなぜ年に一度なのだろう?
毎年巨額の利益を出してる映画である。だったら春休み夏休み冬休みの年三回公開にすれば、もっと利益が出るだろう。子どもたちだって喜ぶはずだ。……なんてことを考える人はいないわな。日本の誇る偉大なクリエイター、藤子・F・不二雄先生の遺産を粗略に扱うなど許されるはずもない。
ひるがえって『仮面ライダー』はというと、年三回公開という体制が定着して久しい。
逼迫したスケジュールがたたってクォリティは落ちる一方、それでも黒字が出ている以上、本数を減らすことはありえない。だいたい東映のスタッフも全員、石ノ森章太郎先生の魂を受け継いで『仮面ライダー』という作品を大切に作っていきますと言ってはいるものの、それが口先だけのものだということは、ファンもみんな了解している。
これが特撮のファン気質なのだ。
このブログで何度も何度も書いてきたが、私は商業主義を全否定するわけではない。問題はバランスなのだ。特撮作品の世界では、商業主義が暴走した際にブレーキ役を果たす存在が何もない。権威主義が通用しないということには良い面も悪い面もあると前回書いた。その悪い面がこれである。
『ウルトラセブン』第12話「遊星より愛をこめて」も、それが本当に被爆者に対して差別的な作品かということは、どうでもいいことなのだ。安藤健二『封印作品の謎』にもそんな書き方がしてあった。つまり、差別的なエピソードが含まれていると言われることが『ウルトラセブン』のイメージを悪化させ、そのことがもたらす損害額と、第12話をソフト化して上げられる利益額、その両者を比較して、前者が後者を上回ると円谷プロが判断した。そうである以上、どうしようもないことなのだ。ファンもみんな分かっている。
そんな現状がいいことだとは私も思わない。特撮ファンはもっと教養を高め、社会問題に対して目を向けるよう務めるべきである、という意見もある。そのためには、この特撮村に来てほしいのは、鳥なき里の蝙蝠なんかではなく、本物の鳥類である。芥川賞に落ちたことを売りにしている人なんかではなく、芥川賞なんかどうでもいいから真摯に小説に打ち込んでいるような人……。
7/29に補論
小谷野敦の本はなぜ売れるのか(中編)
(承前)『ウルトラマンのいた時代』、「序章」の最後の文。
スーザン・ソンタグに「反解釈」という評論があるが(ちくま学芸文庫)、「解釈」するのではなく、あの時代の雰囲気を表しつつ、ウルトラマンを論じる方法を考えて、本書を書いた。ほほう。で、そのソンタグという人はどんなことを言ってんの。と思ったら、何の説明もない。
外国の偉い学者の名前を出しさえすれば、読者は恐れ入ってひれ伏すだろうと思ったらしい。
その後も、「西洋古典への親炙」(p.64)だとか、無教養な人間が自分を賢く見せようと無理して難しい単語を使いまくり、しかもそれが誤用ときては大笑いである。この人には、なんと『頭の悪い日本語』などというタイトルの著書があるらしい。自分のことを書いたのだろうか。
こんな見え透いたこけおどしに引っかかる読者もどうかと思うが、ではなぜ特撮ファンにだけは、この権威主義の手法が通用しなかったのだろうか。
それは、特撮ファンこそは、「権威」から最も遠ざけられた人たちだからである。
『ウルトラセブン』の第12話「遊星より愛をこめて」は欠番になっている。そして解除を求めるファンの声も大きくない。それは、被爆者差別は許せないという権威に膝を屈しているからだ、と小谷野氏は考えた。そこに自分が乗り込んでいけばヒーローになれるに違いない。権威に対抗するためには自らも権威で武装することが必要だ。
だがそれが間違いなのである。
『セブン』12話の解除をファンが求めないのは、単につまらない話だからである。
面白いものは面白いと言う。つまらないものはつまらないと言う。それが特撮ファンである。権威の前に頭を垂れ、つまらないものを面白いと言ったりすることは、絶対にないとは言わないが、他のジャンルに比べれば少ない。
そしてそんな土壌を持った世界に、権威主義の鎧で身を固めた部外者がノコノコやってきて、ピエロを演じる羽目になったというわけである。
権威主義が通じないこの世界を私は愛する。そして自分がその一員であることを誇りに思う。ただ、いいことばかりというわけでもない。(続く)
小谷野敦の本はなぜ売れるのか(前編)

小谷野敦『ウルトラマンがいた時代』(KKベストセラーズ、2013年)
二年前に出た時に、ネットで無茶苦茶叩かれた本である。
別に小谷野氏をかばう義理は私にはない。当時、この本に加えられた批判の九割は、今から考えても妥当なものである。事実関係は間違いだらけだし、そしてそれを突きつけられた時の筆者の言い逃れや開き直った態度の見苦しさは記憶に新しい。特撮をダシに正義を語ろうとするような本とは一線を画すのだとかいいながら、やってることは単なる自分史をダラダラと書き並べているだけ。何歳の時にレトルトカレーを初めて食べたとか、そんな話がウルトラマンのいた時代を理解するのに一体何の関係があるのだろうか。ウルトラヒロインで誰が誰より美人だとかいう話が延々と続くのに対しては、そんなもんお前の好みだろとしか言いようがない。
だからといって残りの一割を見過ごしていいわけではない。明らかに過剰な叩きは存在していた。
「この小谷野という奴は、文学とか歴史とか社会問題とかをテーマにした本を出す際には、決してこのような間違いだらけの本を出そうとは思わなかっただろう。こいつは特撮を他のジャンルに対して明らかに低く見ているのだ。所詮子ども向けの娯楽だと思って馬鹿にしているのだ」という批判が当時あった。だが、小谷野氏は決してそのような人ではない。このことは、氏の名誉のためにも断言しておく。なぜそんなことが言えるのか。この人の、文学とか歴史とか社会問題とかをテーマにした他の本も、似たり寄ったりだからである。そしてアマゾンのレビューなんかを見てみると、「歯に衣着せぬ鋭い舌鋒」「歯切れの良さが痛快」などと褒めたたえ、買う人がいっぱいいる。そのように馬鹿をだまして食い物にするテクニックを自家薬籠中のものとしているのが、小谷野敦という人なのである。
そしてそのような手口が唯一通用しなかった相手が、特撮ファンだったのだ。(続く)
伊上勝の孝行息子

竹中清・井上敏樹『伊上勝評伝』
井上敏樹というのは実はいい人なのではと前から思っていたが、やっぱりいい人のようだ。この本に載っていた、父君である伊上勝氏に関する思い出を綴った文章を読んでいたら、そう思った。
伊上勝氏の偉大さについては今さら述べるまでもあるまい。東映特撮のヒーローの原型を、脚本家として全部一人で作った人である。その超売れっ子がわずか十年ほどの間に才能を枯渇させ何も書けなくなり、酒に溺れて惨めな晩年を過ごすことになったのは、まあ本人に責任がある。売れている間に、自分の作風の幅を広げる努力を何もしなかった(あるいはしたけど実を結ばなかった)からである。
私は時々考える。時代が父を追い越したのか、それとも時代には関係なく父は書けなくなったのか。きっとどちらとも言える。いずれにせよ父は書けなくなったに違いない。ずっと同じ井戸を掘っていてはいずれ水は涸れてしまう。こう井上氏は書く。だが「どちらとも言える」は違う。事実は明らかに後者だ。井上氏によれば、かつてヒーローとは孤独なものであり、一般人にとっては遠くから憧れる対象であった。それが時代とともに変化し、身近で親しみやすい存在となることを要求されるようになっていく。しかし私の見たところ、ヒーロー像が完全に交代したのは1990年代前半頃である。伊上氏が書けなくなったのは1980年頃。明らかに井上氏は、父君を可能な限りかばいたい、という意図を持ちながら書いている。
戦隊シリーズで言えば、曽田博久氏なんてのも明らかにヒーローの孤独さを描く人であった。戦隊って仲間が一杯いるのに孤独なのか、と言われるかもしれない。しかし曽田氏が全共闘の活動家であり、そのスローガンが「連帯を求めて孤立を恐れず」であることを思い起こせば平仄はあっている。
そしてその「大衆にとって遠い存在であるヒーロー」という像に完全に引導を渡したのが、井上氏がメインライターを務めた『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)である。伊上氏はそれを毎週楽しみに見ていたらしい。
自分の息子が自分と同じ職業を選び、自分を乗り越える。これほど父親冥利に尽きることはあるまい。こんなによく出来た、こんなに立派な息子を持ちながら、伊上氏は一体何が不満でアル中になんかになったのだろう。
よっぽど弱い人だったのだろうか。
名作すぎる『ウルトラセブン』
最初に断っておくと、森次晃嗣氏を批判したいわけではないです。批判するほど詳しくないし。ただ「ひし美ゆり子に対する疑念(後編)」のコメント欄で「森次氏は本当に『ウルトラセブン』に思い入れがあるのだろうか」という内容のことを書いてしまって、これが言葉足らずのために誤解を広める事になってしまっては申し訳ないので、補足しておいたほうがよかろうと思った次第。
そもそも『語ろう! 555 剣 響鬼』という本に森次氏のインタビューが載っているのは、『剣』に天王路という役で出演したからである。しかし質問のほとんどが『セブン』に関係したものである。それ自体変なことではあるが、その中身が妙に模範生的なのが気になったのである。まるで、こういう質問をされたらこう答える、ああいう質問をされたらああ答える、というアンチョコが既にあってそれに従って機械的に答えているかのような。
しかしそれは森次氏が『セブン』に対して思い入れがないのではなく、『セブン』という作品が余りにも名作として今まで語られすぎたがゆえに生じた事態なのかもしれない。「ノンマルトの使者」ならこういう解釈、「第四惑星の悪夢」ならこういう解釈、というのがもう完全に固定されてしまって、新しい解釈なんかもう出す余地がないみたいな雰囲気を、『セブン』という作品について感じるのである。
いや、別にそんなに難しく考えることはなく、単にインタビュアーの谷田俊太郎氏の技術が下手というだけのことかもしれない。インタビューというのは相手の本音を引き出すのが仕事であり、自分の意見をしゃべって相手に同意を求めたりするなど問題外。ちなみに脚本家の上原正三氏は『帰ってきたウルトラマン』の「怪獣使いと少年」について聞かれて「あれはテーマ性がナマで出すぎて自分としては気に入っていない」なんてことをしゃべったりしている。そのことがかえって上原氏のウルトラシリーズに対する思い入れをファンに強く感じさせるのである。
インタビューというのはする方もされる方も「段位」というものがあるんじゃないだろうか。
お疲れ様でした、高寺成紀さん

―― 高寺さんがあのときに示してくれた「響鬼イズム」みたいなものの発露が、この先、いろんな形で出てくるといいなぁと思ってます。これからの人たち?
高寺 敗軍の将として、あえて開き直ったものの言い方をさせてもらうとすると、これからの人たちには、もっと「馬鹿なこと」をしてほしいなぁと。
自分はやらんの?
あ、そうか。この人はもう終わった人なのか。
この本『語ろう! 555 剣 響鬼』の「おわりに」によれば、「計3回の取材で合計20時間以上」「その後もメールやスカイプで何度も対話を続け」「約半年かかりました」とのこと。それほどの莫大な手間暇をかけて、高寺氏が『響鬼』でやろうとしたことを探ろうとしたのは、その失敗から学び、経験を糧にして次に生かすためである。しかしそれは高寺氏が次回作のために生かすためではなくて、若い人たちに生かしてもらおうとするためであったらしい。
『ガメラ』の新作を任されているという噂もあったが、頓挫したのかそれとも最初からガセだったのか。
しかしこれだけの手間暇をかけながら、結局は単なる自己正当化にしかなっていないとは。
スーパー戦隊シリーズはなぜかくも長く続いているのか。マンネリと革新を車の両輪に走り続けてきたからである。戦隊シリーズは時代とともに少しずつ少しずつ変化を遂げてきたのであり、ある作品を境に急激に作風が変化するなどということはない。「新しいことへのチャレンジ」なんて毎年やっている。ただ目立たないだけだ。そして目立たずにそういうことをやり続けることが、もっとも大切でありまた困難なことでもある。「完全新生」などと派手な花火を打ち上げるということ自体、偉大なチャレンジでもなんでもないし、しかもそれが力尽きて倒れたのでは評価の対象にもならない。
まあいずれにせよお疲れ様でした。「平成仮面ライダーを立ち上げた男」という肩書があれば一生食いっぱぐれることもありますまい。このブログでも二度と取り上げることはなさそうだし。
ガス抜き、時代劇、特撮ヒーロー(後編)
(承前) 子供は、誰もが自分の目の前に無限の可能性が開かれていると思う(まあ例外もあろうが)。
そして大人への階段を一歩一歩上るにつれて、世の中というのは理想通りにはならないということを思い知っていく。
世の中にはびこる不正や悪を、正義のヒーローがばったばったと撫で斬りにするような番組の持つ意味も、大人向けと子供向けとでは意味が大きく違うはずだ。大人は、正義のヒーローなどというものが現実に存在なんかするはずがないということを知り尽くしている。だからそれは世の中の不満に対するガス抜きとして機能する。松田定次監督が東映時代劇について語っていたように。だが、そんな時代劇をルーツとして生まれたはずの東映特撮ヒーロー物は、子どもたちに対して、不正や悪に立ち向かい、それと戦う勇気を与える番組へと変質した。そう考えると胸が熱くなってくる。
宮内洋氏の言うように、ヒーロー番組は教育番組である。
ただ特撮ヒーロー番組は、大人が作って子供が見るというところに注意を要する。仮面ライダーにしろスーパー戦隊にしろ、圧倒的な強さを持つヒーローは、なぜそんな圧倒的な強さを持つに至ったのか、リアリティがあるように描かなければならない。そんなことを、子供の心を忘れた大人が作るとうっかり省略してしまう。そして大して努力もせずも大して才能もなさそうな普通のあんちゃんが、強くなりたいなあと願っただけで強くなるようなヒーローを出したりなんかしたりすると、かつての時代劇の世界にあっという間に先祖返りだ。
ヒーロー番組を見て正義や理想に対する憧れを植え付けられた子どもたちも、やがては大人になれば忘れる。どうせ忘れるんだから、深く考える必要はないんじゃないの、という意見もあるだろう。本当にそうだろうか。いったん身につけその後忘れる、そういうプロセスをちゃんと経由しないと、現実とフィクションの区別もちゃんとつかない大人になったりしないだろうか。そういえば政治の世界でもやたら「守旧派」だの「抵抗勢力」だの「既得権益層」だのと、自分に敵対する勢力にレッテル貼りをし、あたかも悪代官を成敗するヒーローみたいなノリを持ち込む手法が横行している。となると正義のヒーローにリアリティを感じる子供vs.感じない大人、という対立の図式も単純化しすぎただろうか。本格的に論じ出したら大論文になりそうな気がする。
ガス抜き、時代劇、特撮ヒーロー(前編)

仮面ライダーやスーパー戦隊など、特撮ヒーロー物において東映が断然面白いのは時代劇の血を引いているからだ、などということがよく言われる。
数々のヒット作を生み出した平山亨プロデューサーは元々は京都で時代劇を撮っていた人である。当時のエース監督・松田定次氏に助監督として仕えていた時、大衆娯楽作品を作るノウハウを徹底的に叩き込まれ、後年東京のテレビ部に移った際にそれが生かされたというわけである。
「先生、あんなのないですよ」と笑う平山に、松田は諭すようにこう答える。ただ、違うところも多い。
「平ちゃん、君は大学を出てるからそういうけどね。僕はね、小学校しか出てないんだ。僕と同じような人たちが集団就職で都会に出てきて朝から晩まで働いて日曜にその疲れを癒すために僕の映画を観に劇場に来る。彼らにとって入場料は安くない。その時に神様みたいに千恵蔵が〔ピストルの弾を〕よけると、凄い、と思ってスカッとして、月曜からまた働く意欲がわいてくるんだよ」
――春日太一『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』より
松田氏の教えというのは、要はヒーローの描き方にリアリティなんか要らんということである。片岡千恵蔵の演ずるヒーローが、至近距離からピストルで撃たれてもヒョイヒョイよける。なぜそんなことができるのか。説明なんぞ不要。だいたい正義のために戦うヒーローなどというものが、現実には存在しないことは、観客にも分かりきっている。である以上、そんなところに突っ込みを入れるのは野暮というものだ。
そしてそうやってワンパターン化していった時代劇は、やがて老人だけが見るものへと特化していき、衰退への道をたどっていく(という論を春日太一氏は後年『なぜ時代劇は滅びるのか』で展開することになる)。
しかし特撮ヒーロー物は違う。見るのは幼い子どもたちだ。そして人生の先の見えた大人とは違って、子どもにとっては「正義のために戦うヒーロー」の存在は決して絵空事ではない。現実に存在するものなのである。(続く)
勧善懲悪で何が悪いのか?(後編)
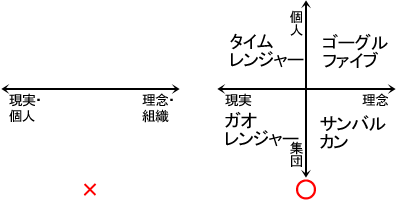
(承前) 『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年)の第40話「紅の復讐鬼! 地獄のモモレンジャー」でモモは変身不能に陥るのだが、それはそれで仕方がないから残りの四人でなんとか鉄カゴ仮面を倒すための作戦を考えよう、という方向に発想が一切いかないというのが面白い。だから、ただひたすらモモは変身能力を取り戻そうともがき苦しみ、他全員ともそれを待つだけだった。
だいたい1970〜80年代は、みんなそんな感じだった。最初に理念というものがある。そしてそれに基いて人員を集め装備を整え戦法を確立させる。そして途中でどんな障害にぶち当たろうと、決して現実に合わせて戦術を修正したりすることはない。つまりこれが、森の中で迷子になったらひたすら北に向かう、に相当する。というか戦隊に限ったことではなく、勧善懲悪のヒーロー物というのはたいていそうだった。そして決して揺るぐことのない固い信念を抱いて困難に立ち向かうヒーローに、視聴者は頼もしさを覚えていたのであった。
ここでまた転換点として名前が出てくるのが『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)である。スカイフォースの知力体力に優れた精鋭隊員に、バードニックウェーブを浴びせて更に強化した人間を戦士にするつもりが、バードニックウェーブを浴びただけのズブの素人を戦士に起用せざるをえなくなった。いきなり最初から修正が入ってしまったわけである。ただ、戦いの根本的な方針は組織によって定められているという限界はあり、極北はやはり『未来戦隊タイムレンジャー』(2000年)になるのだろうか。戦士に最も適任なのはこの五人だ、という保証を誰からも与えられることなく発足した戦隊。戦いの行く末に何が待っているのかすら分からないまま戦いは始まる。そしてひたすらその場その場の判断で、目の前の困難を一つ一つ除去していくだけである。
「理念に基づいた戦い」と「現実に基づいた戦い」を対比させ、これと「集団の戦い」と「個人の戦い」という対立軸とを組み合わせれば、新しく戦隊マップが出来るはずである。ただ、どうしても日本人には、滅私奉公を尊ぶ民族性というものがあって、根本的な方針を定めるのが組織の役割であり臨機応変に判断するのは個人の役割、などという思い込みが染み付いている。理念・現実の軸と集団・個人の軸との違いがどうにもイメージしにくくて、作業がはかどらないのである。
勧善懲悪で何が悪いのか?(中編)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「ガンファイターのび太」
(承前) 結局のところ、迷子になった森の中から脱出するためには、二つの視点を同時に持つことが絶対に必要ということになる。一つは、崖とか沼とか目の前にある危険な地形を避けるという、短期的視点。もう一つは、迂回しつつも全体の道筋としては北へ向かうという、長期的な視点。そしてそれは現実の人生でも、フィクションの中のキャラクターでも同じことである。
今ここでは向かう方向を「北」にしたが、別に北であることに根拠は必要ない。東でも南南西でも構わない。一つに決めさえすれば、どこでもいい。肝心なことは、「北」と最初に決めた以上は、途中で困難な道が延々と続き、「やっぱ東に向かったほうが良かったのかな」という気持ちが沸き上がっても、決して変えないということだ。
「百人いれば百通りの正義がある」などと言われる。多分そうだろう。しかしたとえ「絶対的な正義」が存在しないというのが事実であっても、絶対的な正義というものが存在すると仮定した上でしか人間というものは生きられないというのも事実である。人間はそのような矛盾の中でしか生きられない。短期的な視野しか持たない人間というのは、つまりその日その日を楽しく暮らすことだけしか頭になく、一切の理想も正義も信じずに生きることであるが、絶対不可能とは言わずとも、それはそれでものすごくキツイ生き方のような気がする。
人間の数だけ正義があるとして、じゃあ自分はこの正義に従って戦うんだ、という選択を、どのような覚悟と決意に基いて採ったのか、ヒーロー物の主人公は視聴者の前に明らかにする必要がある。A星とB星が戦争をしていて、主人公が単なる思いつきで片一方を正義、片一方を悪と決めつけて星間戦争に加担したりする、そういう勧善懲悪劇はやはり「くだらないもの」と見なされても仕方ないだろう。そういえば藤子・F・不二雄『ドラえもん』には「どっちも自分が正しいと思っている。戦争なんてそんなもん」という名言があったりするが、連載も後期に入ってのび太が「正義のため」などと口にしていたのにはさすがに驚いた。
ところでその山の迷子の比喩での「短期的視野と長期的視野」という概念、これは戦隊の分類に使えそうな気がする。以前書いたので言えば、短期的視野が右翼、長期的視野が左翼ということになるのだろうが、右翼左翼という言葉はやっぱり手垢がつきすぎて、やっぱり使いにくい。(続く)
勧善懲悪で何が悪いのか?(前編)
戦隊シリーズのファンが、ウルトラマンや仮面ライダーのファンと異なっている最大の点は、勧善懲悪をくだらないものと決めつける風潮が希薄なことではないかと思う。
ウルトラシリーズの名作エピソードを挙げろと言われたら、大抵の人は「故郷は地球」「ノンマルトの使者」「怪獣使いと少年」あたりを挙げる。理由は「勧善懲悪でないから」。勧善懲悪はくだらないもの、劣ったものであるというのが説明不要の前提みたいな扱いになっている。
だったら、『ウルトラマン』の全話が「故郷は地球」みたいな話だったら、もっと名作になっていただろうか? んなわけないだろう。
仮面ライダーシリーズにおける「正義」に関して平山亨氏が二枚舌を駆使していることについては、このブログでも何度も触れたから繰り返さない。
だいたい、勧善懲悪というのは本当にくだらないものなのだろうか。
そしてそんなくだらないものであるなら、なぜこれほどまでに人気があるのだろうか。
山の中で迷子になったとする。
山と行っても道もなく、原生林の茂った人跡未踏の地である。地図はない。視界も悪い。ただし、コンパスだけはある。そういう状況に陥ったと想像してみよう。自分ならどうするだろうか。
闇雲に歩きまわっても麓にたどりつける可能性は低い。こういう時に誰もが考えるのは、北なら北と方向を決めて、一方向に向かって歩き続けることである。そうすれば必ずいつかは山から降りられるはずだ。ただ、その行く手には崖や沼があり、進めなくなるかもしれない。崖はよじ登り、沼は泳いで渡り、あくまでも一直線に突き進むというのも一つのやり方ではあるが、途中でどうしても突破できずに力尽きて倒れる可能性も大きい。やはり険しい道は避けて進むべきではなかろうか。ただしあまりにも歩きやすい道ばかりを選んで歩いていると、同じ所をぐるぐる回っていつまでたっても脱出できない可能性も考える必要が出てくる。(続く)
道化を演じる元特撮俳優たち
爆報フライデーの話を書くのはこれで三度目である。
といっても星光子やだるま二郎とは違って、特に問題のある番組構成だったというわけではない。2012年3月23日に『超電子バイオマン』(1984年)のピンクファイブ・桂木ひかるを演じた牧野美千子氏が築地で佃煮屋をやっているのを、ちょっとだけ紹介しただけである。しかし、「変身ポーズをとってください」と言われたのでとってやった場面で、なんでそこでゲラゲラ爆笑する音声をかぶせるのか。
基本的にこういう低俗バラエティ番組は、人を小馬鹿にして笑いを取るものだから、いちいち腹なんか立ててもいられない。腹が立つのは、こんな番組に出たがる方だ。やっぱり牧野さんも芸能界に未練があるのだろうか。やれるだけのことはやった上で引退したわけではないからなぁ。親の反対がなければ今頃は……などと後悔の念に苛まされながら毎日生きているとしたら辛い話だ。だからテレビに出られるのなら何でもいいと思って飛びついたのだろうか。
だったらもっと実のある話をしてくれればいいのに。
イエローフォーの話とか。
さすがにそれはマズイだろうけど、でも矢島由紀氏の降板の経緯の一部についてバラしたのは牧野さんだ(2010年のトークショーでの話)。それまでは当時のキャスト・スタッフが、降板について触れること自体がタブーだった。牧野さん、後で東映から厳重注意くらったのだろうか。
とにかく、元特撮俳優で当時の話を色々しゃべりたがっている人は多い。ファンも知りたがっている人は多い。にもかかわらず、そういう人たちのブログやツイッターでは、当り障りのない話しか出てこない。上のほうで監視している人がいるのだろうか。実際、当時のことを書いたツイートを後で削除した人を私は知っている。問題になりそうなツイートでは全然なかった。名前は書かないでおくが。
そして一方でこんな低俗番組なんかに出演して道化を演じている人がいる。このミスマッチ、なんとかならないのだろうか。
あしたのジョー、男塾、御都合主義
刷り上がった『少年マガジン』を読んで梶原一騎は頭を抱えた。矢吹丈よりも一回り大きな体格の男として力石徹の登場が描かれてあったからである。ボクシングには体重別の階級というものがあることを、ちばてつやは失念していたのだった。これでは二人をリングで戦わせることができない。力石の過酷な減量物語は、実は二人の作者の行き違いが生んだのである……。
『あしたのジョー』のファンなら誰もが知っているエピソードである。ところがこの話を聞いた時、私は意味が分からなかった。そんなの、力石が威圧感でジョーの目には大きく見えた、ということにしておけば済む話ではないか。そして次からは、普通にジョーと同じ体格の男して描く。マンガ家なら誰もがやっていることだ。『魁!! 男塾』というマンガでもそういうことをやっていた。
そう、誰もがやることを、敢えてやらなかった。『あしたのジョー』だって御都合主義が絶無なわけではない。その場その場の盛り上がりを優先させるために、辻褄が合わなくなってしまったことも確かに色々ある。それでも、これだけは絶対に譲れないという一線があり、それを最後まで守り通した。それが、一流のマンガ作品である『男塾』と、超一流の作品である『あしたのジョー』を分かつものであった。
さて、仮面ライダーの春映画と言えば、もう辻褄なんか無視することが慣例になっている。整合性のつく説明を求めるようなファンがいれば、むしろ野暮呼ばわりされる。細けえことはいいんだよ、どうせお祭り映画なんだから、と。
『仮面ライダー』といえば、藤岡弘の事故が有名である。そしてなんとか辻褄を合わせようと、スタッフ一同必死で智恵を絞っていた時点では、仮面ライダーシリーズも超一流の作品となる可能性を持っていた。一体どこで道を踏み外したのだろうか。多分、死んだはずのライダーマンを、何の説明もなく再登場させた時点ではなかったかと思う。
高寺成紀の復活はもうないのか

・『東映ヒーローMAX』Vol.39(2011年12月)、Vol.40(2012年3月)
・『語ろう!クウガ・アギト・龍騎』(2014年7月)
一体この二年間の間に高寺成紀氏に何があったのだろう。両方とも高寺氏のインタビューが載っていて、しゃべっている内容もほぼ同じ。それなのに語る口調がまるで正反対。もちろん人間なのであるから、考えが変わるということはありうる。人生上り調子の時は天狗になり、下り調子の時は落ち込む、それが普通である。しかし、高寺氏の場合は、2010年の『大魔神カノン』の評判が芳しくなく、その後も『ガメラ』の新作を任されたとかいう話が出た割には目に見えた進展は何もない。にもかかわらず増長の度が増しているのは一体どういうことなのか。
だいたい一年間のテレビシリーズなどというものは、一人の人間の力で出来るものではない。大勢の人間が力を合わせて作るものである。その一方で『クウガ』の手柄を独り占めにしたいという思いもあるのであろう、だから2011〜2012年でのインタビューでは、結局何が言いたいのかよく分からないことになっている。インタビュアーが切通理作氏だから仕方ないと言えば仕方ないのだが、この時点ではまだフタッフに対するリスペクトを語ったりもしている。それが2014年の時点では、もうはっきりと自分以外のスタッフは全員無能という考えを隠そうともしていない。
プロデューサーとして一番大切な仕事は、人を動かすことである。だから、たとえ本心はどうあれ、口先だけでも「このような素晴らしい作品を作れたのは、大勢の優秀なスタッフに恵まれたおかげです」と言う。そうでなければ人はついてこない。
とすると現在の高寺氏は心境はどうなっているのか。答えは一つしかあるまい。もう現場復帰はあきらめたということだろう。
自らの業績に泥を塗る東映プロデューサー

大下英治『日本(ジャパニーズ)ヒーローは世界を制す』(1995年)という本は、東映テレビ番組のキャラクタービジネスの歴史についての本であるが、公平な視点から書かれた本ではないということは、一読してすぐに分かる。重大な決断はすべて渡邊亮徳という人間によって行なわれ、他の人間はその指示に従って行動しただけという書き方で貫かれているからである。他の人間が重大な決断をする際は、固有名詞が出てこない。2014年にこの本の増補改訂版が『仮面ライダーから我狼へ』という題名で文庫化された際、「渡邊亮徳・日本のキャラクタービジネスを築き上げた男」というサブタイトルがついたのは、さすがに中立を装うのにも限度があることを知ったからだろう。
こんな本の間違いをいちいち指摘するのも面倒なだけだから、『がんばれ!! ロボコン』(1974年)に関して記述が一切ない、という一点を指摘するにとどめておく。人気が大変高かったというだけではない、ビジネスモデルを確立したという点においても、重要な作品である。『ロボコン』の超合金に触れないで日本のキャラクタービジネスの歴史を語るということなど絶対にありえない。なぜ触れなかったかというと、渡邊氏の汚点だからである。平山亨氏がロボットコメディ物の企画書を出したら渡邊氏にボツにされ、平山氏はそれを大切にとっておいたら数年後にテレビ局の人の目に止まり、実現させたら大ヒットになったという経緯があったからである。
渡邊亮徳という名前は、平山氏の本の中や吉川進氏のインタビューにもしばしば出てくる。尊敬する上司として。大きな功績のある人だということは確かなのだろう。しかしそれも、こんな本を出した時点で全部台なしである。自分たちの仕事の正確な記録を残すよりも、自分の手柄を誇大に見せかけることのほうが大事だ、という風潮は、今後も東映のプロデューサーに受け継がれていくのだろうか?
それにしても。
人間には誰でも名誉欲というものがある。だったら、どうしてこんなチンピラのライターを使ったのだろうか。ヨイショ本であることを容易に見破られてしまわないような、巧みな文章を書ける腕のいいライターを使おうとは思わなかったのだろうか?
内田有作はなぜ東映を首になったのか

東映の拝金主義的体質は別に最近になって始まったことではない。
ということをこのブログでもさんざん書いてきたわけだが、2010年ごろから仮面ライダーやスーパー戦隊の映画の粗製濫造が限度を超え、ファンの批判的な目が向きはじめただけのことである。「昔は良かった」というわけではない。本当は大切にすべきものを、目先の利益優先で使い捨てにする。昔からそうだったし、そして厄介なことに、そのような社風が『仮面ライダー』のような大ヒット作を作る原動力にもなっていたのだから、一概に否定することもできない。問題なのは、時代が変わって昔からのやり方が通用しなくなり、近年は大ヒット作も作れなくなったのに、社風は依然として昔のままだということである。
「本当は大切にすべきもの」。その筆頭はなんといっても人材であろう。
『東映ヒーローMAX』Vol.40(2012年3月発行)は、東映生田スタジオの所長を務めた内田有作氏の追悼ということで特集が組まれている。
その記事によれば、厳しい条件の下で予算やスケジュールを管理する制作者としての手腕、映画界での幅広い人脈、スタッフを惹きつける素晴らしい人柄。『仮面ライダー』の大ヒットは内田所長の手柄に帰す部分が非常に大きいということになっている。
そんな有能な人が、なんで生田スタジオの赤字の責任をたった一人に押しつけられる形で所長を解任されたりしたのか。
内田氏はウィキペディアに項目もないし、ネットで調べてもよく分からない。退職金も出なかったというのは本当だろうか? 東映を辞めた後の晩年の人生も、映画人として満足のいくものだったとは思えない。
しかしこの記事を読んで一番不気味に感じたことは、内田氏に対する東映の仕打ちに誰一人憤るわけでもなく、まるで「男の生きざま」みたいな美談仕立てにしていることである。一体これのどこが美談なのか。それとも労働者の仲間を裏切ってスト破りした男の末路はこんなものなのだろうか?
『東映ヒーローMAX』なんて雑誌は、東映の大本営みたいな雑誌である。そんな雑誌を読んで、東映という会社の闇の深さを印象づけられるというのも妙なものだ。別に私はこれ以上追及する気はないんだけど。
仮面ライダーと原発(後編)
(前からの続き)仮面ライダーシリーズの原作者が石ノ森章太郎だというのは、単に名義上のことだということは、ファンであれば誰でも知っている(平成だけじゃなくて昭和も)。少なくともテレビ版では石ノ森氏はスタッフの一人でしかないし、その名を原作者に据えることに、何か深い考えが最初からあったとは思われない。しかし『仮面ライダー』が予想を超えた大ヒット作になることによって、妙な事情を抱え込むことになってしまった。
『仮面ライダー』が東映時代劇の血を受け継いでいることは、しばしば指摘されている。大衆に一時的な慰安を与えることこそ使命であり、深いメッセージ性など不要。ただ平山亨プロデューサーを筆頭とするスタッフが、そのことを誇りに思っていたかというと、そういうわけでもない。世間では高尚な文芸作品に比べて大衆娯楽作品は劣るものと見なされていたし、それに対するコンプレックスはぬぐいがたく存在していた。だからこそ石ノ森章太郎という有名なマンガ家を原作者としてクレジットし、『仮面ライダー』が大ヒットしたのは改造人間の孤独であるとか正義と悪の同根性とか、深いテーマ性があったからこそなんだ、などというスタンスを対外的に取り繕う必要があったのである。実際は仮面ライダーって言われるほど孤独でもないんだが。そういった本音と建前の二重構造を打破しようという努力が平成ライダーのスタッフによって試みられもしたが、実を結んだとは言いがたい。結局は毎年新作が発表される度にスタッフ一同「石ノ森先生の遺志を継いで……」みたいな白々しい発言をするのが今でも慣例になっている。
そしてそれは戦後の日本の歩みと奇妙に一致している。人命も美しい国土も伝統文化もすべて犠牲にし、金儲けだけが正義と国民一丸となって突っ走った結果が、戦後の奇跡的な経済成長であるというのは今さら指摘するまでもない。そしてその後ろめたさが、今さまざまな局面で日本社会に軋みを生じさせている。原発もその一つに過ぎないし、そして平山亨氏の原発に関する発言をその文脈に置いた時、その意味の深さも思い知れるであろう。
仮面ライダーと原発(前編)

彼〔青柳誠、引用者注〕はエンジニアとして、原発は危険で、原発は無用だという一種の迷信に反発し、原発は現在の人間生活に必要なものであり、完璧な運営をすれば、絶対に安全なものなのだと言いたかったのだろう。実際今の日本の社会は原発の電力なしでは、経済復興も何もなりたたないのだ。それを考えずに闇雲に原発廃止を迫る人は百年前の飢餓と隣り合わせの生活を覚悟して言っているのだろうか。(平山亨『東映ヒーロー名人列伝』1999年、p.122)平山氏が特に愚かなわけではない。「3・11」以前にはよくいたのである。核物理学なんかまともに勉強したことがあるとも思えないのに、ただひたすら原発の絶対安全性を声高に叫ぶ人というのが。
平山氏の著作を何冊か読んでみれば、この人が徹底的に無思想の人であることが容易に感じられる。理念や哲学を持たないことを、積極的に選択した人である。氏によれば、テレビ番組というものには二種類しかない。面白い番組と、つまらない番組と。そしてそれがプロデューサーとして、数々のヒット作を生み出す原動力にもなった。ただそういう、子供たちの心にいつまでも残るような深いメッセージ性など無用、今が楽しければよいのだ、というスタンスが通用したのは、当時が高度経済成長期だったからだとも言える。経済成長こそが正義だ、経済的に豊かになることが人々の心をも豊かにすることだという考えが何の疑いもなく横行していた時代である。現代ではもはや通用する手法ではない。冷戦が終わり、そもそも正義とは何かということ自体が非常に見えにくくなっている現在の日本において、もはや『仮面ライダー』(1971年)を見てそのストーリーから視聴者が感じ取れることなど何もない。
「3・11」以後、経済成長イコール正義という主張も以前ほど威勢は良くなく、かといってそれに取って代わる新しい理念が台頭してきているわけでもない。大多数の国民は、今後の日本のエネルギー政策がどうあるべきかについて真剣に考えようともせず、原発から目をそらそうとしているように思える。そしてそれは今の混迷の続く仮面ライダーシリーズの状況と奇妙な類似が見られる。(続く)
佐藤健太の問題発言
佐藤健太氏(『高速戦隊ターボレンジャー』のレッド・炎力を演じた役者)の3月29日のツイートから。
ニンニンジャー♪ 来週からも楽しみだなぁ〜♪ 純粋な気持ちで 今後の展開と♪ 役者の皆さんの成長が楽しみですね♪ ネット社会によって 滑舌がどーの・・ とかあるみたいだけど そんな事 子供たちは まったく気にしていない訳で♪( ・∇・) 毎回楽しみに見ています♪(強調は引用者)こういうのを見ていると、今の若い人というのは大変だなあと本当に同情する。
若い役者が「子供向け番組だからこの程度でいいだろ」みたいな発言をしていたら、OBがそれを聞いて「子供をなめるな! 子供をだますということは、大人をだますことよりも難しいのだ」と叱る、それが本来の先輩−後輩の関係というものだろう。佐藤氏だってそうだったんじゃないのか。そして叱られた側の人間が、今度は自分が先輩の立場になった時、若い人たちを叱る側に回る、そうやって芸というものは伝えられてきたはずだ。それが今では先輩のほうが後輩に媚を売っている。
そこまでして戦隊関係の仕事にありつきたいのか。
ニンニンジャーの役者の人達はこんな周囲の雑音に惑わされることなく、芸の向上に頑張ってほしい。というか、西川俊介氏(アカ役の人)の問題は本当に滑舌なのだろうか。滑舌じゃなくて声質の問題だと思うんだが。滑舌ならそのうちにうまくなる可能性はあるが、声質というのは訓練で変えられるのだろうか。変えられなかったらそれこそ大問題。というか、こういうことのアドバイスが出来る人こそが「先輩」ではないのか。
それにしても、である。
どうして私はインターネットをやるたびに、腹を立ててばかりいるのだろう。なにかブログのネタはないか、誰か問題発言をしている奴はいないか、と鵜の目鷹の目で探しているわけでは全然ない。なにか面白いことはないかと思ってネットやっているのに、なんでこういつもいつも不愉快なニュースばっかり簡単に出てくるのだ。おかげでこのブログ、ネタ切れに苦しんだことがない。なんとかしてくれ。
私は本当は早いところ戦隊マップの改訂版に取り組みたい。
天才の平山亨、秀才の白倉伸一郎

『動画王』8号(1999.2)「平山亨・東映プロデューサー時代を語る」
「どうして普通に、大勢の仮面ライダーが力を合わせて巨大な悪と戦うという話にできないのか。どうしていつもいつも、なんやかんやと理由をこしらえて、仮面ライダー同士で戦わないといけないのか」
毎年春のヒーロー大戦系の映画が公開されると、いつもいつもこういう声を聞く。
おそらく、白倉伸一郎プロデューサーというのは、仮面ライダーの生みの親である平山亨氏の考えに忠実に従っているのではないか。仮面ライダーは孤独のヒーローである。そんじょそこらのヒーロー物とは違うんだ。大勢で力を合わせて戦ったりしてはいけない。
んなこと言っても、昭和の時から仮面ライダーはピンチになると、すぐに先輩ライダーが外国から助けに駆けつけてくるではないか、と反論する向きもあろう。映画では五人ライダーとか七人ライダーとか歴代集合ものばっかりだったじゃないか。どこが孤独のヒーローなんだ。まあ、そうなんである。そういう、二枚舌を何の躊躇もなく使えるってところが、平山氏が天才プロデューサーと呼ばれたゆえんであろう。信念だのポリシーだの、そんなもんで飯が食えんのか。客が喜びさえすれば何でもアリなんだ。そういう精神を骨の髄まで染み込ませた人であればこそ、あれだけテレビの世界でヒット作を連発することができた。
それに比べて白倉伸一郎氏はやっぱりインテリだと思う。『ヒーローと正義』なんて本まで出してるくらいだ。仮面ライダーはと何か、仮面ライダーが掲げる正義とはどうあるべきか、などというコダワリに縛られ、ガツガツしたところが欠けている。白倉氏に対して拝金主義者と批判する声はよく聞くし、本人もなんかそんなイメージを気に入っているような節もあるが、この人のプロデューサーとしての限界は、拝金主義に徹しきれないところだと思う。
地獄へは仮面ライダーだけで行っとくれ

映画と関係づけようという無理矢理感が濃厚に漂う22日の新聞のテレビ欄。実際は普通に戦隊とライダーが放映された。
21日に『スーパーヒーロー大戦GP 仮面ライダー3号』がいよいよ公開された。毎年春のヒーロー大戦が糞なのは、まともに時間をかけていないからである。そしてその過密スケジュールを改善する気が東映に全くない以上、今年もまた糞映画であることは、見なくても分かる。まともな頭を持った戦隊ファンであれば、誰だってそうだろう。宇宙刑事ファンだって同様のはずだ。「見なくては批判できない」などと言っているのは、鳥頭のライダーファンくらいのものである。まさに「賢者は歴史から学ぶ、愚者は経験から学ぶ」。
なぜ特撮ファンは毎年春の大戦映画を観に行きまた同じように憤るのかYU@Kの不定期村というブログを見ていたら、こんなことが書いてあった。
違うでしょ。
「特撮ファン」じゃなくて「仮面ライダーファン」。戦隊ファンまで一緒にしないでほしい。
ネットで感想を拾っていると、「なんでニンニンジャー出すんだ」というのを多く見かける。どうもみんな事態がよく見えていないようだ。
最初から仮面ライダーしか出すつもりはないにしても、いかにも戦隊もライダーも活躍しそうな虚偽の予告の映像やポスターを作り、両方のファンとも劇場に来てくださいという雰囲気を盛り上げるという戦略をとることもできたはずである。いや、そうしなかったことのほうが不思議と言ってもいいくらいだ。「三かくマーク」の東映であれば。では何故そうしなかったのか。戦隊ファンはライダーファンよりもかしこいからである。本当にかしこいかどうかは知らん。少なくとも作ってる方はそう思った、ということだ。同じ手で何度でもだませるのはライダーファンくらいのものである。
つまらない映画に対しては「見に行かない」という形で抗議するしかないだろう。それができないというのであれば、仮面ライダーシリーズはファンと一緒に地獄への道を突き進むがよい。ただし戦隊ファンはそんなものへの同道はご免こうむる。
ミロのヴィーナスと『相棒』
3月18日に放映されたテレビ朝日のドラマ『相棒』第13部の最終話が面白いことになっているらしい。『相棒』ファンが「こんな最終回ってあるか!」と悲憤慷慨している一方で、それを傍から見ている東映特撮ファンが
「なんだ、いつもの東映か」
もしミロのヴィーナスに両腕があったら、世界的な美術品ではなかったであろう、なんてことがよく言われるが、確かにそのとおりだと思う。ないからこそ「本当は両腕はどうだったのだろう」と見る者の想像力をかきたてる。しかしそれを勘違いして、なるほど芸術作品というのは完成度が低いほうが名作になるんだなと、最初からわざと完成度の低い作品を作ろうとする人も生じる。まあ今の東映がそうなんだが。だから、話の辻褄なんか無視して視聴者をアッと驚かせることが番組制作者としての使命だと思いこみ、しかし視聴者としては「またその手か」と驚きもしない。いわゆる「パターン破りのパターン化」というやつ。
仮にミロのヴィーナスに両腕があったまま出土したとしても、やっぱりそれなりに高い評価を受ける美術品であったことには間違いない。きわめて緻密で精巧な出来ばえの作品が、九割だけ完成しているからこそ、残りの一割に対する想像力がかきたてられるのであって、粗雑な出来で九割の完成品なんか見て、誰が残りの一割を見たいなんて思うものか。
しかしこういう、仮面ライダーの映画でさんざん使い古され見ている方も全然驚かなくなった手法を、いまさら一般向けドラマが後追いとは。昔は一般ドラマがジャリ番を差別していたが、今はもうどっちが上か分からんな。
白倉伸一郎の降格(後編)
(前からの続き)さて結論である。
白倉氏に対しては、『アギト』や『龍騎』を作っていた頃は天才だったが今はカス、と評価する人が多いようだ。しかしそれって「司馬史観」と同じ気持ち悪さを感じる(明治の日本は良かったがそれ以降ダメになった、という例のやつ)。仮面ライダーを、「大人の鑑賞に堪える」高いドラマ性を持った作品としてヒットさせたということと、粗製濫造して衰亡に導くということとは、連続した流れの上にある。分けて考えることはできない。今まで長々と論じてきたのは、そういうことである。
東映が今まで時代劇や任侠物で延々と続けてきたパターンに、仮面ライダーを乗せることに成功した。そういう意味では白倉氏は間違いなく秀才プロデューサーだったであろう。そして、東映という会社のやり方そのものを変えることはできなかったという点では、秀才どまりであったとも言える。
平成仮面ライダーが始まった最初の三年くらいは良かった、と言っている人は多い。あの頃の作風に戻って欲しいなどという望みを持っているファンもいるだろうが、しかしそんなものはもう捨てたほうがいいと思う。既にサイクルは一周した。
今度の『スーパーヒーロー大戦GP』、戦隊は本当に申し訳程度にしか出てこないらしい。これはもう東映としても本気で仮面ライダーを使い潰すことを視野にいれ、せめて戦隊だけでも切り離して延命させようと考えているのではないか、ということを私は割と本気で勘ぐっている。もともと仮面ライダーとスーパー戦隊というのは歩んできた歴史も違うしファン気質も違う。歴代戦隊集合映画なんてのも、明らかに『ディケイド』に無理矢理おつきあいさせられたようなものだ。戦隊シリーズは昔から日の光を浴びることなく延々と続いてきたんだし、今後も細々と続いていけばいいということに、大方の戦隊ファンは同意するだろう。
しかし、一度は華やかなスポットライトを浴びてしまったライダーファンは、再び日陰者の立場に戻ることに我慢できるかどうか。
最後に白倉伸一郎先生の2013年3月26日のツイートから。
「龍騎以降は仮面ライダーじゃないから見てないけど」「30分のCMでしょ? だから見ないけど」という人にライダーの取材を受ける。10年前なら噛みついてたな〜。今は普通にニコニコ流せる。これって二通りの解釈ができるな。
勝利宣言ととるか敗北宣言ととるかは読む人次第、か。
白倉伸一郎の降格(中編その2)
(前からの続き)

春日太一『仁義なき日本沈没――東宝vs.東映の戦後サバイバル』
『スーパーヒーロー大戦GP』の試写も無事に行なわれ、行ってきた人の感想によれば、まあ例年のような内容らしい。
いよいよ1960年ごろの東映時代劇みたいになってきた。
「様式美」と言えば聞こえはいいが、単に進取の気性を欠いていただけの話。ワンパターンの時代劇を大量生産し、それでも客が入るからと調子こいていたら、黒澤明のような全く異質な天才が現れるや、あっという間に時代遅れになってしまい、衰亡に向かって一直線(いわゆる三十郎ショック)。東映は時代劇そのものを捨てて任侠路線に活路を見出し息を吹き返すのだが、そこでもやっぱり全く同じパターンを繰り返す。そしてその後の実録ヤクザ、異常性愛……。全部同じ。
これが東映という会社の体質かというと、それもまたちょっと違う。東宝もまた同じだからだ。マンネリ大量生産→飽きられる→別の路線を開拓、この繰り返し。出し惜しみしながら続ける、ということができない。これは映画業界の宿痾みたいなもののようだ。
映画作りというのは博打的な要素が非常に強い。一作作るのに金はたくさんかかるし、それがヒットするかどうかは実際に公開するまでわからない。だから、どの程度の客が入るかが、ある程度予想できる「シリーズ物」はものすごく貴重なのである。そしてシリーズの延命が自己目的化して、内容よりも話題作りが優先となり、作ってる方も見ている方も楽しくない作品が延々と作られる、などという事態が容易に生じる。
映画というのは作品であると同時に商品である。どちらが欠けても成立しない。だが商品性は簡単に暴走して肥大化し、作品性を窒息させたりする。そうなると商品性もまた衰え、ジャンル自体が潰える。アニメや特撮の場合は、ジャリ番という差別意識がそれをある程度食い止める役目を果たしていたが、今や仮面ライダーもスーパー戦隊も、もはや閾値を突破したような感じがする。もはや後戻りはありえない。(続く)
白倉伸一郎の降格(中編)
(前からの続き)
東映がピンチに陥ると、ライダー、プリキュア、戦隊はいつでも駆けつけてくれます。今やすっかり有名になった、東映の岡田社長(当時)の発言である。2009年1月29日、『仮面ライダー電王』の劇場映画第四弾の製作が発表された場でのこと。
あの時、ファンは真剣に怒りの声を上げるべきだった。一般映画で作った赤字をなぜアニメと特撮が補填しなければならないのか。しかし、ファンの中にはこの発言を喜ぶ者さえいた。岡田社長(当時)の狙い通りに。
無理もないことである。昔はアニメや特撮が、どれだけ金を稼いで東映に利益をもたらそうが、まったく評価されなかったからだ。ではなぜその風潮が覆ったかというと、一般映画が全然ヒットしなくなったからである。要するになりふり構っていられなくなっただけのことで、「仮面ライダーやスーパー戦隊って、意外と面白いし、しっかりと作ってあるんだなあ」という認識が社内で広まったからでは全然ない。もともと東映というのは、芸術だの文化だのいうよりも、とにかく金を稼いでくるのがいい映画で稼いでこないのは悪い映画だという風潮の割と強い会社だったが、それが一層強まることによって、ジャリ番に対する差別が解消されたのである。だがそれは、アニメや特撮が以前にも増して商業主義にさらされることをも意味した。そして岡田社長の下でライダー・戦隊映画の粗製濫造が進行する羽目になる。
今から思えば、いわれなき差別を受けていたことが、特撮映画のクォリティの低下に歯止めをかけていたのだった。なんという皮肉。
仮面ライダーという作品の素晴らしさを社内社外に知らしめたい、そしてジャリ番と馬鹿にする風潮を覆したいという思いが、白倉氏ら平成ライダーのプロデューサーたちにあったことは疑いえない。そしてその熱意と努力は実を結んだかに見えた。だがそれは結果的に、仮面ライダーの質を低下させるための露払いの役をも果たした。作品としての質が下がれば商品としての質も下がる。興行収入が減少傾向に転ずるや、岡田社長と白倉企画製作部長も退任させられることになる。(続く)
白倉伸一郎の降格(前編)

キネマ旬報 2015年3月下旬 映画業界決算特別号
去年の6月28日に、白倉伸一郎氏が企画製作部長(他に二つ兼任)からテレビ第二営業部長に異動になったというニュースが出た時に、これは降格かそうでないのかががネットでも盛んに議論になっていたが、社員でもなければどっちが格上の役職なのかも分からないので、結局は結論の出ないままに終わった。しかも、それを最初に報じた文化通信のサイトが「第一営業部」と誤記していたので余計に混乱した。ウィキペディアは今でもそうなっている。ついでに「制作」ではなくて「製作」。
で『キネマ旬報』の最新号に、東映に関する記事が二つほど載っていたら、企画製作部長というのは劇場映画のラインナップ全体に責任を持つような、なんか無茶苦茶重要な役職らしい。ということは降格なのか。といっても相も変わらず仮面ライダーに関係する部署にはいるらしく、ライダーファンにとってはどうでもいい情報のようだ。これを機会に何かが変わるわけではないのだから。
ただ、私のように昔から東映特撮を見続けてきた人間にとっては、どうにもやるせない気持ちになる。
昔から東映という会社では、ジャリ番は低く見られていた。ファンはそれを当然くやしく思っていた。子供向け番組で実績を上げ、一般向け番組で実績のない人間が、その両方を統括するような部署の長に昇進するなどということは考えられないことであったし(逆は当然問題ない)、だから白倉氏がトントン拍子で出世し、そのような重要な役職に上り詰めたことは、特撮ファンとしては当然うれしく思うべきことのはずだった。
ところが当の白倉氏は、この人の書いたものとかインタビューとかから判断するんだが、一般向けの映画を作ったりすることに、何の興味も関心もない人である(というか、多分仮面ライダー以外には何の興味もない人だと思う)。そんな人が大層な肩書を与えられて、やりたくもない仕事をさせられれば、大して成果をあげられないのは当然だし、その挙句に責任とらされて降格って、何じゃそりゃ。ふざけんな。
我々は子供向け作品に対する差別がなくなり、一般向け作品と対等に扱われる日が来ることを願っていた。しかし、こういう事態を望んでいたわけでは決してないはずなんだが……(続く)。
小林朝夫の大暴言
我々が若かった頃と比較して、今の特撮ファンをうらやましく思うのは、情報量の多さである。
そして我々が若かった頃と比較して、今の特撮ファンをかわいそうに思うのは、やっぱり情報量の多さである。
昔だって、特撮のスタッフやキャストの中には、こんなジャリ番は踏み台にして早くマトモなドラマに出たい、などと腹の中では考えていた人もいたことであろう(多分)。ヒーロー番組に出るのは子供からの夢でした、などと口先では言いながら。そしてインタビューを受けて本音が思わずポロッと出ることだってあったに違いない。しかしそんなものは活字になることはなかった。編集者がチェックをしていたからだ。もちろん今でもチェックはしているだろうけど、情報量が桁違いだから見逃すことも多い。しかも、ブログやツイッターのような無検閲メディアまである。
かつて特撮ファンはスタッフやキャストに対して大きな憧れを持つことができた。しかしそれは単に情報量が少なかったがゆえに、幻想が成立する余地があったからに違いない。
なんでこんなことを断言するのかというと、2011年2月17日に小林朝夫氏がツイッターに以下のようなことを書いたことがあった。小林氏というのは、『太陽戦隊サンバルカン』(1981年)でバルパンサー・豹朝夫を演じた役者のことである。
海賊戦隊ゴーカイジャーのプロデューサーにギャラいらないから出演させてくれるように交渉中です、、これは明らかに暴言であり、現在の戦隊のスタッフやキャストに対する侮辱発言である。
どう暴言なのか分かりづらいという人もいるであろうから念の為に説明すると、たとえて言えば、かつてプロ野球の名選手で、引退して二十年も経ち、ブクブクに太ってもう全然アスリートの体ではなくなった人が、球団創設何十年のメモリアルイヤーだということで、無報酬でいいから公式戦に出してくれなどと言い出したようなものである。
今の戦隊シリーズは素人レベルだ、と言い放ったも同然の発言である。
これは『ゴーカイジャー』のファンは怒るだろうなと思っていたら、そんな声は全然上がらなかったし、それどころか「感激です」なんてことを言うやつまでいた。もはや今のファンは、特撮番組に対して何の憧れも幻想も持っていないらしい。こういう状況はファンにとって幸福なのか不幸なのか。
少しもダイナミックでない宇宙刑事本

宇宙刑事ファンは昔からなぜか戦隊のことを目の敵にするようなところがあって、あまり好きではなかった。しかし『宇宙刑事ダイナミックガイドブック』などという、中身スカスカの本を「大満足」なんて言っているのを見ると、もはやこの人たちはリングに上がる気はないらしい。宇宙刑事シリーズは過小評価されているなんて言っていたけど、それを正当に評価されることを求める気はもうないんだな。そう思うとライバルを失ったような寂しい気になる。
過小評価なんて全然されてはいない、妥当な評価だ、と私は思う。高寺成紀氏みたいに「子供だまし」とまでは言わないけど、それほど革新的な作風というわけでもなかった。だいたい、たった三年しか続かなかったシリーズだし。メタルヒーローシリーズという言い方もあるが、あれは後付けであって、シリーズとしての一体性など存在しない。
最近になって急に宇宙刑事が復活したのも、別に宇宙刑事の面白さが今の時代に必要とされているという判断があったからではない。以下は別に私の憶測ではなく、白倉伸一郎氏などが公言していることであるが、仮面ライダーシリーズとスーパー戦隊シリーズの人気が下がる中、第三の柱を打ち立てたいという目論見があり、じゃあ何にしようかということで、宇宙刑事が選ばれたというだけの話。別になんでもよかったのである。しかし一旦決まった以上は盛り上げなくてはいけないというので、80年代特撮の金字塔だの、不朽の名作だのと今更になって急に持ち上げ始めただけであって、だいたいそんなに名作なら、なんで今まで塩漬けにしていたのか、説明してみたらどうなんだ。あまりにも見え透いた手口に、さすがに宇宙刑事ファンも乗せられた人は少数派のようで、平成仮面ライダーを休止させて日曜朝に宇宙刑事を復活させろと言っていた連中も、さすがに今ではほとんど見かけない。
それにしてもこの編集者の杉作J太郎という人、インタビュー下手だな。うまい人なら、相手をリラックスさせたり、また怒らせたりしながら本音をぐいぐい引き出したりするもんだが、しょっぱなから相手を不快にさせるなんぞ悪手もいいところだ。そして森永さん相手にパンチラのことで質問してやったんだぜーとはしゃいでる。中学生かお前は。(この本の中身に対する批判はいずれ)
これが平成ライダーのスタッフの本音なのか

(フォーゼの時は)主人公がリーゼントってだけで、相当抗議の嵐が来ちゃったらしくて、それが恐怖症になっちゃったみたいなんですよ。だから抗議されそうなことは先回りしてやめるっていうのは徹底してました。(『語ろう!555・剣・響鬼』から、虚淵玄氏の発言より)『語ろう!クウガ・アギト・龍騎』を読んだ時も思ったが、このレッカ社のインタビュアーって実はものすごく優秀なのではあるまいか。平成仮面ライダーのスタッフというのは、どいつもこいつも手柄は自分のもの、失敗したら人のせい、と思っているみたいで、そのような隠された本音をぐいぐいと暴く手腕にはほれぼれする。ぜひ戦隊シリーズのほうにも来てほしい。
虚淵玄氏にとって『鎧武』は会心の作ではなかったことは確実なようだ。しかしそれは自分のせいではなく、東映がダメだからであり、自分はその東映の方針に従って執筆を行なっただけだという主張をすることによって自分の名誉は守られると思っているらしい。たとえそれが本当でも、視聴者にとってはどうでもいい話だ。問題は完成した作品が面白いか面白くないかだけである。そしてスタッフ一同が面白い作品を作ろうと心を一つにしていない現場で作られた作品が、視聴者にとって面白いものであるわけがない。私自身は『仮面ライダー鎧武』は見たことはないし、一生見る気もないのだけれど。
平山亨『泣き虫プロデューサーの遺言状』という本にも書いてあったが、『仮面ライダーX』で敵の組織に「G.O.D.」というのを出したら宗教者から抗議が来たなんてこともあったらしい。訳の分からないクレーマーというのは昔からいた。その上、ちょっと暴力的な描写を入れればたちまち東映やテレビ局の上層部から文句が来る。そういうのと戦いながら、仮面ライダーやスーパー戦隊はずっと作られ続けてきた。抗議に屈する時もあれば、はねつける時もあった。「おもしろい番組にするためには、この描写は絶対に必要なのです」と断固主張することによって。抗議されそうなことには先回りして全部やめてしまおうというのが今の東映の方針であるならば、そうやって作られたものがつまらない作品であることは、見なくても断言できる。
仮面ライダー俳優の勘違い
仮面ライダーを演った俳優というのは、どうしてこうも変な人ばっかりなのだろうか。
『仮面ライダーX』の神敬介を演じた速水亮氏のブログの2月2日のエントリ「情けない・・・」。
我々、仮面ライダーを演じた俳優は連合赤軍かよっ!?
正義という矜持を、少なからず日々の暮らしの中に
生き様の中に、持って生きている。
それが、正義の味方を演じた俳優の責任だ。
まあ、まさか速水氏も本気でこんなこと考えているわけではないだろうが……。「正義という矜持を持って生きている」なんて、まともな分別を持った大人が言う台詞じゃない。怖すぎる。
こうしている今も中東で、ウクライナで、ナイジェリアで、人々が殺し合いをしている。それに対して別に何かしてあげるわけでもなく、日本みたいな豊かで安全な国でぬくぬくと生きている人間に「正義という矜持」も何もないだろう。たかが過去に正義のヒーローを演じた俳優だという程度のことで、何を思い上がっているんだろうか、この人は。
世界に広がる巨大な悪に対して、一人の人間など余りにもちっぽけな存在である。だから普通の人は気安く「正義」などという言葉を口にしない。いや、日本でも昔、世界の悪に対して本気で戦おうと勘違いした人たちがいて、そして彼らは「善意で舗装された地獄への道」を突っ走っていった。1970年代前半、つまり『仮面ライダーX』と同じ時代のことなんだがな。
平山亨氏を筆頭に、仮面ライダーのプロデューサーはやたらと、ライダーは普通のヒーロー物とは違うんだとか言う。正義のために戦うのではなく自由のために戦うヒーローなのだとかなんとか。それはこのブログでも散々書いてきたことだけど、そのライダーを演じた俳優が、こんな幼稚な善悪観を自分のブログで披瀝したりしているのを見ると、一体何が「普通のヒーロー物とは違う」んだか。
嗚呼、懐かしき「イスラム国」
「後藤さん殺害」か:「イスラム国」の声明全文
久しぶりに本格的な「悪の組織」を見たなあ。
「我々はお前たちの血に飢えている」などという、「イスラム国」のベタベタな声明文を読んでいたら、そんなことを思ってしまった。
スーパー戦隊シリーズに出てくる悪の組織は、1980年代頃まではこんな感じだった。交渉とか妥協とかいうものが入る余地は一切なし。こっちが滅びるか、あっちが滅びるかの二者択一。もちろん彼らにも言い分はあるが(サイクス・ピコ協定がどうとか)、それとこれとは別問題。世の中にはそういう存在があるのだ、ということを我々は子供の頃にスーパー戦隊シリーズを見て学んだのである、悲しいことではあるが。
私が最近の戦隊シリーズを見ないのは、敵が全然怖くないからだ。なんか妙に人間臭くて親しみばっかり湧いてくる。ヒーローたちも正義のためとは言いながら、スポーツやゲームのような感覚で戦っているようにしか見えない。もっとも、そういうことを批判する気もなかった。昔は日本の近くに「ソ連」という国があって、核戦争の危機は、人類を絶滅させる可能性が本当にあった。それに比べれば今の中国や北朝鮮の脅威なんか屁みたいなもんである。冷戦が終わって人々が恐怖を味わわなくて済むようになり、その結果としてテレビ番組から悪の迫力が失われたとしても、そんなことで文句を言ってはバチが当たる……。
と思っていたら、実は違っていたのである。世の中は全然平和になんかなっていなかった。単に日本人が無関心だっただけで、中東じゃあ延々ずっと殺し合いをやっていた。今回の事件も犠牲者がたまたま日本人だったからマスコミも騒いだし人々も関心を持ったに過ぎない。
この事件をきっかけにして、日本人の意識も変わるのだろうか。いや変わらんだろうな。ニュースを見てたら、安倍首相は例によって原稿棒読みの抑揚のない声で「罪を償わせる」などと言っていた。この人はやたら口だけは勇ましいことを言うが、別に日本も戦いに加わろうと声を張り上げるわけでもなくて、やっぱり他の国に金をばらまいて何とかしてもらおうということらしい。改憲派の脳内お花畑度は護憲派を上回っている。そして圧倒的多数を占める無関心派。クソコラ祭りと自己責任論の横行は海外でも報道されて、「日本人は薄情」「冷酷」「不気味」というイメージが世界中で急速に拡散中だとか。
『スーパーヒーロー大戦GP』における戦隊の扱いは?
今年3月21日公開の『スーパーヒーロー大戦GP』に戦隊が出ないことは、ほぼ確実と思われる。現在出ている予告映像や事前情報では、仮面ライダーの話だけ。戦隊ファンに劇場に来てもらおうという気があるとは全く思えない。たとえ出るにしても、おもちゃの販促のためにニンニンジャーがアイテムを使うプロセスを長々と写す程度のものであろう。
この件に関してライダーファンは、やっぱり、恥ずかしいとか悔しいとか思っているんだろうか。
仮面ライダーだけの映画を作りたいのであれば、『仮面ライダー大戦GP』という名前にすればよい。しかしそれでは予算もおりないのであろう。だから仮面ライダー以外のヒーローもたくさん出しますよという体裁だけとって企画を通さなくてはならなかった。ずいぶんと情けない話ではある。
「スーパーヒーロータイム」などという呼称が提唱されたのは2003年。それ以来、戦隊もライダーも両方見ましょうという雰囲気を作るため、テレビ朝日も東映も必死になってきた。しかしそれまでは、戦隊とライダーのファンの間に特別な親近感など全くなかった。二つのシリーズは歩んできた歴史も全然違うしファンの気質も全然違う。それどころか、ライダーの関係者もファンも、ずっと戦隊のことを下に見るような発言ばかりしてきたではないか。こういうことは、言った方はすぐに忘れても、言われた方は覚えてたりするのだな。
そして今でも、高寺成紀氏とか白倉伸一郎氏とか、戦隊ファンの目につかなさそうな所では、相も変わらず戦隊を見下すような発言を続けている。仮面ライダーシリーズは他の子供だましのヒーロー物とは違うんだ、改造人間の悲哀であるとか仲間殺しであるとか、高尚なテーマが盛り込まれているのだ、とかなんとか。このブログでもさんざん書いてきたことですが。
そうやって、今まで自分たちが見下してきた「仮面ライダー以外のヒーロー」の力を借りて金を集めて映画を作る気分はどうですか?
「イスラム国」の現実感のなさ、特撮ヒーローの困難
いったいこの現実感のなさはなんだろうか。
「イスラム国」によって日本人二人が拘束されたという報道が流されたのが1月20日。それを受けて、その「イスラム国」から送られた画像をもとにコラージュ画像が大量に作成され、ツイッターを通じて世界中にばらまかれている、などということが海外のマスコミなどでも紹介されているらしい。「日本のシャルリー」たちは、日本人には脅しなど通用しないということをクソコラでテロリストどもに知らしめた、とかなんとか好意的に扱った所もあるそうだが、それは結果論であって、単に多くの日本人は、この事件に現実感を感じていない、それだけの話だ。
これを「不謹慎」「平和ボケ」と批判して済むような話とも思えない。だいたい総理大臣にしてからが「テロには屈しない」と言ってみたり「人命第一」と言ってみたり。どっちなんだよ。口先だけは勇ましいが、具体的にどんな解決のイメージを持っているのか全然判然としないのは、政府を追及する野党やメディアも同じだ。もう日本は「イスラム国」から堂々と敵国認定されたわけで、「金だけ出す」などという従来のやり方を今後とも続けていけるとは思えない。事件が終わった後も、今後日本の外交はどうするのか。対米協調か独自外交か、決断を迫られているはずだ。それなのに、どいつもこいつも5800キロ離れた遠い外国の話というイメージしか持っていないように思える。いや、こんなこと書いてる私自身、頭で理解しているだけで、全然実感として感じることができていないから、偉そうなこと言う資格もないが。
日本でずっと特撮ヒーロー番組が作られ続けてきたのは、正義と平和を愛する人々の気持ちをずっとすくい続けてきたからだ。「人類絶滅を企む悪の組織」も、冷戦時代の国際情勢の反映であるということは、さんざん書いてきた。冷戦が終わってからは、新しい時代に即した「正義と悪」を描こうという挑戦がずっとなされ続けてきたはずだった。今の戦隊物は、正義のためと一応口では言いながら、もうスポーツかゲームのような感覚でヒーローは敵と戦っているようにしか私には見えない――などと書いたら「懐古厨死ね」と言われるに決まっているから今まで控えていたのだが、もう構わんだろ。そういう時代だ。
東映の取締役は算数もできない
「仮面ライダー2014年問題」とか「2014年危機」とか言われているが、それが計算間違いであるということについては、去年の10月26日のエントリで述べた。もっともこれは私自身が気づいたことではなく、ネットで前々から言われていたことであって、私はそれをまとめて整理しただけである。
だから、当然こんなものはとっくの昔に東映の人の耳にも入っているだろうと思っていた。ところが、どうも入っていないらしい。最近『語ろう! 555・剣・響鬼』という本が出たが、そこで白倉伸一郎氏が相も変わらず2014年問題について述べ立てていた。
これってかなりマズイ状況なのではあるまいか。
人間は誰にも勘違いというものはある。だからそんなものは厳しく咎めるものではない。問題は、白倉氏が勘違いをし、「白倉さん、それ計算が間違ってますよ」と忠告してくれるような人が周囲に誰もいなかった、ということである。周りは全部イエスマンということか。そういう人が、今現在取締役で、東映特撮の指揮をとっている。
白倉伸一郎という人にはファンも多いがアンチも多い。ネット上では「冷徹なビジネスマン」というイメージが横行している。会社に利益をもたらすためには何をすればいいのかを知り尽くしており、そのためにはファンの思い入れを踏みにじっても何とも思わない人、とかいうような。買いかぶりだと思う。たとえば『仮面ライダー大戦』の時なんて、今どき昭和ライダーと平成ライダーの対立をあおるとか、その勝敗をファン投票で決めるとか、なんかいかにも発想が安直で幼稚という気がする。本人は思いつきだけでしゃべっていることを、ファンは必要以上に持ち上げ、アンチは必要以上におびえ、周囲が勝手に盛り上げているだけに見える。そしてこんな簡単な計算違いにも気づかない。
そんなことしているから松竹に興収で抜かれたんじゃないの。
内田樹先生、そんなにお金が好きですか

東映、14年年間興行収入は116億円で31%減
松竹(139億)にも逆転されたということで、さっそく特撮ファンの間からは喝采が上がっている。
もちろん東映を憎んでいるのではない。今までのやり方ではダメだということに東映が気づき、心を入れかえることを願っているのである。
まあそれも無理だと思うけど。
内田樹という人がいる。この人の書くものは私も好きで、物の考え方をこの人から学んだこともあった。それが2005年くらいからあれよあれよという間に劣化が進行し、中身スカスカの本を大量に出しているというのが現状。最近の本は以前どこかで書いたことの使い回しばかり。対談本なんか特にひどい。このへんの事情は某映画会社とそっくりだから詳述しないが、深刻なのは、この人が資本主義の批判をしているということである。
「金は不浄のもの」という教育が日本から失われたのは嘆かわしい、などと書いている人である。その当人が、資本主義のシステムに首までどっぷりと浸って身動きがとれなくなり、駄本の濫発をしているのである。
どうも本人もその矛盾に気がついてはいるらしい。ツイッターでは定期的に、仕事を減らすぞ仕事を減らすぞというツイートが上がっている。にもかかわらず出版ペースは上がる一方。全力でペダルを踏み続けなければ倒れてしまう自転車みたいな状態。
話を東映に戻す。世の中には映画なんか作るより、もっと楽してたくさん金をかせぐ仕事はいっぱいある。それをわざわざ東映というヤクザ会社に入社したということは、よっぽど映画が好きな人たちに違いない。彼らがその「いい映画を作りたい」という初心に立ち返れば、再び東映特撮は輝きを取り戻すはずだ。……などとファンが夢想するのも無理はない。東映の減収に喝采を叫んだのも、多分そういう人たちだろう。しかし、内田樹先生が駄本を大量に出しているのも、東映が仮面ライダーの映画を粗製乱造しているのも、大本になるのは資本主義というシステムである。そしてシステムに対しては、個人の「心構え」だとか「志」だとかが太刀打ちできるものでは全然ない。このことは認識しておく必要がある。
まあ、仮に本当に東映が心を入れかえて、一作一作にじっくりと予算と時間を投入するという方針に転換したところで、粗製乱造が粗製寡造になるだけだろうけどね。
『仮面ライダー鎧武』の自己破産宣告
前回に引き続き『仮面ライダー鎧武』の公式読本の武部直美×虚淵玄の対談。
虚淵 まぁ、言ってしまえば「実験作」だと思うんですけど、こういったアプローチで1年やりきったということが大きいと思います。(中略)可能性を示したことで、少なくとも「平成ライダー」というシリーズに対する閉塞感のようなものは払拭できたんじゃないかと思っています。なにこの志の低さ。
作家が自作について「これは実験作です」などと言うことは、自ら失敗作だと認めるに等しい。そんなの創作の世界では常識でしょ?
要するにこの二人は、無難に60点を取りにいけば楽なのに、あえて新しいことに挑戦して100点か0点かという道を選びました、偉いでしょ、ということを言いたいらしい。そういうことは、100点をとって初めて胸を晴れることだ。実験してなおかつ成功した人は堂々と「成功作です」と言う。実験して失敗した人に限って「これは実験作です」という言い方をする。60点を狙って0点をとるのも、100点を狙って0点をとるのも、一緒のことだ。0点をとって「可能性を残した」もなにもあるか。
この対談では他にも、小さな子供には残酷なものを見せたくないという教育方針の家庭がどうのこうの。そんなことは仮面ライダーシリーズが昔から格闘してきたことだろう。いったい何が新しいのか。自己弁護満載の対談なのだが、よく考えたら私は『鎧武』は一度も見たことないし、平成仮面ライダーに何の興味もない。今の仮面ライダーシリーズがこんな甘ったれた言い訳の通用する世界になっているんだったら、私のごとき部外者が容喙する必要もなかろう。
ただ、武部氏は次の『手裏剣戦隊ニンニンジャー』のプロデューサーでもある。お願いですから、こういう気風は仮面ライダーだけにしておいて、戦隊に持ち込まないでくださいね。仮面ライダーでは何か新しいことに挑戦をしたというだけで評価されるのかもしれませんが(知らんけど)、戦隊の方では挑戦をして、なおかつそれを成功させて初めて評価されるのです。
「視聴率なんか気にしていない」という嘘
『仮面ライダー鎧武』の公式読本で、プロデューサーの武部直美氏とメイン脚本家の虚淵玄氏の対談が載っていた。『鎧武』なんか一話も見たことのない私であるが、仮面ライダーシリーズって今こんなに志が低くなっているのかとビックリした。
二点ほど触れる。その一つ。『鎧武』の人気について話が及んでいるのだが、話されているのは玩具の売上と、ファイナルステージの客の入りだけ。視聴率について触れないのは例年のことだが、なんと劇場映画の客の入りについても完全無視。ついに馬脚を現したか。
人気の話をしているのに、ファイナルステージのほうが劇場映画より重要なんてことがあるわけないだろ。
「視聴率なんか気にしていません」。ここ数年における東映特撮のプロデューサーの態度は一貫している。しかしそれは、録画機器の普及とか他にも色々理由があって視聴率が時代遅れの指標になったとか、そういうことではない。本当は気にしているのである。しかし体面が悪いから、気にしていないと言い張っているだけだ。
だいたい、本当に視聴率を気にしていないということであれば、このツイートなんだ!
でじたろう「鎧武の視聴率が上がってきているようで一安心」2013年11月18日視聴率が良くても悪くても何も発言しないのなら筋は通っている。しかしこの人達は、視聴率が良かった時だけはそれについて触れ、悪くなればダンマリである。これで「低視聴率は気にしていない」などと言ったところで誰が信用するか。
吉田メタル「第25話”グリドン・ブラーボ最強タッグ” 視聴率がかなり良かったらしく プロデューサーから お礼を言われました!!」2014年4月17日
白倉伸一郎「昨日の『鎧武』キカイダー編、なんと鎧武史上最高視聴率だったとかなんとか。ご覧くださった方々に、心から感謝です」2014年5月19日
2ちゃんねるの視聴率スレなんかでも、視聴率が低迷するとすぐに「視聴率なんかもう時代遅れの指標だ。玩具の売上がすべてだ」と擁護する信者が現れて、スレを荒らすのが通例だった(2013年度なんかは特にひどかった)。最近はそういうのも随分と少なくなったような気がする。
ついでに現在放映中の『仮面ライダードライブ』。第一話だけは視聴率は高くて、その時の関係者のツイッター・ブログ。
片岡鶴太郎「『仮面ライダードライブ』御視聴有難う御座います。お陰様で3年振りの高視聴率でした。有難う御座います」(無意味な改行は削除した)2014年10月6日その後『ドライブ』の視聴率は急落。当然のことながら、誰も触れなくなった。さて一年後、どういうことになっているのだろうか。(続く)
長谷川圭一「ドライブ! 初回の視聴率も好調のようで超嬉しいです!」2014年10月6日
仮面ライダーの人気低下は本当か
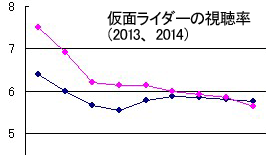
「仮面ライダー」人気低下か?クリスマス商戦で不人気ぶりが話題 アマゾンで投げ売り状態
アナウンス効果というものがある。仮面ライダーの人気は下がっていると、大した根拠もなく言い続けていると、本当に下がってしまう。そういう現象というのは実際に存在する。こういう記事が出て以来、さっそくネットのあちこちで「仮面ライダーのくせにバイクに乗らないのがいけない」とか「二話完結が飽きられた」などと百花斉放である。そしてそういうのに影響されて見なくなる人というのは確実にいる。
東映は抗議したっていいくらいのものだ。
だいたい元の記事だって、今年は仮面ライダーの玩具に品薄感がないという、そんなことを根拠に人気低下とか言うのも無茶な話である。個人的にツイッターとかやっているプロデューサーも多いんだから、反論すればいいのに。なぜしないのか。できないんだろうな、やっぱり。
だいたい玩具の売り上げというのは作品の人気に正比例するわけではない。玩具そのものの出来というのもあるし、いかに視聴者の購買欲を刺激するか、その戦略にも左右される。今年は『妖怪ウォッチ』の影響もあるだろう。それに『ドライブ』の売り上げが良くないといって、毎年200億売ってるのが今年は150億しか行かなさそうだ、という程度のものじゃないのか。そんだけ売れりゃ、スポンサーだって文句はつけられない。しかしネットの上では、玩具の売り上げ高が高ければ高いほど良い作品だ、とみなす風潮が猖獗を極め、前の年から一円でも下げれば失敗作呼ばわりされる。そもそもこんな風潮を作ったのは誰か。東映のプロデューサー自身である。昔は、たとえ口先だけでも、子供に夢や希望を与える番組を作りたいと言っていた。最近はもう露骨に金の話ばかりして恥じない人が多い。そしてその結果として、あやふやな根拠をもとにして仮面ライダーが不人気だという記事が出たところで反論もできない。自業自得である。
それにしても、『鎧武』で仮面ライダーシリーズ史上最低視聴率を記録し、『ドライブ』ではそれをさらに下回った(9話時点)。仮面ライダーの人気低下についての記事だというのに、視聴率については一切触れないとは。この記事を書いたのは、どんな書き方をすれば東映が困るか、知り尽くしている奴に違いない。
特撮技術の進歩は何のため?

佛田洋『特撮仕事人』
戦隊ロボの在り方を見ても、昔は1年に1体のロボットでやっていて、それがだんだん2号ロボ、3号ロボと増えていって、そういう進化がシリーズの面白さや発展に繋がったんだけど、以前に比べてロボに乗ることのありがたみが薄れてる気がするというか。昔は、“このロボがやられたら大ピンチなんだ!”という緊迫感があったけど、今は“やられても、また次のロボが出るんだろ”みたいな。(佛田洋『特撮仕事人』p.178〜179)断っておくと、佛田氏は別に今の東映の商法に対して批判的なわけでは全然ない。ただ戦隊シリーズの初期からスタッフとして関わり、『地球戦隊ファイブマン』(1990年)からはずっと特撮監督を務めている佛田氏が私と全く同じことを考えていたので、都合のいい部分だけ抜書きして、虎の威を借る狐をやろうと思った次第である。
私は『超新星フラッシュマン』の第15話をリアルタイムで見ているが、フラッシュキングの腕がもげ、火花をまき散らしながら倒れたシーンの衝撃は今でも忘れられない。なにしろ巨大ロボがシリーズ史上初めて敗北した回なのである。目の前で何が起こっているのか、理解するのにしばらく時間がかかった。今の若い人たちには、戦隊シリーズを見てこれほどの衝撃を味わうことなどないであろう。――なんて書き方をしたら自慢みたいに思われるだろうか。
また、この本では、佛田氏を筆頭とする特撮班が、面白い映像を撮るためにどれほど粉骨砕身しているかも書かれているのだが、会心の画が撮れたからといって、おもちゃの売り上げに結びつくとは限らないらしい。それよりも、たくさん出すことのほうが重要だと(p.165〜166)。売り上げのためには、質を高めるよりも量を増やすほうが効果的、そして量を増やすことは質の低下につながりやすい。
だからといって、じゃあ今からロボの数を減らせば、一体一体に対する子供たちの愛着が以前のように増すかといったら、それも無理だろう。単に物足りなく思われるだけだ。今の若い人たちに、『フラッシュマン』の第15話を見せたところで、衝撃なんか感じるとはとても思えんし。結局このまま物量作戦を続けていくしかないのだろうか。
昔はCGなんかなかったし、ミニチュア感丸出しの特撮や、不自然なオプチカル合成とかもあった。イラストがそのまま出てくることも。それでも別に大した不満はなかった。今は昔に比べて技術は格段に進歩し、にもかかわらず、子供たちが番組から感じる興奮や感動が、昔に比べて劣っているとしたら、いったい何のための技術の進歩なんだろう。
プロレスと同じ道をたどる特撮ヒーロー
「プロレスの試合に筋書きがあることくらい、ファンは昔から知っていた。知った上で楽しんでいたんだ」
プロレスファンはだいたいこういうことを言う(小林よしのり『ゴーマニズム宣言』2巻とか)。
嘘をつくな。
少なくとも力道山の時代には、観客は真剣勝負だと思って見ていた。だからレスラーも、観客に見破られまいと、体を鍛え、技を磨き、必死になって迫真の勝負を演出していた。時代が下るにつれ、プロレスにブックがあるという事実が知れ渡ってくると、技をかけられる側も協力しているということが素人目にも分かるような、不自然な技を出すことにも躊躇を感じなくなってゆく。昔と今とでどちらのほうが試合に迫力があり、ファンもドキドキしながら見ていたか、言うまでもなかろう。
プロレス人気の凋落に従い、「嘘と分かってだまされてあげる、それがプロレスの見方。まことにプロレスは奥が深い」などという、ひねくれた言い方で弁護する連中が現れ始める。ナマの現実の感動と、つくりものの感動と、どちらが優れているか、言うまでもないだろう。
で、それがどうも現在の特撮ヒーロー番組の置かれた状況に重なって見えて仕方がない。
昨今の、スーパーヒーロー大戦系のヒーロー総出演映画で、ストーリーの辻褄が合っていないとか、キャラクター改変だとかに対して批判が起こると、それに対する弁護の仕方は決まって「細けえことはいいんだよ」「どうせお祭り映画なんだし」「子供向け番組に何目くじら立ててんの」。
『スーパーヒーロー大戦GP』の発表を受け、「仮面ライダー3号とは何者だろう」とワクワクと議論にいそしんでいる人たちのネット上での書き込みを見ていると、衰退に向かっていた時期のプロレスファンと雰囲気がそっくりなんだが。そういえば、特撮ファン全体、作品に対して真剣に怒って批判している人も、その批判に対して真剣に擁護しようとする人も、一時期に比べてずいぶんと減っているような気がする。
1980年代と言えば軽薄短小の時代として知られるが、まさかそんな時代の亡霊と今になって邂逅を果たすとは、ちょっと信じられない気分である。そういえば、白倉伸一郎氏も、1980年代に青春時代を送った世代なんだっけ。関係しているのか……?
誰がスーパーヒーロー大戦を批判できるのか

レッカ社「語ろう! クウガ アギト 龍騎」(2013年)
『スーパーヒーロー大戦GP 仮面ライダー3号』の制作が先日発表になったというのに、今年はあまり批判の声に勢いがないような気がする。こんな映画は過去のヒーローを貶めるような内容になるに決まっているのだし、もう濫発はやめろという声が湧き上がるのが毎年恒例のはずなのだが。
この『語ろう』という本にも、宇多丸氏による『仮面ライダーディケイド』劇場版「オールライダー対大ショッカー」(2009年)の批判が収録されている。東映の特撮ヒーロー大集合系の映画に対する批判の典型的なものであり、内容自体は全くの正論である。だが、こんな批判のやり方には何の有効性もないし、共感の輪が広がることもありえない、という理解がファンの間にも浸透したということだろうか。遅まきながら。
この本の最大の目玉は、高寺成紀氏という人がここまでイタい人だということを明らかにしたことである。『仮面ライダークウガ』を、自分一人だけの力で成功させたと思っているプロデューサー、という噂は前から聞いていた。しかし『宇宙刑事』だの『仮面ライダーBLACK』だの、子供だましの作品ばっかり作って活気を失っていた当時の東映特撮を、『クウガ』が全部変えたという話が出てくるに及んでは、読んでいて開いた口がふさがらなかった。
宇多丸氏を含めた他の六人は、さすがにここまでイタいことは言ってはいない。だが、『クウガ』およびそれに続く平成仮面ライダー初期作品は、従来の東映の特撮ヒーロー物とは違っていたがゆえに素晴らしく、またヒット作になったのだ、という認識は、多かれ少なかれ全員に共通しているように見受けられる。新しい世代が新しいものを付け加えた、というのは事実である。しかし昭和ライダーのブランドの力がなければそもそも企画自体が存在せず、また戦隊やメタルを作り続ける中で維持されてきたノウハウがなければ、『クウガ』を完成させることもできなかった、という認識が余りにも薄い。
先輩たちに対する感謝の念を忘れ、全部自分たちの功績だとうぬぼれていた連中が、今度は自分たちが先輩の立場になったとき、後輩からどのような扱いを受けることになるのか。
『クウガ』や『アギト』、『龍騎』が成功したおかげで平成仮面ライダーは今なお続いている。それは事実である。そしてその恩を忘れ、その平成初期作品が持っていた志も魂も踏みにじり、過去のライダーたちを十把一絡げに扱った映画が毎年濫発されている。だがそれに対して怒る資格は誰にもない。それは「報い」というものだ。
東映ほどファンを大切にする会社はない(悪い意味で)

スーパーヒーロー大戦系の、戦隊・ライダーが大集合する映画のあまりの濫発ぶりに、東映というのはファンの気持ちを大切にしない会社だ、という声が巷に満ちている。しかしそれは言いがかりであると、声を大にしていいたい。
そもそも、柳の下にドジョウがいれば、十匹でも二十匹でも捕りつくさずにはおれない、それが東映魂である。それが顰蹙を買いトラブルの種をまき「義理欠く恥かく人情欠く」の三かくマークと陰口をたたかれる原因ともなる一方、大衆の求めるものは何かと常に血眼になって探しまくる、そのバイタリティが映画作りの原動力になっていたのもまた事実である。
こういう考えに私が至ったのも、東映の歴史についての本を最近ずっと読みあさっていたからである。時代劇もヤクザ映画もポルノも、ずっとそういう姿勢で作り続けてきたわけだ。そして今の戦隊・ライダーもまたその東映の血を濃厚に受け継いでいることは明らかである。ただし、ずっと小粒化した形で。
最近で言えば『仮面ライダー大戦』(2014年)。ファン投票をするとか言い出した時に、非難や落胆の声が上がったのは、手口の余りのセコさからだ。これが昔の東映であれば、昭和ライダーと平成ライダーが最後の一人になるまで徹底的にブチ殺しあう、それくらいのことはやっていたはずだ。今のサラリーマンプロデューサーにはそんな決断なんか下せるわけがない。適当に両者に花を持たせるような結末は、最初から目に見えていた。こんな安っぽい手口に食いつくのはネットイナゴくらいのものだろう。そんなに客を呼びたいのなら、吉永小百合を悪の女幹部役で呼ぶくらいのことはしたらどうなのか。嗚呼、豪放磊落、破天荒の伝統はどこに行った!
1980年代の戦隊ヒロインがあれほどまでに輝いていたのは何故か。女の人も男に守られているばかりではなく、きちっと戦っていくという所を子供たちに見せたい、などという思いがあったのは事実である。しかしそれは一面であって、女の子にミニスカはかせてキックさせたいとか、縛られて地面にのたうち回ってヒィヒィ悲鳴をあげる女の子を撮りたいとか、そういうギトギトした欲望が裏になかったとは言わせない。上品さと下品さは表裏一体のものだ。今じゃ坂本浩一程度で「エロ監督」とか呼ばれてるんじゃなあ。
エロだろうがグロだろうが、大衆はこういうものを求めてるんだと思えば何でもかんでもガツガツ喰らいつき、骨までしゃぶる。かつて東映が持っていた猥雑で下品なパワーはすでになく、かといって高尚な芸術理論なんかもともと持ってる会社ではない。ファンの期待に応えねばという気持ちだけは依然として旺盛だから、結局やってることがどんどんチマチマしてくる。
イケメン特撮ブームの裏で何が進行しているのか
12月1日のエントリの続き。竹熊健太郎氏のツイート「女性が見る特撮は私にとって特撮ではない。特撮魂が曇る。」について。この発言自体は擁護のしようもないが、それを叩いて正義感に浸っている人たちも、事の深刻さが分かっているとは思えない。
「子どもと一緒に番組を見ているお母さんたちは、亭主よりもかっこいいイケメンが出ているのなら、抵抗なく、応援してくれるものです(笑)。だから、以前の仮面ライダーを演じる俳優は、アクションが似合う武闘派のイメージがある、武骨なタイプが多くて、年齢も高めでしたが、平成仮面ライダーでは若いイケメン系の俳優を起用して、若々しいキャラクターにしました。初期の仮面ライダーにあった改造人間という暗く陰のある部分も描くのをやめて、変身した後もナマっぽい生物的なスタイルから時代を引っぱるクールなデザインに変えて、子どもや女性が見やすいライダーにしました」(なぜ「仮面ライダー」で若手俳優は成長するのか 輝く男の発掘・育成法(2))なんか無茶苦茶である。仮面ライダー1号・本郷猛役の藤岡弘氏だって、若い頃はさわやかなイケメンだった。年をとってから渋みのある顔になったのである。それに昭和の仮面ライダーも言われているほど暗くはない。むしろ平成のほうが「同族殺し」という、仮面ライダー本来のテーマと真剣に向かい合っている、という人もいるくらいである(見たことないから知らんが)。
いったい誰がこんなことを言っているのか。
東映の鈴木武幸専務である。
鈴木氏と言えば、スーパー戦隊シリーズのプロデューサーを十五年も連続して務めた人である。しかし平成仮面ライダーにはほとんどタッチしていないはずだ。確かに『クウガ』のプロデューサーではあった。途中からだが。管理職の人がそれほど現場の実務にコミットしていたとは思えない。そしてググってみると、平成仮面ライダーの成功は、自分の手柄だと思い込んでいるような発言も多々出てくる。
これはかなり深刻な事態である。女性の視聴者を獲得するためには、ぬるめの話にする必要があるのだ、という先入観を持っている人間が、上の方に居座っているということだ。こういう管理職の連中が現場に口出しをしてきたら、一体どういうことになるのか。
竹熊健太郎などという一編集者の戯言なんかとは比較にならない。
それにしても、この記事、この後で戦隊シリーズでは仮面ライダーほど役者がブレイクしていない、という話になるのだが、その理由の分析は読んでいて「なるほど」と思わせる。十五年も戦隊の現場に関わってきたのは伊達ではないということか。
だったら戦隊の話だけしてろよ。
鈴木武幸氏という人は、私の尊敬する人の一人である。戦隊シリーズ第一期は、女戦士は男たちのオマケという雰囲気を、完全に払拭するには至らなかった。払拭できたのは、鈴木氏がチーフプロデューサーに就任してからである。女の人もきちっと生きていける、そういう時代の理想の女性像を示していきたい、と言っていた鈴木氏である。その人が今じゃあ、女の人に見せるには、暗くて陰のあるものじゃダメ、どうせ顔しか見てないんだし、なんてこと言ってるのか。
東映の拝金主義と『がんばれ!! ロボコン』
1〜26話 一期生編 70点
27〜50話 二期生加入編 80点
51〜72話 大山美容院編 60点
73〜94話 三期生編(前) 20点
95〜118話 三期生編(後) 20点
「したがって、総合評価、『がんばれ!! ロボコン』50点」
「えーっ! なんでなんで!? 超合金もたくさん売れたし、ポピーさんを大儲けさせたんだよ!」
「キャラクタービジネスに関しては100点だった。
しかし、人気が出たために番組の引き伸ばしを図ろうと無理をしたため、二年目以降になるとマンネリの話が続出した。それにロボコンが成長してしまうと物語が終わってしまうという制約から、ロボコンを同じ失敗ばかり繰り返している、向上心のないロボットであるかのように描かざるをえなくなってしまった。
たまにロボコンが活躍しても、無理矢理に減点の種を見つけてハートマークをとらせないという姿勢もあからさますぎた。
それに超合金を売りたいがために、次から次へと新しいロボットを登場させる。三期生になると全然キャラが立っておらん。ロボメロなどロボペチャの下位互換にしかなっていない。
その上、マンネリを打破しようと焦って、ロボチャンなんかを出し、ご都合主義的なストーリーのためにロビンまでものすごく間抜けなキャラクターにしてしまったではないか。
何よりいけないのは、おもちゃの売上を伸ばすことに目的を特化させ、視聴者の子供たちを楽しませるという本来の任務をおろそかにしたことだ。この番組がなまじ成功してしまったがために、東映の姿勢が完全に固まってしまい、これが二十一世紀になってもなお続いているんだぞ!
したがって50点減点。50点だ」
「うららぁ〜」
東映特撮YouTubeで『がんばれ!! ロボコン』全話視聴完了。これを見ると、東映の拝金主義的な姿勢ってのは最近になって始まったことではないんだなあ、とつくづく思った。義理欠く恥かく人情欠くの東映三かくマークは伊達じゃない。
ただ昔は才能のあるスタッフもたくさんいた。職人魂と商人魂がガッチリと組み合わさって、ヒット作をたくさん作ることもできた。その後職人としての腕は落ちる一方なのに、商人としての才は健在なままだから、ゼニゲバ体質だけが目立ってしまうということなのだろう。
ちなみに職人魂だけがあって商人魂がなかったのが円谷プロ。
特撮と『なぜ時代劇は滅びるのか』

9/19のエントリのコメント欄で勧められた本、結局読んでしまった。多くの特撮ファンが「対岸の火事ではない」という反応を示しているのもうなずける。特に『水戸黄門』に関する記述は衝撃的だ。
『水戸黄門』がまだ人気があった時にも、やはり批判はあった。あんなマンネリのワンパターンのどこが面白いのかと。それに対する反論は、「大いなるマンネリ」というものだった。マンネリの作品を作る事こそが実は本当に難しく、本当に素晴らしいことなのである、と。しかしそれは真実なのは半分だけで、残りの半分は嘘だった。大いなるマンネリという開き直りが、実は時代劇衰亡への道を着々と用意していたのである(これは私の解釈がかなり入った要約なので、詳しく知りたい人はこの本読んで下さい)。
そして特撮ヒーロー(特に戦隊)もまた、マンネリがあたかもプラスの価値を持つかのように語られることの多いジャンルである。「様式美」とか言い換えて。
これは確かに他人事ではない。
ところで、この本は業界の内部の人たちにはどのように読まれているのだろうか、と思って探したら、こんなのが出てきた(抜粋)。
切通理作 10月25日過去形かよ!
『水戸黄門』が途中から老人向けに特化した為に時代劇ジャンルの衰退を招いた事を春日太一さんは『なぜ時代劇は滅びるのか』で指摘していますが、SF特撮映画も子どもが喜ぶからといってそこに傾斜した時代がありました。
確かに特撮ライターなんてものは、「この作品をほめる文章を書きなさい」と編集者に言われたら、その通りの文章を書くだけの職業だから、大して期待もしていなかったが、それにしてもひどい。時代劇ではそれなりに志の高い人がこうやって本を出しているのに対して、特撮の方はなんという違いだろう。
『利家とまつ』以降の、大河ドラマが女に媚びだしてからおかしくなっていったという論に対しては、疑問がなくはない。それでも一応論拠を示した上での議論である。この本を読んでいる最中に、竹熊健太郎という人が、あまりにもレベルの低い議論をやってツイッターを炎上させているという情報が入ってきた。特撮の方はなんかもう色々終わっているな。
竹熊健太郎「女性が見る特撮は私にとって特撮ではない。特撮魂が曇る。」
スーパーヒーロー大戦は作り過ぎか?
1956/1/15 赤穂浪士 天の巻・地の巻(松田定次)
1957/1/3 任侠清水港(松田定次)
1957/8/11 水戸黄門(佐々木康)
1958/1/3 任侠東海道(松田定次)
1958/8/12 旗本退屈男(松田定次)
1959/1/15 忠臣蔵 桜花の巻・菊花の巻(松田定次)
1959/8/9 血斗水滸伝 怒涛の対決(佐々木康)
1960/1/3 任侠中仙道(松田定次)
1960/8/7 水戸黄門(松田定次)
1961/3/28 赤穂浪士(松田定次)
1962/1/31 天下の御意見番(松田定次)
1963/1/3 勢揃い東海道(松田定次)
出演者の一人が自分のサイトでフライング発表をしたせいで、来春もまた歴代スーパーヒーロー大集合映画が作られることが明らかになった。もう毎年やる方針のようだ。
そして批判の声も多い。オールスターというのは、たまにやるからこそワクワクするのである。安直に客を呼べるからといって毎年やっていたら、興奮も感動も下がる一方じゃないか、と。
しかし本当に作り過ぎなのだろうか。
かつて東映時代劇は、やたらオールスター映画を作っていた。片岡千恵蔵と市川右太衛門という、二人の重役スターが一緒に出てる映画だけ挙げてみてもこの通り。他にも、『風流使者 天下無双の剣』とか『天下の伊賀越 暁の血戦』とか(いずれも1959年、松田定次監督)、豪華キャストの映画が大量に制作されていた。片岡・市川の他に大友柳太朗、月形龍之介、東千代之介、大川橋蔵、中村錦之助、美空ひばり……。普段は主役しか演らないようなスターたちが、次から次へと目まぐるしくスクリーンに登場、観客はその度に「待ってました!」と心のなかで叫ぶ、まあ、それだけの映画だったのだが、客の入りはよかったらしい。そしてそんな映画を大量に作っているうちに、やがて衰亡に向かっていったわけである。
1956年は東映創設五周年であり、『赤穂浪士 天の巻・地の巻』はいかにも「満を持して」という感じだったのだろう。それが好評を博したために、あっという間に年に二回のペースが定着。現在のスーパーヒーロー大戦の映画は年に一回であることを考えると、まだ少ないとか思っていそうだ。ちなみに松田定次というのは当時の東映時代劇のエース監督で、その下で助監督を務めていたのが八手三郎こと平山亨氏である。
時代劇のスター俳優というのはプライドがやたらと高い。そんな人たちをきちんと捌いて一本の映画を作るというのも、並大抵の苦労ではなかったようだ。全員にきちんと等分の見せ場を設けなければならない。誰かが誰かの引き立て役になったりするようなシーンなどもってのほか。そんなことばかりに神経を使って撮影をしていれば、ストーリーのほうが疎かになりそうなもんだが、それは別に構わなかったらしい。
現在のスーパーヒーロー大戦を見ていると、確かに東映時代劇のオールスターの伝統を忠実に引き継いでいるようにみえる。悪い部分だけ。
東映特撮ヒーローは本当に時代劇に源があるのか
しつこく『泣き虫プロデューサーの遺言状』の話。平山亨氏という人は本当に、死ぬまで子供の心を持った人だったのだなあと、つくづく思った。悪い意味で。
自分のことを本当に尊敬し慕ってくれるファンと、「平山亨」というネームバリューを利用しようと近づいてくる人とを、見分ける目を死ぬまで持つことがなかったようだ。晩年「監修・平山亨」というクレジットのある映像作品が何作か作られたが、これは内容についてはノータッチで、名前貸してくれと言われて貸しただけらしい。そういうことをやっては駄目だろ。そんなことするから、業界ゴロが近寄ってくるんだ。唐沢俊一とか。
そういう連中にとっては、平山亨のネームバリューが高ければ高いほどよい。だから仮面ライダーやスーパー戦隊について、あれも平山さんが考えたことだ、これも平山さんのアイディアだ、などと吹聴し、平山氏が積極的に否定して回らない限り、それが定着する。そういう連中に囲まれていると、平山氏本人もまた仮面ライダーやゴレンジャーについて、なんでもかんでも自分で考えたみたいに思い込み、うっかりインタビューでそんなふうにしゃべったりするのだろう。本人に悪気はないんだろうとは思うが。
私は別にプロデューサーの手柄話なんかに興味はない。純粋に、『ゴレンジャー』がどのような経緯で企画され、制作に移されたかについて知りたいだけである。そういう人間にとっては大迷惑な話である。
特撮ヒーロー番組において東映が一人勝ちを収めることができたのは、時代劇の下地があったからだ、ということがよく言われる。それを否定するわけではない。だが、それも単に一要素に過ぎないものを、平山氏の取り巻きが過度に強調している可能性もある。『ゴレンジャー』の頃になると、時代劇というよりは刑事ドラマの手法の影響のほうが大きいような気がする。ちなみに平山氏は東映京都撮影所出身、吉川氏は一般ドラマ出身。
批判がましいことばかり書いてるが、私だって数多くのヒット作を手がけた平山氏の業績に対しては、尊敬の念を抱いている。その偉大なテレビプロデューサーが、あれも俺が作った、これも俺が作ったなどと、無様な姿を晒して晩年を過ごしていたかと思うと胸が痛む。そして平山氏が亡くなった今、業界ゴロどもが次のターゲットとして狙いを絞っているのが息子さんというわけか。
もう勝手にしろ――『シャイダーNEXT』感想

私の場合は彼を信じてくれたから、がんばれたんだけどないきなりこれかよ。
「彼が信じてくれたから」なのか「彼を信じていたから」なのか。その両方が入り混じった気持ちを表現するセリフ……なわけないわな。単に仕事が雑なだけだ。
これは60分間の映像の中で、アニーが大を、大がアニーをパートナーとしてどのように思っていたかを示唆する唯一のセリフである。それが日本語としておかしいんじゃ話にもならん。
森永奈緒美さんはこれを機会に本格的に女優業に復帰する気など全くないらしい。こんなものに出たところで自分にとっては何のプラスにもならないわけだし、頼まれたから仕方なく出てやったという感覚だったのだろう。初代シャイダーの円谷浩氏は絶対に出演できない事情だし、また予算も時間も碌にかけられないVシネマである。あなたが出なければセールスが悲惨なことになるのですと言われれば、そりゃ断れんわ。ファンにとっても、二度と顔を見せることはないと思われていた人が顔を見せてくれたのである。文句を言ったらバチが当たる。
しかしそれにしてもなあ。
森永奈緒美と言えば、特撮界におていは伝説的女優の一人である。私は当時から文句言いだったからファンにならなかったけど、みんながこぞってアニー、アニーと夢中になっていた気持ちもよく分かった。その人に、こんなしょうもない仕事をさせるのか。モグリの医者という設定も、何が面白いのかよく分からないし。沢村大のその後に関しても、「視聴者に解釈を委ねる」と言えば聞こえはいいが、要するに逃げだなこれは。
ストーリーについては特に何か言うこともない。戦隊やライダーでこんな話作ってたら、ボロクソに叩かれていただろう。
しかし今の時代、坂本浩一程度で「エロ監督」なんて呼ばれてんのか。
仮面ライダーのプロデューサーの自己顕示欲
引き続いて『泣き虫プロデューサーの遺言状』について。平山亨氏に対しては私はあまり知らなくて、たくさんのヒット作を生み出した天才的なプロデューサーという印象を漠然と抱いていただけであったが、この本を読んで印象が変わった。『変身忍者嵐』は序盤は『ウルトラマンA』に視聴率で勝っていたとか、信じられないことが書いてあって、あまり信憑性の高い本ではないようだが。その本書p.337
僕がプロデュースした『仮面ライダー』のファンに、『平成仮面ライダー』を仮面ライダーとして認めようとしない子がいるんだ。そんなことを言わずに寛容に観ればいいのに。この人本当に何も分かっていないんだなあ。
昭和仮面ライダーは、視聴率で前作を上回った作品をただの一作も生み出すことができなかったという事実を、知らぬはずはあるまい。仮面ライダーというブランドは、あのままでは先細りになる運命だった。平成仮面ライダーが成功を収めることができたのは、昭和仮面ライダーからの流れを断ち切ったからである。昭和ライダーに思い入れのあるファンから「あんなものは仮面ライダーではない」と言わることこそが、平成ライダーにとっての勲章なのである。――だったら仮面ライダーなんて名乗るな、という批判が来そうだが、いやまあそこは「大人の事情」というやつだ。今の東映特撮のスタッフには、一から新しいものを作り上げるだけの能力はもはやない。だから仮面ライダーの名前を借りているだけ、そんなことはファンなら誰もが知っている。最近では『鎧武』なんてそれこそ「あんなものは仮面ライダーではない」という声が上がらなきゃいけないはずで、しかしそんな声は全然聞かない。そっちのほうこそ仮面ライダーにとって危機だろう。
自分は平成仮面ライダーの面白さが分かるんだ、自分はまだまだ現役の人間なんだ、と必死にアピールする姿勢が、若者に擦り寄る年寄りみたいで見苦しい。
平山氏が平成仮面ライダーなんか理解できるわけないだろう。氏にとって理想の映画とは、インディアンを騎兵隊がブチ殺しにする西部劇である。「正義の相対性」などという考えが理解できる人ではない。仮面ライダーの企画会議には脚本家の市川森一氏も参加し、「正義のために戦う、なんてやめましょう」と提案したというのは有名な話である。そして実際に出来上がった番組では、仮面ライダーは普通に正義正義と叫んでいた。そして「市川先生のアドバイスのおかげで、『仮面ライダー』は他のヒーロー番組とは一線を画す存在になったのです」などとぬけぬけと言っていたりする。
前にも書いたことだが、なんで仮面ライダーのプロデューサーというのは、ああも自己顕示欲が強い人たちばかりなのだろう。本来プロデューサーって裏方だろ。平山氏の場合は、『ひめゆりの塔』のような高尚な文芸作品に対するコンプレックスから、結局一生解放されることがなかったようにも思える。そういう部分が高寺成紀氏や白倉伸一郎氏に受け継がれているんだろうか。平山氏ほどの実績もないのに。
そういう気風、頼むから仮面ライダーだけにしておいて、戦隊に持ち込まないでくださいね。
平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。

テレビの昭和ライダーではこうした主題を十分展開できませんでしたが、それでも多くの視聴者が『普通のヒーロー番組とは違う、暗い雰囲気の話』と感じていた。この本質をおさえれば、表面上は荒唐無稽でも現実との接点を保った仮面ライダーをつくれると考えています。(白倉伸一郎インタビュー「仮面ライダーの敵」 『朝日新聞』2013.4.12)
仮面ライダーやスーパー戦隊を作ったプロデューサーのインタビューを読んでいると、首を傾げたくなることがよくある。自分の作っている作品をやたらと高尚・高級なものとして持ち上げたり、自分の手柄を大きく見せようとしたり。もっとも、インタビューとは元々そういうものかもしれない。だから、仮面ライダーは初期の怪奇路線をやめて雰囲気を明るくしてから人気が出たのが真相だ、とかそういう突っ込みはやらない。問題にしたいのは「仮面ライダーは普通のヒーロー番組とは違う」という発言の方。
平山亨氏や吉川進氏や鈴木武幸氏など、昔の東映のプロデューサーも、おかしな発言をすることはある。しかしこういう、自分の作っている作品だけは他のジャリ番とは違うんだ、みたいなことを言うことはなかった。本心ではどう思っていたかは知らない。しかし世間から見ればみんな同じようなものである。そんなみっともない発言はするまいという意識は共有されていた。
この手の発言が増えたのは、平成仮面ライダーからである。高寺成紀氏などは『語ろう!クウガ・アギト・龍騎』(2013年)において、自分が入社した当時の東映特撮がいかにチャチな子供だましであり、それに比べて自分の作った『クウガ』は……なんてことを延々としゃべっていた。過去の栄光にすがる以外にない人だから、気持ちは分からんでもない。しかし取締役にまで出世したはずの白倉伸一郎氏までこんな発言をするとは。良くも悪くも冷徹なビジネスマンだと思われている人だが、意外とコンプレックス持ちなのだろうか。
私は戦隊にしか興味がないので、平成仮面ライダーは見たことがない。見たほうがいいのだろうか、と時々思うことはある。しかし作ってる連中がこんなんばっかりじゃあ、下品さが伝染りそうな気がしてどうにも踏んぎりがつかない。なぜかスーパー戦隊を担当したプロデューサーには、こういうこと言う人はあんまりいない。何が違うのだろうか。
こんなので満足なのか――『シャリバンNEXT』感想
「最近の若者はなってない。俺達が若い時はこうではなかった」
などという不満を日々募らせているおっさんたちに、溜飲を下げさせる。Vシネマ『宇宙刑事シャリバン NEXT GENERATION』はそういう映画。
伊賀電(初代)から日向快(二代目)へと、シャリバンの名が受け継がれる物語。快が電から学び、電もまた快から学び、二人とも成長していく、というのではない。一方的に快が電から学ぶだけの話である。そして「宇宙刑事とは何か」と迷っていた快は、一人前へと成長し、電に感謝して深々と頭を下げる。
若い人に受けることは最初から全然考えていないのはいいとして、おっさんが見ても面白いのだろうか。快が得た「宇宙刑事とは何か」に対する答えというのは、まんま1980年代のヒーローの価値観なのである。それは当時であれば、わざわざ学習するまでもなく、ヒーローの誰もが自然に身につけていたものだ。努力して身につけようとする、もうその時点でシャリバンの名を受け継ぐ資格はないし、そんなもん受け継がなくていい。1980年代に子供時代を過ごし、ヒーローの活躍に胸をときめかせ、そして今おっさんになった人たちなら絶対に分かっているはずのことと思ったが。
私は今のスーパー戦隊や仮面ライダーにも色々問題があることは承知している。しかし「不易流行」をめざして頑張っている、ということだけは事実である。戦隊やライダーが毎年戦っているリングに、宇宙刑事も上がってくるのかと思ったら、早々に降りてしまったようだ。
それでもネット上の感想を見ていると、ファンも手放しで喜んでいるわけではなさそうだ。平成宇宙刑事として今後シリーズ展開するのであれば、このままVシネマで続けてほしい。そういう声が圧倒的である。
渡洋史氏(伊賀電役の人)のブログを見たら、このVシネマがバカ売れして、劇場映画やテレビシリーズにつながることを期待するとか書いてある。分かっていないのは作り手の側だけのようだ。
なぜ「懐古厨」の反対語は存在しないのか
「スーパー戦隊シリーズの時代区分」を書いていて「懐古厨」なんて言葉をつい使ってしまって(書き直したけど)、ふと疑問に思ったのだが、「懐古厨」の反対語って一体何だろう? 「新規厨」という言葉はあるらしいが、実際に使っているのを見たことがない。
たとえば原発をめぐる議論なら、「安全厨」だの「危険厨」だのとそれぞれ相手を罵っていたりする。それに対して「嫌韓厨」という言葉はあるが、「親韓厨」などという言葉は滅多に使われることはない。「原作厨」はあるが「原作離れ厨」となると概念自体が存在しない。……などと考えていたら、だいたい事の本質が見えてきた。
日本人にとって韓国とは「嫌い/嫌いではない」という問題なのである。「嫌い/好き」という問題ではない。韓国叩きを見てゲンナリする、という人は多いが、別に自分の好きな国が叩かれているからゲンナリしているわけではない。「原作にこだわる/原作にこだわらない」という対立はあるが、「原作から離れるべき」などという立場は存在しない。
要するに、「昔は良かった」という人がおり、それに対して受け身で「いや、昔もそんなに良いことばかりではなかった」と反対する人はいる。しかし積極的に「今のほうが昔より良い」などと主張する人はほとんどいない。「懐古厨」という言葉は存在し、その反対語が存在しないという現状は、そういった風潮を反映したものである。
これって実は相当恐ろしいことなのではあるまいか?
「今の日本はどんどん悪くなっている」。この意見が本当に正しいかどうかについては、軽々しく結論を下せる問題ではない。肝心なことは、みんながそう思っているということである。未来に希望はないとみんなが思っていれば、当然社会から活力は失われ、本当に希望のない未来が到達する。高度経済成長期の日本では、「昔は良かった」なんて思っている人が、そんなにいたとは思えない。
などということを考えていたら、映画『仮面ライダー大戦』のことを思い出した。昭和ライダーと平成ライダーとを戦わせ、どっちが勝つかをファン投票で決めるだなんて発表があった時の、ネット上のしらーっとした空気を思い出す。炎上商法にはもうウンザリ、というのもあったが、そもそも平成ライダーを昭和ライダーと対等の土俵に立たせるなんて、誰も望んではいなかっただろう。平成は昭和の恩恵を受けているけど、昭和は別に平成から何も受け取ってはいないんだよねえ(考えてみれば当たり前のことだが)。
しかも票数の操作までしていたとか。もう、なんと言ったらいいのか……。
「仮面ライダー2014年問題」という予言の自己成就
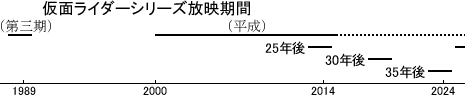
『仮面ライダー鎧武』の年平均視聴率が5.2%という酷さだったので、東映の白倉伸一郎氏の慧眼を称える声がネット界隈に満ちている。なんか、白倉氏が2014年ごろに仮面ライダーシリーズが危機に陥ることを、ずっと以前から予測していたらしい。
予測してたんなら対策しろよ。
しかもその予測の根拠、なんかものすごく変。
(1)仮面ライダーを子供の頃に見なかった人間が親になると、子供もまた仮面ライダーに興味を持ちにくい。その弊害が現れるのが2014年頃。
(2)しかしそこを乗り切れば、『クウガ』を子供の頃に見ていた人間が親になり、子どもと一緒に見るようになる。それまで5年の辛抱。
仮面ライダー第三期の最終作『BLACK RX』が終わったのが1989年。2014年といえば25年後になる。また『クウガ』は2000年の作品だから、2014+5年は19年後。
つまり、人間というものは19歳になったら子供を作り始め、25歳になった途端にピタリと作るのをやめる、ということを前提にしていることになる。
一体どこの国の話をしているのだ。
普通こういう議論では、一世代は30年として計算するのが普通である。父子の年齢差はだいたい25〜35と見ておけばよい。つまり、仮面ライダーシリーズ第三期を子供の頃に見ていた男の子が親になり、その子供がライダー適齢期に入る、そういう子供たちが2014年から増えていくのである。いったいどこが「危機」なのか。
おかしな点は他にもある。子供の頃にライダーを見ていなかった人間が親になると、その子供がライダーに興味を持ちにくくなるというが、戦隊やメタルヒーローをやっていただろう。ライダーの関係者というのは、とにかく戦隊やメタルを見下したがるが、オタク的気質のない一般人にとっては、みんな一緒である。
「予言の自己成就」という言葉がある。さして根拠もなく「こうなるぞ」と言っていると、人々は無意識的にそれに影響を受けた行動をとってしまい、結果として本当に予言が実現してしまう現象のことである。地位の高い人の発言は、そのような事態を起こしやすい。だから発言は慎重になる。
白倉伸一郎という人、取締役にまで出世して、いったい何をやってるの。
追記
なぜ『仮面ライダー鎧武』の視聴率は低いのか
断っておくが、私は『鎧武』は見たことがない。こういう人間が口出しをしていいものかとは思うが、まあ現在仮面ライダーシリーズが抱えている問題は、「スーパー戦隊シリーズの視聴率(改訂版)」で書いたこととほとんど変わらないし、他に真剣に考察している人もいないみたいなので、まあいいか。
『鎧武』の視聴率が低い原因は、どう考えても十月開始のせいだろう。
昨年までは九月開始であった。仮面ライダーにとって、クリスマス商戦の重要さは今さら言うまでもないし、年内にグッズは全部作中に出しておかなければならない。その期間が一ヶ月減った。そのためストーリーの盛り上げを二の次にして、とにかくキャラクターやアイテムを劇中にドカドカ出すことに専心しなくてはならなくなった。虚淵玄氏も確かそんなことをしゃべっていたはずである。だいたいこういうことは十月開始という発表がなされた時点であちこちの掲示板などでも危惧されていたことである。
そしていったん離れた視聴者は、その後どれだけ面白くなったところで再びテレビをつけることはない。そういうものである。
スーパー戦隊に比べて、仮面ライダーの方はまだしも新しいことにチャレンジしようという精神を持っている。そのためにわざわざ外部から特撮未経験の脚本家を招聘したのであろうが、その人の持ち味を存分に発揮させるための環境を整えるのであれば、販促計画を根本的なところから見直すか、それとも今年一年間は将来への投資と割りきって、売上が落ちても構わないと腹をくくるべきだった。なんでこんなちぐはぐなことになっているのか。
というか、そもそもなんで十月開始にしたのだろうか? 視聴者の多くも疑問に思っているはずのことを、どうして特撮雑誌はプロデューサーにインタビューしに行かないのか。それが不思議である。
販促に熱心なのはいい。今の東映特撮の問題は、販促だけが大事で、他のことはどうでもよくなっていることである。『鎧武』はその状況を打破するために送り出したのではなかったのか。その『鎧武』、玩具の売上だけは良いらしい。
こんなことで本当にいいのか?
公式に失敗作認定された『ギャバン THE MOVIE』
白倉伸一郎氏「決して失敗だったとは言いたくないですが……」
プロデューサーという立場にあるものが、こんなことを公の場で言っていいのだろうか。これって、失敗だったと言ってるのと同じだぞ。
『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』(2012年)は私は見ていない。見る予定もない。それは、誰の目から見ても失敗作としか言いようのない、ひどい出来ばえの作品だったのだろうか? だからといって、こんな発言をしていいとは思えない。
たとえば鈴木武幸氏は、1981〜1995年の15年間戦隊のプロデューサーをつとめた人だが、自分の関わった作品について、こんな発言はしたことがない(「成功だった」とは言う)。自分一人で作った作品ではない。脚本やら監督やら音楽やらデザインやら、莫大な数の人間が力を合わせて作った作品である以上、いくら自分が最高責任者だからといって、軽々しくしていい発言ではないだろう。ファンに対しても失礼である。『ギャバン THE MOVIE』がどれほどつまらない作品であったとして、それを心ゆくまで楽しんだ観客はいるはずだ。プロデューサーがこんな発言をしたことで、スタッフにとってもファンにとっても、一体どんな得があるのだろうか?
だいたい作品が成功か失敗かなどということが、そんなに簡単に決められるものだろうか。たとえば東映の『柔道一直線』は高視聴率にもかかわらず大赤字だった。ところがその作品の制作過程で蓄えられたノウハウは、『仮面ライダー』に生かされ莫大な利益を生み出した。こうなると赤字だから失敗作と簡単に決めつけられるものでもない。
ひょっとしたら今の東映というのは、プロデューサーが「来年の戦隊はこういうのにする」と決め、スタッフはその手足となってその構想を忠実に実行するだけ、というふうな制作体制になっているのだろうか。だとすれば、プロデューサーが作品の成功・失敗に対して一人で全責任を背負っている気になるのも不自然ではない。しかし、だとするとそれは創作の現場としては、かなりまずいことではあるまいか。そこでは「たくまざる傑作」というのは絶対に生まれないのだから。
というか、そもそも今の東映特撮は本当に「創作物」なのだろうか。単にベルトコンベアに乗せられた、工業製品のような気がしてくる。昨今の、とにかく話題を作って客が入りさえすればいいという映画作りの手法を見ていたら。そして、そんなやり方を続けていけば、先細りは目に見えている。
CG特撮のどこがいけないのか
現在も(戦隊=引用者注)シリーズは楽しんで観ていますよ。「オプティカルの合成カットは1話につき3箇所まで」みたいな制約があった当時からすれば、今の画面は夢のような出来だと思います。『大戦隊ゴーグルファイブ』のDVDの第五巻収録の解説書には、スタッフの一員であった久保宗雄氏のコメントが載っている。この「今の画面」というのは、コンピュータ・グラフィックス(CG)に代表される、進化した現在の映像技術を使った画面のことを言っているのであろう。今の戦隊シリーズとは何の関わりもない久保氏が何を考えようが自由だが、現在の戦隊シリーズのスタッフの人たちまで、まさかこんな「夢のような出来」などと考えたりしているわけではあるまいな。
いくら映像技術が進化したところで、それを使うのは人間である。ビルが爆発炎上して火の手があがる、破片が舞う、海での戦闘での水しぶき。空気や水の表現には、撮影する人間のセンスが問われる。しかしCGという文明の利器のおかげで、映像センスがゼロの人間でもそれなりの絵が撮れるようになった。「こんな高い技術を使って、こんな低いセンスの絵を撮るとは!」というギャップに視聴者はうんざりするのだ。
今の作品に比べたら、確かに昔は貧弱な技術しかなかったし、ひどい映像も多かった。しかし見ているほうとしては「そういうもの」だと思ってから、別にひっかかりも感じなかった。ひどい絵については脳内で補えばいいのである。CGを使った画面はなまじ絵が小ぎれいなだけ、視聴者に脳内補完を許さない。イライラするだけだ。
古参の特撮ファンにはCGを嫌っている人が多い。しかし彼らだって、一流のセンスを持った人間がCGを使ってすばらしい映像を見せてくれれば何の文句もないはずだ。三流のセンスしか持ってない人間がCGを使ってそこそこの絵を撮り、自分では一流の映像を作った気でいる。それが問題なのだ。
平成仮面ライダーの幼稚さ
苦情殺到の『仮面ライダー ディケイド』「続きは映画で!?」の真相を直撃!
――(仮面ライダーシリーズの)ヒットとロングランの秘訣は何でしょうか? やはり手を替え品を替え、戦略的に緻密に計算されていたわけですか?
白倉 逆にそうせざるを得なかったんですよ。ヒットの法則なんてあればいいですよね。レンジャーシリーズみたいに「とりあえず5人の戦士がいて最後に大悪党を倒して終わり」的なものが、実は仮面ライダーシリーズにはないんですよ。
白倉伸一郎氏も東映の特撮スタッフなんだから、「戦隊シリーズ」という名前も言えんのか。なんだよ「レンジャーシリーズ」って。「戦略的に緻密に計算」する必要がある、高尚なる仮面ライダーシリーズとは違い、「とりあえず5人の戦士がいて最後に大悪党を倒して終わり」さえすればいいだけの戦隊シリーズなんて、正式名前を覚える必要もない、ということをわざわざ言いたかったのか。
子供みたいな人だな。
まあ子供番組を作ってる人が子供じみた精神構造を持っていても何も不思議なことはないのだが、そういう人たちに限って、子供だましの戦隊シリーズとは違い、仮面ライダーシリーズは高尚なドラマ性を持った大人向けの番組なんですよとか言いたがる。
こういう幼稚な人たちが作っているのが平成仮面ライダーシリーズというわけだ。
オタクの旗は降ろせ! 非実在青少年規制問題について
東京都の「青少年健全育成条例」改定案問題については竹熊健太郎氏のブログで知ったのだが、継続審議になったことは、とりあえず目出度いことではある。しかしそれはあまり知られないうちにコッソリ通してしまおうという敵のやり口に反発してこその世論の盛り上がりであり、また、今回は時間があまりにもないので小異を捨てて大同についたが反対運動の進め方には違和感を持っている、なんて言ってる人もいる。条文が拡大解釈されて言論の自由のない社会が到来するのでは、という恐怖心から反対運動に馳せ参じた人は多いだろうが、「でも何らかの規制は必要では?」と漠然と思っている人もやっぱり多いだろうし、そういう人たちを説得するような理論を、次に議会が開かれる六月までに構築できるのだろうか? 中には、説得どころか、そういう規制の必要を感じている人たちを上から目線で馬鹿にすることしか考えてない人のブログなんかもあって、そういうのを見るにつけ非常に不安になる。
それはそうと、こういう動きが起こるたびに思う。いいかげんオタクの旗は降ろしたほうがいいのではないか。
「オタク」というのはもともと蔑称である。それを逆手に利用し、オタクは素晴らしい、世界に誇る日本の文化だ、とアピールしてきたつもりが、世間様のほうはというと、一体どのような土壌があってこそのオタク文化が花開いているのかについて、全く理解なさっていないし、なさろうともしていない。有益なものも有害なものも含めて文化なのであり、有害なものだけ取り除いて有益なものだけ育てようとしても枯死するだけだ、ということが全然分かっていない。
そういうことを今回の動きであらためて知らされた。
二次元のキャラクター相手に恋をする、そんなことは普通のことである。すぐれた創作作品にはそれぐらいの力があって当然だ。ところがそれをわざわざ「オタク」だの「萌え」だのと、何か特殊な概念であるかのように命名し、その結果どうなったか。自分たちがすぐれた存在であるかのようにアピールしたつもりかもしれんが、世間様からは、ああいうのは特殊なメンタリティを持っている人間なのだ、というぐらいの認識しかされていない。
特殊な人間だから規制したって構わない、と思われるのだ。
弾圧の呼び水になっているとしか私には思えん。
特撮をマンガ・アニメ等と一緒くたにするな
少なくともこの五年ほど、謀巨大掲示板の特撮!板では「キャラ萌え」が、いいイメージを伴った言葉として使用されるのを私は見たことがない。
単に「○○が好き」を「○○萌え」と言い換えただけの、深く考えず使っている人たちがいる。それ以外はこんなふうな使われ方をする。『シンケンジャー』を嫌いな人間が、「『シンケンジャー』を好きだなんてのは、どうせ『殿萌え〜』とか言ってる連中だけだろ」。
その場限りの感動を視聴者に与えることはあっても、心の奥底に触れることはない、現実の手触りを欠いた薄っぺらな作品を指して使われる言葉である。
「萌え」というものを何かしら新世代の文化のように唱える人たちにとっては、そんなものは間違った使い方だと言いたくなるかもしれないが、間違っていようがいまいが、とにかくそういう使われ方をしているのだから仕方がないだろう。だいたいオタク論だとか萌え論だとかを展開している偉い学者や評論家の先生たちは、アニメ・マンガ・ゲーム・ライトノベルについては詳しいかもしれんが、特撮についてはあまり知識も思い入れもないように見受けられる人が多い。山本弘氏や岡田斗司夫氏みたいなのは論外としても、アニメ・マンガ・ゲーム・ライトノベルについては真面目に議論をしているような人たちですら、特撮についてはろくに知りもしないまま、「オタク文化全般」について詳しいふうを装って、適当なことをしゃべっている。大迷惑だ。
絵に描くのと、実際に生身の役者が演じるのとでは、作品を成立させるリアリティというものに対する考え方が相当違うということが、彼らには分かっていない。仮に「萌え」がアニメ・マンガ・ゲーム・ライトノベルにとって新しい時代を切り開く概念だとして(よく知らんけど)、特撮にそんなものを導入しても、それは今まで特撮が独自に発達させてきた文化を切り捨てるものだ。切り捨てている、という事実に気づくことすらないだろう。もともと思い入れなんてないのだから。
特撮に対して無知なくせに特撮をも含めてオタク論、萌え論を垂れ流しているやつらは、アニメ・マンガ・ゲーム・ライトノベルとは異なった、今まではぐくまれてきた特撮独特の文化を、自分たちが圧殺し衰亡に導こうとしていることを自覚すべきだ。
特撮番組に子役は本当に不要か?
『天装戦隊ゴセイジャー』の第一話を見ていると、いきなり子どもが出てきたので「子役レギュラーの復活という噂を聞いていたが、こいつのことか」と思ってみていたら、そいつがレッドに変身したのでびっくりしてしまった。
昔の特撮番組を見ていると、やたら子役が出てくる。子どもの頃にそういうのを見て、反感を持ったと言っている人は多い。彼らは、子ども番組だから子どもを出さなければいけないなどという安直な固定観念に当時のスタッフが捕らえられていたと批判する。そのため「少年隊員」などという、わけの分からない無理のある設定をこしらえていたのだ、と。だが、最近の番組を見るにつけ、確かに子役の比重は減ったが、まるでそれを補おうとするかのように、ヒーローたちがどんどん子どもっぽくなってきた。容姿もそうだし、性格設定もそうだ。そういうのを見るにつけ、子どもの興味を引きつけるには子どもを出さなければならないと考えた昔のスタッフの方が結局は正しかったのであって、「安直な固定観念」とも言えないのではないかという気もしてくる。
アニメでは昔から、子どもがヒーローとして戦うという話は普通にあった。しかし絵に描けばいいアニメとは違って、実写でそれをやるのはかなり困難である。だから特撮ではヒーローはあくまで大人であった。視聴者である子どもたちがあこがれる対象、自分も大人になればあんなふうに強くてかっこよくなりたいと思わせる存在。しかしそうはいっても今現在は子どもである。無力で、大人たちに守ってもらわなければならない。正義感ゆえに無茶な行動をとったとしても、ヒーローの足を引っ張ることにしかならないのだ。そういう現実を視聴者に教え込む装置として、かつてのヒーロー番組における子役というのは機能していたのではないか。だから視聴者たちは子役を嫌ったのだ、と考えることはできないか?
さて、現在のヒーローは以前に比べて、何も考えずにがむしゃらに突っ走るタイプが多くなった。あまり大人の責任とか使命感とかを感じるようなシーンも減った。「憧れ」よりも「親しみ」を、という路線はそれはそれでいいのだが、『ゴセイジャー』の第一話でアラタは、子どもに「悪いことをしたら謝らなければならない」と説教するという、大人としての役目を担っていた。にもかかわらず、そのくせ自分はカードをうっかり落としたり正体を人間に見られたり、そして大して反省している素振りも見せず、しかも仲間もそんな彼を「結果オーライ」などと言う。
子ども型ヒーローにするのか大人型ヒーローにするのか、ちゃんと決めておいたほうがいいのではないのか。
いいとこ取りというのはたいてい失敗するものだ。
オタクは差別が大好きである(後編)
唐沢俊一検証blogの1月11日の記事「「コミックマーケット77」レポート(後篇)」を読んでいたら、人の目を見て話をしないのがオタクとしての正しい態度だと竹熊健太郎氏がおっしゃった、みたいなことが書かれてあったのにも首をひねったが、それよりも
自分は会長(と学会会長の山本弘氏のこと。引用者注)も唐沢俊一と同じで「直接話している限りではいい人」だと思っていたので、別に意外ではなかった。だいたい、50歳を過ぎて『生徒会の一存』の同人誌を作っている人が悪い人のわけがない。
……この人たちは一体いつになったら目が覚めるんだろうか?
大人になってもアニメやマンガを好むことは、別に恥ずべきことでもなんでもない。だからといって、別に自慢に思うことでもない。単に趣味の問題である。だがオタクであることが何かしら素晴らしいこと、知的であることであるかのような幻想をふりまき続けている人たちがいる。と学会の唐沢俊一氏、岡田斗司夫氏、山本弘氏等のことだが、そのため彼らはオタクたちによって持ち上げられ、あがめたてまつられてきた。今や、彼らが書いてきたことがどれだけデタラメに満ちているかについては、さまざまなサイトで検証されている。(唐沢氏はそれに加えて盗作の常習犯でもある。)オタクどももそろそろ自分たちが食い物にされてきたことに気がついてもよさそうなものだ。だがまだ気がつかないらしい。唐沢氏らの化けの皮ははがれたが、唐沢氏らがふりまいてきた、自分たちオタクが知的存在だという主張はやっぱり正しいのだ、と。アニメの同人誌を作れば、自分たちは特権階級にいられる、そういう幻想に、いまだしがみつくつもりだ。そして「唐沢俊一はオタクではない」と必死に叩くことによって、自分たちこそが真のオタクであるという夢に、いつまでもまどろんでいられると思っているらしい。
山本弘氏が今までどれほど人を傷つける発言を繰り返してきたかを知っていれば、こんなことを書く人の気が知れない。それとも『生徒会の一存』からはカタルシスウェーブが出ているとでも言うつもりか。
そういえば、以前謀巨大掲示板に「唐沢俊一を特撮ヒーローにしよう」というスレが立ったことがあった。 唐沢俊一の糾弾に立ち上がれと、檄を飛ばしにきた人が立てたようなスレだったが、正論をはいているはずの自分たちがなぜ冷笑を浴びせられたのか、多分彼らには一生かかっても理解することは無理だろう。
世間ではマンガもアニメも特撮もオタクとして十把一絡げにされているが、特撮ファンは業が深いのである。
オタクは差別が大好きである(前編)
私がオタクを嫌いなのは理由がある。
岡田斗司夫『オタク学入門』(1976年)より。
この戦隊シリーズ、普通の人から見れば、いったいオタクたちは何が嬉しくて毎回ビデオに録ってまで見ているのか、さっぱりわからないだろうと思う。(中略)
「どうせオタク連中は、ヒロインのパンチラが嬉しいんだろう」、などといわれたりしてしまう。
が、それは下司の勘ぐりというもんだ。戦隊シリーズのヒロインはアイドル性も高くなく、パンチラもあまり見えても嬉しくない。(強調は引用者による)
岡田斗司夫氏はアニメや特撮すべてのジャンルについて詳しいわけではない。(当たり前だ。そんなことは不可能だ。)しかし「オタキング」(オタクの王)などと名乗って活動を続けていく以上、すべてに詳しいフリをしなければならない。その結果、知りもしないことについて原稿を依頼され、適当なことを書きなぐることになる。岡田氏の知識がいかに出鱈目なものかについて検証してあるサイトはいくらでもあるので、ここではやらない。やるのは、なんでこんなのがオタクの代表者などとして、一時期とはいえ通用することが可能になっていたかである。
それはオタクのコンプレックスを見事についたからだ。
実際、大人になってマンガやアニメや特撮のファンというだけで、犯罪者予備軍の扱いを受けた時代があった。好きなものを好きだというだけで世間からの白眼視に耐えねばならなかった。そこに、オタクというのは知的に進化した新しい人類であるとか、世界中で日本製のアニメが大ヒットしているとか、江戸時代から続く日本文化の正当な後継者であるとか唱える人物が現れれば、あっとういまに救世主扱いをされたのも無理もないところだ。ところがそれは、現実をもとに理論を組み立てたのではなかった。理論が先にあって、それに合致するようにオタク像をこしらえあげたのである。理論に合致しないものは切り捨てた。
その一つが特撮ヒロインのファンである。
アイドル性も高くないということを、何か根拠があって言っているわけではない。単に理解できないだけである。自分に理解できないことは切り捨てる。それは、世間がオタクに対して向けたまなざしと全く同じものを、岡田氏は戦隊ヒロインのファンに対して向けたのだ。そして目ざわりな者をすべて切り捨てたあと、残った者たちを相手にして、君たちオタクは知的エリートなのであると吹き込む。
オタクは差別されていた。そしてこれ以上差別されたくないと思った。だが、彼らは差別そのものを問題にしようとはしなかった。自分たちが差別する側に回りたいと願ったのだ。そしてそのようなオタクどもによって、岡田氏はオタキングとして崇められた。
さて、同じような「オタクの代表者」に唐沢俊一氏がいる。(続く)
「と学会」と零下300度
開巻わずか八ページ目にあるこの一文こそ、本作に大ケッ作の座を確保させた名文である。「零下三百度」というのが千両ではないか。今日び子どもマンガにもここまで非科学的な数字は出てこない。絶対零度などという不粋なものをこの作者は顧みないのである。
他人を見くだしバカにすることによってウケをとることを職業としていながら、これを書いた唐沢俊一氏というお方は「有効数字」という概念も知らんらしい。この調子で「江戸幕府三百年」にもツッコミいれてみてはいかがか。
これは『トンデモ本の逆襲』(1996年)に掲載された五島勉『危機の数は13』についての書評だが、無知なのか、それとも読者の笑いをとるために無知を装っているだけなのか、前年の『トンデモ本の世界』にしろ、今読むと他人を見くだして優越感に浸ろうという、さもしさばかりが鼻につく(いちいち挙げないけど)。
「と学会」の人たちも認めていることだが、『トンデモ本の世界』が売れたのは、オウム真理教事件のさなか、オカルトの蔓延に対抗するための武器を求める風潮にのっかったからだ。しかしそれは、オカルトに対抗する立場でさえあれば多少の問題があっても大目に見ましょうという風潮でもあった。
「と学会」は売れてからつまらなくなった、堕落した、なんて言ってる奴がいるが大嘘。質の低さは最初からだ。
わが国におけるSFの開拓者の功に報いるために何一つしなかったSFファンは、こんなものに星雲賞やってたんですか(しかも2年連続)。
ウケをとるためには、原典をゆがめて紹介しても構わないという連中がのさばっている限り、『ジェットマン』や『カーレンジャー』が真面目に論じられるようになる日は遠い。
『ドラえもん』の最低エピソード
「お金をたくさんかけさえすれば、いい作品ができる」という幼稚な勘違いをそのまんまマンガにしてしまった「宇宙ターザン」(てんとう虫コミックス16巻)は、特撮ファンとしては読むに堪えない。
『ドラえもん』は大人になってから読んでも面白い作品と、そうでない作品の差が激しすぎ。
ところで「視聴率が下がったために制作費が減らされた」というセリフは今読むと違和感を感じる。高視聴率であっても関連商品の売り上げが不振であれば打ち切りを食らうなど、子供向け番組にとっては視聴率よりもグッズの売り上げのほうが重要である、という認識が当時はまだ行き渡っていなかったということか、それとも単に藤子・F・不二雄先生が無知だっただけか? ちなみに初出は1978年。
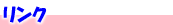
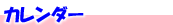
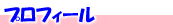
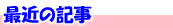
- スーツアクターという難題 (03/26)
- 仮面ライダーは面白くなければいけないのか (03/23)
- とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』 (03/21)
- 誰が橋本環奈を殺したのか?(後編) (03/19)
- 誰が橋本環奈を殺したのか?(前編) (03/17)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(後編) (03/14)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編) (03/09)
- 『仮面ライダー1号』、井上敏樹、「七光」? (03/07)
- 水木しげるは本当に「反戦」と言わなかったのか(後編) (03/05)
- 水木しげるは本当に「反戦」と言わなかったのか(中編) (03/03)
- 水木しげるは本当に「反戦」と言わなかったのか(前編) (03/01)
- シャーロック・ホームズと仮面ライダーの差 (02/27)
- 原点が頂点ならば、その後はずっと下り坂 (02/19)
- 平成仮面ライダーは「恩返し」をしたのか (02/10)
- 平成宇宙刑事とは何だったのか(後編) (02/01)
- 平成宇宙刑事とは何だったのか(前編) (01/30)
- 平成仮面ライダー、昭和に膝を屈する (01/28)
- ヒーロー番組に残虐描写は必要か(後編) (01/25)
- ヒーロー番組に残虐描写は必要か(前編) (01/23)
- 『仮面ライダークウガ』は過去の作品である(その4=完結) (01/19)
- 『仮面ライダークウガ』は過去の作品である(その3) (01/16)
- 「スーパーヒーローイヤー」? なにそれ? (01/14)
- 『仮面ライダークウガ』は過去の作品である(その2) (01/12)
- 『仮面ライダークウガ』は過去の作品である(その1) (01/10)
- なぜ大葉健二を叩かないのか (12/03)
- 平成の次に来るヒーロー?(後編) (12/01)
- 平成の次に来るヒーロー?(前編) (11/29)
- 特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(後編) (11/26)
- 特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(中編) (11/24)
- 『七人の侍』は本当に名作か (11/19)
- 特撮に出た俳優はなぜ勘違いするのか(前編) (11/17)
- ギャバンとアトムと維新の党 (11/15)
- オダギリジョーはいったい何をバカにしたのか?(後編) (11/10)
- オダギリジョーはいったい何をバカにしたのか?(前編) (11/08)
- 作品を作ることの喜びと悲しみと (11/04)
- 『仮面ライダークウガ』第25・26話の幼稚さ (10/19)
- 特撮ヒーローへの「誇りの強要」(補論) (09/29)
- 特撮ヒーローへの「誇りの強要」(後編) (09/24)
- 特撮ヒーローへの「誇りの強要」(前編) (09/21)
- 仮面ライダーと日本国憲法 (09/18)
- なぜ元ヒーローのブログは恥ずかしいのか (09/16)
- 『ウルトラマンメビウス』の大迷惑 (08/29)
- 鈴木美潮という特オタ女の勘違い(補論) (08/21)
- 鈴木美潮という特オタ女の勘違い (08/14)
- 炎上商法をナメるな――『進撃の巨人』をめぐって (08/07)
- 小谷野敦の本はなぜ売れるのか(後編) (07/27)
- 小谷野敦の本はなぜ売れるのか(中編) (07/25)
- 小谷野敦の本はなぜ売れるのか(前編) (07/23)
- 伊上勝の孝行息子 (07/16)
- 名作すぎる『ウルトラセブン』 (07/05)
- お疲れ様でした、高寺成紀さん (06/30)
- ガス抜き、時代劇、特撮ヒーロー(後編) (06/17)
- ガス抜き、時代劇、特撮ヒーロー(前編) (06/15)
- 勧善懲悪で何が悪いのか?(後編) (06/04)
- 勧善懲悪で何が悪いのか?(中編) (06/02)
- 勧善懲悪で何が悪いのか?(前編) (05/30)
- 道化を演じる元特撮俳優たち (05/25)
- あしたのジョー、男塾、御都合主義 (05/14)
- 高寺成紀の復活はもうないのか (05/11)
- 自らの業績に泥を塗る東映プロデューサー (05/05)
- 内田有作はなぜ東映を首になったのか (05/01)
- 仮面ライダーと原発(後編) (04/11)
- 仮面ライダーと原発(前編) (04/08)
- 佐藤健太の問題発言 (04/01)
- 天才の平山亨、秀才の白倉伸一郎 (03/30)
- 地獄へは仮面ライダーだけで行っとくれ (03/27)
- ミロのヴィーナスと『相棒』 (03/21)
- 白倉伸一郎の降格(後編) (03/16)
- 白倉伸一郎の降格(中編その2) (03/14)
- 白倉伸一郎の降格(中編) (03/12)
- 白倉伸一郎の降格(前編) (03/10)
- 小林朝夫の大暴言 (03/08)
- 少しもダイナミックでない宇宙刑事本 (02/22)
- これが平成ライダーのスタッフの本音なのか (02/20)
- 仮面ライダー俳優の勘違い (02/12)
- 嗚呼、懐かしき「イスラム国」 (02/05)
- 『スーパーヒーロー大戦GP』における戦隊の扱いは? (01/31)
- 「イスラム国」の現実感のなさ、特撮ヒーローの困難 (01/28)
- 東映の取締役は算数もできない (01/26)
- 内田樹先生、そんなにお金が好きですか (01/23)
- 『仮面ライダー鎧武』の自己破産宣告 (01/12)
- 「視聴率なんか気にしていない」という嘘 (01/10)
- 仮面ライダーの人気低下は本当か (12/31)
- 特撮技術の進歩は何のため? (12/29)
- プロレスと同じ道をたどる特撮ヒーロー (12/19)
- 誰がスーパーヒーロー大戦を批判できるのか (12/16)
- 東映ほどファンを大切にする会社はない(悪い意味で) (12/10)
- イケメン特撮ブームの裏で何が進行しているのか (12/05)
- 東映の拝金主義と『がんばれ!! ロボコン』 (12/03)
- 特撮と『なぜ時代劇は滅びるのか』 (11/28)
- スーパーヒーロー大戦は作り過ぎか? (11/26)
- 東映特撮ヒーローは本当に時代劇に源があるのか (11/22)
- もう勝手にしろ――『シャイダーNEXT』感想 (11/19)
- 仮面ライダーのプロデューサーの自己顕示欲 (11/17)
- 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。 (11/04)
- こんなので満足なのか――『シャリバンNEXT』感想 (10/31)
- なぜ「懐古厨」の反対語は存在しないのか (10/29)
- 「仮面ライダー2014年問題」という予言の自己成就 (10/26)
- なぜ『仮面ライダー鎧武』の視聴率は低いのか (10/05)
- 公式に失敗作認定された『ギャバン THE MOVIE』 (09/19)
- CG特撮のどこがいけないのか (04/10)
- 平成仮面ライダーの幼稚さ (03/28)
- オタクの旗は降ろせ! 非実在青少年規制問題について (03/20)
- 特撮をマンガ・アニメ等と一緒くたにするな (02/27)
- 特撮番組に子役は本当に不要か? (02/19)
- オタクは差別が大好きである(後編) (02/17)
- オタクは差別が大好きである(前編) (02/07)
- 「と学会」と零下300度 (04/01)
- 『ドラえもん』の最低エピソード (03/24)
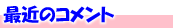
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ percetakan jakarta (04/20)
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
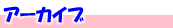
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)