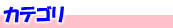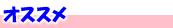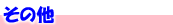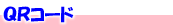シャーロック・ホームズと仮面ライダーの差

アンソニー・ホロヴィッツ『シャーロック・ホームズ 絹の家』(原書2011年)
昔のキャラクターを利用して新作を出すという商売は全世界のどこでも行なわれているが、その中で最も活動が盛んなのは間違いなくシャーロック・ホームズ物であろう。コナン・ドイル没後も世界中でホームズの冒険譚は絶え間なく作られ続けており、この『絹の家』もまたその一つである。ただ、ミステリーとしてよく出来ているとか、ホームズやワトソンのキャラクターの再現度も高いとか評価されている一方で、話が暗くて爽快感が少ないという批判にもまたさらされている。おそらく書いた人の志が高すぎたのであろう。
『絹の家』のホームズは単に犯罪捜査を行なうのみならず、より巨大な社会悪に戦いを挑む。ということは、ドイル自身によって書かれた、いわゆる「正典」においては、ホームズはその社会悪に対して見て見ぬふりをしていた、いやそれどころか加担者ですらあったという事実が読者の前に浮き彫りになる。
これは明らかにホームズに対する批判である。
コナン・ドイル財団も、よくぞこんな小説に公認を与えたものだと思う。
その試みは必ずしもうまくいっているとは思わない。二十一世紀的な価値観で十九世紀の人間の行動を裁くという無理もなくはない。ただ、ホームズを完全無欠のスーパーヒーローのように思い描いていたファンにとっては幻滅であるのは事実である。作者は、無難なパスティーシュを書くことを自分に許さなかったのだ。シャーロック・ホームズの名はこれからの時代も永久に輝き続けるものでなくてはならない。そのためには現代の価値観でホームズはどのように見られるかに無頓着であることは許されず、たとえ「正典」を傷つける結果になろうとも、それを避けて通ることはできなかったのだ。
さて本題である。世界的な名キャラクターであるホームズと比べるのもどうかとは思うが、少なくとも平成ライダーが始まった当初は、そこには同じような志の高さもまた存在していたように思われる。そして、新しい時代の価値観に即した仮面ライダーを新たに作るということは、旧作もまた無傷のままでいられる保証はない。平成ライダーに対して「こんなのは仮面ライダーではない」と抗議の声を上げた人たちは、おそらくそのことに気づいていたのだろう。
時代は移り、かつては新作が作られるたびに聞かれた「こんなのは仮面ライダーではない」という批判の声は、近年はもうさっぱり耳にしなくなった。理由については書くまでもない。
戦隊ヒロインとホットパンツ(後編)
(承前)廃止運動が長らく起こらなかった理由の一つに、ブルマーがかつては女性解放運動のシンボルであった、という威光をまとっていたからのように思われる。
女性が自分の意志で自分の手足をのびのびと動かすことを好ましく思わなかった封建制度は、女性に男性よりも動きにくい服装を強いた。それを打破するための運動の一環として、女子のブルマー着用があったのである。最初はもっとブカブカだったものが、ぴったりブルマーへと進化していったのも、ひたすら「動きやすさ」を追求した結果である。聖なる女性解放闘争に対して欲情を催すなどあるはずのないことであり、あってはならぬことであった。
そして性における禁忌の存在は、それを破った時の興奮をいっそう高める作用がある。
話は特撮ヒロインについても当てはまる。
特撮ヒーロー番組というのは大人が見るものではなかった。そこで女性がセクシーな格好をするなど許されざることである。スーパー戦隊のヒロインがホットパンツを着用するのも、悪者たちと格闘をするためにも少しでも動きやすい格好をすることが必要だったからであり、パンツからスラリと伸びる二本の脚は、見ている子どもたちに健康的な美しさと力強さをアピールするために存在するものであった。
そしてそんな純粋無垢な世界を覗き見て、そこにエロチックなものを感じた大人の男たちは、罪悪感とともに目のくらむような快感を同時に覚えたのである。
だから、1980年代を境に、特撮ヒーロー番組の作り手側もオタクも視聴対象として意識するようになると、罪悪感も快感もともに減っていった。であれば以後は、戦隊ヒロインのはくショートパンツもミニスカートも、かつてほど丈の短いものである必要性を失う結果になったのである。
肝心の子どもたちは、それをどのように思っていたのだろうか。以下は個人的な記憶を基にしている。「せいよく」などという言葉すら知らない子供が、そんなことを意識することなどあるわけがないが、かといって無感覚というわけでもない。多分無意識下に刷り込まれていたのではないか。理由もよく分からないまま、体だけ反応していたような気がする。そしてそんな子どもたちが成長し、当時のことを思い出すたびに身を包む甘酸っぱい思い出は、何十年経っても決して減衰することはない。幼い日々に熱く感じたのは胸だったのか股間だったのか、はっきりと思い出せぬまま。
ネットを見ていると、1980年代の特撮ヒロインのファンというのは特に熱狂的な感じがする。
今のスーパー戦隊を見ている子供達は、三十年後にはどんなことを感じているのだろうか。
戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)

『ブルマーの社会史』高橋一郎/萩原美代子/谷口雅子/掛水通子/角田聡美
スポーツ社会学に関するいたって真面目な本。
ブルマーというのは今から思えば非情に奇妙な服装である。なんであんなエロい格好が、長らく我が国の学校における女子体育教育の標準の地位にあったのだろう。トップアスリートを目指すというのならともかく、大多数の平凡な女子生徒にとっては単に恥ずかしい格好でしかなかったし、だがそれも受忍すべきものとも考えられ、廃止要求運動が盛り上がることもなかった。それが、1993年頃に突然ブルマー廃止の動きが始まるや、またたくまに全国に燎原の火のごとく広がり、わずか十年ほどの間に学校の現場から完全に駆逐されてしまったのである。
ということについて社会学的に研究した本なのであるが、疑問がすべて晴れたわけではない。ただ感じたのは、何がエロい格好で、何がエロくない格好なのかということを規定するのは、自然よりも文化の力のほうが強いのではないか、ということである。確かにあんな下着みたいな格好で人前に出ることが恥ずかしくないわけがないのだが、「女子が体育をするときは、こういう格好をするものである」という社会通念の力によってやすやすと押さえ込まれていた。そして見ている男の方も、今自分は劣情をもよおしているのか、それとも若々しい女性の健康美に素直に感動しているのか、区別もついていなかった、というかそのような区別が存在するということすら思いつかなかったのではないか。そして「いやあれは間違いなくエロい格好なのだ」という指摘が一度成立してしまえば、それを学校の現場から排斥しようという動きに対して抵抗らしい抵抗など何一つ起きなかったのである。きっかけはまず間違いなくブルセラショップであっただろうが。
それで思ったのは、昔の特撮ヒロインってなんであんなにエロい格好をしていたのだろうか。ピチピチのホットパンツは股も臀部も体の線がくっきり、裾もほとんどないから、脚が付け根から丸見えだ。下着が見えることもあった。これが視聴率対策でないことは明らかである。1980年代の初頭くらいまでは、小学生より上の視聴者なんか想定されていなかったのだから。そして逆に、今みたいにオタクが見ることを想定するようになって、逆にエロくなくなっていったのである。
ということを前から疑問に思っていたのだが、この本を読んで答えが見えてきたような気がする。(続く)
原点が頂点ならば、その後はずっと下り坂
白倉伸一郎センセイの悪口を言うのはもう一生やめよう。
今春公開予定の映画『仮面ライダー1号』のキャッチコピーが「原点にして頂点」だと知った時、そう思った。
原点が頂点ということは、つまり後はずっと落ちっぱなしということである。ガンダムやゴジラに対してそう言ったところで、文句を言う人はいない。第一作だけが伝説的名作であり、そのブランドバリューだけでシリーズが延々続いているというのは誰もが認める事実だから。別に恥ではない、シリーズとは元々そういうものだ。
仮面ライダーシリーズはそれらとは違う――はずだった。
たとえば脚本家の會川昇氏は『語ろう!』シリーズの本でこんなこと言っていた。
僕はね、平成ライダーは昭和ライダーより優れている点がいっぱいあると思うんですよ。というよりも、僕は平均的には平成ライダーの方が優れていると思ってます。多数派というわけではなかったが、極端に変わった意見でもなかった。仮面ライダーシリーズは一度は終わったコンテンツだった。それがよみがえったのである。新しい時代にふさわしい価値観をまとって。平成仮面ライダーは「平成仮面ライダー」というブランドなのであり、昭和仮面ライダーの養分に寄生しているのではない――そのような主張が一時期は大真面目に存在していたのである。
その栄光を全部捨てる気らしい。
白倉センセイだって取締役にまで出世したんだし、「平成仮面ライダーをここまで大きく育て上げた男」という勲章も得たのだから、後は会議室でふんぞり返っていればいいのである。そして「今の若い人たちにはもっと頑張ってもらわなくては」などと偉そうなことを言っていれば万事収まる。しかしこの人は自分の勲章を自分の手でむしりとってしまった。もちろんそこには、「平成ライダー初期」なんか持ち上げたところで今後の商売にとっては有利にはならず、昭和ライダーを持ち上げたほうがいいという冷静な計算に基いているのであろうが、商人根性もここまで徹底していればもう敬服するしかない。
「平成ライダー初期」を持ち上げていた人たちには気の毒ではあるけれど。
『ニンニンジャー』は人気なかった?
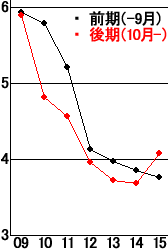
山谷花純氏のツイートから。
ニンニンジャー最終話の視聴率 5.2%でした。強く思えば叶うんですね。皆さんの熱い応援があったからこそです。本当にありがとう。1年間の感謝の思いは、今日アップするブログにまとめて書きます。ひとまず先に…わっしょーい!!このツイートは現在削除されている。ビデオリサーチ社との契約違反だからだ。詳しい契約内容は知らんが、視聴率が出ればキャストやスタッフには即座に教えてもらえるが口外するのは禁止らしい。だからブログやツイッターには具体的な数字ぬきに漠然と高かったとか低かったとかしか書けない。
一回だけなら「うっかりしていた」で済まされるが、山谷氏の場合は明らかに故意犯である。なぜなら丁度一年前もまた同じことをやっているからだ。
ニンニンジャー初回視聴率でましたね。 気になる数字わ…なんと 4.8%! ゴーカイジャー以来の4%越えらしいです。このまま忍ばすわっしょいしていくぜ!やはりこのツイートも直後に削除された(ちなみに『キョウリュウジャー』の初回視聴率も4%超えているからこれは間違い)。数字を出してはいけないということが分かっていて、わざとやっていると断言して差し支えあるまい。
視聴率を見るにも正しい知識というものが要る。時刻とか天候とか裏番組の強さとか、数字にはさまざまな要素がからんでいる。ところが視聴者が大多数はそんなことは知らない。単に数字が高ければ人気が高い番組で、数字が低ければ人気の低い番組だと思い込んでいる。だからテレビ番組のキャスト・スタッフの中には、視聴率のいい時だけは視聴率がよかったとツイッターに書き、悪い時は何も書かず、世論を誘導しようとする人もいる。だが一般ドラマのことは知らんが、そんな手は特撮ファンには通用しない。『ニンニン』に関する視聴率の分析には、とうの昔に着手ずみだ。「そこまで必死になって『ニンニン』の人気の高さを仕立て上げたいというとこは、よっぽど人気がないのか?」と逆に疑われるのがオチである。そういえば山谷氏も俳優歴は七年だが、特撮番組でレギュラーをつとめたのは初めてだったっけ。
『ニンニン』の視聴率といえば、その年間推移はかなり特異なものだった。後期が前期より高いなんて普通なら絶対にありえないことである。特撮ファンの間では早くも解析が始まっている。
戦隊シリーズは「同じことをやらない」?
「子供の大河ドラマ」 スーパー戦隊シリーズが40作目(読売新聞、2016.2.9)
読売の記事なんか真面目に批判するほどの価値があるとも思えんが、とりあえず批判しておく。
長年シリーズに携わってきた東映の鈴木武幸専務は、40作続いた理由を「同じことをやらない〔という方針があるから」と語る。〕忍者戦隊の三回目をやった直後で何を言うか。
その前に恐竜戦隊を三回やったとこだろ。
それでも『ニンニンジャー』の企画立案時には、前の二回との差別化を図ろうという考えもあることはあったらしい。ところが妖怪退治が『カクレンジャー』と丸かぶり。『妖怪ウォッチ』へ便乗した結果と言われているが、それでどうでもよくなった、というのはメインライターの下山健人氏の弁である。
だいたい、同じことをやって別に悪いわけではない。むしろ逆である。同じことを二回やってはいけないのであれば、もうとっくにネタは尽きている。戦隊シリーズのメインターゲットは未就学児〜小学校低学年であり、毎年新しい視聴者が入ってくる一方でどんどん出ていくから、五年も経てば完全に入れ替わる。十年くらい間隔をあけて同じネタをやったところで何の問題もない。
鈴木武幸氏は1981年から1995年まで連続して戦隊シリーズのプロデューサーを務めた人だが、確かにその十五年間は「同じことをやらな」かった。今年は司令官がいない戦隊にしよう、友達だったのが敵味方に分かれて戦う話はどうか、五人の戦士がきょうだいだったら……。やりたいことは山ほどあった。当時は少なかった中高生の視聴者もまた、次はどんなことをやるのかと期待しながら毎年二月を迎えていた。
今はもうそんな時代ではないことは、誰もが分かりきっている。
まだやっていないことなど残されてはいない。いや残されているだろうけど、玩具の販促に少しでも不利になるようなことは最初に選択肢から除外されている。
しかしだからといって新しいことを開拓しなくていいのか、だいたい同じことの繰り返しというのは、クリエイターとしてのプライドが許すのだろうか、と懸念する人もいるであろう。別にいいんじゃないの。だいたい今の戦隊シリーズのスタッフで、自分のことを「クリエイター」なんて思っている人がいるとも思えない。
鈴木専務もこんなこと言っていると老害扱いされまっせ。
十七の小娘になめられた戦隊シリーズ
『手裏剣戦隊ニンニンジャー』の百地霞役、山谷花純氏の2月9日のブログ記事「モモニンジャー 百地霞。」(最終回放映の翌々日)
私はアイドルじゃなくて女優です。なんじゃこりゃ?
だから、朝の30分 子供番組でも、ちゃんと芝居を見せたかった。(強調は引用者)
さらに続けて。
役と作品への向き合い方を、同年代のキャストへ背中で伝えたかった。なんで背中……?
スーパー戦隊シリーズでは、主役の戦士はキャリアが一年とか二年とかの、新人同然の俳優から選ばれることが慣例になっている。彼らにとっては、死に物狂いでものにすべきチャンスである。演技力を磨いて名を売って、将来もっと大きなチャンスを掴むためのステップボードにしようと全力投球せねばならない時である。そのためにはジャリ番などと気にする余裕などあるはずもない。
山谷氏をのぞいて。
彼女は十一歳でデビューしているから、七年のキャリアがあった。他の五人(追加戦士を含めて)とは切実さが全然違う。私は他の人とは違って別格なのよと思っていても不思議はない。とはいってもたった七年ではないか。検索をかけた限り、特に注目された役をこなしてきたわけでもないようにみえる。そんな十七(当時)の小娘にすら見下されるとは、スーパー戦隊シリーズもよくもここまで落ちぶれたものだ。
無論こういう勘違いをしたまま現場にやって来るキャストは昔からいた。というか、若い頃にはありがちなことである。そして彼らは一様に、撮影の現場でスタッフの人達がどれほど真剣に番組制作に打ち込んでいるかを目の前にして、自分の勘違いを思い知らされ恥じ入ったのである。山谷氏は一年を通じて自分の考えが変わった部分もあったことについて書いているが、「子供番組でも」など考えていた自分の傲慢さに思い至ったという記述はない。今の戦隊シリーズの撮影現場にどれほど弛んだ雰囲気が充満しているのか、察しがつくというものだ。こんなことをブログで晒されて、スタッフの人達は情けないとか恥ずかしいとか思っているのだろうか。
そういえば小川輝晃氏や塩谷瞬氏がゲストで出演した時、自分たちの頃に比べて俳優たちがスタッフから叱られることが少ないことに驚き、心配になったなどと言っていたことがあった。
心配すべきは俳優ではなくてスタッフの方だったようだ。
平成仮面ライダーは「恩返し」をしたのか
「一体これのどこが『仮面ライダー』なんだ?」
東映YouTubeで『クウガ』が終わったので引き続いて『アギト』を見ている。確かに面白いことは面白いが、番組の名前に「仮面ライダー」と付いている理由が分からない。
……などということを、十五年前の視聴者は熱っぽく議論していたのだろうか。今となってはもはや話し相手になってくれる人などいない。「そんなもん、商売の都合に決まっているだろ」。これで議論はオシマイになる。
平成仮面ライダーが始まった2000年頃は、「こんなもの俺は『仮面ライダー』とは認めない」などと言う人もいたらしい。老害だの懐古厨だのと言われていたようだが、しかし十五年経った今となっては、結果的に彼らの言い分の方が正しかったと言わざるをえない。なぜなら結局のところ「恩返し」がなされなかったからである。
昭和仮面ライダーの築き上げたブランドバリューの恩恵を平成仮面ライダーが受けていることについては異論の余地はあるまい。しかし時代の流れに合わなくなった部分も出る。それを切り捨て、新しいものを付け加え、今の時代にふさわしい仮面ライダー像を更新する。そしてそれを次の世代へと手渡す。それを「恩返し」というのである。もちろん平成仮面ライダーのスタッフも、当時はそういう気概も持っていたとは思う。だが結果的に彼らは次の世代に何を残したというのか。昭和の仮面ライダーを見て育った世代は、『クウガ』が始まった時、番組名に「仮面ライダー」という文字が入っているというだけの理由で見始めた人がたくさんいただろう。しかし「仮面ライダー」という文字は、単に商売の都合だけでつけているということが天下周知の事実となってしまった今となっては、『クウガ』や『アギト』を見て育ったからといって、番組名に「仮面ライダー」という文字が入っているというだけの理由で『鎧武』や『ゴースト』を見始める人が一体どれだけいるだろうか。
いやそういうことを言うのであれば、『V3』以降の昭和ライダーも全部そうじゃないかと言われるかもしれない。確かに仮面ライダーブランドを築いたのは初代『仮面ライダー』だけで、あとはずっと遺産の食いつぶしをし続けていただけとも言える。そして今春『仮面ライダー1号』の映画公開。同族争いだの親殺しだの事故否定だの、ゴチャゴチャと理屈をこねまわしていた白倉伸一郎プロデューサーも、ついに自分たちは何も新しいものを生み出すことがなかったことを、正直に認める気になったのだろうか。
「デスガリアン」に期待できるか
「デスガリアン」という名前からして期待できそうにない。
-ian というのは人を表す接尾辞である。コメディアンは喜劇役者、ケインジアンはケインズ主義者、ブラジリアンはブラジル人、クリスチャンはキリスト教徒。組織につける名前ではない。つけるのなら何故「デスガリアンズ」にしなかったのか。まるでメンバーが一人だけの組織みたいだ。濁音とラ行音さえ入れておけば悪の組織っぽい語感になるというわけではないぞ。
前置きはこれくらいにして。
『動物戦隊ジュウオウジャー』の敵組織「デスガリアン」に関するバレ情報はすでに行き渡っているが、それを読んで最初に思ったことは「逃げたな」。
デスガリアンは、宇宙の星ぼしを破壊してきた悪の軍団。どれだけ生き物を苦しめて葬るのかを争う遊び「ブラッドゲーム」をくり返し、99コの星を滅ぼしてきた。100番目の遊び場として、地球をえらんだ。最近のスーパー戦隊に対する不満はいくらでもあるのだが、まるでスポーツかゲームの戦いのようにしか見えないというのがある。正義と邪の戦いには見えない。だったら最初から敵組織の目的がゲームだということにしよう、そうすれば「ゲームにしか見えない」という批判をかわすことができる、これはいい考えだ……って、そういう問題じゃないだろ。
いや確かに今みたいな時代にあっては、魅力のある悪役を描くというのが非情に困難であることは分かる。昔は正義のヒーローには正義のヒーローとしての理念と行動原理があり、悪には悪の理念と行動原理があり、その対比が物語の縦軸を作り視聴者を引きつけていた。今や正義も悪も明確な理念というものを持ちづらくなり、悪の組織は単に正義のヒーローの行動を妨害するだけの置物みたいな描き方をせざるをえない。ボーリングのピンのような。
だからといって最初から逃げてどうする。
思い出すのはボーゾックである。『激走戦隊カーレンジャー』に出てきた悪の組織である彼らは、客観的に見れば歴代戦隊の敵組織としては凶暴度ではかなり上位に来るはずだが、どうも視聴者としてはそんなイメージを持てない。理由として考えられるのは、彼らにとって星々を破壊するのは、遊びだったからである。理念も損得も関係ない。ただし『カーレンジャー』はもともとそういう作品であった。デスガリアンの行き先はどうなるだろうか。
なぜ戦隊内恋愛は成立しにくいのか

酒井順子『儒教と負け犬』
井上敏樹氏が以前『鳥人戦隊ジェットマン』についてのインタビューで、なんで戦隊内恋愛を描いたのかについて聞かれ、「若い男女がいつも一緒にいて何も起こらなかったらそっちのほうが不自然」と答えているのを読んで、井上先生にしては随分とつまらないことを言うのだなとガッカリした記憶がある。
というのは『大戦隊ゴーグルファイブ』の男の四人が、ゲストキャラの若い女性に対してはデレデレするくせに、ミキに対しては優しい態度一つとろうとしないことについて、妙にリアルなものを感じたことがあるからである。
男女のカップルというのは男のほうが偉くないとバランスが取れない。両性の平等を定めた憲法が施行されてから七十年にもなるが、人間の意識というものはそれほど簡単に変化するものではないらしい。たとえば女性は学歴や収入が高くなるほど結婚難に見舞われるという現象がある。これは男から敬遠されるというのもあるし、女性自身もパートナーとして望むのは、自分より格上の頼りがいのある男だからである(などということが酒井順子の本に書いてある)。
『ゴーグルファイブ』では例の第39話で、ミキ絶体絶命の大ピンチに男四人は何の役にも立たなかった。男ならば好きな女に向かって、俺は君を守ってやるぐらいのことは言いたい。しかしできない。男の四人にとっては、ミキよりも一般人の女性と一緒にいた時のほうが気分が安らいだであろうことは容易に想像がつく。たいていの戦隊でも事情は同じようなものである。
要するに、戦隊内恋愛は起こらないほうが自然なのであるし、仮に起こったとして、それを描くことは一般ドラマで恋愛を描くことよりも難しいのである。
そしてその困難に挑戦し、やり遂げたからこそ『ジェットマン』は名作と呼ばれているのである。実際、単に戦隊内恋愛が出てくるというのであれば、『ジャッカー電撃隊』もそうであった。あまりうまくいったとは言いがたい。
新しいことに挑戦しさえすれば、それを意欲的な野心作であるかのように評価する傾向がある。しかし、単に新しいことに挑戦するだけなら、こんな簡単なことはない。戦隊シリーズでも、今まで一度も使用されたことのない設定はたくさんある。それを使えばいい。しかし肝心なことは、その一度も使用されたことのない設定を使い、なおかつ面白い作品を作ることである。これは簡単なことではない。
さて今年の新作『動物戦隊ジュウオウジャー』では、戦隊初の三形態(以下略)
金に目がくらんだ安彦良和
金もうけ自体が悪なのではない。金もうけのことしか考えない、という現在の特撮界の風潮を批判したいのである。そう思ってこのブログをずっとやってきたが、アニメ界のエゲツナさに比べればまだマシかもしれない。
ということを思い知らされたのが『朝日新聞』ウェブ版2015年12月8日に載った安彦良和氏のインタビュー「「戦争はかっこいい」と誤解招いたガンダム」である。
安彦氏といえば、自分自身もまたスタッフとして関わった『機動戦士ガンダム』(1979年)について、以前から「今となっては古びて観るにたえないものになってしまった」という発言を繰り返していた。これが当時企画中であった『ガンダム』(ファースト)のリメイクを成功させるための方便であることは見え見えだった。わざわざリメイクをするということは、『ガンダム』が名作でなければならないし、それを上回る可能性がなければリメイクする意味がない。しかしそんな見通しはない、だから「今見て面白いものではない」ということを必要以上に強調せねばならなかったのである。この辺の事情は『宇宙戦艦ヤマト2199』とかなり似ている。ちなみに私がその『ガンダム』を見たのは二年くらい前なのだが、それなりに面白く、「観るにたえない」は明らかに言い過ぎだと思った。
しかしそれでは不十分と思ったのか、今度は、戦争はかっこいいという誤解を招いた作品だ、とまで言い出す。
『ガンダム THE ORIGIN』を成功させるためとはいえ、そこまでやらなければいけないのか。
東映特撮では、過去の名作や名キャラクターを表向きはうやうやしく持ち上げつつ利用するだけ利用し尽くすが、アニメの方では表向きからして泥をぶっかけた上で利用し尽くすものらしい。
しかも驚いたことに、この記事が出た後でツイッターではファンの間で大論争が巻き起こったが、この安彦氏の発言が本心からなされたものであることを誰も疑おうとすらしない。登録しなきゃ読めない部分も含めて、安彦氏は何一つ目新しいことを言っていない。戦争マンガやヒーロー物について昔から言い古されていたことを繰り返しているだけである。にもかかわらず、本当に『ガンダム』は戦争をかっこいいものとして描いていただろうか、などとみんな真剣に議論している。
アニメファンというのは世間知らず、もとい、純真な心を持った人が多いのだろうか。
平成宇宙刑事とは何だったのか(後編)

(承前)宇宙刑事シリーズというと、東映特撮ヒーローのピンチを救った作品だと思っている人は多い。実際書籍にもそんなことが書いてある。たとえば吉川進プロデューサーは『宇宙刑事大全』(2000年)で
『ギャバン』が始まる直前の81年というのは、東映ヒーロー存続の大ピンチだんたんですよ。私が東映テレビ部のキャラクター作品を担当する企画営業第二部部長に就任したのは78年なのですが、その後、東映ヒーロー危急存亡の危機が2回ありました。「だんたんですよ」というのは原文ママ。ところが同じ吉川プロデューサーが、以前は全く異なる発言をしていたことを知っている人は少ない。『宇宙刑事ギャバン(ファンタスティック・コレクションNo.41)』(1984年)では
1回目は78年の末。〔中略〕そして2度目が81年というわけです。
このようにいつも、悲愴な感じで、背水の陣の中で東映キャラクター路線の命脈を保ってきたのですが、それらの場合〔75年と78年の危機のこと〕と大きく違って製作本数が一本増えるという、積極的にして、前向きの考え方のなかに、〔「ギャバン」の〕企画が成立したのです。78年が危機というのは事実。75年が危機というのも意味不明。
「ゴレンジャー」や「スパイダーマン」が、あとのない厳しい環境で製作した作品であるとするならば、「宇宙刑事ギャバン」は、日本晴れの青空の環境で製作された作品であると言えます。
実のところ『ギャバン』はそれほど大した作品ではない。少なくとも東映としての認識はそうである。ただ東映特撮としては戦隊と仮面ライダーの二つだけに頼りっきりというのも心もとないし、宇宙刑事シリーズをプッシュしようという動きが間歇的に出てくる。しかしハッキリ言って『ギャバン』にはそれほど画期的なインパクトがあったわけではないから、その結果宇宙刑事が東映特撮ヒーローの危機を救ったという歴史が捏造されたのである。
宇宙刑事ファンは、宇宙刑事シリーズが不当に低く扱われているかのように思っている人もいるようだが、そんなことはない。現状の扱いは妥当である。そして東映が商売の都合によって持ち上げたり下げたりし、その度にファンは付き合わされ一喜一憂させられる。そういうのをずっと繰り返してきた。
こんな歴史はいいかげんに断ち切られるべきではないか。
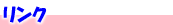
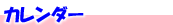
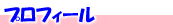
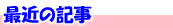
- シャーロック・ホームズと仮面ライダーの差 (02/27)
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(後編) (02/25)
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編) (02/22)
- 原点が頂点ならば、その後はずっと下り坂 (02/19)
- 『ニンニンジャー』は人気なかった? (02/17)
- 戦隊シリーズは「同じことをやらない」? (02/15)
- 十七の小娘になめられた戦隊シリーズ (02/12)
- 平成仮面ライダーは「恩返し」をしたのか (02/10)
- 「デスガリアン」に期待できるか (02/08)
- なぜ戦隊内恋愛は成立しにくいのか (02/05)
- 金に目がくらんだ安彦良和 (02/03)
- 平成宇宙刑事とは何だったのか(後編) (02/01)
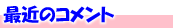
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ percetakan jakarta (04/20)
- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
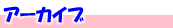
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)