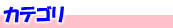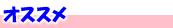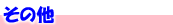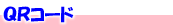金に目がくらんだ安彦良和
金もうけ自体が悪なのではない。金もうけのことしか考えない、という現在の特撮界の風潮を批判したいのである。そう思ってこのブログをずっとやってきたが、アニメ界のエゲツナさに比べればまだマシかもしれない。
ということを思い知らされたのが『朝日新聞』ウェブ版2015年12月8日に載った安彦良和氏のインタビュー「「戦争はかっこいい」と誤解招いたガンダム」である。
安彦氏といえば、自分自身もまたスタッフとして関わった『機動戦士ガンダム』(1979年)について、以前から「今となっては古びて観るにたえないものになってしまった」という発言を繰り返していた。これが当時企画中であった『ガンダム』(ファースト)のリメイクを成功させるための方便であることは見え見えだった。わざわざリメイクをするということは、『ガンダム』が名作でなければならないし、それを上回る可能性がなければリメイクする意味がない。しかしそんな見通しはない、だから「今見て面白いものではない」ということを必要以上に強調せねばならなかったのである。この辺の事情は『宇宙戦艦ヤマト2199』とかなり似ている。ちなみに私がその『ガンダム』を見たのは二年くらい前なのだが、それなりに面白く、「観るにたえない」は明らかに言い過ぎだと思った。
しかしそれでは不十分と思ったのか、今度は、戦争はかっこいいという誤解を招いた作品だ、とまで言い出す。
『ガンダム THE ORIGIN』を成功させるためとはいえ、そこまでやらなければいけないのか。
東映特撮では、過去の名作や名キャラクターを表向きはうやうやしく持ち上げつつ利用するだけ利用し尽くすが、アニメの方では表向きからして泥をぶっかけた上で利用し尽くすものらしい。
しかも驚いたことに、この記事が出た後でツイッターではファンの間で大論争が巻き起こったが、この安彦氏の発言が本心からなされたものであることを誰も疑おうとすらしない。登録しなきゃ読めない部分も含めて、安彦氏は何一つ目新しいことを言っていない。戦争マンガやヒーロー物について昔から言い古されていたことを繰り返しているだけである。にもかかわらず、本当に『ガンダム』は戦争をかっこいいものとして描いていただろうか、などとみんな真剣に議論している。
アニメファンというのは世間知らず、もとい、純真な心を持った人が多いのだろうか。
水木しげる「怠け者になれ」の真意

怪奇漫画家「村木しげる」(水木しげる『ポコポコ』)
水木しげる先生の訃報に接して一ヶ月以上になるが、この人の「幸せになりたかったら怠け者になりなさい」という発言、なんか随分と勘違いされて広まっているような気がする。
そもそもこの人自体がものすごい勤勉家で努力家だ。奥さんの書いた『ゲゲゲの女房』にもそう書いてある。水木しげるという人は確実に、何十年に一度という非凡な才能の持ち主なのであって、そういう人であればこそ「怠け者になれ」という言葉が深遠な意味を持つのであり、我々凡人はやっぱりアクセクと働くしかない。
マンガ家が不幸になる道は二つある。一つは売れないこと。もう一つは売れること。何か一つヒット作を飛ばしたら、たちまち各社の編集者が大量にやって来て、二番煎じ三番煎じの企画を押し付けてくる。そして睡眠や食事の時間も削ってひたすらペンを動かす毎日の到来。マンガ家を志した人であれば、誰もが自分の本当に描きたいテーマを持っているものだが、そんなものは忘れてただひたすら「売れるものを描け」という編集者の指図に従うのみ。そうやって金も名声も手に入れたはいいものの、無理がたたって早死にする、そういう人は多い。
仕事断ればいいのに、と素人は思う。金のための仕事は仕事としてほどほどにこなし、それと並行して本当に自分の描きたいテーマをマイペースで描いていく、というやり方もあるだろう。しかしそうもいかないらしい。なぜならお金とか名声とかいうものは、ないならないで困るが、あったらあったでもっと欲しくなるものだからだ。
水木氏にとって、『ゲゲゲの鬼太郎』がヒットし、それまでの極貧生活から脱出できた時、過度の競争主義に巻き込まれまいとすることが、いかに切実な意味を持っていたか。「怠け者になれ」という言葉の意味もその文脈で理解すべきものだ。
しかし水木氏はなぜそんな生き方が可能だったのだろうか。多分、本当に自分の描きたいテーマを描き、その作品もやはりヒットしたからであろう。『鬼太郎』ほどではないにせよ、戦争体験モノも伝記モノも売れたし賞も獲得した。自分も満足できるし編集者だって『鬼太郎』の二番煎じを無理強いさせることはできない。
逆に言うと、水木しげるほどの大天才でなければそのような生き方は不可能だということになる。
私は最近の販促で雁字搦めになった仮面ライダーやスーパー戦隊の批判ばっかりしているが、別に販促を一切止めろと言っているわけではない。ただもうちょっと緩めるわけにはいかないのか。そしてその分、クリエイターにとっての本当に自分の作りたいものを作ってくれたら、もっとみんな幸せになれるんじゃないのか。そう思っていた。しかし水木しげるクラスの才能の持ち主にして初めてそういうことが可能ということであれば、今後も東映とバンダイの姿勢は永久に続くと考えておいたほうがいいのかもしれない。
ゲゲゲの正義漢

水木しげる『ゲゲゲの鬼太郎』「海座頭」。悪い妖怪をやっつけるだけのワンパターンになっていったことに対する自虐ネタ?
『藤子・F・不二雄大全集』をほぼ読み終わったので、先日から『水木しげる漫画大全集』を読み始めたら、その矢先に水木先生の訃報。
その追悼記事や追悼番組で、「水木作品の素晴らしいところは、単なる勧善懲悪ではないところである」という表現を何度目にしたかしれない。確かにそうかもしれない。とすると、将来「水木しげる論」が書かれるであろう際に、『ゲゲゲの鬼太郎』はどういう扱いになるのかが気になる。なぜなら、水木先生が生涯描いた莫大な数の作品の中で、ダントツの人気と知名度を誇るのが『ゲゲゲの鬼太郎』であり、そしてそれが大ヒットしたのは、単純な勧善懲悪物にしたからである。
実際、『ゲゲゲの鬼太郎』って確かにあまり面白くない(もちろん「水木作品の中では」という意味だが)。これのヒットで水木先生は貸本漫画時代の極貧生活から抜け出すことができたのであって、いかにも編集者から「売れるためにはこういう描き方をしなさい」と言われて素直に従って描いた作品という感じがする。しかしそのことが却って良かったようにも思える。めちゃくちゃ面白い作品ではないが、読んでて不愉快になる作品でもない。水木先生の作品に対する思い入れのなさを反映してであろうか、鬼太郎もまた妖怪を退治して高揚感なく、淡々と事務的に作業を進めているようにも見える。おかげで正義のヒーローにありがちな傲慢さや独善さを作品から感じることが少ない。
さて、1970〜80年代のスーパー戦隊シリーズが今見てなお面白いのは、作り手が本気で正義を信じていたからである。正しい科学の発展が、いずれ人類を理想の世界へと導くであろうと本気で思っていたからである。今この2010年代に、そんな作品を作るのはどう考えても無理だし、だったら無理して熱血漢を演じるより、いっそのこと鬼太郎みたいな眠たそうな目つきをしたヒーローを復活させてみるのも手ではないかと割と本気で思う。そうすれば戦隊の人気も少しぐらいは回復するんじゃなかろうか。
心の奥底では正義を信じていないにもかかわらず、信じているふりをして(あるいは本人も信じているような気になって)、正義の名のもとに暴力をふるう。世の中にこれ以上不愉快なことはない。
トキワ荘の真の敗残者は誰か

伊吹隼人『「トキワ荘」無頼派――漫画家・森安なおや伝』
今の東映の拝金主義はけしからんと批判するだけなら簡単なのである。
映画人として、いい作品を作りたい、見てくれる人の精神の糧になるような物を作りたいと全く思わない人などおるまい。しかし映画というのはとにかく金がかかる(特撮ならなおさら)。「いい作品」よりも「金になる作品」を作らねばならない、という彼らに対する圧力もまた相当のものである。である以上、軽々しい気持ちで批判することもまた慎まねばならない。
その点、映画よりはずっと製作費が安くつくマンガの場合はどうなのだろうか。
「森安なおや」というマンガ家の生涯は、実態以上に不幸で惨めだったというふうに脚色され世間に流布されているようだ。なんのためにというと、もちろんマンガ界の伝説、「トキワ荘グループ」の輝かしい成功者である藤子不二雄(F・A)・石ノ森章太郎・赤塚不二夫らを引き立たせるためにである。ドキュメンタリーやら映画やらでも敗残者扱いが定番。森安氏が死んだのは急性心不全だが、アパートで一人暮らしだったから遺体の発見は二日後になってしまった。しかし近所に住む家族とは行き来もあったし友達もいた。それが「孤独死」なんてことにされてしまう。
マンガ家という職業を選んだ人間にとっての最大の苦悩は、なんといっても「描きたいもの」と「売れるもの」との食い違いである。両立させられればいいが、それでもどっちかを選ばなければならないとなった時、前者を選んだのが森安氏で、後者を選んだのが藤子・F氏らである。どっちが幸福かは、軽々しく結論の出せる問題ではない。にもかかわらず、前者を選んだ者の悲惨さや無残さだけが特に強調され、マスコミを通じて拡散していく。(ということは、逆の方も疑う必要があるということだ。藤子・F先生の生前の知り合いは皆、口をそろえてF先生が充実した悔いのない人生を送ったかのようなことを言うが、果たしてどこまで本当なのか。)
財産や名声を得たからといって幸福とは限らない。俺は俺の描きたいものを描きたいときに描きたいだけ描いたのだから、俺の人生に満足している――と本人は思っていても、世間の誰も耳を貸してくれない可能性がある。そして実態以上に無残な人生を送ったかのように言われる。
勇気の要ることだ。
藤子・F・不二雄作品の主人公の顔
藤子・F・不二雄先生の批判ばっかり書いてると、ファンから恨まれるんじゃないかと内心ビクビクしていたんだが、ファンの方がよっぽど辛辣のようだ。こんなもん見つけた。
【効き藤子F主人公クイズ!】 主人公の顔を画像から選べ基本的に藤子・F先生のマンガは日常と非日常の出会いから話が始まる。非日常サイドの主人公のほうは、いずれもユニークなデザインで魅力的なキャラクターばかりなのに対して、日常サイドの主人公のほうは手抜きがすごい。顔がほとんど一緒だ。顔だけではなく、中身も同様。これといった特徴なく、魅力の乏しい平凡人が多い。
いやこれは本当に手抜きだろうか。平凡なほうが読者としても感情移入しやすいと思ってワザとそうしているのではないか。確かにそういうセオリーはある。それが勘違いであることは、藤子・F先生の大ヒット作品がここに一つも入っていないことからも明らかである。大原正太、須羽みつ夫、野比のび太と、いずれも平凡なだけのキャラクターではない。ま、木手英一やつづれ屋21エモンのように、特徴のある顔で大ヒットしなかったのもあるが。あと、佐倉魔美や春日エリのように、主人公が女性の場合は方針が違うらしい。
以前藤子・F先生はインタビューで、のび太のことを「どこにでもいる、ごくありふれた男のコ」などと言ったことがある(大全集『Fの森の大冒険』に収録)。んなわけあるか! たとえば学校の成績にしたって、0点が普通なんてのは、のび太くらいのもんだろう。藤子Fワールドにおける日常サイドのキャラクターと非日常サイドのキャラクターの関係が、『ドラえもん』だけが他の作品と違って特殊だということは、愛読者なら誰もが知っていることであって、それを作者が把握していなかったなどということは、ちょっと信じがたいんだけど。
そういえば大原正太というのはA先生のキャラクターなのだった。『オバケのQ太郎』が藤子不二雄にとっての初の大ヒット作になったのは、そのことが大きいのかもしれない。その後はなぜか合作はやめてしまうのだが、続けておれば、もっとたくさん大ヒット作を生み出していたのだろうか。
藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(後編)
(承前)このような問題は子ども向け作品に限った話ではない。映画『二十四の瞳』(1954年)などに対してもついても同様の批判が存在している。しかし子ども向け作品の場合は事情はより切実だ。子どもは大人に比べればさらに理解力は低い。戦争だとかエコロジーだとか真の友情とは何かとか、重いテーマを作中で取り上げようと思えば、程度を落として描かざるをえない。子どもの頃に意味が深いと思いながら見ていたマンガやテレビ番組も、大人になってから見るとどうしても批判的な部分に目がいく。
そしてそういう見方をされることこそが、子ども向け作品にとっての名誉ではないかと思う。
「程度を落とす」と言えば聞こえは悪いが、しかし『ドラえもん』を読んだ子どもがそれをきっかけにして日本の戦争について興味を持つようになり、中学生・高校生へと成長するに従って年齢に応じて程度の高い本を読むようになれば、それは素晴らしいことである。重いテーマにそもそも触れないような作品は、子どもの頃にどんなに大好きであっても、大人になってから見返してみた時に単に懐かしさ以外の感情が沸き上がってくることはないし、議論する気にもならない。程度を落とさずに扱えば、そもそも子どもには理解できないから心にも何も残らない。程度を落としすぎず落とさなさすぎずという困難を達成した作品は名作と呼ばれるべきである。
もちろん、子どもの頃に感動し、大人になってから見返しても子供の頃と何一つ変わらぬ感動を与えてくれる作品、という名作もないわけではない。しかしそれは単にその人間が子供の頃から成長していないだけではないのか。
さて話は最後に戦隊に戻るが、戦隊に出演した俳優で、サイトやらブログやらをやっている人はいっぱいいるが、自分の出演した作品を本当に名作だと思い、出演を誇りにしている人は、批判的な目で自分の出演した作品について語るのではないだろうか。しかしそんな人は滅多にいないのである。
なぜフニャコフニャ夫はFよりA似なのか

左から順にフニャコフニャオ67年/フニャコ・フニャオ68年/フニャ子フニャ雄70年/フニャコフニャオ71年/フニャ子フニャ夫74年/フニャ子フニャ雄77年/フニャコ82年/フニャコフニャオ89年
いまだに「F」だの「A」だのと言った呼び方に慣れない。
そりゃ確かに合作していたのは『オバQ』までで、その後は二人とも別々に描いていたというが、「僕たちは二人で一人だ」という意識が藤子不二雄の作風を規定していたのは間違いなく、それを今さら「これはFの作品、これはAの作品」とか言われてもハイそうですかと受け入れる気になれない。「不二」は「二つではなく一つ」という意味だ。
象徴的なのがフニャコフニャ夫という存在である。
F先生のマンガに出てくるキャラクターである。常に締め切り追われているマンガ家。F先生とA先生の似顔絵を混ぜて更にブサイクにしたような顔をしている……と言われている割には、どう見てもA成分のほうが圧倒的に大きい。普通こういうのって逆にしないか。と思って抜き出して年代順に並べてみたのが上の図である。
こうして見ると、最初は確かにFA半々だったのが、徐々にFもAも抜けていって、普通のマンガ家というキャラになっていくのが分かる。そしてフニャコフニャ夫が最も大きな活躍をしたのが『ドラえもん』の「あやうし!ライオン仮面」(1971年)である。
F先生のトレードマークは何といってもベレー帽とパイプである。だから潰れた目・タコみたいな口・メガネ・低い背と、全体的にはA先生を踏まえていても、ベレーとパイプさえ描いておけばFA半々といった趣になる。しかし「あやうし!ライオン仮面」では飛んだり跳ねたりわめいたりの大暴れだから、口に何かをくわえさせるのは無理があった。A成分はまだまだ残ったまま、F成分はベレー帽だけという、その時点でのフニャコフニャ夫で世間一般のイメージが定着した。
結果として、自分より自分の友だちのマンガ家をネタにしたキャラクターが大暴れして、「あやうし!ライオン仮面」は『ドラえもん』の中でも屈指の爆笑回になったわけだが、これが果たして最初から二人別々のマンガ家という意識のもとで執筆されていれば、これほど面白い話になっていたかどうか。

藤子・F・不二雄『ウメ星デンカ』「スイカとギャング」にも、ものすごくヒドい役でA先生が出演。
藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(中編)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「階級ワッペン」より。この見方も単純過ぎる。
(承前)平和と繁栄を謳歌している21世紀のトーキョー。しかしその高度な科学技術文明も、設定によれば、人類が自力で築き上げたものではなく、地球に来訪した宇宙人から与えられたものである。それが、純粋な善意によるものなのか、それとも地球に利用価値があったからなのかについては、よく分からない。一つだけ確実なのは、地球にとって宇宙人の指導を受けるか受けないかの選択の余地などなかったということである。
年表によれば、1983年ごろに第三次世界大戦の危機があり、そして人類はそれを自力で解決できず、宇宙人が介入してくれたおかげで防ぐことができたという。そしてその後、地球は星間連盟に加入し正式に宇宙人との交流が始まったが、こういう経緯がある以上、地球に自治権が認められたとは考えにくい。
二人連れの客が「地球を地球人の手に取り戻せ」と演説をぶちあげたのは、そのような事情が背景にあったと思われる。
そしてその主張に対して、21エモンは何の関心も示さない。
21エモン、そしておそらくは他の圧倒的多数の地球人にとっても、豊かで安全な生活が保証されてさえいれば、独立の気概とか地球人としての誇りとかどうでもよい、と考えられているようなのだ。まさに鼓腹撃壌。
これが戦後日本の似姿であることは言うまでもない。藤子F先生が何を考えてこんな話を書いたのか、ちょっとよく分からない。F先生といえば1933年生まれ、生まれた時から戦死こそ名誉と周囲の大人たちから叩きこまれ、それがある日いきなり引っ繰り返った。この世代の人間には、だから深刻なトラウマを抱えた人もいる一方で、大多数は大した苦悩も葛藤も経ず、自分たち庶民は悪い指導者にだまされて戦争に協力させられ犠牲を強いられていたのだとみなし、アメリカのような優れた文明国の指導を新しく受けることになったことを光栄に感じたのだった。
それは同時に日本人に対して、戦争というものは、するもしないも決めるのは上のエライ人たちであって、我々庶民はそれに振り回されるだけの存在なのだ、という考えを植え付けた。『ドラえもん』において語られる大東亜戦争も、それは我々日本人が日本国の名のもとに戦った戦争であるという意識が極めて薄い。それは後続世代にも受け継がれることになった。しかしそんな戦争観が国際社会で認められるはずもないのである。(続く)
藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(前編)

藤子・F・不二雄『21エモン』「あやしい客」より。
最初に断っておくと、藤子・F・不二雄『ドラえもん』の「ぞうとおじさん」や「白ゆりのような女の子」は、児童に戦争体験を伝えるという意味において非常に優れた作品だと私は思っている。そしてそれを読んだ子どもたちが、やがて成長して色々な本を読んで勉強を積み重ね、戦争について更に理解を深めていくのであれば、申し分のないことである。
ところがどうも現実はそうはなっていない。
この国の大人の大多数は、戦争に対する認識が『ドラえもん』のレベルにとどまっているように思われる。
そうなると、藤子F作品における戦争の描かれ方についても、きちんと検討を加えておく必要があるのではないか。もちろん、これはF先生の責任ではない。F先生は『ドラえもん』が大人の鑑賞に堪える作品であるなどと発言したことなど一度もないのだから(多分)。この国が余りにも幼稚なのが悪いのである。
さて、藤子F先生にとって「戦後」とはどのようなものだったのか。
それが最も端的に現れたのは、『21エモン』(1968年)の「あやしい客」(前後編)ではないかと思う。『21エモン』の舞台は2018年のトーキョー。地球連邦政府が樹立され世界から戦争はなくなり、また科学技術の長足の進歩によって人々は極めて便利で快適な生活を営んでいる。まさに夢のような未来世界。だが、裏設定を読んでいると、これはまさしくアメリカの庇護のもとで「平和と繁栄」を謳歌している戦後日本の姿そのものであることが分かる。
裏設定? そんなものがあるの? 『21エモン』の愛読者でも、そう思う人が大多数であろう。一度雑誌に掲載されたっきりで、2010年に『藤子・F・不二雄大全集』で初めて単行本に収録されたとあれば、広く知られていないのも仕方がない。
そしてこの、平和で豊かで、理想そのものに見えるこの世界において、社会体制に不満をもつ人間が登場した唯一の回が「あやしい客」である。つづれ屋に泊まったこの二人連れの客が、新左翼の活動家をモチーフにしていることは一目瞭然。ちなみにこの「あやしい客」も、最初と二度目の単行本化の際には省かれ、三度目でやっと収録された。(続く)
パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
(承前)インターネットをやっていると、最近のスーパー戦隊はダメだ、昔はよかった、と言っている人と、いやそんなことはない、今のほうが面白い、と言っている人との間で不毛な罵り合いが行なわれている場に容易に出くわす。「不毛」と書いたのは、両者とも議論の前提が共有されていないということが分かっておらず、自分にとっての常識を相手に押し付けているだけだからである。
それは何かというと、「使命の重さ」の描き方、この一点に集約されるように思われる。
大勢の人々の命のかかった戦いである。主人公たちは重圧を感じてしかるべきであり、それが最近の作品からは感じられない、という点については両者とも異論あるとは思われない。意見が別れるのは、昔に比べて脚本や演出や俳優の技量が落ちたためにそうなっているのか、それとも描く必要性が昔に比べてなくなったから描かれなくなっただけなのか、という点である。
そもそもヒーロー番組の根底にあるのは「暴力」である。ヒーローが暴力をふるうのも、大勢の人々の命を救いたいという思いがあるからこそ正当化されうるのであって、それをないがしろにするということは、単に正義の名のもとに強いものが弱いものをやっつける快感を子どもたちに植えつけるだけの行為にすぎない。これはもっともな批判である。それに対して、だいたい子どもたちは使命の重責に苦しむヒーローを見たいとは思わない、という反論がある。実際、それは視聴率によって裏づけられている。
つまりここには子供番組とはいかにあるべきか、という古くて新しい問題が横たわっている。「大人が子どもに見せたがるもの」か、それとも「子ども自身が見たがるもの」か、という。
どっちが正しいかについて、容易に結論の出せる問題ではない。さしあたって必要なのは、意見の違いがある、ということを認識することである。不毛な議論をするよりは、実りのある議論をしたほうがよい。ただ、議論が起こるということ自体は、特撮ヒーロー番組がいかに人々から愛される存在であるかの証であるから、悪いことではない。いくつになっても、ヒーロー番組は心の故郷なのだ。同じ子ども向けの作品である、『ドラえもん』と比べてみると、そのことがより一層痛感できる(結局言いたかったのはそれかい)。
パーマンをやることは義務なのか(その4)
(承前)「等身大のヒーロー」と聞けば、ああこれは『パーマン』のテーマだなと藤子・F・不二雄ファンなら思うところであろうが、実はこれ1990年代半ばのスーパー戦隊(『激走戦隊カーレンジャー』や『電磁戦隊メガレンジャー』等)のテーマでもあった。
ただし『パーマン』が正真正銘の等身大であったのに対して、戦隊の場合はじっくり見れば決して視聴者にとって等身大の存在であったとはいえない。
メガレンジャーになる五人は高校生である。そして彼らにとって最も関心があるのは、地球の平和とか人類の未来とかいうことよりも、自分たちの高校生活を充実したものにすることである。つまり勉強とか、仲間との友情とか、文化祭とか、そしてその一環として、メガレンジャーとしての活動が位置づけられている。
しかしそれは決して、それ以前の戦隊ヒーローに比べて彼らが任務に対して真面目さに欠けているということを意味しない。学園生活を充実させるためにこそ、メガレンジャーとしての活動に真剣に打ち込む必要があるのだ。そして、人類は果たして守るに値する存在なのか、などといった困難な問題とも真正面からぶつからざるをえなくなる。それが戦隊史上随一とさえいえる、最終盤の展開の重苦しさである。
一見彼らはフツーの高校生のように見える。しかし何十億人もの人類の運命を背負って戦っているという事実が厳然として存在している以上、高い意識を持った戦士へと成長しないわけにはいかない。厳密な意味で「視聴者と等身大」であることなど不可能である。狭い世界(身近な人間関係)と広い世界(地球の平和)との関係が、いちおう切断されている『パーマン』の世界とは違って、戦隊ではそれは切り離すことはできない。
ところがどうも最近の戦隊を見ていると、スタッフは本当の意味で等身大ヒーローを作ろうとしているのではないか、という気がしてならない。それこそ「鵜の真似をする烏」なのだが、そう考えた時、たとえば今年の『手裏剣戦隊ニンニンジャー』を面白いと言っている人もいれば、つまらないと言っている人もいる、その両方の気持ちが理解できるはずだ。
なんかダラダラ書いてきたが、いよいよ結論が見えてきたような感じがする。(続く)
パーマンをやることは義務なのか(その3)

藤子・F・不二雄『モジャ公』「ナイナイ星のかたきうち」。仲間が命を狙われているってのにこの態度。これで人気が出るわけがないだろ……。
(承前)『ドラえもん』にしろ『パーマン』にしろ、藤子・F・不二雄の児童マンガを大人になってから読んで違和感を感じるのは「責任感」というものの描き方である。
大きな力を持つ者は、大きな責任もまた背負う。その大きな力をふるうことによって、大勢の人々の運命を救うこともできるし、あるいは破滅に導くこともできるからである。にもかかわらず、ドラえもんやパーマンたちはなぜ重圧に押しつぶされそうにならないのだろうか。ドラえもんの四次元ポケットの中には、それこそ世界の運命を左右しうる力を持った道具が満載であるにもかかわらず。
藤子・F・不二雄の最も得意とするのは、小学生の日常生活という「狭い世界」を舞台にした日常ギャグマンガであり、『オバケのQ太郎』(1964年〜)が大ヒットして以来、そのジャンルで次々と名作をものにしてきた。ところがマンガ家というもの、「好き」と「上手」は一致するとは限らないようで、本当に描きたかったのは、宇宙や未来を舞台にして活躍する冒険活劇だったらしい。『モジャ公』という、作者の大のお気に入り作品は、不人気ゆえに一年ももたずに打ち切られている。
それでも作者は未練があったのだろうか、『ドラえもん』でも時々妙にスケールの大きい「広い世界」を舞台にした話が描かれることがある。しかしキャラクターは普段通り、「狭い世界」を舞台にした時の感覚そのままに動くから、色々変な所が出てくる。長編だとその傾向はさらに著しい。
ただしそれは結果的に『ドラえもん』の長編映画の人気向上には貢献したのではないか。子どもたちは、大きな力をふるって大活躍するヒーローに憧れはするが、その上で、大きな力を持つ者としての責任を背負わされるのはイヤなのである。そういう虫のいい願望を、『ドラえもん』の映画は充足させてくれる。そしてそれは大人が見たところで何の感動ももたらされることはない。
とはいっても『ドラえもん』は大人の鑑賞に堪える作品であるべきだなど思っている人などいるとは思えないから、別にそれはいい。しかし、スーパー戦隊シリーズがそれでは困るのである。(続く)
パーマンをやることは義務なのか(その2)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「ぞうとおじさん」。このコマだけは大人になってから読んでもじわじわくる。
(承前)いちおうここはスーパー戦隊のブログである。それがなぜ最近藤子・F・不二雄先生のマンガの話ばっかりしているかというと、それが「子ども向け作品とはどうあるべきか」という問題について考える際の、格好の補助線になると思うからであって、最後はスーパー戦隊の話に着地させる予定である。
子ども向け作品を作るにあたっては二つの立場がある。一つは、子どもが喜びさえすればそれでいい、というもの。もう一つは、子どもが喜ぶのは当然として、その子どもが成長し大人になってもなお心に訴えかけるものがあるような作品であるべきだ、というもの。どっちが正しいかを性急に決めるつもりはないのだが、ただ伝統的には特撮ヒーロー物というのは後者でずっとやってきたわけだし、最近になって前者の立場が大きくなってきたことに対する反発の声が上がるのは当然であろう。その二つの異なる考えが存在しているということを、まず理解しておく必要がある。
さて、『ドラえもん』の「ぞうとおじさん」もまた、大人になってから読み返すと非常に違和感を感じる話である。
なぜドラえもんとのび太はゾウ一匹救って大満足なのだろうか。
タイムマシンを使って過去を改変するなどという行為が許されるのであれば、なぜ第二次世界大戦の勃発そのものを防がないのか。大きな改変は許されないが、小さな改変は許されるという話なのだろうか。だったら、同じ動物園のトラやライオンもついでに救おうと思わなかったのか。それで大して手間が増えるとも思えない。戦中に殺処分された動物園の生き物は、他にもたくさんいたということを知らぬはずはあるまい。
タイムパラドックスがどうのこうのという、SF設定のまずさは今はとりあえず棚に上げておく。問題にしたいのはドラえもんとのび太の心である。ゾウはかわいい動物だから救わなければならないが、トラやライオンなんか別に殺されたところでどうでもいいという考えのもとにドラえもんやのび太は行動したというのは紛れもない事実である。そしてそれが心あたたまる感動的な物語として、この国の子どもたちによって読み継がれてきたという事実を、一体どのように考えたらいいのか?(続く)
パーマンをやることは義務なのか(その1)

「反面教師としての『ドラえもん』」からの続き
「正義のために戦う」ということについて、藤子・F・不二雄先生はやっぱりよく分かっていなかったのではないか――ということを感じさせるのが、『パーマン』の「パーマンはつらいよ」という話である。
みつ夫にとってパーマンの活動が過剰負担になっているというのが話の発端である(負担軽減のためにコピーロボットがあるのだが、それでも追いつかない)。だから辞めたいとスーパーマンに直訴する。最後には翻意しパーマンの活動を続けることを決心するラストシーンは、なんか美談っぽくまとめてはあるものの、どうもこれは作者がこの問題について徹底的に突き詰めて考えることを放棄した結果としか思えない。
パーマンは常人の6600倍のパワーを持つ。そのような力を持ちながら、なぜ当時苛烈さを増していたベトナム戦争を終わらせるために力をふるわなかったのだろうか。
外国のことなんか知ったことではないのかもしれない。しかし国内に限っても、事故や犯罪や自然災害が起きて多くの人々が死んだり傷ついたりしない日など一日もない。パーマンが救った人命など、パーマンが救えなかった人命に比べればほんのわずかだ。その中には、学校なんか行かず、パーマンが駆けつけておれば助かった人命もたくさんあっただろう。その事実に思いを馳せ、みつ夫が心を痛めるなどというシーンは、決して作中に出てこない。
『パーマン』とはそういう話なのである。別に人類を救うとか世の中を良くするとか地上に平和をもたらすとかのために戦っているのではない。自分のできる範囲内で頑張ろう。それが一番大事なことなのだ。そういう話なのである。
だったら辞めたくなったら辞めればいいではないか。
パーマンの活動が過剰負担だというのなら、少しくらいサボっても、責められるいわれなんかないはずである。そのせいで何千人の人命が失われたとして、なんで今さらそんなことが問題になるのか。なんでこの回に限って唐突に、「大きな力を持てる者の義務」みたいな話が出てくるのか?
もともと藤子F先生は児童マンガ一筋の人である。だから分相応に、たわいのない話だけ描いていればよかったのだ。それを何を勘違いしたのか「ヒーローの責任」みたいな深刻なテーマを作品に盛り込もうとし、結果として墓穴を掘った――と言っていいのだろうか?(続く)
反面教師としての『ドラえもん』(その4=完結)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「正義のみかたセルフ仮面」。正義のヒーロー「あらわし仮面」の活躍をテレビで見て興奮するのび太(六年生)。
(承前)七十年前に日本が大東亜戦争に敗北して終わった時、その反省は国内の世論に二種類の潮流を生んだ。
一つは、もう二度とこのような誤った戦争はするまいという誓い。
もう一つは、もう二度と戦争はするまいという誓い。
もちろん理論的に正しいのは前者である。スーパー戦隊や仮面ライダーも当然こちらの側に立った。ただ、正しい戦争などありえない、今後日本という国は一切の戦争を拒否する、という考えも容易に否定できるわけではない。徹底すればそれも一つの信念である。国民学校六年生で終戦を迎えた藤子・F・不二雄先生もまた後者の立場に立つ者であったことは、その作品の傾向から判断してまず間違いないと思われる。
だが結局それも徹底されることはなかった。1980年に『のび太の恐竜』劇場公開。成功への野心に目がくらみ、作家としての魂を捨てたF先生は、とうとう悪者をやっつける話に手を染めた。一度そこに手を出してしまった以上、もはや後戻りはできない。以後ドラえもんたちが正義の拳を悪者どもの上にふるい続ける話を続けざるをえなくなった。ペンを手に机に突っ伏して死ぬその日まで。
「あらわし仮面」をバカにしていたドラえもんは、自分が同じことをすることになったことを、どう思っていたのだろうか。
そしてそれは日本の戦後の平和運動が常に負け続け、ずるずると後退戦を強いられてきた歴史と重なり合う。
もちろん戦争はしないにこしたことはない。だからといって実際に戦争が起きた時のことを考えずに済ますことはできない。普段から常に平和とはなにか、正義とはなにかという問題について真剣に考えておくことは必要であって、スーパー戦隊も仮面ライダーもその通りにやってきた。「現実に目を向けない理想主義者」は、現実に戦争の可能性が目前に迫ったら何をどうしていいのか分からなくなる。そして目の前にエサをぶら下げられるや、いとも簡単に「理想に目を向けない現実主義者」に豹変する。
『ドラえもん』の話をするつもりが、なんでまたこんな話になったんだろう。別に安保法制の話なんかする気なんか全然なかったんだけど。
「パーマンをやることは義務なのか」に続く
反面教師としての『ドラえもん』(その3)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「ぼく、桃太郎のなんなのさ」 鬼退治に来たはずのドラえもんたちは意外な真実を知る。
(承前)「桃太郎」に題材を得た創作作品は昔から数限りなくあるが、実は鬼のほうが被害者であり、村人のほうが狭量陰険な加害者であったなどという発想を持ち込んだ人は他にいただろうか。『ドラえもん』の「ぼく、桃太郎のなんなのさ」は、まぎれもなく藤子・F・不二雄先生が不世出の大天才であることの証となる作品である。
しかしその天才の輝きが大長編において発揮されたことはただの一度もなかった。
大長編ではだいたい中盤になって「いいもん」と「悪いもん」が出てくる。そして悪いもんをやっつける話になる。しかしその悪いもんは本当に悪い人たちなのか? 彼らは一体どのような出自を持ち、どのような理念に基づいて行動しているのか、何も明らかにならない。たいていの場合、いいもんの方がドラえもんたちに先に接触する。「○○人は悪いやつらなんだ」「○○人さえやっつければ、世の中に平和が取り戻されるんだ」。ドラえもんたちはその言い分を鵜呑みにし、○○人をやっつけ、最後は英雄気取りで元の日常生活へと戻ってゆく。本当にそれで平和が戻ったのかどうか、確認することもなく。
それは子ども向け作品としては正しい態度である。
その点、スーパー戦隊や仮面ライダーのほうが異常なのかもしれない。
もちろん、『ドラえもん』みたいな話がないわけではない。しかしそんな作品を作れば必ず批判される。「どうせ子ども向けなんだから」という擁護は通用しない。むしろ、子ども向けだからこそ疎かにするなと言われるくらいだ。戦隊シリーズでは、悪役というものを登場させる時、なぜ彼らが悪なのか、具体的にどのような悪いことをしているのかについての説明を省くことなど絶対にあってはならないことである。少なくとも建前では。それをやれば、単に正義の名を借りて強い奴が弱い奴をやっつけるだけの話になってしまうからである。
同じ子ども向け作品でありながら、この差は一体どこから出てくるのだろう。
結局は、藤子・F・不二雄という天才をもってしても、戦後日本の絶対平和主義という枠組みから逃れることはできなかったということなのだろうか。なんか話がどんどん大きくなってきた。まとまるんだろうか。(続く)
反面教師としての『ドラえもん』(その2)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「恐竜ハンター」より。未来の世界で流行っている「おもしろいスポーツ」。狩った恐竜はペットにする。
(承前)大長編第一作「のび太の恐竜」を子供の頃に見て、その懐かしい思い出を大人になってからも持ち続けている、というだけの人については別に何か言いたいとは思わない。だが大人になってからこの作品を読んで感動したなどと言っている人とは、絶対にお近づきになりたくないと思う。
ピー助は生まれた時から人間に育てられ、自力で餌をとったことはない。それをもうこれ以上育てられなくなったといって、白亜紀に置きざりにされたのでは、常識的に考えて生きていけるわけないだろう。
のび太のやったことは、飽きたからペットを捨てる人間の行為と何が違うのか。
元はといえば、のび太がピー助を飼い始めたのも見栄のためである。
この長編の中盤には恐竜ハンターというのが出てくる。悪役として。しかしドラえもんやのび太のやっていることが正しく、恐竜ハンターのやっていることが間違いであるということに何の根拠があるのか。やっていることは同じではないか。人間さまの都合で動物を飼ったり、またそれを自然に戻したりしているという点において。ドラえもんやのび太自身が恐竜狩りの経験者である。しまいには恐竜ハンターをなじるにあたって「航時法」という法律まで持ち出す。おい、セワシくんがドラえもんをのび太の家に送り込んだという行為が航時法違反でなくて何だというのだ?
自己正当化しようとすればするほどボロが次から次へと出てくるドラえもん。
ふだん勧善懲悪を書いたことのない作家が勧善懲悪物を書くとどうなるかの典型である。
もちろん優れた作家である藤子・F先生が、この問題について苦悩しなかったとは思えない。そしてそれを瑣末な問題として無視することに決めたその瞬間、藤子・F先生は作家としての誇りを捨て、堕落への第一歩を踏み出したのである。
スーパー戦隊や仮面ライダーにおいても、悪役というものは必ず登場する。そしてその悪役がなぜ悪なのか、具体的にどのような悪いことをしているのか。それは絶対に揺るがせにしてはならない最重点事項である。それを揺るがせにした瞬間、正義のヒーローは単なる暴力の行使者と何も変わらなくなってしまうからである。(続く)
反面教師としての『ドラえもん』(その1)
「子供をだますのは大人をだますのよりも難しい」
特撮ファンであれば誰もが耳にしたことのあるセリフであろう。スタッフやキャストのインタビューによく出てくる。子ども向け作品を作るのは大人向け作品よりも難しい、という文脈で。しかしこういう言い方、もうそろそろ止めにしたほうがいいのではないだろうか。
実際子供と大人とどっちがだましやすいかと言われれば、「場合による」というのが正解である。大人は子供よりも人生経験や知識が豊富である。しかしそれが先入観となって、面白いものを面白いと感じる感性を鈍らせるということはありうる。大雑把に言って、大人向け作品は理性重視、子ども向け作品は感性重視といえようか。
しかし世の中には「子供だまし」という言葉はあるが「大人だまし」という言葉はない。子供をだますのは大人をだますのよりも易しいというのが世間の多数派の意見である。それに対抗するために、戦略してとあえて逆の主張をしていたのである。
そもそも、クリエイターにはプライドというものがある。子ども向け作品は、子供が喜びさえすればよい。だが、その子供が成長し大人になっても心の片隅に残り続けるような作品を作りたいとクリエイターは常に願うものである。そのためには、理性と感性の両方に強く訴える作品でなければならず、それは最初から大人向けに的を絞った作品を作るよりも当然ハードルは高くなる。
昨今はインターネットの普及により、子供としての幼稚な心を持ったまま大人になったような人が、自分の意見を発表する場を持つようになった。そういう人たちによって、子供だましでしかない作品が、「子ども向けでありながら、大人になっても楽しめる作品」などと持ち上げられ方をされるような妙な傾向が出てきた。
藤子・F・不二雄先生の『大長編ドラえもん』もまたそのような作品の一つに思える。(続く)
『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(後編)

次のページでは↓

『ドラえもん』「ラジコン大海戦」より
(承前)藤子・F・不二雄は国民学校六年生の時に終戦を迎えた。
物心ついた時から神国日本は不滅と教えこまれ、それに何の疑問も持つことなく育った少年。それがある日を境に突然、大人たちが掌を返すがごとくアメリカ軍に尻尾を振って民主主義バンザイを叫び始めたことが、幼き日の藤本弘少年の心にどんな痕跡を残したかは容易に想像できる。
ウルトラ・スーパー・デラックスマンを筆頭に、藤子・F・不二雄ワールドに出てくる「正義感の強い人間」はまず間違いなくどこか心が歪んでいるのは、このことと無関係ではあるまい。
では藤子・F先生は反戦平和主義者なのであろうか。それも違う。氏の主張は『ドラえもん』の「ラジコン大海戦」に明確である。戦いに敗れ、ずぶ濡れになってトボトボと家路につきながら、つぶやくスネ夫とスネ吉。「戦争は金ばかりかかって、空しいものだなあ」。
ここだけ見るとあたかも反戦のようにも見える。だが次のページに行くと戦いに勝ち潜水艦をゲットしたのび太の満面の笑顔。
「反戦思想なんてのは所詮戦いに負けた奴の言うことだ」。藤子・F先生の心の叫びが聞こえてくるかのようである。
「正義のための戦い」などというものは存在しない。そのことを幼き日に胸に深く刻み込んだ藤子・F先生にしてみれば、「反戦」もまた一つの正義でしかない。
そしてそれは、所詮この世は弱肉強食、泣く子と地頭には勝てぬというニヒリズムとは紙一重のところにある。『のび太の宇宙小戦争』にしたって、必ずしも嫌々書いた作品とばかり決めつけることもできまい。できれば、この話には続編があり、悪の独裁者を倒した後でスネ夫がピリカ星人に帰化してこの星に居続けたいと駄々をこね、やがて疎ましく思ったピリカ星人たちが毒殺を企てる、などという結末を見たかったところではある。もっともチビっ子の読者にとってはそんなもん見せられても困るだけだろうが(何の話か分かりますね)。
勧善懲悪の考えを否定することがかえって勧善懲悪を推し進めることがある。逆もまたしかり。だいたい「勧善懲悪はダメな作品、勧善懲悪でないのは良い作品」という発想の形式そのものが勧善懲悪的ではないか。そしてその逆説を理解できたときに初めて、「『ノンマルトの使者』は勧善懲悪でないからすばらしい」などという決めつけの安易さもまた見えてくる。
『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
(承前)「理に落ちる」という言葉がある。『のび太の宇宙小戦争』で、ラストの銃殺寸前からの大逆転を見た時に脳裏に浮かんだのは、まさにそれである。
理屈が通っていて悪いことはないだろう、と言われるかもしれない。しかし冒険活劇である以上、読者は主人公が理屈を超えた活躍をするのを見たいのである。正義と平和を愛する心でもいいし、仲間との信頼の絆でも自分の力を信じる心でも構わない、それが奇跡を呼び起こし、彼我の圧倒的な戦力差をひっくりかえして勝利する。我々は普段の生活では奇跡など滅多に起こらないことを知っている。だからこそフィクションの世界ではカタルシスを感じさせてほしいのである。もちろんやりすぎると、御都合主義という批判を招かざるをえないが。
フィクションには二種類ある。常識を守る物語と、常識を壊す物語である。藤子・F・不二雄の作家としての資質は明らかに前者を向いている。『ドラえもん』でも、のび太はひみつ道具を使って常に失敗をする。パーマン、魔美、左江内氏と、超常の力を持った主人公も決して常識の枠を超えた活躍をすることはない。奇跡の大逆転が起きないのがFワールドの掟である。
この二種類の物語は、どっちが高級でどっちが低級ということはない。ほんとうに良質の作品を作ろうと志す者にとっては、道の険しさはどちらも等しい。だが、現代は量産の時代である。何かヒット作が生まれれば、たちまちシリーズ化され、じっくりとアイディアを練る暇もなく次から次へと作品を作るよう急かされる。派手な注目を浴びて客を呼びやすいのは常識破壊型、作るのが楽なのは常識防御型である。常識は疑うより守るほうがやりやすい。その結果として、見かけは常識破壊型でありながら中身は常識防御型、という作品が巷に氾濫することになる。その欺瞞性の極北が『水戸黄門』であろう。
そして我々が「勧善懲悪なんかくだらない」と言う際にイメージするのは、まさにそのような物語なのではないか。だからといって勧善懲悪を十把ひとからげに否定するのは間違っているし、そのような不毛な認識の上に立って一足飛びに「故郷は地球」「ノンマルトの使者」「怪獣使いと少年」等を持ち上げたところで、それらの作品に対しても失礼なことである。(続く)
『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)

藤子・F・不二雄『ドラえもん のび太の魔界大冒険』より。人間界のあらゆる常識が通用しない魔界、そのボスがなんでこんな陳腐きわまるセリフを口にしているのだろう……。
「『ドラえもん』をやめさせてくれないんだ」
晩年の藤子・F・不二雄先生は嫌々『ドラえもん』を描いていた、というのはファンの間では有名な話である――ということを以前「なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その4)」で書いた。だから私は『大長編ドラえもん』は大嫌いである。読んでないけど。しかしいつまでも食わず嫌いも良くないと思ったので、先日意を決して『藤子・F・不二雄大全集』の二巻を読んでみた。
はぁー……。
おいたわしや、藤子F先生……。
もともと『ドラえもん』は日常生活を舞台にしたギャグマンガである。五人のキャラクターもそれに合わせて作ったものである。それを冒険活劇の世界に持って行ったものだから、当然のことながらあらゆる場面で無理が出ている。その上、なんか妙にモタモタしたコマ運び、迫力の欠けたアクション、説明ゼリフ。そして生気のないゲストキャラ。
短距離走の金メダリストをマラソンに出せば、こんな具合になるのだろうか。
私は最近のスーパー戦隊については批判がましいことばかり書いてきた。しかし大長編ドラえもんに比べれば、はるかにマシだ。今まで厳しい態度をとりすぎていたことについては反省している。それはともかく。
わが家の本棚には『ドラえもん』のてんとう虫コミックスが19巻まである。子供の頃に、何度も何度も繰り返し読んだもので、ボロボロになっている。子供の頃に大好きだったマンガがかくも無残な姿をさらしているのを見るのは辛かった。
だが、藤子・F・不二雄というマンガ家が、日本の歴史上有数の偉大なクリエイターである、という事実をいったん頭から追い出し、まっさらな心で改めて長編ドラを読んでみれば、実はそんなに悪くはない、そこそこ楽しめる作品になっていることに気づかされる。
以前に「勧善懲悪で何が悪いのか?」他で、勧善懲悪は程度の低いものであると無根拠に決めつける風潮について論じた。長編ドラのつまらなさは、この問題を考える糸口を提供しているような気がする。(続く)
愛の批判・憎悪の批判

『藤子・F・不二雄大全集』を読んでおったら、『エスパー魔美』第一巻「くたばれ評論家」に誤字を発見。「祅」(しめすへんに夭)ではなくて「祆」(しめすへんに天)。
それはともかく。
この「くたばれ評論家」という話、なんかやたらとブログで取り上げられている話のようだ。ブロガーなら誰にとっても、他人事ではない切実なテーマなのだろうな。ブログで人や作品をけなしたり叩いたりしている人は多い。その動機は大きく分けて二つある。一つは好きだから叩くのであり、もう一つは嫌いだから叩くのである。ところが本人は好きだから叩いているにもかかわらず、人からは嫌いだから叩いていると勘違いされ、結果トラブルに発展することも多い。その手の勘違いが魔美に取り返しのつかない誤りを犯させる、という「くたばれ評論家」のストーリーの流れは実に読み応えがある。藤子・F先生にも似たような体験があったのだろうか。それはともかく。
魔美は極度のファザコンで、軽率で思い込みの激しい性格もまた彼女の魅力である。しかしなあ、普通は分かるでしょ。
好きで叩いているのか嫌いで叩いているのかくらいは。
どこで見分けるのか。字数である。好きだから叩いていると、たいてい長い長い文章になる。相手に対して敬意を抱き、きちんとした態度で批判するためには、やはりそれに見合うだけの文章量は必要だ。「寸鉄人を刺す」というのは、長文を書くだけの気力がないのをごまかすために使われる言葉と思って差し支えない。短い文章でズバッと相手の弱点を突くというのも、そうそう出来ることではないのだ。一般的に、憎悪よりも愛情のほうが、人に与えるエネルギーの量は大きい。
なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その4=完結)

(承前)『劇画・オバQ』という作品がある。
『新オバケのQ太郎』の最終回でオバケの国へと帰ったQちゃんが、十五年ぶりに人間界へやって来て、大人になった正ちゃんと再会する。テーマは「子供時代との訣別」。しかし、大人といっても、素敵な大人もいれば、つまらない大人もいるはずだ。一体ここまで正ちゃんをつまらない大人にする必要があったのだろうか。あまりにも夢のない話になっていて、ファンの中には「これを正式な後日譚とは認めたくない」と言う人もいるらしい。気持ちは分かる。
大人になるということは、悪いことばかりではないはずだ。しかし藤子F先生にはそんな話は描けなかったのだろうか。
もし当初の予定通りの『チンプイ』の最終話を描いておれば、同じようになっていた可能性は高い。しかし描かなければ「もし描いていれば感動的な最終回になっていたかもしれない」という言い訳の成り立つ余地がある。実際ネットで『チンプイ』ファンの声を拾っていると、その作戦は成功したように見える。かくして名声に傷がつくのは避けられた。
藤子F先生は『チンプイ』という作品に愛着がなかったわけではないだろう。ただ利害打算がそれを上回っただけの話である。
「『ドラえもん』をやめさせてくれないんだ」
生前、藤子F先生は家族に向かってそういう愚痴をこぼすことがあったらしい(ソースは『藤子・F・不二雄SF短編PERFECT版 7』収録の藤本匡美「父の持論」)。といっても別に小学館から暴力的な恫喝を受けていたとかいう話ではあるまい。自分はもう財産も名声も十分に得た、あとは本当に自分の好きな仕事だけをしたい、というふうに腹をくくったなら、編集者だって無理じいは不可能だったはずだ。ということは、それほど切実な苦悩でもなかったのだろう。
そして『ドラえもん』の原稿を描きながら机に突っ伏して死んだ。
藤子・F・不二雄はまぎれもなく日本史上屈指の偉大なクリエイターである。その人ですら、カネや名声のための仕事か、本当に自分のやりたい仕事か、どっちかを選ばねばならない時にどっちを選んだかを考える時、仮面ライダーやスーパー戦隊シリーズに関する今の東映の拝金主義を強く批判する気にはどうしてもなれないのである。
なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その3)

氷室冴子(作)/山内直実(画)『なんて素敵にジャパネスク』より
(承前)「玉の輿に乗りたくない」というのは少女マンガにおける一つのパターンとして確立している。財産も地位も何になろう、女の子にとって本当の幸せは愛し愛される人との結婚である。『ジャパネスク』の瑠璃姫など、それらのヒロインには一つの共通点がある。いずれも強い意志の持ち主だということである。
毎回毎回「マール星の科法の世話になんかなりません!」と言いながら結局は世話になっているエリは明らかにこの系列から外れている。
なぜエリは科法の世話になることに抵抗があるのか。チンプイもワンダユウも別に恩に着せるわけではない。それが却って「借りの感情」をエリの心の底に少しずつ少しずつ積もらせていく。また科法のもたらす便利さ・快適さに一度慣れてしまったら、そこから抜け出せなくなるのではという恐怖もある。そして毎回誘惑に屈し、結局は科法の世話になるということが示唆するのは、妃殿下なんかになりたくないというエリの意志がそれほど強いものではないということである。
エリは内木くんのことが好きである。ではどの程度の「好き」なのか。内木くんと結婚できさえすれば他には何も要らない、たとえ将来食うや食わずの極貧生活を送ることになっても、愛さえあれば耐えていける――と思うほどなのかというと、別にそういうわけではない。というか、十二歳でそんな具体的なことまで考える女の子は普通いない。内木への恋心はいかにも子どもじみた、たわいのないものである。その一方内木はというと、もうエリのことを単なる友達としか思っていない。
理屈はともかくとして、エリが妃殿下になったら結局は夢のない話になるのではないか、と思う向きもあるだろう。そういう人には『ローマの休日』を見ることを勧める。あれは、最後に王女が自発的に大使館に戻るから感動的な話として成り立っているのである。最後にエリが妃殿下になる決意をし、それを美しく感動的な話として描く余地は十分にあったはずだ。ではそれが執筆されるに至らなかった理由はなにか。(続く)
なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その2)

藤子・F・不二雄『チンプイ』「殿下に負けないで」より
(承前)では『チンプイ』はどんな結末を迎えるはずだったのか。それについて論じる前に、まず「エリのクローンを作ってマール星へ行ってもらう」説を片づけておく。
といっても、「クローン人間はコピー人間ではない」という事実を指摘しておくだけで十分だろう。一卵性双生児は性格までそっくりと勘違いしている人も多いようだが、そんなことはない。エリのクローン人間を作ったとして、性格も知力体力も音楽の趣味も、全く異なる人間ができあがる。これでは解決にはならない。
それともマール星の科法は、単なるクローン人間ではなく、精神まで完璧にそっくりにコピーする技術を有しているのかもしれない。しかし、人間の心だとか人格だとか、そんなものまで自由自在に操れる技術があるのであれば、もう何だってアリだろう。さっさとエリを洗脳してマール星へ連れて行け。一体ワンダユウは何を苦労しているのだろうか。
人の心は自由にはならないという制約があるからこそ、人の世にドラマは生まれるのである。
しかしこのクローン人間説の最大の問題は、その発想の貧困さにある。読者の願いは、エリが幸せになることである。しかし「エリが幸せになる」ということと、「エリの欲求が通る」ということは別のことのはずだ。なぜ、エリの気が変わる可能性は絶対にないということを前提にする必要があるのか。
エリはルルロフ殿下のお妃になんかなりたくないと言っている。しかしエリのその気持の根拠は相当薄弱なものだ、という描き方は第一話から一貫している。エリはルルロフ殿下やマール星について十分な知識を持っていないし、持とうと思うことすらない。とにかく嫌なものは嫌だと言っているだけである。虫歯になった子供が歯医者に行くのを嫌がって駄々をこねているのと大して違いはない。
チンプイの立場に立って考えたい。ワンダユウがマール星本位の考えをエリに押し付けようとする傾向があるのに対して、チンプイはエリのことが純粋に好きである。そのチンプイが、エリにマール星に来て妃殿下になってほしいと言っている。それがエリにとっても幸せなことだという強い確信があるからである。そしてエリの側は、マール星なんかに行きたくないという自分の気持ちを相手に分からせるには、どういう言い方をすればいいのだろうか、と考えてみようとすら思わない。結末は最初から目に見えている。(続く)
なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その1)
『チンプイ』は藤子・F・不二雄に見捨てられた作品である。
などと書いたらムキになって反論してくる人もいよう。F先生は完結に執念を燃やしていたのだが、病魔に倒れ無念にも果たせなかったのである、とかなんとか。しかし『チンプイ』の雑誌連載が終わり、少しだけ描き足して完結させますというアナウンスが出てから、F先生が病没するまで五年以上。体調は良くなかったと聞くが、それでも『大長編ドラえもん』のほうはちゃんと仕事をしていたではないか。『チンプイ』はメジャーな作品ではない。エリちゃんに幸せな結末を迎えてほしい、というファンの痛切な願いに応えるより、億単位のカネの動く『ドラえもん』の映画のほうが大事だったのだろう。
もっとも、金儲け主義の犠牲になって『チンプイ』が未完のまま終わったなどという事実は藤子プロにとっても体面の悪いことではあるらしい。当時の編集者やらアニメ関係者やらは、最終回についてF先生から構想をうかがったことがあるとか、思わせぶりなことをやたら口にしたりしている。しかしシチュエーションが不自然な割には中身のある話はゼロときている。そんなので読者が騙されるとでも思ったか。ふざけんな!
もっとも、『チンプイ』を虚心に読めば、どのような結末に向けて話を進める予定であったのかは明白であって、議論の余地などないはずだ。ただしそれはF先生のファンにとっては受け入れがたいことのようだ。彼らは一様に、F先生は読者に対して誠実であろうとしたがために却って未完になってしまったのだ、などという無理のある前提をもとに推論を組み立てる。だから、最終回はエリのクローンがマール星へと旅立つなどという珍説が生まれたり、そしてそれが支持を集めたりする。これは人様のブログだが
「チンプイ」未完結の理由を考察私は別に商業主義を悪と思っているわけではない。それはこのブログでも何度も書いてきた。しかし商業主義であるにもかかわらず、いやこれは商業主義に走った結果ではない、読者・視聴者のことを真に思ったがゆえだと言いくるめる手法、そしてそれにまんまと乗せられるファン心理は、いずこも同じのようだ。東映特撮に限った話ではないらしい。(続く)
「チンプイ」未完結の理由を考察 の補足
あらためて「チンプイ」
なぜ庵野秀明は言い訳ばかりするのか
このブログでは高寺成紀氏や白倉伸一郎氏を何度も何度も槍玉に挙げてきたが、それも彼らに対する最低限の信頼があるからこそである。何の信頼も抱いていない人を批判したりはしない。
この人達は言い訳をしない。多分、していないと思う。
それは恐らく、特撮ヒーロー番組のメインターゲットがなんやかんや言っても子供たちだ、というところから来ている。子供は面白いものには食いつく、つまらないものにはそっぽを向く。このつまらなさにはどのような深い意味が隠されているのだろう、などということをいちいち考えたりはしない。そんなものを考えるのはオタクだけだ。
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』及びゴジラ新作映画に関する庵野秀明のコメント『ヱヴァ』は見てないし見る気もないし、「ヱヴァが完結しない理由(わけ)」というエントリで書いた以上のことにを書くつもりはなかったのたが、1996年の『新世紀エヴァンゲリオン』のブームを体験した人間として、あと一言だけ。
あの時は、宮崎駿は引退を宣言していたし(後に撤回)、その後の日本のアニメ界をリードしていくのは間違いなく庵野秀明であろう、と誰もが口を揃えていた。『エヴァ』のブームは終わったが、これからも次から次へとヒット作を連発していくことをみんな期待していた。
それが、まさかこんなことになるとはねぇ。
人間なら誰でも自分の力量を越えた仕事を間違って引き受けてしまうことはある。だったらさっさと謝って、手を引けばいい。この人はいつもいつも言い訳ばかりだ。
意味のないものを、いかにも意味がありそうに見せかける。二十年前にそうやって『エヴァ』を大ヒットさせた手腕は確かに見事だった。そして今庵野氏は自分を使ってそれをやっている。『ヱヴァ』がいつまでたっても完結しないのは、自分の才能が枯渇したからではない、もっと深い意味が存在しているのだ、と。そんな手法が二十年経った今もなお通用すると思っている。実際ある程度通用しているけど。アニメファン相手に。
しかしアニメから逃げて特撮に来るとは、ずいぶんと度胸がいいことだな。特撮ファンはアニメファンほど甘くないぞ。
『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)

安藤健二『パチンコがアニメだらけになった理由(わけ)』
2015年である。
いまだに『ヱヴァンゲリオン新劇場版』の完結を待っているファンの人がいるらしい、ということを最近知って、さすがに驚いた。「社会現象」とまで言われた1996年の『エヴァ』ブームをリアルタイムで体験した人間としては、『ヱヴァ』なんかに興味を持てるはずもなく、だから見てもいないんだけど、ただ余りにもかわいそうだから、教えといてやろうか。
そもそもなぜ庵野秀明氏が新劇場版なんか始めようと思ったのかというと、1997年に投げっぱなしにする形で『エヴァ』を終わらせたことに対して、ずっと後悔の念にさいなまされ、再びきちんとした形で完結させたいという執念を燃やし続けてきた、というわけでは全然ない。パチンコの金が入ったからである(ということがこの本に書いてある)。新劇場版のための資金を捻出するために色んなところに頭を下げて必死になって金をかき集めたわけでもなく、だからちょっと自分の思い通りにならないことが起きたらすぐにまた投げ出すのもまた最初から決まっていた。まさに Easy come, easy go.
しかもアニメ関係者というのは、作品がパチンコになって金が入ってくることに対して、やはり後ろ暗い思いをしている人は多いらしい(ということもこの本に書いてある)。もともとは知的ゲームという側面もあったパチンコだが、今じゃ脱法賭博以外の何物でもない。『エヴァ』のパチンコがヒットしたというのも、新しい確率変動システムをいち早く取り入れたおかげであって、これもまた別に『エヴァ』という作品の力があったからではない(ということもまたこの本に書いてある)。正々堂々と手にした金でないものを注ぎ込んで作った作品だという意識があるから、仕事に熱が入らないのも当たり前。
もちろん世の中には、汚い手段を使って金を稼ぐことに何の良心の痛みを感じない人もたくさんいる。庵野秀明氏がそういうタイプの人間ではなかったということを、ファンは喜んでもいいと思うのだが。
桐野夏生の連合赤軍小説が始まった

桐野夏生・山本直樹対談 『文學界』2008年10月号
『文藝春秋』の2014年11月号(10月10日発売)において桐野夏生『夜の谷を行く』の連載小説が始まった。桐野氏は以前から連合赤軍事件に興味があると言っていたから、いよいよその思いを結実させる時が来たということなのであろう。
連載第一回目だけを読んでこういうことを言うのもなんだが、多分あんまり面白いものにはなるまい。私は連合赤軍に関するフィクションもノンフィクションも結構読んでいるが、圧倒的にノンフィクションのほうが面白いのである。
十四名にも及ぶ同志殺害事件。しかしこの奇怪な事件も、四十年も経てば真相もかなり明らかになってくる。それは決して残虐な性格をした無能なリーダーに、他のメンバー全員が服従を強いられた結果として起きた事件、なんかではない。原因は事件に関わった全員にある。社会経験に乏しいくせに正義感だけは強く、視野が狭く、意志も弱くて勇気も決断力もない。ただし、その程度の事なら若い時分には誰にだってある。多少愚かではあっても、それほど極端に愚かではなかった、一人一人は。その愚かさが積もり積もった結果として、「普通の若者たちが起こした異常な事件」は起きた。
だから結局連合赤軍事件の真相に迫ろうと思うのであれば、マクロの視点が不可欠である。山本直樹『レッド』もまたフィクションではあるが、評価が高いのは徹底してその視点から事件を描いているからである。一人の人物に焦点を合わせて事件を見ようとしても、何も見えてこない。もっとも桐野氏も優れた実績を持った小説家であれば、こんなことは分かりきっているのであって、そこを敢えてミクロの視点から事件に挑もうというのは、何か隠し球でもあるのだろうか。私の予想を裏切って面白くなることを期待。
そういえばナチズムなんてのも、昔は悪魔の如き知謀に長けた一人の独裁者が国全体を地獄に導いた、みたいな描き方をするのが普通だったなあ。最近になって、ヒトラーも一人の人間でしかなかったという観点からナチズムを見ようという動きが出てきている。例の、おっぱいぷるんぷるん!の映画とか。多分そっちのほうが正しいと思う。
急につまらなくなった山本直樹『レッド』

『レッド』7巻219ページ
1971年12月24日に起きた新宿クリスマスツリー爆弾事件。警視庁のサイトによれば「警察官2人と通行人10人が負傷」とある。死亡者なんか出てないのである。『レッド』はフィクションであるから、現実と少し変えている部分はある。しかし意味なく変えたりはしない。多分間違った資料を参照してしまったのだろう。どうも7巻の真ん中あたりから、急に作者にやる気がなくなったような気がしてならない。
連合赤軍を描いた作品は数多くあるが、『レッド』が最高峰だと今でも私は思う。連合赤軍事件が、四十年以上も昔の事件であるというのに、いまだに高い人気を持ち続けているのはなぜか。「世の中をよくしたい」という純粋な善意から始まったはずの運動が、かくも悲惨で愚かな結末を引き起こしたという、その過程が人々の心を引きつけるからである。真面目で純粋で正義感の強い人達が、なぜこんな事件を起こしたのか? それに対しては、真面目で純粋で正義感が強いからこそ、こんな事件を起こしたのだ、と答えるのが定説になっていた。ところが山本氏の回答はそうではない。人間とはもともと愚かなものであり、愚かな人間が愚かな事件を起こしただけのことである。真面目で純粋で正義感が強いということは、人間の愚かしさを加速させるわけでもなければ減速させるわけでもない。それらはこの事件の本質ではない。それが『レッド』の描き方である。
事件の全貌が明らかにされたわけではない。「なぜ」(WHY)が解き明かされてしまっても、「どうやって」(HOW)が残っているだろうと。しかしこれはもはや単なるありふれた猟奇殺人事件でしかない。山本氏の熱が冷めたところで、とがめることはできない。読者にとってもこれ以上読み続けても、1970年前後の「叛乱の時代」から学ぶことは何もないし、2010年代を生きる現在の我々にとって、教訓が得られるわけでもない。単に知的好奇心を満足させるだけである。ここで連載を投げ出したところで、誰も文句は言わないと思うし、『レッド』が傑作であるという事実に変わりはない。
続けるなら、脚本家の曽田博久氏と対談してほしい。それだけが心残り。
『ドラえもん』は子供の読み物

てんとう虫コミックス1巻「ご先祖さま がんばれ」
藤子・F・不二雄先生も、まさか本気でこんなことを考えていたわけではあるまい。『ドラえもん』は小学生の読み物だから、それに合わせて程度を落として書いていたのであろう。普通の小学生にとっては、戦争なんて「正しいのはどっちか」という形でしか考えることはない。だからこそ、小学生の時にこのドラえもんのセリフに接した人は、新鮮な衝撃を受けたのだし、『ドラえもん』が優れた児童文学であるということの証左でもある。だが、いい年こいた大人が『ドラえもん』の名ゼリフを拳々服膺していたりするのは、それはやっぱりマズいだろう。
もちろん、自分が正しいと双方が思っている戦争というのもある。だが、それがすべてではない。単なる領土拡張欲だったり、メンツや保身が原因で、「自分が正しい」なんてカケラも思っていなくて戦争を始める政治家なんて、有史以来数限りなくいた。そして大義名分なんてものは、後から考えるものである。
F先生が終戦を迎えたのは、国民学校六年生の時である。そんな年齢で批判精神など持ちようもないし、おそらくは大東亜戦争が正義のための戦いであることを、固く信じていたに違いない。そしてその後、国民に死ねと呼号していた戦争指導者たちが、戦後になってぬけぬけと「自分は本心では戦争に反対であった」などと言い出し、大して心理的葛藤もなく面従腹背というのでもなく、米軍の対日占領政策に進んで協力していったことを、F先生はどのような思いで見つめていたのであろうか。果たして大東亜戦争は日本にとって「自分が正しいと思ってやった戦争」だったのか。一応断っておくと、連合国が正義で枢軸国が悪の戦争だったなどと言いたいわけではない。そんなのは論外。
じゃあF先生は本当はどのような戦争観を持っていたのか。知りたきゃ『SF短編集』読めばいい。ちゃんと読者の年齢に応じて作品を描いている。
昨今のウクライナやイラク・シリア情勢について、ツイッターを見ていたら、経済学も地政学も何も知らず、ただ「正しいのはどっちか」という観点でしか戦争について考えられないツイートばかりなことに心底呆れて驚いた。こういう世の中であれば、『ドラえもん』を読んでる人はそれだけでもマシなのかもしれない。
F先生はあの世でどう思っているだろうか?
『サイボーグ009』とポリティカル・コレクトネス
島本和彦『アオイホノオ』の主人公は、大学生時代の作者がモデルである。1980年ごろのアニメとかマンガとかの話が出てきて面白いのだが、『サイボーグ009』の二度目のアニメ化(1979年)が始まった時、主人公がそのオープニングを見て大感激をするというシーンがある。サイボーグ戦士が一人ずつ画面に出てきてはその能力を見せるのだが、それがいかに素晴らしいセンスで演出がなされていることかについて事細かく延々と力説する主人公。しかし私は003のくだりで噴き出してしまった。

みもふたもないことを。
やっぱりみんな003のことをマスコットヒロインだと思っていたんだな。戦士じゃない。
『ジャッカー電撃隊』と『サイボーグ009』は、どちらもサイボーグ戦士団の戦いを描いた、石ノ森章太郎の作品である。片や打ち切り、片や石ノ森の代表作扱い。ずいぶんと差がついたものである。
ところが、『ジャッカー』の流れを汲むスーパー戦隊シリーズは、男と対等同格の女戦士を登場させ、戦士としての強さと女の子としてのかわいらしさの両方の魅力を持ったヒロインを打ち出し、大きな成功をおさめた。それに対して女の子としてのかわいらしさしか持たされなかった『009』の003は、言っちゃ悪いが、今見ると大して魅力的なヒロインではない。
2001年には三度目のアニメ化となった『009』だが、他のサイボーグたちは大岩を軽々とジャンプする一方で、いちいち男たちに手を引っ張ってもらわないと岩も登れない003は、はっきり言って変すぎる。なんで一人だけ性能がこんなに違うの。
『009』の原作が初めて世に出たのが1964年である。今読めば、偏見や差別と受け止められる可能性を持つ箇所も多い。それがリメイクのたびに問題になる。原典のままにするのか、修正するのか。適宜判断していくしかないだろう。しかし2001年版のアニメは、人種・民族に対しては、神経過敏と言ってもいいくらいの修正を施しながら、性に対してはほったらかし。
石ノ森プロの問題意識って一体どうなってんのよ。
特撮ヒロインの女性学 第二章
クラリスは現実に存在するか?
オタクは世界に誇る日本の文化だ、と言いたがる人たちの心の支えになっているのが宮崎駿監督である。
アニメなんか子どもの見るものであり、大人になってアニメなんか見ているのは幼稚な連中だと、世間から迫害されてきた、しかし今や見返してやる時が来たのだ、と。日本のアニメは今や世界から高く評価されているのだ。賞もたくさんもらっているではないか。
ところがその宮崎氏のほうはというと、オタクを毛嫌いする発言をしょっちゅう繰り返している。自分の作っているアニメは、オタクどもが好むアニメなんかとは格が違うんだと思っておられるに違いない。
しかし、どう違うというのだろう?
クラリスにしろナウシカにしろ、宮崎作品に出てくる女の子なんて、現実にいそうにもないタイプばかりではないか。
実際そんなふうに直接言われたこともあるそうで、それに対する宮崎監督の答え。
「現実にいますよ」
物語のキャラクターは当然架空の存在だが、ゼロから作り上げるわけではない。現実の人間を元に抽象化・理想化して作るものである。その抽象化の度合いが高すぎれば、物語の受け手にとっては「現実にいそうもない」「現実味がない」という感想を抱くことになる。作り手にとっては現実にしてキャラクターを創造しているつもりであっても、そんなふうに受け手に思われたということは、それは作り手の力量不足の現れであって、だからクリエイターとしては、反論なんかしているヒマがあるのなら、反省してもっと現実感のあるキャラクターを創造するよう努力しなければならない。
しかしここに一つ問題がある。
クラリスみたいな女の子が現実にいるわけねーだろと言っている人たちが、同時に『カリオストロの城』は日本アニメ映画史上の最高傑作だ、などと言うのである。
リアリティなんか必要ない、私たちは架空の人物を架空の人物として愛することができるのです。こんなふうに言われたら、作家としては立つ瀬がないではないか。
だから宮崎氏としては、こういう連中は物の価値の分からない馬鹿どもだ、オタクはこれだからダメなんだと、罵倒し軽蔑するしかない。
最近の宮崎監督は「悪人をやっつければ世界が平和になるという映画は作りません」なんて発言をしてたりして、これって明らかに『カリオストロの城』等、オタク受けをした自分の作品を否定したいという意志の現れなんじゃないか。
もっとも、現在の宮崎氏の作っている作品にリアリティがあって、見る人に現実の手触りを感じさせるような出来に果たして仕上がっているのかというと、それは……。
宮崎氏に限らず、作り手の側は「オタク」という言葉を劣ったものとして使用する人が多い。
『北斗の拳』が突きそこなったもの
特撮ヒロインの女性学第二章で『北斗の拳』のことを「女戦士の存在意義を真っ向から否定する」と書いてしまったが、これは勇み足だったような気がする。
レイがマミヤに向かって「お前は俺が守ってやる。戦うのはやめろ。女には女の幸せがある」と口がすっぱくなるほど言い続けたのは、もちろんレイがマミヤを好きだったからだ。愛する者を危険から遠ざけたいと思うのは、当然の心理である。ではレイはマミヤのどこが好きだったのか。
どうも、彼女が自立した女性だったから、のような感じがするのである。
頼れる者など誰もいない人生。それを戦い抜いぬこうとする強靭な意志が、彼女を内面から輝かせ、レイが彼女に魅かれたのもそれが理由なのではないか。その結果として彼女に戦いをやめさせたくなったのであれば、これは矛盾である。
しかしこういうアンビバレントな感情、たいていの男には身に覚えがあることではなかろうか。
さて思想的に考えた場合、レイは保守なのかフェミニズムなのか。
この作品ではリンやアイリも「私も戦うわ!」と言っていた。文明の崩壊した世にあっては、たとえ女であっても戦いを避けて通ることはできない。しかし暴力による支配が剥き出しになった世紀末の荒野では、女の細い腕で戦ったところでたかが知れている。この矛盾点。ここに、あと一歩踏み込んでさえいれば。性別役割分業イデオロギーを肯定するのか否定するのかなどという、旧弊な二分法そのものが、あたかも経絡秘孔を突かれたかのように崩壊するのを、読者は目にしていたに違いなかった。
少年マンガなんてのは、「女には手を上げない主義」などというくだらないキャラクターが出てきたりして、男性中心主義の世界観を舞台にした作品がほとんどなのだが、ときどき侮れない作品がある。
特撮ヒロインの女性学 第二章
『科学忍者隊ガッチャマン』の栄光と限界
私はあまりアニメは見ないのだが、療養中に見た『科学忍者隊ガッチャマン』(1972年)はものすごく面白かったので、その唯一残念だった点について書く。
最終回。いまわの際にコンドルのジョーがジュン(科学忍者隊の紅一点)に語りかけた言葉。
「健と仲良くな。こんな危ねえ仕事は早くやめて、 女の子らしい幸せをつかめよ」
……そういうことはもっと早く言え!
戦いは男の仕事である。今でもそうだが、1970年代はなおさらそうだった。だからこそ、『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年)において、モモレンジャーが男と対等に戦う女戦士として登場した時、視聴者は大変な衝撃を受けたのであった。じゃあ、『ガッチャマン』の白鳥のジュンは衝撃ではなかったの?と言われれば、衝撃ではなかったんだろうなあ。こっちのほうが先なんだが。
女でありながら戦士としての道を選ぶのは、男がそうするのに比べてはるかに大きな覚悟が必要だったはずだが、それはどのようなものであったのか。戦いが辛くてやめたいと思ったことはなかったのか。女の普通の幸せについて、どんな考えを持っていたのか。それらの問題について、仲間はどう考えていたのか。以上のような点について、作中でも真剣に取り上げたことは一度もなく(多分)、死を前にしてなんか感動的な台詞をジョーに言わせる必要性ができて唐突に出てきたのが「女の子らしい幸せ」。
もし仮に、ジョーが普段から、戦いは男の仕事なのであるから女はでしゃばるなとかゴッドフェニックスでお留守番でもしてろとか偉そうに言うキャラクターとして描かれていたのであれば、このラストも感動とともに視聴者の胸をえぐったことであろう。ジュンに対する憎まれ口も、彼女の幸せを本当に願っていたからこそだったんだ、ということで。(その「戦いは男の仕事である」という考え方そのものが正しいか間違っているかは別にして。)
『ガッチャマン』はアニメ史上に燦然と輝く不朽の名作ではあるが、ジェンダーの問題について真剣に取り組んでいたのであれば、その名声はさらに大きなものになっていたことであろう。まあ、多分それがアニメの限界ということか。名誉を『ゴレンジャー』に譲ることになったのは。
特撮ヒロインの女性学 第三章
ヤマトにはなぜ女が一人しか乗っていないのか
この齢になって初めて『宇宙戦艦ヤマト』(1974年の第一作・テレビ版)を見た。とても感動した。そこでさっそくジェンダー分析をやる。
宇宙戦艦ヤマトの女性乗組員は森雪一人だけである。これは非常に奇妙な設定である。女が十人ぐらい乗っている、あるいは一人も乗っていない、というのなら分かる。しかし一人だけって。
このことについて何か筋の通った説明をひねり出すことは不可能だし、意味もない。問題にするのは背後にある思想だ。
最終回では、彼女は古代進の命を救いたい一心で、コスモクリーナーDを起動させたということになっている。文献でそう書いている人も多いし、劇中での描写も確かにそのような感じである。
しかし、そもそも森雪はヤマトの乗組員に選ばれるくらいのであるから、使命感も旺盛で勇気のある女性のはずだ。実際の描写もそんな感じである。ヤマト乗組員全員の福利厚生のために働き続けた生活班のチーフである。艦内に放射能ガスが満ちようとしたとき、だから艦を救うため、地球の未来を救うために我が身を犠牲にして放射能除去装置を作動させたとしても、なんら不自然なことはない。それをなんか無理矢理、艦を救うためではなく、古代進一人を救うために命を落としたということにして話を進めようとしているように見える。
「女が英霊になったら困る」という思想が見え隠れする。
男は「公」、女は「私」に生きるべきものである。かりに女が男以上にヒロイックな行動をとったとしたら、いやあれは公的ではなく私的な動機によって行動したのだと無理矢理にでも解釈する、そうやってヤマトは男の船である、男のロマンであるという観念をなにがなんでも守らねばならぬ。
主人公は古代進である。あくまで古代の視点で物語は展開されなくてはならない。そうである以上、女性乗組員が「私」から「公」へと越境しようとしたとき、それをすかさず引き止めるためには、その女は古代とプライベート上の深い関係性を持っていなくてはならぬ。要するに恋愛関係のことだが、古代がドンファンではない以上、限度は一人である。
とまあここまでくれば謎は解けたも同然であろう。
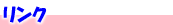
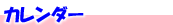
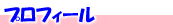
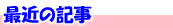
- 金に目がくらんだ安彦良和 (02/03)
- 水木しげる「怠け者になれ」の真意 (01/21)
- ゲゲゲの正義漢 (12/17)
- トキワ荘の真の敗残者は誰か (10/15)
- 藤子・F・不二雄作品の主人公の顔 (10/12)
- 藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(後編) (10/06)
- なぜフニャコフニャ夫はFよりA似なのか (10/03)
- 藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(中編) (10/01)
- 藤子・F・不二雄にとっての「戦後」(前編) (09/26)
- パーマンをやることは義務なのか(その5=完結) (09/14)
- パーマンをやることは義務なのか(その4) (09/10)
- パーマンをやることは義務なのか(その3) (09/05)
- パーマンをやることは義務なのか(その2) (09/03)
- パーマンをやることは義務なのか(その1) (09/01)
- 反面教師としての『ドラえもん』(その4=完結) (08/19)
- 反面教師としての『ドラえもん』(その3) (08/16)
- 反面教師としての『ドラえもん』(その2) (08/12)
- 反面教師としての『ドラえもん』(その1) (08/10)
- 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(後編) (07/10)
- 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編) (07/02)
- 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編) (06/28)
- 愛の批判・憎悪の批判 (06/20)
- なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その4=完結) (05/22)
- なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その3) (05/20)
- なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その2) (05/18)
- なぜ『チンプイ』は完結しなかったのか(その1) (05/16)
- なぜ庵野秀明は言い訳ばかりするのか (04/04)
- 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ) (03/18)
- 桐野夏生の連合赤軍小説が始まった (11/02)
- 急につまらなくなった山本直樹『レッド』 (10/17)
- 『ドラえもん』は子供の読み物 (09/17)
- 『サイボーグ009』とポリティカル・コレクトネス (03/22)
- クラリスは現実に存在するか? (03/07)
- 『北斗の拳』が突きそこなったもの (02/05)
- 『科学忍者隊ガッチャマン』の栄光と限界 (02/03)
- ヤマトにはなぜ女が一人しか乗っていないのか (01/14)
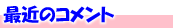
- スーツアクターという難題
⇒ Manju (10/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい
⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。
⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか
⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)
⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ
⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢
⇒ 市民X (05/19)
- スーツアクターという難題
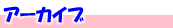
- March 2016 (12)
- February 2016 (12)
- January 2016 (13)
- December 2015 (13)
- November 2015 (11)
- October 2015 (14)
- September 2015 (13)
- August 2015 (12)
- July 2015 (13)
- June 2015 (14)
- May 2015 (13)
- April 2015 (13)
- March 2015 (13)
- February 2015 (12)
- January 2015 (13)
- December 2014 (14)
- November 2014 (12)
- October 2014 (14)
- September 2014 (14)
- April 2011 (3)
- March 2011 (3)
- February 2011 (9)
- July 2010 (1)
- June 2010 (2)
- May 2010 (2)
- April 2010 (7)
- March 2010 (8)
- February 2010 (11)
- January 2010 (11)
- October 2009 (1)
- June 2008 (3)
- May 2008 (2)
- April 2008 (4)
- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)
⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判
⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)
⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)
⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)
⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)
⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』
⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)
⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)
- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)